今日はニクラスのアレンジ・レッスン。
それぞれ好きな曲を選らんで4編成のアレンジを作ってこないといけない。
来週のレッスンが最後で、ファイナルを飾る大きなアレンジを作ることになっている。
今日は途中経過発表。
作ったアレンジは他の人に弾いてもらわないといけない。
なので、この2、3日は集まって練習、練習。
なぜかこの宿題にピリピリしている人もいて、ちょっとでも間違うと
「私のアレンジは完璧なんだから、下手な演奏で台無しにしないで」と怒られる。
命令口調もいちいち気にさわる。
普段はいい人なのに。
昔、オーケストラの人が、指揮者の性格次第でとてもやりにくくなると愚痴っていたことを思い出した。
その当時、ふーん って聞いていたけど今は「そう、そう」と思う。
って聞いていたけど今は「そう、そう」と思う。
完璧でかっこいいアレンジを用意されても、楽しくない人と一緒にはやりたくないものだ。
さて私の番。ヴェルムランドの明るい2拍子の曲。
(Rejländer från Skillingmarkという曲。TVfolk.netの右上の国旗でSwedenを選択。
曲名(melody欄)から探すと映像付で聞けます)
「みんながくらーい曲ばかり選ぶから、ハッピーな曲を選んだ」
と私が言うと、ニクラス、
「スウェーデン人、暗い曲すきだからね。OK. Make me happy!」
(じゃあハッピーにしてもらおうじゃないの!)
4人に弾いてもらうので私は監督のように譜面片手にそばの椅子に座って全体の様子を見る。
そしてニクラスのアドバイス。
「ユニゾンの箇所は効果的。でも何度も使うのは良くない。1度きりにしたら?」とのこと。
ふむふむ。
そしてoutro(introの反対。曲のエンディング)がイメージ道りに出来なかったとアドバイスを求めると
「räka(エビ)とかつけたら?」
「はい?海老? 」
」
例としてニクラスは細かいクロマチックな装飾を弾いてくれた。
「これ、海老 」
」
へー!
変な呼び方!
別の人のアレンジで興味深い例があった。
テクノロジーの進化で、今は便利なことにパソコン・ソフト上で音をいじってアレンジが出来る。
もちろん便利なだけに危険もある。
イメージ通り自在に操れるからと複雑怪奇なリズムにしたり、みんなで弾いたときに
かっこいいコードになるからという理由で変な指使いをしないといけなったりする。
その人のアレンジがあんまり弾きにくいから「自分で弾いてみた?」と聞くと
「Oh no、まさか。優秀なプレーヤーなら問題ないでしょ?
パソコンで聞いたときかっこよかったからこの通り弾いて」
いやいや。
何かが違う気がする。
「ここのリズムが分かりにくいから弾いてみて」と言うと
「え?パソコンでやったから…。鳴らしてみないとわかんない」
これは非現実的なアレンジというのではないでしょうか…。
と言いつつも、便利は便利。
ということで楽譜を作ったり再生するソフトについて。
スウェーデンでも一番メジャーは「フィナーレ」というソフト。
無料ダウンロード版は制限が多いらしい(未確認)。まともに買うと数万円。
私はScore Magineという1000円のダウンロード・ソフトを使っています。
シンプルな楽譜を書く分には問題ない。
楽譜の編集、MIDI、そしてGIFとして保存するというメニューもあり。
それぞれ好きな曲を選らんで4編成のアレンジを作ってこないといけない。
来週のレッスンが最後で、ファイナルを飾る大きなアレンジを作ることになっている。
今日は途中経過発表。
作ったアレンジは他の人に弾いてもらわないといけない。
なので、この2、3日は集まって練習、練習。
なぜかこの宿題にピリピリしている人もいて、ちょっとでも間違うと
「私のアレンジは完璧なんだから、下手な演奏で台無しにしないで」と怒られる。
命令口調もいちいち気にさわる。

普段はいい人なのに。
昔、オーケストラの人が、指揮者の性格次第でとてもやりにくくなると愚痴っていたことを思い出した。
その当時、ふーん
 って聞いていたけど今は「そう、そう」と思う。
って聞いていたけど今は「そう、そう」と思う。完璧でかっこいいアレンジを用意されても、楽しくない人と一緒にはやりたくないものだ。
さて私の番。ヴェルムランドの明るい2拍子の曲。
(Rejländer från Skillingmarkという曲。TVfolk.netの右上の国旗でSwedenを選択。
曲名(melody欄)から探すと映像付で聞けます)
「みんながくらーい曲ばかり選ぶから、ハッピーな曲を選んだ」
と私が言うと、ニクラス、
「スウェーデン人、暗い曲すきだからね。OK. Make me happy!」
(じゃあハッピーにしてもらおうじゃないの!)
4人に弾いてもらうので私は監督のように譜面片手にそばの椅子に座って全体の様子を見る。
そしてニクラスのアドバイス。
「ユニゾンの箇所は効果的。でも何度も使うのは良くない。1度きりにしたら?」とのこと。
ふむふむ。
そしてoutro(introの反対。曲のエンディング)がイメージ道りに出来なかったとアドバイスを求めると
「räka(エビ)とかつけたら?」
「はい?海老?
 」
」例としてニクラスは細かいクロマチックな装飾を弾いてくれた。
「これ、海老
 」
」へー!
変な呼び方!
別の人のアレンジで興味深い例があった。
テクノロジーの進化で、今は便利なことにパソコン・ソフト上で音をいじってアレンジが出来る。
もちろん便利なだけに危険もある。
イメージ通り自在に操れるからと複雑怪奇なリズムにしたり、みんなで弾いたときに
かっこいいコードになるからという理由で変な指使いをしないといけなったりする。
その人のアレンジがあんまり弾きにくいから「自分で弾いてみた?」と聞くと
「Oh no、まさか。優秀なプレーヤーなら問題ないでしょ?
パソコンで聞いたときかっこよかったからこの通り弾いて」
いやいや。
何かが違う気がする。

「ここのリズムが分かりにくいから弾いてみて」と言うと
「え?パソコンでやったから…。鳴らしてみないとわかんない」
これは非現実的なアレンジというのではないでしょうか…。
と言いつつも、便利は便利。
ということで楽譜を作ったり再生するソフトについて。
スウェーデンでも一番メジャーは「フィナーレ」というソフト。
無料ダウンロード版は制限が多いらしい(未確認)。まともに買うと数万円。
私はScore Magineという1000円のダウンロード・ソフトを使っています。
シンプルな楽譜を書く分には問題ない。
楽譜の編集、MIDI、そしてGIFとして保存するというメニューもあり。





























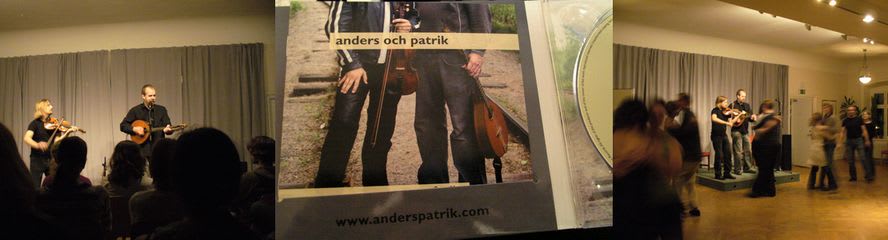





 )
)
 写真右は今日のFika(ティーブレイク) 。
写真右は今日のFika(ティーブレイク) 。
 (←ちょっと変わった雰囲気に持っていくと喜んでくれる)
(←ちょっと変わった雰囲気に持っていくと喜んでくれる)
 私も途中から参加。
私も途中から参加。
 「Make me happy.」(僕のこと喜ばせてね!)とニクラス。
「Make me happy.」(僕のこと喜ばせてね!)とニクラス。


 今日は、学校からみんなでウプサラへ。
今日は、学校からみんなでウプサラへ。
 その後は、すぐ近くのウプサラ大学のカフェテリアでランチ。
その後は、すぐ近くのウプサラ大学のカフェテリアでランチ。 原始的なのだが、まずカタログ室へ入ると、地方、ジャンルなどカテゴリー別に分かれた小さな引き出しがたくさんあり、インターネットでキーワードを入力して検索するように、自分の調べたいキーワードを元に探していく。
原始的なのだが、まずカタログ室へ入ると、地方、ジャンルなどカテゴリー別に分かれた小さな引き出しがたくさんあり、インターネットでキーワードを入力して検索するように、自分の調べたいキーワードを元に探していく。



