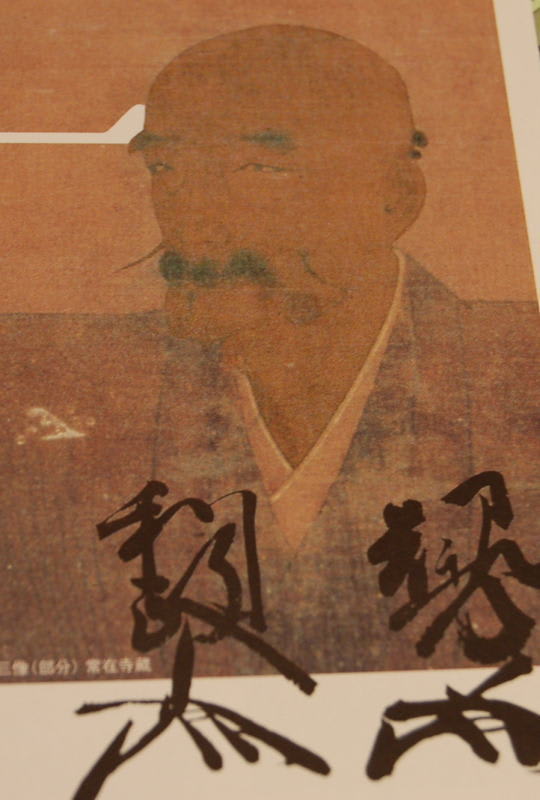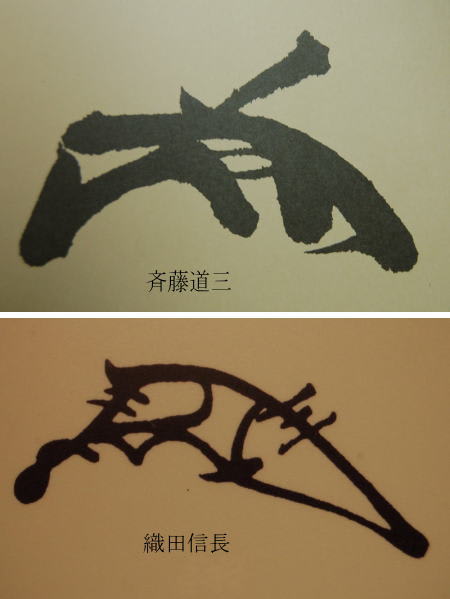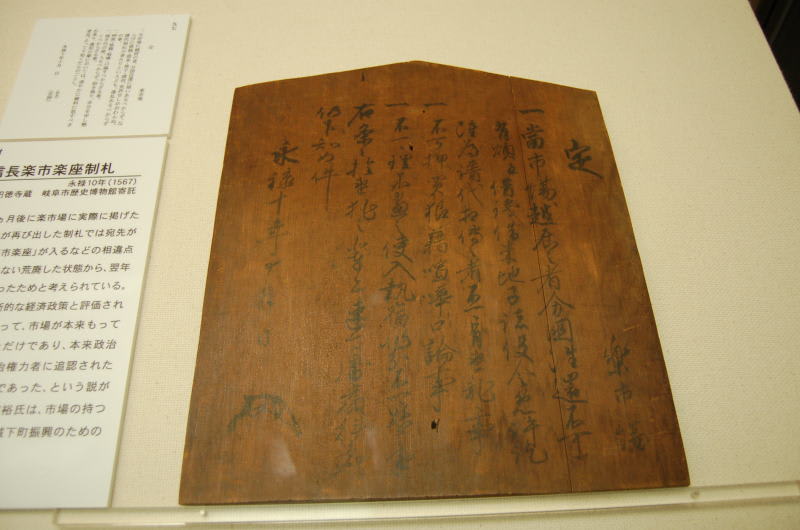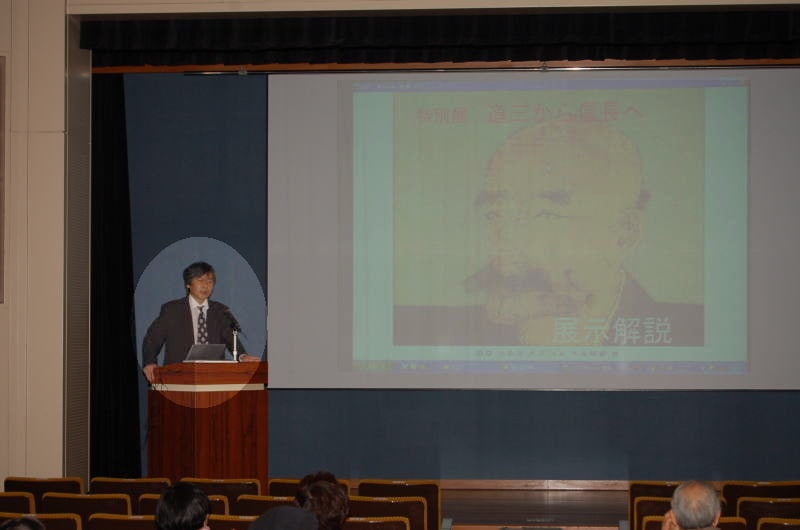歴史博物館では
「岐阜和傘を作る」と言う講座が、講師を招いて
行われました。
受講者の皆さんが今年1月2月を掛けて、
見事和傘を完成させました。
そこで、折角作った和傘、飾っておくだけでは
意味がないということで、受講者全員で歴史博物館の周囲を
傘を差して歩こうという提案があり、実現しました。
その様子を同行して撮りましたのでご覧あれ!!
番傘、蛇の目傘、とりどりです。
歴史博物館前で記念撮影。

雨が降ってるように見えますが、曇ってはいるものの
雨は全く降ってなくて良かったって感じです。

途中の公園内では銅像等の説明に耳を傾けました。

三重の塔をバックに記念撮影。
今回の町歩き提案者の○川さんです。

和傘はカラフルで、独特の雰囲気がありますね。


長良川河畔にある護国神社へ......

護国神社前には「鵜飼桜」があり、そこでしばし記念撮影です。


和服にはこーもり傘は似合わない、やはり和傘です。

川原町を歩いて終了でした。お疲れ様!

岐阜市歴史博物館
アスカと花と散策
「岐阜和傘を作る」と言う講座が、講師を招いて
行われました。
受講者の皆さんが今年1月2月を掛けて、
見事和傘を完成させました。
そこで、折角作った和傘、飾っておくだけでは
意味がないということで、受講者全員で歴史博物館の周囲を
傘を差して歩こうという提案があり、実現しました。
その様子を同行して撮りましたのでご覧あれ!!
番傘、蛇の目傘、とりどりです。
歴史博物館前で記念撮影。

雨が降ってるように見えますが、曇ってはいるものの
雨は全く降ってなくて良かったって感じです。

途中の公園内では銅像等の説明に耳を傾けました。

三重の塔をバックに記念撮影。
今回の町歩き提案者の○川さんです。

和傘はカラフルで、独特の雰囲気がありますね。


長良川河畔にある護国神社へ......

護国神社前には「鵜飼桜」があり、そこでしばし記念撮影です。


和服にはこーもり傘は似合わない、やはり和傘です。

川原町を歩いて終了でした。お疲れ様!

岐阜市歴史博物館
アスカと花と散策