2011年9月23日(金)、木曽駒ケ岳に行きました。
新田次郎の小説「聖職の碑(いしぶみ)」を読んだ。
約100年前の大正2年(1913年)の8月27日、
木曽駒ケ岳で実際に起こった遭難事件を題材にした小説です。
宿泊を予定していた山小屋が焼失していた上に、
急に北上してきた台風の暴風雨に見舞われるという、
不運が重なり、子供を含む11名が凍死するという話だった。
遭難シーンがとても迫力があり、どんな場所か実際に見たくなった。
ならば直ぐに・・ということで、木曽駒ケ岳に行ってきました。
コースマップ 赤:9/23(土) 青:9/24(日)
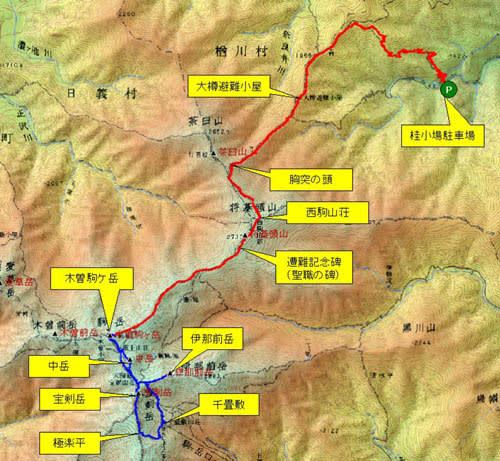
桂小場の駐車場 (下山時に撮影)
ヤマケイ・アルペンガイドには5台くらいの駐車スペース・・と書いてありましたが、
15~20台くらいは停められそうでした。

桂小場の登山口を午前6時に出発。
やたら寒いです。 もう秋ですね。

桂小場からの登山道は、良く整備されており、とても歩きやすかった。
1時間ほどで水場に到着。 今日は寒いから見るだけで通過です。

権兵衛峠への分岐

白川分岐

大樽避難小屋
このあたりから胸突八丁の急登が始まる。

津島神社

ここにはヒカリゴケがありました。

アサヒビールからの寄付金で登山道が整備されていた。

小さな赤い石碑(三角測量の石標か?)を通過したら、そろそろ急登も終わりだ。

ほどなく、胸突きの頭に到着。
ここからは緩やかな道になる。 ヤレヤレ。

分水嶺

稜線に出たところで振り返る。 たぶん、これが茶臼山だろう。

少し先に、夏道への分岐があった。

昔はこの夏道はなく、遭難した中学生たちは稜線コースを歩いたらしい。
夏道を歩き、西駒山荘に到着。

100年前には、この山小屋はありませんでした。
遭難事件の後、しばらくしてから建てられたそうです。
小屋の広場のベンチで休憩

山小屋の広場なのに誰もいないな・・と思っていたら1人登って来て通り過ぎていきました。
これが将棊頭山で・・

こっちが将棊ノ頭だ。 ややこいい名前だ。

西駒山荘を出発して小さな丘を越えると、素晴らしい景色が待ってました。
登ってきて良かった~

そして、丘を下っていくと、コレがありました。
遭難記念碑(聖職の碑)です! とても大きい。


小説「聖職の碑」を持参しました。
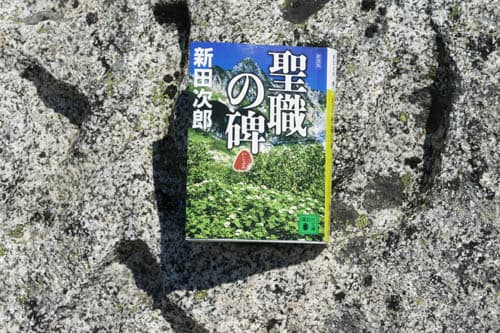
先ほどから歩いてきた胸突きの頭~遭難記念碑までの稜線は、
遭難事件で死んだ11人のうち9人が力尽きて凍死した場所です。。
稜線上は隠れる場所もなく、強烈な雨と風を受けて体温を急速に奪われたのだそうです。
気の毒に・・と思って、手を合わせました。
今日は、ここで引き返すつもりでしたが、
荷物が軽かったおかげで、予定より早く到着できました。
どうしようか迷いましたが、この景色を見たら引き返せません。
写真中央が木曽駒ケ岳

伊那前岳

引き込まれるように、馬の背の稜線に進みました。
あれが濃ヶ池だな。

テント場が見えるようになった。 そろそろ山頂だ。

そして、木曽駒ケ岳山頂に到着。


伊那前岳~中岳

中岳~宝剣岳

登って来た馬ノ背の稜線

午前11頃までは山頂付近は快晴だったのですが、
私の到着したお昼の12時ごろには山頂付近にガスが出てきました。
あと1時間早く出発すれば良かった・・。
山頂でお昼を食べ少し休んだら、登ってきた道を戻ります。
ガスで眺めは悪く、午後3時ごろにはかなり雲が増えてきて雨が降るかと思ったほどでした。
今日は木曽駒ケ岳にピストンするだけで精一杯だったので、
明日はロープウエーに乗って千畳敷に行くことにします。
新田次郎の小説「聖職の碑(いしぶみ)」を読んだ。
約100年前の大正2年(1913年)の8月27日、
木曽駒ケ岳で実際に起こった遭難事件を題材にした小説です。
宿泊を予定していた山小屋が焼失していた上に、
急に北上してきた台風の暴風雨に見舞われるという、
不運が重なり、子供を含む11名が凍死するという話だった。
遭難シーンがとても迫力があり、どんな場所か実際に見たくなった。
ならば直ぐに・・ということで、木曽駒ケ岳に行ってきました。
コースマップ 赤:9/23(土) 青:9/24(日)
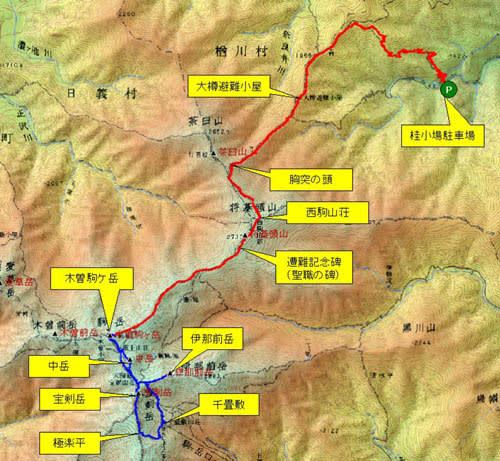
桂小場の駐車場 (下山時に撮影)
ヤマケイ・アルペンガイドには5台くらいの駐車スペース・・と書いてありましたが、
15~20台くらいは停められそうでした。

桂小場の登山口を午前6時に出発。
やたら寒いです。 もう秋ですね。

桂小場からの登山道は、良く整備されており、とても歩きやすかった。
1時間ほどで水場に到着。 今日は寒いから見るだけで通過です。

権兵衛峠への分岐

白川分岐

大樽避難小屋
このあたりから胸突八丁の急登が始まる。

津島神社

ここにはヒカリゴケがありました。

アサヒビールからの寄付金で登山道が整備されていた。

小さな赤い石碑(三角測量の石標か?)を通過したら、そろそろ急登も終わりだ。

ほどなく、胸突きの頭に到着。
ここからは緩やかな道になる。 ヤレヤレ。

分水嶺

稜線に出たところで振り返る。 たぶん、これが茶臼山だろう。

少し先に、夏道への分岐があった。

昔はこの夏道はなく、遭難した中学生たちは稜線コースを歩いたらしい。
夏道を歩き、西駒山荘に到着。

100年前には、この山小屋はありませんでした。
遭難事件の後、しばらくしてから建てられたそうです。
小屋の広場のベンチで休憩

山小屋の広場なのに誰もいないな・・と思っていたら1人登って来て通り過ぎていきました。
これが将棊頭山で・・

こっちが将棊ノ頭だ。 ややこいい名前だ。

西駒山荘を出発して小さな丘を越えると、素晴らしい景色が待ってました。
登ってきて良かった~

そして、丘を下っていくと、コレがありました。
遭難記念碑(聖職の碑)です! とても大きい。


小説「聖職の碑」を持参しました。
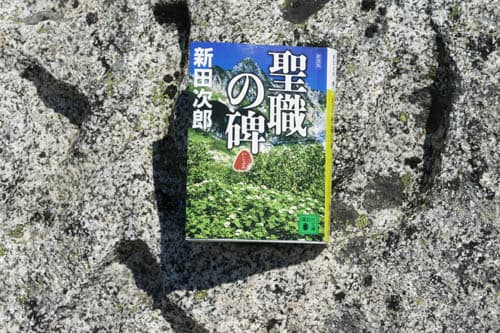
先ほどから歩いてきた胸突きの頭~遭難記念碑までの稜線は、
遭難事件で死んだ11人のうち9人が力尽きて凍死した場所です。。
稜線上は隠れる場所もなく、強烈な雨と風を受けて体温を急速に奪われたのだそうです。
気の毒に・・と思って、手を合わせました。
今日は、ここで引き返すつもりでしたが、
荷物が軽かったおかげで、予定より早く到着できました。
どうしようか迷いましたが、この景色を見たら引き返せません。
写真中央が木曽駒ケ岳

伊那前岳

引き込まれるように、馬の背の稜線に進みました。
あれが濃ヶ池だな。

テント場が見えるようになった。 そろそろ山頂だ。

そして、木曽駒ケ岳山頂に到着。


伊那前岳~中岳

中岳~宝剣岳

登って来た馬ノ背の稜線

午前11頃までは山頂付近は快晴だったのですが、
私の到着したお昼の12時ごろには山頂付近にガスが出てきました。
あと1時間早く出発すれば良かった・・。
山頂でお昼を食べ少し休んだら、登ってきた道を戻ります。
ガスで眺めは悪く、午後3時ごろにはかなり雲が増えてきて雨が降るかと思ったほどでした。
今日は木曽駒ケ岳にピストンするだけで精一杯だったので、
明日はロープウエーに乗って千畳敷に行くことにします。



















