アメリカの心理学者Klaus F. Riegelが書いた"A dialectical interpretation of time and change"の一節。
人間の発達というものは、業績やテストの点のような、その人が残した物によって捉えられるべきものではありません。そうではなく、人間の発達は、その人が経験した過去について注意深く意識することで初めて理解できるのです。なぜならば、過去の経験は、個人のなかに積み重なっていき、その人を未来へと向かわせる力となるからなのです。
The development of the individual, likewise, should no longer be apprehended by the products left behind, such as achievements and test scores but by the critical awareness of past experiences, which remain with the individuals and direct them for their future.(p.96)
過去に成し得た業績ではなく、それをとおして、心のなかに蓄えられた経験こそが人を未来へと向かわせる原動力になる。こうして人々は、過去と現在と未来をつないで生きていく。
人間の発達というものは、業績やテストの点のような、その人が残した物によって捉えられるべきものではありません。そうではなく、人間の発達は、その人が経験した過去について注意深く意識することで初めて理解できるのです。なぜならば、過去の経験は、個人のなかに積み重なっていき、その人を未来へと向かわせる力となるからなのです。
The development of the individual, likewise, should no longer be apprehended by the products left behind, such as achievements and test scores but by the critical awareness of past experiences, which remain with the individuals and direct them for their future.(p.96)
過去に成し得た業績ではなく、それをとおして、心のなかに蓄えられた経験こそが人を未来へと向かわせる原動力になる。こうして人々は、過去と現在と未来をつないで生きていく。










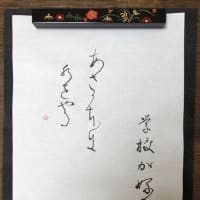
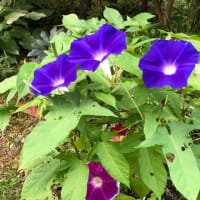








学校を解明するのと一緒に、人が成長するってなんだろう、と興味を持ちました。オリジナリティあふれる保育園と学童で育ったため、クラスの子とは行動も発想も一致することが少なかったのが、きっかけかもしれません。大学入るまでになんとなく思っていたことは、日本人が挫折する出来事はかなり共通している(受験とか親との確執とか)し、その数は少ない。成長していく過程で人格が形成されていくから、今の自分は過去の蓄積の表れである。人を理解するときは、現在の生活も大切だけど、育った環境も重要である。
大学で発達心理とか学習心理とか教育心理とか感情・思考・志向の発達の変化を勉強したとき、西平直喜さんの「成人(おとな)になること―生育史心理学から」に出会って、やっぱりそうだったんだと腑に落ちました。
(「脱学校論」も衝撃的でしたが、それ以上のものがありました)
今、私は期待していることと実際に成せることのギャップが大きくて焦っています。今日の「過去から未来へ」を読んで、そんなに焦らなくていいのかなと思いました。そして、西平さんの本を思い出しました。
「過去に成し得た業績ではなく、それをとおして、心のなかに蓄えられた経験こそが人を未来へと向かわせる原動力になる」とは上手いことを言いますねえ。
確かにそうですね。
こころに蓄えられた自分の経験が未来を作っていくのだと思います。
日常生活の何気ない経験は、すぐに忘れてしまいますが、決して消え去ることはありません。心のなかに静かに蓄積されていきます。そうした「自覚」されない経験も、同じように大事なものでしょう。未来を作るという意味で。
>心のなかに蓄えられた経験こそが人を未来へと向かわせる原動力になる。こうして人々は、過去と現在と未来をつないで生きていく。
わたしはまだまだ何が過去で未来なのか分からず、バラバラの状態です。時々、自分がバラバラになりそうで怖くなります。今、カウンセリングを通してそれをつないでいます。
過去・現在・未来をつないで生きていけるようになりたいです。