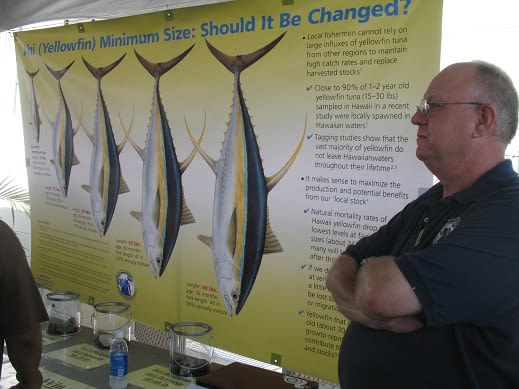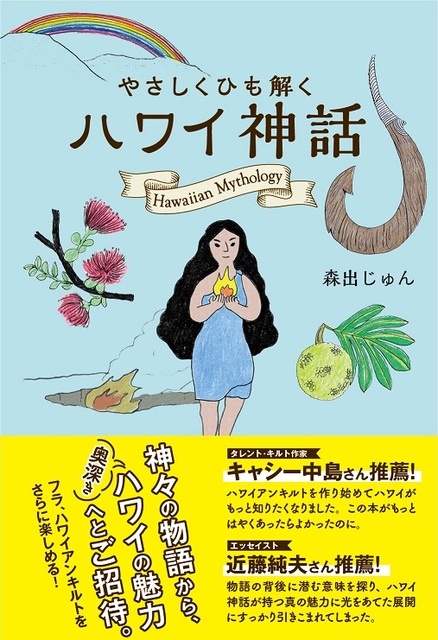3月末に家族でハワイ島のキラウエア火山を訪れた際。キラウエアの火口の一つである、キラウエア・イキ・クレーターを縦断するハイキングを楽しみました。

キラウエア・イキ・クレーターは直径約6.4キロ。1959年の噴火でできた火口だそうで、それ以前、この火口は森で覆われ、今の倍の深さがあったそうです。それが1959年に火口が爆発して、なんと1200度というキラウエア観測史上最高の熱い溶岩が噴き出し、森を埋め尽くしてしまったそうです! 火口内ではほぼ平らな溶岩平原が続きますが、場所によっては、まだ少~しだけ、スチームが吹き出していました。
一帯はほぼ溶岩の野原なのですが、オヒア・レフアの木はもちろん、いくつかの植物がたくましく育っていました。ベリー状の実がなっているのは、オヘロベリー。ハワイではジャムの材料になったりしています。元々オヘロベリーは火山の女神ペレに帰属する植物だそうで、最初の1粒はペレに捧げてから食べないと、ペレが怒って火山が噴火する、と信じられています。


オヘロベリーは以前、ハレアカラ火山の火口でキャンプした際に見たことがあったのですが、キラウエアでこれを見たのは、恥ずかしながら今回が初めてでした。
そんな溶岩性?の植物を見たり、きてれつな溶岩の形状を楽しみながら、けっこうアッという間、2時間のハイキングで火口を縦断。今度はきつい登り坂を登って、クレーター・リム・ロードに到着しました。計2時間30分の、別世界のハイキングを楽しみました。いい汗かきました~。

最後の登り坂の30分は、シダなどが鬱蒼と茂る森の中を歩くので、なんだかドクター・スウスの絵本に出てきそうな不思議な植物もあちこちに。

ハワイは海もいいですが、山もまた深いので、ハイキングも楽しいですよね。ああ、写真を見ていたらまた、キラウエアに戻りたくなってきました。女神ペレが私を呼んでいる…のでしょうか?