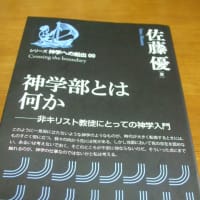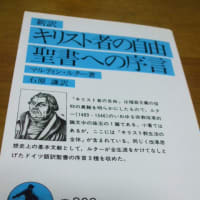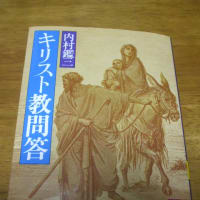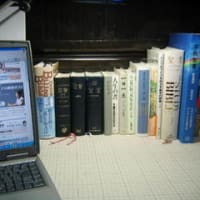つづき
旧約聖書略解 日本基督教団出版局 をまとめて
『召されぬまま王宮の庭に立ったエステルに、王は「金の笏を差し伸べた」。それは彼女が死を免れ王の好意を勝ち得たことを示す。
エステルは王とハマンを今日酒宴に招待したいと申し出る。
エステルは、王の面前で対決する覚悟でハマンの同席を求める。
それとは知らず王妃の私的な招待に有頂天のハマンの様子を伝える。
その日エステルは王に真意を打ち明けず、明日もう一度酒宴を準備するので「ハマンと一緒にお出ましください」と述べるにとどまる。
時間をかけて相手を油断させ、事態を有利に導こうとする戦略だろうか。
結果としてこの延期は、その夜のうちに舞台の大逆転を準備することになった。
酒宴の帰途、ハマンは再び王宮の門で何の敬意も表さないモルデカイを見て、怒りがこみ上げる。
ただモルデカイ一人の存在ゆえに「そのすべてが私にはむなしいものとなる」とハマンは告白せざるを得ない。』
新聖書講解シリーズ エズラ記・ネヘミヤ記・エステル記 いのちのことば社 をまとめて
『本章には王とエステル、ハマンとモルデカイの四人の主要人物が一斉に登場し、四人の性格が浮き彫りにされている。
さて、本章において、教えられる第一のことは、明け渡された心の確信と自由についてである。
禁を犯して王宮の内庭に立つエステルのその時の心境ほど澄んだものはなかったであろう。
「われもし死ぬべくば死ぬべし」と、神の御旨の中に自らは完全に明け渡された。
教えられる第二のことは、神のしもべの知恵と分別についてである。
エステルは王に自分の本心をすぐには打ち明けなかった。
エステルは機会をうかがい、時を待った。王に心中を打ち明けるための最も効果的な環境を作るためであった。
エステルのこの知恵と分別に学びたい。
1、彼女は人の心を動かすためには食事を共にすることが極めて有効である、という実際的知恵を持ち合わせていた。
2、招待を繰り返し、その秘密の願いを持ち出すことを遅らせることによって事の重大性をにおわせ、王の興味と関心を倍加させた。
3、ハマンを共に招くことによって、彼を有頂天にさせ、その心にすきを作り、彼を彼女の圏内に引き込んでしまった。
4、「もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしくて、私の願いをゆるし、私の望みがかなえていただけますなら・・・・あす、私は王様のおっしゃったとおりにいたします」と、エステルの願いから王の命令へと主導権を完全に王に移した。
こうしたエステルの知恵と分別は、御霊の賜物であろう。
祈りつつ、神の知恵を求めつつ、エステルは一歩一歩慎重に駒を進めていった。
本章における最後の学びは、ハマンに見る人間の恐るべき邪悪性についてである。
虚栄・頑迷・貪欲・高慢・残忍などのいずれもが、ハマンの性格をよく表している。
しかも不思議なことに彼はその輝かしい富を誇り、子供の多きを誇り、王や王妃と共に国の最高位に上げられたことを自慢しつつも、それでもなおあくなき成功を望んでは憂鬱になっているのである。
一国の大宰相ともあろう者が、たった一人の役人の行動が気になり、それによって彼の誇りも、喜びも奪われてしまうとは、不思議である。
しかし、ハマンに見る人間の恐るべき邪悪性はよそごとではない。
今、われらの内に巣くうハマン的精神があるなら、それこそが木にかけられ、のろわれ、完全な終焉を遂げなければならない。』
お祈りしますm(_ _)m
恵み深い天の父なる神さま
沢山の財産や地位を持つ人間でさえ、ただ一人の自分に敬意を示さない人間の行いに、
怒りをこみ上げさせて、すべてをむなしく思わせてしまう、弱さを持っています。
モルデカイの信仰の強さをおもう時、ハマンの弱さをもおもいます。
ハマンの自分の劣等感への裏返しなのかもしれません。
自分に対する態度で、大きく自分の感情を左右してしまうところが、ハマンと自分を重ねあわせるところでもあります。
弱さによる怒りで、さらに多くの罪を犯してしまうことのないよう、神の憐れみを祈るばかりです。
主イエス・キリストの御名によって、お祈りします。
アーメン
旧約聖書略解 日本基督教団出版局 をまとめて
『召されぬまま王宮の庭に立ったエステルに、王は「金の笏を差し伸べた」。それは彼女が死を免れ王の好意を勝ち得たことを示す。
エステルは王とハマンを今日酒宴に招待したいと申し出る。
エステルは、王の面前で対決する覚悟でハマンの同席を求める。
それとは知らず王妃の私的な招待に有頂天のハマンの様子を伝える。
その日エステルは王に真意を打ち明けず、明日もう一度酒宴を準備するので「ハマンと一緒にお出ましください」と述べるにとどまる。
時間をかけて相手を油断させ、事態を有利に導こうとする戦略だろうか。
結果としてこの延期は、その夜のうちに舞台の大逆転を準備することになった。
酒宴の帰途、ハマンは再び王宮の門で何の敬意も表さないモルデカイを見て、怒りがこみ上げる。
ただモルデカイ一人の存在ゆえに「そのすべてが私にはむなしいものとなる」とハマンは告白せざるを得ない。』
新聖書講解シリーズ エズラ記・ネヘミヤ記・エステル記 いのちのことば社 をまとめて
『本章には王とエステル、ハマンとモルデカイの四人の主要人物が一斉に登場し、四人の性格が浮き彫りにされている。
さて、本章において、教えられる第一のことは、明け渡された心の確信と自由についてである。
禁を犯して王宮の内庭に立つエステルのその時の心境ほど澄んだものはなかったであろう。
「われもし死ぬべくば死ぬべし」と、神の御旨の中に自らは完全に明け渡された。
教えられる第二のことは、神のしもべの知恵と分別についてである。
エステルは王に自分の本心をすぐには打ち明けなかった。
エステルは機会をうかがい、時を待った。王に心中を打ち明けるための最も効果的な環境を作るためであった。
エステルのこの知恵と分別に学びたい。
1、彼女は人の心を動かすためには食事を共にすることが極めて有効である、という実際的知恵を持ち合わせていた。
2、招待を繰り返し、その秘密の願いを持ち出すことを遅らせることによって事の重大性をにおわせ、王の興味と関心を倍加させた。
3、ハマンを共に招くことによって、彼を有頂天にさせ、その心にすきを作り、彼を彼女の圏内に引き込んでしまった。
4、「もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしくて、私の願いをゆるし、私の望みがかなえていただけますなら・・・・あす、私は王様のおっしゃったとおりにいたします」と、エステルの願いから王の命令へと主導権を完全に王に移した。
こうしたエステルの知恵と分別は、御霊の賜物であろう。
祈りつつ、神の知恵を求めつつ、エステルは一歩一歩慎重に駒を進めていった。
本章における最後の学びは、ハマンに見る人間の恐るべき邪悪性についてである。
虚栄・頑迷・貪欲・高慢・残忍などのいずれもが、ハマンの性格をよく表している。
しかも不思議なことに彼はその輝かしい富を誇り、子供の多きを誇り、王や王妃と共に国の最高位に上げられたことを自慢しつつも、それでもなおあくなき成功を望んでは憂鬱になっているのである。
一国の大宰相ともあろう者が、たった一人の役人の行動が気になり、それによって彼の誇りも、喜びも奪われてしまうとは、不思議である。
しかし、ハマンに見る人間の恐るべき邪悪性はよそごとではない。
今、われらの内に巣くうハマン的精神があるなら、それこそが木にかけられ、のろわれ、完全な終焉を遂げなければならない。』
お祈りしますm(_ _)m
恵み深い天の父なる神さま
沢山の財産や地位を持つ人間でさえ、ただ一人の自分に敬意を示さない人間の行いに、
怒りをこみ上げさせて、すべてをむなしく思わせてしまう、弱さを持っています。
モルデカイの信仰の強さをおもう時、ハマンの弱さをもおもいます。
ハマンの自分の劣等感への裏返しなのかもしれません。
自分に対する態度で、大きく自分の感情を左右してしまうところが、ハマンと自分を重ねあわせるところでもあります。
弱さによる怒りで、さらに多くの罪を犯してしまうことのないよう、神の憐れみを祈るばかりです。
主イエス・キリストの御名によって、お祈りします。
アーメン