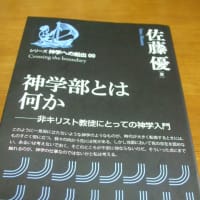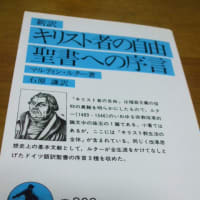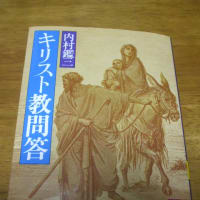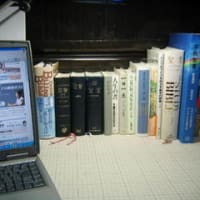前回の投稿から、ほんとに長いこと間が空いてしまった(⌒◇⌒;)ああ
仕事が忙しくなったからと、言い訳できない。
世の煩いに悩まされていたと、言い訳できない。
いかんなああああ。
サタンに負けてはいけない。
神さまから離れてはいけない。
サタンは神さまから離れさせようといつも人間を世の煩いへ誘惑している。
サタンに打ち勝つために、聖書ブログを投稿しようと注解書を開いてみた。
が、この聖書箇所の注解は、難しくて頭が混乱してきた。
まとめられない(⌒◇⌒;)
うががが。
大変!!!
ので、ほとんど、そのまま転記のようになってしまう。
でも、ぼつぼつと進んでいくしかないな。
では。
つづき
新約聖書略解 日本基督教団出版局 を、まとめて。
『全人類の罪が弁解の余地なく明らかにされた今、信仰による義が定義され、解説される。
21節「ところが今や」というこの新しい書き出しは、長い人類の罪の歴史からそれが終止符を打たれる瞬間へと読者を導く。
パウロの言行のすべてはこの歴史の終わりに立つという意識によって規定されている。
新約聖書の各文書は、終末に関して、それはイエスの出来事によって実現したという「現在的終末論」とそれはやがて来るという「未来的終末論」との間で様々に考えられている。
パウロの場合「いまだ」と「すでに」の緊張関係の中で終末は既に始まっていると意識されている。
この意識に支えられて「神の義」が新しく終末の出来事そのものとしてとらえ直される。この場合「義」は、単に神の属性や性質、正義とか恩義といった道徳的・社会的徳目ではなく、人間と神との関係を作り出す救いの働きを意味する。
この終末論的出来事は、前段までの確認から明らかなように「律法と預言者によって立証されて」示される。
キリスト教徒が「旧約聖書」と呼んでいるものをユダヤ教徒は正式には「律法と預言者たちと諸書」あるいは略して「律法と預言者」または短く「律法」と呼ぶ。
キリスト教徒はそれをキリスト証言として理解する。
パウロは律法のわざによる救いは否定するが、神の民の歴史における神のわざと福音の連続性は重視する。
22節「神の義」は律法の所有ではなく、「イエス・キリストを信じること」によって「信じる者すべてに与えられる。
これを「イエス・キリストの真実によりすべての信仰者に」と解することも不可能ではないが、全体の文脈からは新共同訳が自然であろう。
罪の普遍性に対応してここでは信仰の普遍性が「そこには何の差別も」ないと強調される。
23節は罪の普遍性が個々人の罪の現実に対応していることを明らかにしている。
原罪が個人の罪過として現実となることは5・12以降で再度取り上げられる。
「栄光は古代人にとっては具体的に夜空の星の輝きであり、正しい人々が終わりの日にそれに浴するという希望と結びついたイメージであるが、これは神の似像を意味し、アダムの堕罪によって失われてしまったものである。
パウロは普遍性の議論を罪のそれから信仰のそれへと移行させ
24~26節に贖罪論的キリスト論の伝承を導入する。』
つづく
仕事が忙しくなったからと、言い訳できない。
世の煩いに悩まされていたと、言い訳できない。
いかんなああああ。
サタンに負けてはいけない。
神さまから離れてはいけない。
サタンは神さまから離れさせようといつも人間を世の煩いへ誘惑している。
サタンに打ち勝つために、聖書ブログを投稿しようと注解書を開いてみた。
が、この聖書箇所の注解は、難しくて頭が混乱してきた。
まとめられない(⌒◇⌒;)
うががが。
大変!!!
ので、ほとんど、そのまま転記のようになってしまう。
でも、ぼつぼつと進んでいくしかないな。
では。
つづき
新約聖書略解 日本基督教団出版局 を、まとめて。
『全人類の罪が弁解の余地なく明らかにされた今、信仰による義が定義され、解説される。
21節「ところが今や」というこの新しい書き出しは、長い人類の罪の歴史からそれが終止符を打たれる瞬間へと読者を導く。
パウロの言行のすべてはこの歴史の終わりに立つという意識によって規定されている。
新約聖書の各文書は、終末に関して、それはイエスの出来事によって実現したという「現在的終末論」とそれはやがて来るという「未来的終末論」との間で様々に考えられている。
パウロの場合「いまだ」と「すでに」の緊張関係の中で終末は既に始まっていると意識されている。
この意識に支えられて「神の義」が新しく終末の出来事そのものとしてとらえ直される。この場合「義」は、単に神の属性や性質、正義とか恩義といった道徳的・社会的徳目ではなく、人間と神との関係を作り出す救いの働きを意味する。
この終末論的出来事は、前段までの確認から明らかなように「律法と預言者によって立証されて」示される。
キリスト教徒が「旧約聖書」と呼んでいるものをユダヤ教徒は正式には「律法と預言者たちと諸書」あるいは略して「律法と預言者」または短く「律法」と呼ぶ。
キリスト教徒はそれをキリスト証言として理解する。
パウロは律法のわざによる救いは否定するが、神の民の歴史における神のわざと福音の連続性は重視する。
22節「神の義」は律法の所有ではなく、「イエス・キリストを信じること」によって「信じる者すべてに与えられる。
これを「イエス・キリストの真実によりすべての信仰者に」と解することも不可能ではないが、全体の文脈からは新共同訳が自然であろう。
罪の普遍性に対応してここでは信仰の普遍性が「そこには何の差別も」ないと強調される。
23節は罪の普遍性が個々人の罪の現実に対応していることを明らかにしている。
原罪が個人の罪過として現実となることは5・12以降で再度取り上げられる。
「栄光は古代人にとっては具体的に夜空の星の輝きであり、正しい人々が終わりの日にそれに浴するという希望と結びついたイメージであるが、これは神の似像を意味し、アダムの堕罪によって失われてしまったものである。
パウロは普遍性の議論を罪のそれから信仰のそれへと移行させ
24~26節に贖罪論的キリスト論の伝承を導入する。』
つづく