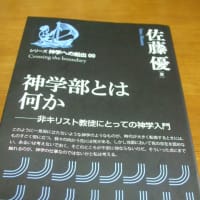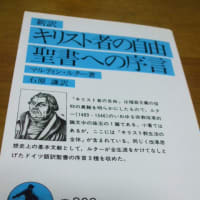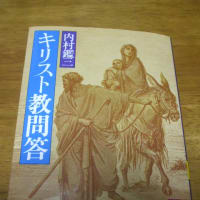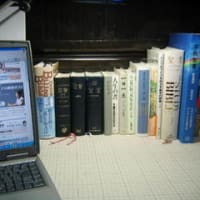つづき
新約聖書注解Ⅱ を、まとめて。
『前節までの異教世界に向けられていた議論のほこさきが、突如ユダヤ人に向けられる。
神を知らないという言い逃れを封じた今、神を知ることをその最大の特権と考えたユダヤ人が槍玉にあげられる。
「あなた」と指弾されているのは直接的にはユダヤ教徒であるが、ユダヤ人キリスト教徒も観客席で傍観者を決め込むことはできない。
律法を持っていると誇る「ユダヤ人」は救いの道を自分たちは知っていると主張するあらゆる人間の典型として理解されているからである。
問題は民族としてのユダヤ人ではなく、自分は神を知っていると称して「人を裁く者」なのである。
自分を棚に上げて人を裁くことは、神を知らないことと同様、「弁解の余地」のない「罪」だからである。
「人を裁くな」という一般的な倫理的戒めがここでは、神を知らない異邦人を裁くユダヤ人に適用されている。
「神の裁き」は、5節の「怒りの日」、16節の「裁かれる日」から明らかなように、終末の時に行われる最後の審判を意味している。
「悔い改め」は、単に心を改めるということではなく、生き方を全面的に変え、神に帰ることである。
そしてこれは「神の憐れみ」が引き起こすことなのであるが、自らの悪行に対する無自覚と、その原因である背信はこれを認めず、神の豊かな憐れみである「慈愛と寛容と忍耐」が彼らに悔い改めの機会を与えていることに気付かない。
むしろ彼らはそれをよいことに自分勝手な生活を続け、神が彼らに対し弱く無力であるかのように、神をないがしろにしている。
パウロはこれを「かたくな」と総括的に断定する。
それはパウロのユダヤ教徒に対する基本的な評価でもある。
神の憐れみを拒否することは、神の怒りを最後の日まで自分のために「蓄えている」ことにほかならない。
「神はおのおのの行いに従ってお報いにな」るからである。
各自の行いによって報いる、というパウロの主張は、信仰によって救われる、という信仰義認と矛盾すると考えて、この矛盾を解こうとする試みが主としてプロテスタントの解釈者の中でなされてきた。
例えば、これはパウロがユダヤ教の立場に立って仮定的に語っているとか、福音が来る前の状態を回顧しているに過ぎないとか、この議論はそれ自体未整理であるとか、信仰は出発点であって行為によって仕上げられるのでなければならないとかいった議論がなされてきた。
こうした議論の背後には、信仰か行為かといった誤った二者択一が存すると思われる。
信仰は神の憐れみの下に身を置くという人間の態度である。
この態度の有無が人間を二分する。
7節以降にパウロはこの二種類の人間の間を、従来の「ユダヤ人とギリシア人」という二分法を越えるものとして提示する。
ここでは「栄光と誉れと不滅のものを求める者」が「善を行う者」として一方に、
「反抗心にかられ、真理ではなく不義に従う者」が「悪を行う者」としてもう一方におり、
前者には「栄光と誉れと平和」と「永遠の命」が、後者には「怒りと憤り」とその結果としての「苦しみと悩み」が与えられるとされる。
後者の「悪」はその内容から、倫理的というよりは、宗教的・党派的色彩が強い。
この二種類の人間に対する祝福と呪いは、最終的には終末の時に与えられるものであるが、パウロにとってこの終末は間近に迫っていると考えられているため、既に現在の人間の有様として認めえるのである。
この二分法が従来の「ユダヤ人とギリシア人」という枠を超えるということは、救いに対する律法の役割を根底から問い直すことを意味する。
ユダヤ人を異邦人から区別し、救いについての特別な立場にいると誇らせる権利はこの律法の所有にあると考えられているからである。
パウロは7~10節の議論を11~12節では律法論で展開する。
「律法」(ノモス)はギリシア語で「宇宙、世界の一般法則、原理」という広い意味を持つ「法」であるが、
ユダヤ人にとっては(旧約)「聖書」そのもの、その中心をなす神の戒め、したがって神の言の啓示であり、その生活や意識のすべてを規定する絶対的基準であった。
事実、彼らはこれを所有するか否かによって人間世界を二分して考えてきた。
パウロは一応この考え方の上に立ちながら、律法を知っているかどうかが問題ではなく、つまり、「律法を聞く者」ではなく、「これを実行する者」が人間を二分すると説く。
各自の行いによって報いる、という神の公平な態度がここにも貫かれているとする。
パウロは一歩踏み出して、律法の内容が実際に生かされているところでは、「自分自身が律法なの」だと語る。
この主張をパウロが自然法を認める典拠としたりすることもあるが、これは現実的判断と体験に根ざす彼の発言であろう。
むしろ問題は、このように、神の義の消極的側面である罪について語る際に、ユダヤ人の特権ないし救いの歴史における特別な位置が失われてしまう恐れが出てきたことである。
この点については三章で再度取り上げられる。
「律法の要求する事柄」が、「心」「良心」「心の思い」に示されると語る。
これはヘレニズム世界の通俗哲学の用語であるが、モーセが十戒を与えられる以前のアダムやノアが持っていた戒めと考えられている、人間がその自由と自覚によって己の行動を律するという行動規範をパウロはここで語っている。
しかし彼はさらに、人間は、自分を越えた、外からの声によって導かれるとも考えていると思われる。
いずれにせよ、この人間の二分法が明らかとなるのは最後の審判の「日」である。
パウロはこの結論は、自分を含む人間の議論の限界を表明するとともに、彼の議論に対する自信をも示している。』
お祈りしますm(_ _)m
恵み深い天の父なる神さま
わたしは、悔い改めのできない者です。
まったく生き方を変えられない者です。
神様、どうか憐れんでください。
「律法を聞く者」ではなく、「律法を実行する者」となれますように。
愛ある行いができる者にしてください。
主イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン
新約聖書注解Ⅱ を、まとめて。
『前節までの異教世界に向けられていた議論のほこさきが、突如ユダヤ人に向けられる。
神を知らないという言い逃れを封じた今、神を知ることをその最大の特権と考えたユダヤ人が槍玉にあげられる。
「あなた」と指弾されているのは直接的にはユダヤ教徒であるが、ユダヤ人キリスト教徒も観客席で傍観者を決め込むことはできない。
律法を持っていると誇る「ユダヤ人」は救いの道を自分たちは知っていると主張するあらゆる人間の典型として理解されているからである。
問題は民族としてのユダヤ人ではなく、自分は神を知っていると称して「人を裁く者」なのである。
自分を棚に上げて人を裁くことは、神を知らないことと同様、「弁解の余地」のない「罪」だからである。
「人を裁くな」という一般的な倫理的戒めがここでは、神を知らない異邦人を裁くユダヤ人に適用されている。
「神の裁き」は、5節の「怒りの日」、16節の「裁かれる日」から明らかなように、終末の時に行われる最後の審判を意味している。
「悔い改め」は、単に心を改めるということではなく、生き方を全面的に変え、神に帰ることである。
そしてこれは「神の憐れみ」が引き起こすことなのであるが、自らの悪行に対する無自覚と、その原因である背信はこれを認めず、神の豊かな憐れみである「慈愛と寛容と忍耐」が彼らに悔い改めの機会を与えていることに気付かない。
むしろ彼らはそれをよいことに自分勝手な生活を続け、神が彼らに対し弱く無力であるかのように、神をないがしろにしている。
パウロはこれを「かたくな」と総括的に断定する。
それはパウロのユダヤ教徒に対する基本的な評価でもある。
神の憐れみを拒否することは、神の怒りを最後の日まで自分のために「蓄えている」ことにほかならない。
「神はおのおのの行いに従ってお報いにな」るからである。
各自の行いによって報いる、というパウロの主張は、信仰によって救われる、という信仰義認と矛盾すると考えて、この矛盾を解こうとする試みが主としてプロテスタントの解釈者の中でなされてきた。
例えば、これはパウロがユダヤ教の立場に立って仮定的に語っているとか、福音が来る前の状態を回顧しているに過ぎないとか、この議論はそれ自体未整理であるとか、信仰は出発点であって行為によって仕上げられるのでなければならないとかいった議論がなされてきた。
こうした議論の背後には、信仰か行為かといった誤った二者択一が存すると思われる。
信仰は神の憐れみの下に身を置くという人間の態度である。
この態度の有無が人間を二分する。
7節以降にパウロはこの二種類の人間の間を、従来の「ユダヤ人とギリシア人」という二分法を越えるものとして提示する。
ここでは「栄光と誉れと不滅のものを求める者」が「善を行う者」として一方に、
「反抗心にかられ、真理ではなく不義に従う者」が「悪を行う者」としてもう一方におり、
前者には「栄光と誉れと平和」と「永遠の命」が、後者には「怒りと憤り」とその結果としての「苦しみと悩み」が与えられるとされる。
後者の「悪」はその内容から、倫理的というよりは、宗教的・党派的色彩が強い。
この二種類の人間に対する祝福と呪いは、最終的には終末の時に与えられるものであるが、パウロにとってこの終末は間近に迫っていると考えられているため、既に現在の人間の有様として認めえるのである。
この二分法が従来の「ユダヤ人とギリシア人」という枠を超えるということは、救いに対する律法の役割を根底から問い直すことを意味する。
ユダヤ人を異邦人から区別し、救いについての特別な立場にいると誇らせる権利はこの律法の所有にあると考えられているからである。
パウロは7~10節の議論を11~12節では律法論で展開する。
「律法」(ノモス)はギリシア語で「宇宙、世界の一般法則、原理」という広い意味を持つ「法」であるが、
ユダヤ人にとっては(旧約)「聖書」そのもの、その中心をなす神の戒め、したがって神の言の啓示であり、その生活や意識のすべてを規定する絶対的基準であった。
事実、彼らはこれを所有するか否かによって人間世界を二分して考えてきた。
パウロは一応この考え方の上に立ちながら、律法を知っているかどうかが問題ではなく、つまり、「律法を聞く者」ではなく、「これを実行する者」が人間を二分すると説く。
各自の行いによって報いる、という神の公平な態度がここにも貫かれているとする。
パウロは一歩踏み出して、律法の内容が実際に生かされているところでは、「自分自身が律法なの」だと語る。
この主張をパウロが自然法を認める典拠としたりすることもあるが、これは現実的判断と体験に根ざす彼の発言であろう。
むしろ問題は、このように、神の義の消極的側面である罪について語る際に、ユダヤ人の特権ないし救いの歴史における特別な位置が失われてしまう恐れが出てきたことである。
この点については三章で再度取り上げられる。
「律法の要求する事柄」が、「心」「良心」「心の思い」に示されると語る。
これはヘレニズム世界の通俗哲学の用語であるが、モーセが十戒を与えられる以前のアダムやノアが持っていた戒めと考えられている、人間がその自由と自覚によって己の行動を律するという行動規範をパウロはここで語っている。
しかし彼はさらに、人間は、自分を越えた、外からの声によって導かれるとも考えていると思われる。
いずれにせよ、この人間の二分法が明らかとなるのは最後の審判の「日」である。
パウロはこの結論は、自分を含む人間の議論の限界を表明するとともに、彼の議論に対する自信をも示している。』
お祈りしますm(_ _)m
恵み深い天の父なる神さま
わたしは、悔い改めのできない者です。
まったく生き方を変えられない者です。
神様、どうか憐れんでください。
「律法を聞く者」ではなく、「律法を実行する者」となれますように。
愛ある行いができる者にしてください。
主イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン