本日の日経近畿web版からです。第三セクターの北近畿タンゴ鉄道。このところ経営悪化が伝わっていますが、そんな中の31日、筆頭株主の京都府から北近畿タンゴ鉄道の一部が通っている兵庫県に対して、線路の一部を廃線にする案が打診されていたことが分かったそうだ。
2008年度からの急激な経営悪化で、自治体からの補填額が拡大。京都府は兵庫県と負担額が折り合わず、廃線を含めた経営改革を目指すという。この日までに、筆頭株主で経営権を握る京都府は、兵庫県が負担額を増やさない場合は廃線もあると伝えたとのこと。
廃止も視野に入れているのは、記事の文章では「輸送人数の少ない宮津線の兵庫県豊岡市方面で、」とあり、宮津線のどの辺りからだろうか?、天橋立駅とか、峰山駅とか、その辺りから豊岡駅までの区間を指していると思います。実際この区間は国鉄時代から輸送量が少なくそれ故、特定地方交通線に指定され、第三セクター移管となった経緯があります。
年度内に周辺自治体と交通網について検討する委員会を発足させ、仮に廃止した際の代替交通も検討するとのこと。一部区間の廃止で赤字拡大を抑制できるということですが、これはどの程度の抑制になるだろうか。地上設備の固定費は抑制できますけど。
北近畿タンゴ鉄道の赤字には、京都府と兵庫県及び沿線市町が補填しており、その額2009年度の経常赤字約7億円に、京都府からは運営助成費として約5億円。一方で兵庫県からは約1000万円であるとのこと。この兵庫県からの助成を京都府としては増やしてほしいというとこですね。
北近畿タンゴ鉄道は、宮津線西舞鶴~豊岡間83.6kmの路線と、宮福線宮津~福知山間30.4kmの二つの路線があります。宮津線は国鉄宮津線より継承した路線で、天橋立や丹後ちりめんを控えた東半分は集客があるものの、西半分は草深いローカル線。
宮福線は、鉄道建設公団建設路線が凍結された宮福線を、北近畿タンゴ鉄道が経営を引き受けることで建設が再開され、近年に開業した線路で線形も良く、後に電化されて大阪・京都からJR西日本の電車による特急が運転されています。なんでもこの3月に直通の特急は運転を止めるそうですが。
そんな北近畿タンゴ鉄道ですが、大阪・京都からの短絡効果がある宮福線にほぼ並行して京都府道路公社の綾部宮津道路が開通し、大きなライバル出現となっております。最近の経営悪化もその辺りにもあるのでしょうね。













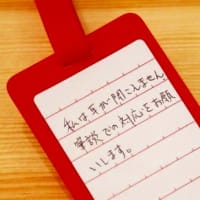
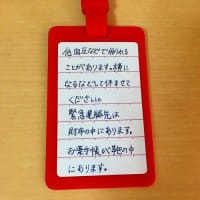





3月には大阪から天橋立への直通特急が廃止されてしまいますが
このままではますます利用客が減るような気がします。
タンゴエクスプローラーも故障が多いらしいので廃車が近いかも知れませんね。
経営は大変そうですが、一方で負担金の少ない兵庫県への圧力とも見て取れます。
宮福線の電車特急運転取りやめは、経営よりも車両が変わる点に分けがありそうです。
現在の183系が引退し、替わって新造の287系と紀勢線から転属の381系となることから、乗務員の訓練や、走行車両が変わることの国交省届出。
そんなところかと思います。
折角の丹後地方を行く鉄道ですし、このまま鉄道として、そして京都大阪からの直通列車があってほしいですね。
余談ですが明治初期、県再編の過程で、舞鶴から豊岡まで、そして福知山まで沿線の辺り一帯は、豊岡県という一つの県でした。
京都からの短絡効果はほとんど無視できる程度です。
宮津から特急に乗り、福知山乗り換えで特急で京都に行く場合、宮津から各停で西舞鶴に行っても同じ特急に乗り継ぎできることもあるくらいですよ。
京都方面ですと接続点が福知山駅ではなく綾部駅になりますので、四角形の二辺同士に近い関係となり、仰る通りになりましょうね。
宮福線は線路状態が良い(はず)なので、その分特急ですと早いような印象がありました。
公共交通の必要性と経営の問題。
いつの時代でもどこの地域でも、これは付いてまわります。
またバス・鉄道は、決してそこの自治体住民全てに便益を与えるものではありません。
駅・停留所に近く普段から乗る人は便利を感じ、そうでない人はなんら感じ得ないもので、行政の平等性から必ず論議になりやすいものですね。
まあ、天橋立ー豊岡間の廃止はもう目に見えてますね。今年の3月のダイヤ改正で、福知山線の「北近畿」「文殊」「タンゴエクスプローラー」が廃止され、「こうのとり」が新設され、運転区間も定期運用では「新大阪ー福知山」「新大阪ー豊岡」「新大阪ー城崎温泉」となり、GWや盆休みや年末年始のようにいつもの倍需要がある期間は福知山発着の一部の列車が天橋立発着に変わる形となりました。一方で、舞鶴線・山陰(嵯峨野)線の「たんば」「タンゴディスカバリー」も廃止され、「たんば」は「きのさき」、「タンゴディスカバリー」は「はしだて」「まいづる」に吸収されました。「はしだて」と聞くと天橋立のイメージが強く、京丹後市のイメージはほとんどなく、それの一部が豊岡まで延長運転する形なので、もはやこの区間の廃止は目の前と判断できます。まあそれを言い出せば、「きのさき」「こうのとり」も豊岡のイメージが強いにもかかわらず、実に7割は福知山発着、しかも「こうのとり」(臨時列車)の一部は天橋立発着なのでそれもそれでどうかと思いますが。私としては、今年、豊岡ー福知山間に新設された「たんごリレー」はKTR線全区間に調和するので、豊岡発着の「はしだて」は豊岡ー天橋立間、「こうのとり」の延長運転時は福知山ー天橋立間で「たんごリレー」として運転し、発車標上では、この区間を含めた案内をする形にしたら良いかと思いますが。
KTRの宮津線の岩滝口駅から向うは、とにかく駅ホームが短く、草深いローカル線と伺っています。
大阪・京都方面からの優等もなく、まさに一地方の交通ですね。
現在は両端で他の線路と接続しており、舞鶴・豊岡双方からの流動が期待できます。
さすがに豊岡からは県境越ですので、少ないですが。
鉄道はネットワークを保つことが大切と考えますが、昨今はまたぞろローカル線廃止の動きが増えつつあり、地元から不要との意見が多数を占められれば、廃止の動きとなるでしょう。
私がまだ足を踏み入れたことの無い土地ゆえ、細かい状況をお知らせ頂き、有難うございます。
以前、宮津線が国鉄再建法により、廃止となった時、西舞鶴~天橋立間は、廃止基準を大きく上回っていたものの天橋立~豊岡間が廃止基準に大きく達していた事が要因し、3セク化しました。宮福線が開通した事により、現在この区間は、普通列車のみの運行ながら、西舞鶴駅に基地が有るのと、景色が良いので、タンゴ悠遊号やタンゴ浪漫号が運行されている為、まだ見込みがあると判断出来ますが、天橋立~豊岡間は20年経っても不振続きなので、将来の見込みは0と考えた方が良いかと改めて思います。宮福線は、一時は工事が凍結したりしましたが、計画から約20年程後に再開して見事開通し数年後には電化され、最も経営が安定していると言えますが。
話は、変わりますが、新大阪への直通の列車廃止の一番の理由は、新大阪~天橋立間は100km以上150km未満ですが、新大阪~福知山間の地点で約110kmの為150kmまでの特急券を払い、残りの区間で50kmまでの特急券を払うので不経済→一方京都~天橋立間は、新大阪同様100km以上150km未満ですが、京都~福知山間が約90kmで100kmまでの特急券を払い、残りは50kmまでの特急券を払う為、バランスが良いからまだ残っているのだと思います。まあ、それ以外にも2005年に起きて100人余りもの死者を出した福知山線尼崎脱線事故の影響もあると思いますが。この影響で、利用客の多くが阪急や地下鉄に流れたと聞きました。
国鉄時代末期の再建特別措置法による鉄道廃止は、線名ごとに判断して行われました。
宮津線は宮津、天橋立への輸送がそこそこありましたが、その西がアカンのですよね。
区間ごとに判断することせず、政治的に処理されましたので、宮津線全線が特定地方交通線に指定され、廃止となりました。
明治の一時期、但馬と丹後は一つの豊岡県で江戸時代から交流はそこそこあった地域です。
しかし明治時代の政治的な判断で、丹後が京都府に移管され、但馬は兵庫県に行ってしまいました。
私思いますけど、旧丹後国が今は京都府なのですが、どうもしっくりきません。
兵庫県の日本海側も私が普段行く神戸近辺と気候も風土も違い、昔の豊岡県のような存在があれば、あの辺りもっと違った形で発展していたかと思います。
ちなみに福知山は国鉄時代、鉄道管理局が置かれていました。
その福知山鉄道管理局、管内に県庁所在地の駅が一つもないという管理局でした。