ツイッターで知った情報ですが、昨年(2016年)9月に起きた、茨城県筑西市の関東鉄道常総線踏切で、自転車に乗っていた小学四年生の男児が列車にはねられて死亡した事故について、国の運輸安全委員会は事故報告書を公表し、男児が列車に気付かず踏切に入った可能性が高く、当該の踏切を廃止するよう求める内容だそうです。
NHKニュースが報じております。
NHKニュース:関東鉄道常総線の遮断機などない踏切 廃止など検討を
運輸安全委員会の当該概要。こちら。
報告書本文。こちら。(PDF)
NHKニュースや報告書報告の通り、当該踏切は遮断機も警報機も無い、いわゆる「第四樹踏切」。
第四種踏切は、黄色と黒色の警戒色の柵(通称:トラ柵)があるだけの、線路横断は、横断者自身が列車の接近の有無を確認して亘るもの、とされています。
非常に安全性が低く危険なので、できうることであれば無くすべく対象となっています。
第四種踏切は、第一種化、或いは、単に踏切廃止かの対策が必要です。
第一種踏切は、遮断機と自動であれば警報機が設置されている踏切で、踏切保安方式としては最も優れているものです。
しかしながら、警報機・遮断機を設置しようとすると、一か所当たり数千万の費用がかかります。
安全のためですので、この費用は惜しむべくものではない、という理屈がありますが、中小の鉄道会社にとってはかなり厳しい出費です。
踏切廃止も簡単ではなく、踏切廃止は道路廃止とも関連があり、一鉄道会社の判断ではできず、地元自治体との協議が必要です。
なにかと厄介な第四種踏切です。
***追記***
コメントを頂きました、第二種踏切の数から、全国の事業者別、踏切道の数です、国土交通省資料より。→>こちら。
NHKニュースが報じております。
NHKニュース:関東鉄道常総線の遮断機などない踏切 廃止など検討を
運輸安全委員会の当該概要。こちら。
報告書本文。こちら。(PDF)
NHKニュースや報告書報告の通り、当該踏切は遮断機も警報機も無い、いわゆる「第四樹踏切」。
第四種踏切は、黄色と黒色の警戒色の柵(通称:トラ柵)があるだけの、線路横断は、横断者自身が列車の接近の有無を確認して亘るもの、とされています。
非常に安全性が低く危険なので、できうることであれば無くすべく対象となっています。
第四種踏切は、第一種化、或いは、単に踏切廃止かの対策が必要です。
第一種踏切は、遮断機と自動であれば警報機が設置されている踏切で、踏切保安方式としては最も優れているものです。
しかしながら、警報機・遮断機を設置しようとすると、一か所当たり数千万の費用がかかります。
安全のためですので、この費用は惜しむべくものではない、という理屈がありますが、中小の鉄道会社にとってはかなり厳しい出費です。
踏切廃止も簡単ではなく、踏切廃止は道路廃止とも関連があり、一鉄道会社の判断ではできず、地元自治体との協議が必要です。
なにかと厄介な第四種踏切です。
***追記***
コメントを頂きました、第二種踏切の数から、全国の事業者別、踏切道の数です、国土交通省資料より。→>こちら。













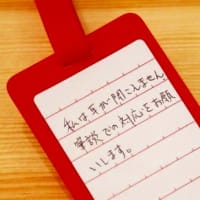
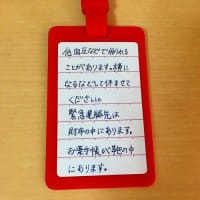





今時に第4種が有るなんて、第4種は死語と思って居ました。 こうしてみると余り何時もの踏切以外は通行して無いと言う事かな?
第2種も見た事無いですね。今も有りますか?
第4種を第1種にするのは中小鉄道会社にしたら大変なこと、 だが、何とか無くして欲しいです。
耳から目からと、どうしても2系統で知らせて呉れなくては、子供や身障者は困ります。
一番いいのは高架化ですが、 自治体は(住民)負担が大きく此れもなかなかねェ。
今の時代にも第四種踏切は、あります。
ローカル線の、しかも人(+軽車両)しか通れない踏切に残っています。
第二種は、数をお知らせしようと、本文追記の形で、国道交通省資料の全国踏切道数を載せました。
よろしければご覧ください。
第二種踏切は、一定時間、踏切掛がいて、遮断機を操作するものの、その時間外は遮断を行わず、つまり第四種踏切と同じ状態で、極めて紛らわしく、国鉄では昭和40年頃に全敗していると伺っています。
掲載した資料でも、第二種踏切は、全国数でも0となっています。
名鉄で、第四種踏切が1か所となっていますが、これ、西枇杷島駅から犬山線の砂入信号場へ至る、連絡線(三角線)とも呼ばれる線路の途中にあるもので、基本、列車は走行しません。
枇杷島の三角線の中に、かつては一軒お宅があり、そこへ至る路(法制上の道路ではなさそう)の踏切です。
今はそのお宅が無くなり、家人が通ることは無くなりましたが、屋外広告物(看板)の設置業者や、名鉄の施設が三角の中にありますので、業務用の通路として残っています。
高架化は、道路交通量との兼ね合いで、都市計画事業として行われます。
線路横断か所を、自治体単独で歩道橋で渡す方法もありますが、状況によっては、エレベータ設置の必要もあり、これも大変です。