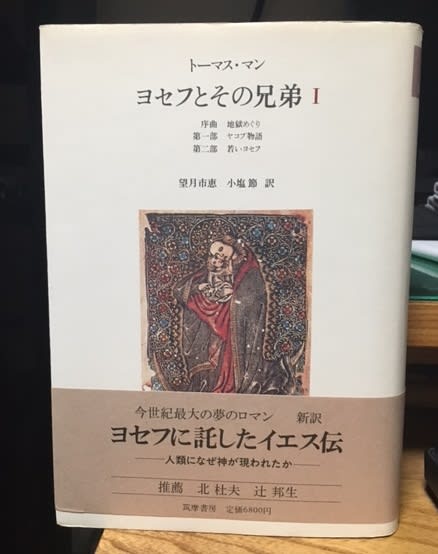トーマス・マンは創世記のヨセフとその兄弟の話を長大な小説にしたが、それを映画化しても面白いかもしれない。創世記の最初はジョン・ヒューストンが天地創造という邦題で映画にした。欧米の人と日本人でもクリスチャンなら、誰でも知ってるシーンばかり。神聖な聖書をああやって映画にするとある意味滑稽。絵画にも旧約、新約の絵は山ほどある。見ないで信じるものは幸いだと書いてあるのに、所詮人間は見ないと信用できない。聖書のどこにもイエス・キリストは長髪だったなどとは書いていないけれど、絵画でも映画でもみなイメージは統一されている。ダビンチの最後の晩餐の絵は有名だけれど、当時の食事スタイルは寝そべって食べるのが普通などと言ってもそれが問題ではないのは当たり前。ノアの箱舟の映画を観て当時の船はというのと同じ。バッハのマタイ受難曲に感動するのは聖書に忠実だからではない。バッハの信仰心、つまり人の信じる気持ちに感動する。相当前に読んだので内容を忘れてしまったが、遠藤周作の「沈黙」も強い信仰を持った人ではなく「ころぶ」といって信仰を捨てる人が主題ではなかっただろうか。ヨーロッパの教会へ行っても若者はほとんどいない。こちらで思うほど熱心に信じているわけではないが、たぶん子供の頃から宗教の時間はあるから根にあるのはキリスト教。その程度だから強い信仰心であるわけがない。「洟たれ小僧がアメリカで常任指揮者になったといってピアノを買う手合いは、大騒ぎしているらしいが「マタイ受難曲」は彼には振れまい。」と五味康祐は書いている。洟たれというのはボストンの指揮者になった小澤征爾のこと。何だかんだといってもキリスト教は欧米人の奥底にあるもので、いい環境ならもちろん厳しい環境でも神父、牧師が街にいて心の支えになっている場合もあるのかと想像する。だから神はいるが前提なので無神論が出てくる。日本は神はいないが前提なので無神論だといっても、あなたに一度でも神はいたことあるのかになる。でも五味康祐のいうことはどうか。小澤征爾の評価はさておいて日本人は受難曲どころかバッハも演奏できないということはあるまい。評論家はよくシベリウスならフィンランドの指揮者を推薦盤にするが、音楽はジャンル問わずそんな狭いものではないはずだ。ユダヤの救世主はなぜナチの虐殺に沈黙していたのか。日本に神がいなかったからインパールで犬死にしたのか。ケネディが頭をぶち抜かれたとき、そこには神はいなかったのか。見ないと信用できなくても信じる心を持てなくて、どうやってつらく厳しい社会を通り抜けることができようか。
そこでイエスは言われた、「わたしがこの世にきたのは、さばくためである。すなわち、見えない人たちが見えるようになり、見える人たちが見えないようになるためである」。そこにイエスと一緒にいたあるパリサイ人たちが、それを聞いてイエスに言った、「それでは、わたしたちも盲人なのでしょうか」。イエスは彼らに言われた、「もしあなたがたが盲人であったなら、罪はなかったであろう。しかし、今あなたがたが『見える』と言い張るところに、あなたがたの罪がある。
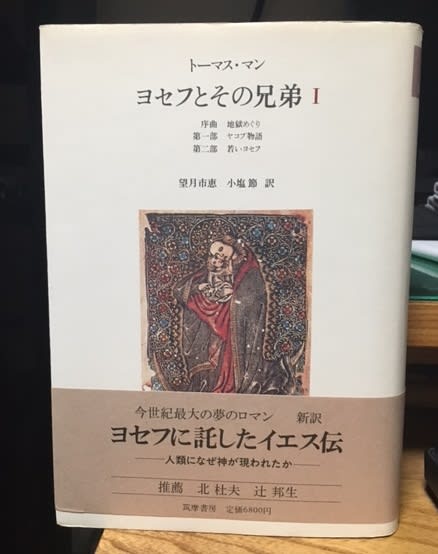
そこでイエスは言われた、「わたしがこの世にきたのは、さばくためである。すなわち、見えない人たちが見えるようになり、見える人たちが見えないようになるためである」。そこにイエスと一緒にいたあるパリサイ人たちが、それを聞いてイエスに言った、「それでは、わたしたちも盲人なのでしょうか」。イエスは彼らに言われた、「もしあなたがたが盲人であったなら、罪はなかったであろう。しかし、今あなたがたが『見える』と言い張るところに、あなたがたの罪がある。