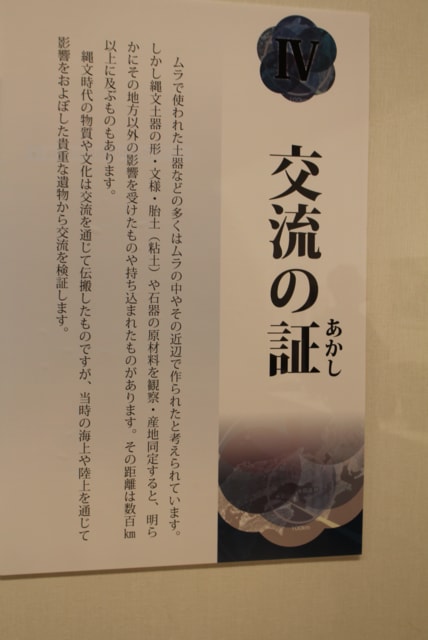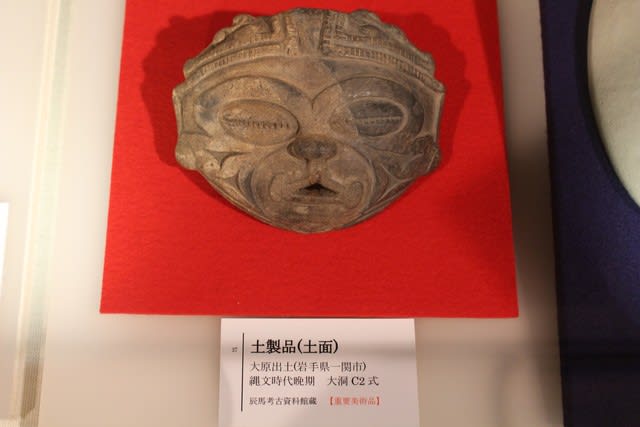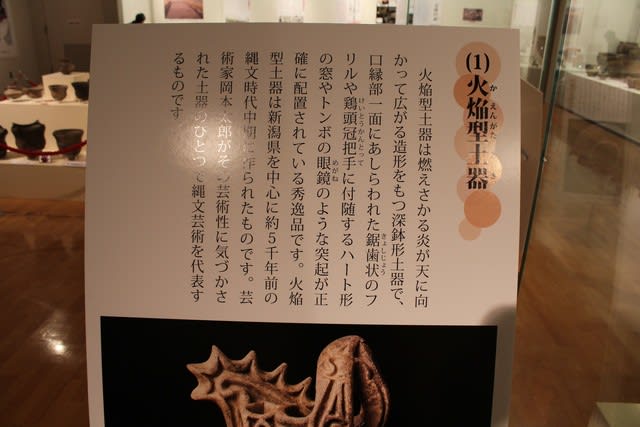弥生時代は必ずしもモノトーンの世界ではなかった。空や海の青さ、山や木々の緑、秋になれば紅葉の朱や黄色などの天然色は、現代同様弥生期でもそうであった。人工的に加工されたものでは威信財としての装飾品では、朱色ビーズの首飾り、翡翠の勾玉や管玉の首飾り、貝の釧とよぶ腕輪は、白く場合によっては螺鈿の輝きがあったであろう。其の中にベンガラや水銀朱で彩られた木製品や土器も存在したのである。これを見ているとモノトーンの世界は、後世の室町・戦国期・あるいは江戸期の鄙びた田舎で、弥生期の田舎はカラフルな感じがする。

朱と黒の鮮やかな部分は復元部分で、本来の朱は黒ずんだ部分にほんのりと確認できる。


以上が木製品に朱色の加工をした彩文鉢である。以下は土器に加工朱色である。



それにしてもデザインは斬新で現代にも通用するほどである。
<了>