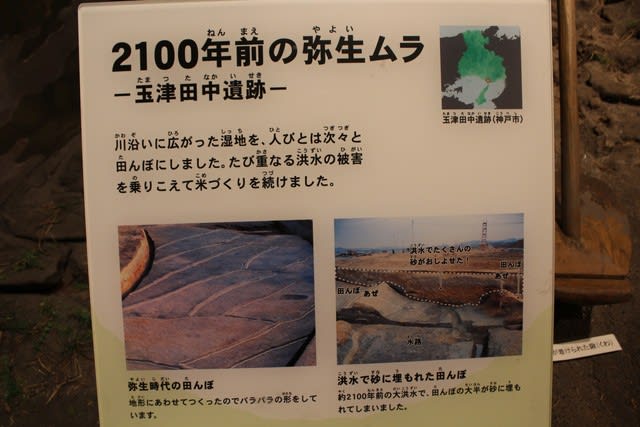弥生時代の播磨の交易として一連の展示がなされている。それを紹介する。移動が必ずしも容易ではなかった時代に、四方と交易を行っていたのである。


朱の原料は徳島県から来ました・・・と説明されているが、展示物は三重県産となっていた。



洲本の下内膳遺跡出土の簾状文大型細頸壺とある。胴部に鉄の鋲を打ち込んだような装飾で洒落た感じがする。





面白いな~。同じ弥生時代の北九州や山陰、丹後は同じような土笛である。なぜこのように異なるのか?


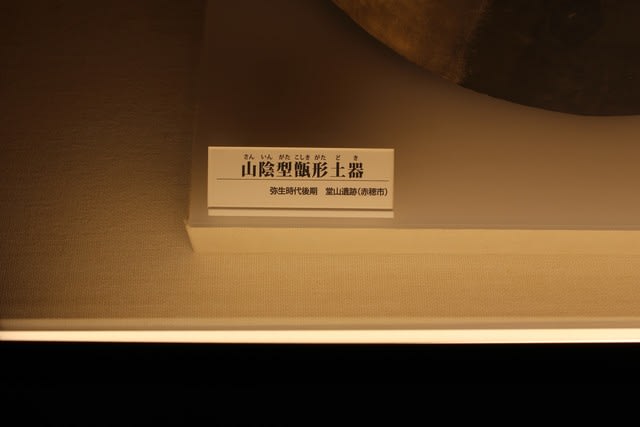
何に用いられたのか不明なようだが、山陰型甑形土器とある。珍しい形の土器を交易のため、山陰の弥生人が持ち込んだものであろう。


九州から国産鏡(仿製鏡)が、播磨に持ち込まれた。瀬戸内海を渡海してきたのであろう。


中細形銅剣である。出雲・荒神谷からは同系の銅剣が358本出土した。出雲から交易で持ち込まれたか?




翡翠と云えば糸魚川の姫川産。弥生時代のみならず、近世の江戸期にあっても難所である。難所も厭わず交易したものと感心する。
<了>