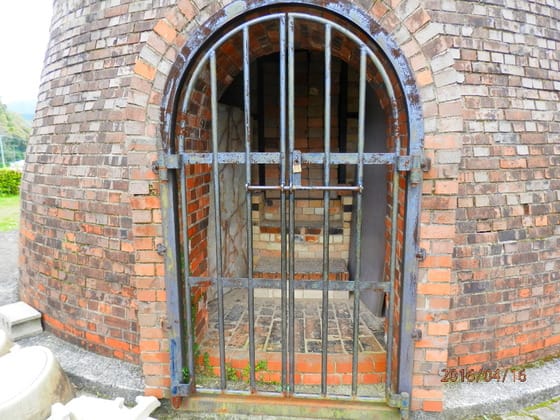先に紹介したサンカンペーンの鉄絵見返り麒麟文盤である。紹介したように10-20%程度の確率で後絵の可能性があるが、個人的には本歌と信じている。しかし、この夏頃には、科学的分析にかけたいと考えている。
今回は、そのような話ではなく、見返りの麒麟文様の話である。前述のように疑問も残るが、先ずサンカンペーン鉄絵見返り麒麟文盤を再度紹介しておく。
蹲り見返る姿で描かれている。尻尾は立ち、其の先端は団扇のようである。これはサンカンペーンや北タイ、中でもカロンのオリジナルであろうか?・・・そうでは、なそうだ。明の民窯染付に同じデザインの麒麟が描かれている。下の写真がそれで、パヤオ・ワットシーコムカム付属文化センターで見た、明染付の見返り麒麟文盤である。
何やら頭部の先に描かれている丸いもの(太陽か月?)を見返しているように思われるが、尻尾の描き方は上のサンカンペーン鉄絵盤と同じで、サンカンペーンの盤が本歌とすれば、ここから構図を拝借したことは間違いないであろう。それにしても、明染付の太陽か月と思われる構図が気になる。その話に触れる前に、先の明染付見返り麒麟文を更に崩した文様も存在する。それが下の写真であるが、それはバンコク大学付属東南アジア陶磁館展示されている。崩れていく過程が理解頂けると考える。
一方で、明末と思われる染付盤の構図も存在する。それが下の写真である。この盤もバンコク大学付属東南アジア陶磁館の展示であるが、キャップションによると、15世紀末から16世紀初頭とある。
この盤は文様の煩雑さを逃れ、いかにもシンプルであるが、見返しているのは三日月であることが分かる。従来の理解度はここまでであったが、これは何やら“伝言ゲーム”のようである。
先に示した三日月を見返した麒麟のような文様もカロンに存在する。それが上図であるが、三日月は写されず、日輪かピクンの花のような文様が、3箇所描かれている。写される都度文様が変化し、まさに伝言ゲームの様相である。カロンには上図と異なる見返り麒麟文も存在する、それが下の写真である。
大きな盤は明染付、小さな皿がカロンの鉄絵見返り麒麟文、カロンの玉壺春瓶には鉄絵で見返りの麒麟が描かれている。
ここで、陶磁文様に麒麟文が現れるのは、何時からであろうか?・・・中国陶磁については、全くの素人なので的外れと思うが、元染めであろうと考えている。
それがトプカプ宮殿博物館所蔵の麒麟文盤であろう(初出が間違っておればご容赦ねがいたい)。
麒麟の頸から胴は鱗のようなもので覆われている。上から2番目の写真に眼を戻すと、胴は格子のような線がはしる。これは元染の鱗を簡略化したものであろう。ところが3番目の写真を見ると、その格子さえ省略されている。弛緩というか伝言ゲームそのものであろう。
元染で蹲る麒麟を見ない(浅薄な知識なので、存在するとも思われるが?)。それでは明染付に存在するのは何故か?明時代のオリジナルであろうか?
過日、世界陶磁全集13巻 遼・金・元を捲っていると、下の青磁盤が目に入った。
見ると、サンフランシスコ・アジア美術館の蔵品で、元代・青磁犀牛望月図盤とある。龍泉青磁であろうか?
この犀牛望月なるものを四字熟語辞典や中国故事辞典などで探すがヒットしない。ヒットするのは中国・簡体字ばかりである。そのなかの百度百科によると、出典は「漢書芸文誌」に採録されている「関尹子」のようであるが、偽作とも云われている。
そこで、犀牛望月とは・・・、天の神将だった犀が天の戒(「一日一餐三打扮」)を破り「一日三餐一打扮」を行った為ため、天の怒りにふれ地上に降ろされ、かつて棲んだ天上界を懐かしんで天を見あげる・・・諺と云う。天の戒とは、一日に食事は一回、身だしなみ・・・つまり身辺を清楚に整えることを一日に三回行えと云う、精進潔斎の教えである。
元染めの画材は故事、元曲から選択されたものが多い。登場するのは呂洞賓、西廂記の登場人物、王昭君等々多彩である。その一環としての犀牛望月であろう。その初出は何時であろうか? 定窯には白磁印花犀牛望月盤が在るという。
写真は、北京・故宮博物院の蔵品である。更には耀州窯にも青磁犀牛望月文碗が存在するとのことである。すると、犀牛望月図の陶磁への採用は宋代に遡るのであろう。
まさに伝言ゲームである。見返の犀は麒麟に変化し、その麒麟が三日月を見返しているが、ついには三日月が日輪らしきものに変化し、ついには見返の麒麟だけになっている。
次の盤はバンコク大学付属東南アジア陶磁館に展示されているミャンマー・トワンテの青磁盤である。
キャップションによると、15世紀末―16世紀初頭とある。時代感から云えば、明染付絵に刺激されて生まれたモチーフであろう。尻尾は木の葉っぱに変化し、口には花喰鳥のごとく、花を銜えている。まさに伝言ゲームのような変化の過程を見ているようである。
中国・宋代と思われる犀牛望月図の本来の意味は伝承されず、文様だけが独り歩きし、その文様も大きく変化する姿を追って見た。
韓国陶磁に当該文様を見るのかどうか知らないが、存在するとすれば、宗主国のことであり、実直にうつすであろうが、そこは東南アジアの国であった。