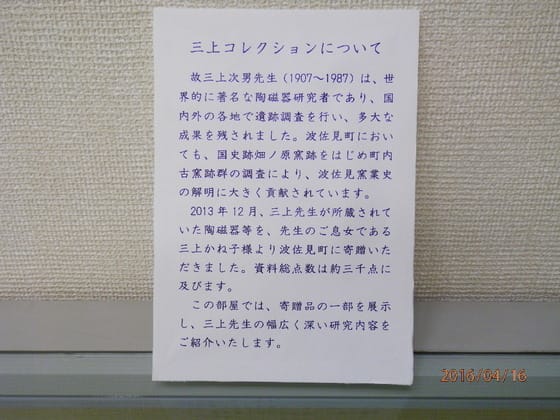仕事の関係でチェンマイに赴任して1年目頃であったろうか、ターペー通りの骨董店にて、「洪憲年製」の落款入りの盤をみた。その盤についての噺である。
洪憲年製陶磁については、天野浩伊知氏の著作に詳しく記述されている。概要は以下のとおり。
1915年、辛亥革命に乗じて中華民国の大総統に就任した袁世凱は、帝政復活の野望を抱き、1916年元旦をもって元号を「洪憲」と定め、自らが皇帝になる事を宣言する。しかし、その野望は崩れ去り、1916年2月9日に予定されていた「皇位戴冠式」は行われず、袁世凱は失脚した。帝政復活を宣言し、新元号を「洪憲」と定めたのが1915年の年末、そして袁世凱が失脚したのが1916年の3月22日である。
中国では清朝以来、皇位戴冠の際に部下の高官に対して高級磁器を配るという慣行があった。袁世凱は自分の堂斎銘である「居仁堂」という銘款を入れた焼き物を作らせていたので、戴冠式に向けて高級磁器製作を景徳鎮に命じたであろうと言われている。しかし、袁世凱は失脚、予定されていた戴冠式も行われず、その為に用意されていた高級磁器もその役割を果たせぬままとなった。その後陶磁器の所在は?である。ところが後年、「洪憲年製」と落款された磁器が存在することが明らかになった。
それらが果たして本当に袁世凱が作らせたものかどうか?僅かに散見される「洪憲年製」磁器は清朝でも、最高の磁器が製作された「乾隆帝時代」のものと比べて、遜色ない出来栄えのものが多い。中国陶磁研究者の中には、この「洪憲年製」磁器はよく出来た贋物だという人が存在する。つまり、袁世凱が大総統時代に焼いていた「居仁堂」にあやかり、でっち上げたというものである。
つまり、袁世凱が「洪憲」という元号を決めたのは1915年の年末であり、皇帝戴冠式は2月である事から、時間的にまず磁器の製作が間に合わないと言う事実。また、当時は景徳鎮から北京までの陸送に1ヶ月以上かかっていた。つまり時間的に符合しないということである。
一方、中国古陶磁器研究者の中で「洪憲年製」磁器は間違いなく存在したという説がある。袁世凱は「洪憲」と言う元号を随分以前から決めており、その時に大量の磁器の製作を景徳鎮に命じたいたという事が一つ。もう一つは現存する「洪憲年製」磁器の品質は清時代の官窯の作品と比べても遜色のない出来栄えで、こんなに優れた贋作は有り得ないという説である。
この言い分に対して反論する人は、当時はまだ清時代皇帝専属の窯、いわゆる官窯で働いていた熟練陶工がまだ存命な上、生活が苦しかったので、贋作者の注文にも必死に応じたのではないかという意見である。
何やら堂々巡りのようで、容易に結論はでないが、「洪憲年製」は偽款(倣款)と見るのが妥当であろう。しかし、青花・赤色・藍料の方款「居仁堂製」・「洪憲年製」・「洪憲御製」は、その優品に限って1916年から1925年までの10年間の品々、これらは本歌ではないが、本歌に準ずる品として珍重されている。
そのような精作に、ターペー通りの骨董店で出あった。それが下の写真である。先ずは何故、香港や上海ではなく、チェンマイでということであるが、それは驚くことではない。チェンマイには多くの中国人移民が存在するからである。


 実に手の込んだ落款で、朱と金彩で描きこまれている。先に示した10年間以降、つまり1925年以降の焼成品と考えられなくもない。しかし、見込みに描かれる龍鳳凰文や花唐草は精作そのものである。
実に手の込んだ落款で、朱と金彩で描きこまれている。先に示した10年間以降、つまり1925年以降の焼成品と考えられなくもない。しかし、見込みに描かれる龍鳳凰文や花唐草は精作そのものである。
上海で入手した書籍「清代瓷器賞鑑」が手もとにある。

 大清光緒年製なる官窯銘をもつ粉彩龍鳳凰文盤が掲載されている。先の「洪憲年製」の盤と比較すると、龍と鳳凰の形はやや異なるが、その精緻さにおいて引けをとらない。
大清光緒年製なる官窯銘をもつ粉彩龍鳳凰文盤が掲載されている。先の「洪憲年製」の盤と比較すると、龍と鳳凰の形はやや異なるが、その精緻さにおいて引けをとらない。
同書には、倣款が掲載されている。それが下の写真である。そして「洪憲年製」をもつ陶磁は、すべて倣作として取り扱っている。
 インターネット・オークションには、洪憲年製の落款をもつ陶磁が出品されているが、いずれも雑な絵付けであまりにも酷い。すべての写真を掲載すれば、商売の邪魔になるので、出品陶磁の落款のみ掲載しておく。
インターネット・オークションには、洪憲年製の落款をもつ陶磁が出品されているが、いずれも雑な絵付けであまりにも酷い。すべての写真を掲載すれば、商売の邪魔になるので、出品陶磁の落款のみ掲載しておく。



 袁世凱も死して、後世に話題を提供しているさまは、本望であろうか。ターペー通りの骨董店で入手した洪憲年製・粉彩龍鳳凰文盤を見るたびに、袁世凱の禿げ頭を思い出す。
袁世凱も死して、後世に話題を提供しているさまは、本望であろうか。ターペー通りの骨董店で入手した洪憲年製・粉彩龍鳳凰文盤を見るたびに、袁世凱の禿げ頭を思い出す。
<続く>
洪憲年製陶磁については、天野浩伊知氏の著作に詳しく記述されている。概要は以下のとおり。
1915年、辛亥革命に乗じて中華民国の大総統に就任した袁世凱は、帝政復活の野望を抱き、1916年元旦をもって元号を「洪憲」と定め、自らが皇帝になる事を宣言する。しかし、その野望は崩れ去り、1916年2月9日に予定されていた「皇位戴冠式」は行われず、袁世凱は失脚した。帝政復活を宣言し、新元号を「洪憲」と定めたのが1915年の年末、そして袁世凱が失脚したのが1916年の3月22日である。
中国では清朝以来、皇位戴冠の際に部下の高官に対して高級磁器を配るという慣行があった。袁世凱は自分の堂斎銘である「居仁堂」という銘款を入れた焼き物を作らせていたので、戴冠式に向けて高級磁器製作を景徳鎮に命じたであろうと言われている。しかし、袁世凱は失脚、予定されていた戴冠式も行われず、その為に用意されていた高級磁器もその役割を果たせぬままとなった。その後陶磁器の所在は?である。ところが後年、「洪憲年製」と落款された磁器が存在することが明らかになった。
それらが果たして本当に袁世凱が作らせたものかどうか?僅かに散見される「洪憲年製」磁器は清朝でも、最高の磁器が製作された「乾隆帝時代」のものと比べて、遜色ない出来栄えのものが多い。中国陶磁研究者の中には、この「洪憲年製」磁器はよく出来た贋物だという人が存在する。つまり、袁世凱が大総統時代に焼いていた「居仁堂」にあやかり、でっち上げたというものである。
つまり、袁世凱が「洪憲」という元号を決めたのは1915年の年末であり、皇帝戴冠式は2月である事から、時間的にまず磁器の製作が間に合わないと言う事実。また、当時は景徳鎮から北京までの陸送に1ヶ月以上かかっていた。つまり時間的に符合しないということである。
一方、中国古陶磁器研究者の中で「洪憲年製」磁器は間違いなく存在したという説がある。袁世凱は「洪憲」と言う元号を随分以前から決めており、その時に大量の磁器の製作を景徳鎮に命じたいたという事が一つ。もう一つは現存する「洪憲年製」磁器の品質は清時代の官窯の作品と比べても遜色のない出来栄えで、こんなに優れた贋作は有り得ないという説である。
この言い分に対して反論する人は、当時はまだ清時代皇帝専属の窯、いわゆる官窯で働いていた熟練陶工がまだ存命な上、生活が苦しかったので、贋作者の注文にも必死に応じたのではないかという意見である。
何やら堂々巡りのようで、容易に結論はでないが、「洪憲年製」は偽款(倣款)と見るのが妥当であろう。しかし、青花・赤色・藍料の方款「居仁堂製」・「洪憲年製」・「洪憲御製」は、その優品に限って1916年から1925年までの10年間の品々、これらは本歌ではないが、本歌に準ずる品として珍重されている。
そのような精作に、ターペー通りの骨董店で出あった。それが下の写真である。先ずは何故、香港や上海ではなく、チェンマイでということであるが、それは驚くことではない。チェンマイには多くの中国人移民が存在するからである。



上海で入手した書籍「清代瓷器賞鑑」が手もとにある。


同書には、倣款が掲載されている。それが下の写真である。そして「洪憲年製」をもつ陶磁は、すべて倣作として取り扱っている。





<続く>