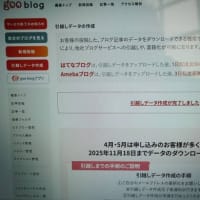午前中に出掛けた陶芸教室ではこの前に作っていた一連のぐい呑のうち、織部釉を除く7個が焼きあがっていて、中では4個はまずまずかなと、いずれも形は同じ茶碗風に作って織部と黒織部風以外は釉薬を志野釉で統一して、下絵や志野釉の濃さを変化させてどうなるかと試みてみたものであるだが。
冒頭の7個を並べたもののうち真白く見えるのは志野の釉薬を濃縮させて釉の厚みを出そうとしたものだが、下絵は見えなくなってしまって、土がもっと粗いものだと釉薬が爆ぜてザックリとした風景が出るらしいが今の土では無理だそうで、次回は土の表面を荒らしてみて再チャレンジしてみようかなと思っているが、いずれにしてもこれだけ厚く釉薬をかける場合は下絵は意味がなくなるということが分かった。ということでそれぞれの特徴がよく出た物を4個選んでみた。

まずまずと選んだ4個はそれぞれ釉掛けが違っていて、一番左は通常の志野、次は鉄釉に志野釉を重ねて鼠志野風を狙ったもの、その次が厚い志野釉の中でも自分では形が気に入っているもの、最後が黒織部まがいに遊んだ絵付のぐい呑である。見て分かるように通常の志野と鼠志野を狙ったものは逆に志野釉がやや薄めで中でも鼠志野は特に薄すぎた、もう少し厚めにして三番目のものとの中間を次回は試みてみよう。黒織部風はこんなものかな、やはりまがい物だから本物のようにはいかないが、雰囲気は出ていると思う。

この日は夜に友人との飲み会があって、いくつか持って行って誰かにくれてやろうかなと思っているところだ。失敗作ですよーと言ってね。