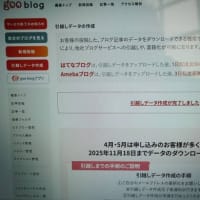ここまでで案内は終了でしょうとばかりに我々は残った時間を有効にと、前回は見られなかった古代出雲歴史博物館(冒頭写真)を見物して、そのあとまだ時間があれば神門通りの門前町商店街を巡ってみようかと、また戻って出雲大社を横切って、その先にある博物館に急ぎ足で向かうことに。
 途中には古代の3本組の岩根御柱を復元していたが、往時ほどの大木ではないから迫力は今一つ
途中には古代の3本組の岩根御柱を復元していたが、往時ほどの大木ではないから迫力は今一つ
古代出雲歴史博物館はモダンな建物で、展示内容はこの地で発掘された多くの銅鐸や銅矛の展示がメイン、これに出雲大社の古代から江戸時代までの模型や出雲風土記の世界の様子などが常設展示となっていて、さらに特別展示室があって、今回は板締の世界という面白い手法の型染めの技法の展示となっていた。これらがかなり見応えがあって時間が足りない、最後は端折って残り時間を少しだけ作って、神門通リの散策は手前を少しだけということとなってしまった。このあとに立寄ることになっているいずもまがたまの里伝承館はこの前に見たから、そちらは止めてこちらの時間を伸ばしてもらいたかったなと、こういう都合がつかないのが団体ツアーの難だよね。
まずは常設展示から、館内での写真撮影はフラッシュを使わなければ自由ということで。
 まずは発掘された岩根御柱が入口中央ロビーに、古くから棟持の宇豆柱と呼ばれ、杉の大木で鎌倉時代前半造営のものらしいと
まずは発掘された岩根御柱が入口中央ロビーに、古くから棟持の宇豆柱と呼ばれ、杉の大木で鎌倉時代前半造営のものらしいと
 寛文期の復元模型は今と同じのようだが神楽殿は無かった、調べたら神楽殿は明治になってと、それでステンドグラスがあるんですか
寛文期の復元模型は今と同じのようだが神楽殿は無かった、調べたら神楽殿は明治になってと、それでステンドグラスがあるんですか
 雲太、和二、京三と言われた往時の高さ48mの模型が
雲太、和二、京三と言われた往時の高さ48mの模型が
 実物大の千木と鰹木
実物大の千木と鰹木
 銅鐸と銅矛の展示室
銅鐸と銅矛の展示室
 銅鐸と銅矛の発掘時の状況が写真で
銅鐸と銅矛の発掘時の状況が写真で
 圧巻の銅矛展示
圧巻の銅矛展示
 銅鐸はほとんどが国宝とか
銅鐸はほとんどが国宝とか
青銅の出来立てはキンキラキンに輝いていたと、復元されたこれらの展示とは別に実際に鳴らすことができる銅鐸もあって、風鈴みたいにいい音色を響かしてくれる、何かの祭祀に使われたんでしょうかね。
 往時の新品はと復元すればキンピカ
往時の新品はと復元すればキンピカ
 勾玉なども
勾玉なども
 銅鏡も
銅鏡も
 卑弥呼の鏡かと景初三年銘のある三角縁神獣鏡が
卑弥呼の鏡かと景初三年銘のある三角縁神獣鏡が
 古墳時代の鉄剣も、出雲は砂跌の産地
古墳時代の鉄剣も、出雲は砂跌の産地
 保存状態が驚くほどよかったというものも、こんな状態で発見されたとはビックリ
保存状態が驚くほどよかったというものも、こんな状態で発見されたとはビックリ
 復元品
復元品
 馬上の大首長の実物大推定像
馬上の大首長の実物大推定像
常設展示の見物のあとはこの時の特別展示の板締の世界に、出雲と京都と中国の三技法を展示とあった。
 入口
入口
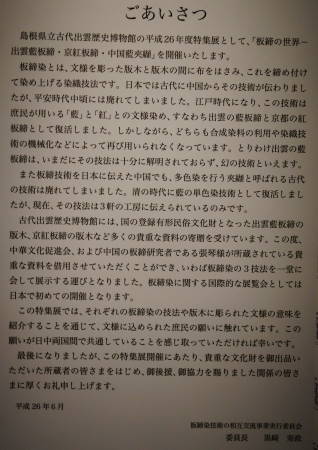 特別展のごあいさつ
特別展のごあいさつ
 板締の型板と染め上がりが
板締の型板と染め上がりが
 工程説明
工程説明
 これが染める時の状態らしい
これが染める時の状態らしい