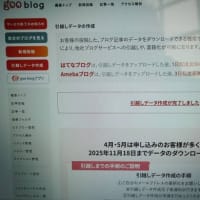もう15年近く前になるが、旧軽井沢のロータリー手前の喫茶店の2階で、辻常陸大掾という厳めしい名前の窯元だけの有田焼染付磁器の展示即売をやっているという看板を見て、大掾という平安時代の役職名が気になってフラリと入ってみた。
名前からは常陸の国の守、介に次ぐ役職名だから、なんで有田焼の窯元の名前になっているんだと。展示即売している陶器屋は確か三鷹のほうに店をもっていて、夏場だけこちらを借りてやっているということであった。そして名前の由来を聞いたらこの窯元は江戸時代から続くそうで、朝廷御用の栄誉を受けて名誉職としてこの名を与えられたんだそうだ。明治以降も宮内庁御用達の窯であったから、一般にはあまり出回らないということで、年に一度こちらでだけ販売しているという。
さすがにどれもかなりのお値段で、大きいものはとても買えないと一室に並べられた器や花瓶など見て回ったら、小さな皿なのだが呉須の色が奇麗で、鷺の姿が軽妙、それに全体のバランスがいいこの5枚セットが目に留まった。小さいから比較的に安め、それにこれより絵が劣ると思うような同じぐらいの大きさのものよりも安い値札が付いている。店の人もこちらの方が出来がいいから値段が逆じゃぁと思うけれど、この値札が付けられてきたからと言う。作者はもう高齢で、これからは作品がかなり少なくなるだろうとも。
皇室と同じ器を使うとなれば名誉ですな、と冗談をいいながら購入して、家に帰ってから調べたら、確かに歴史がある窯元で、その当時の当主は14代目でもう米寿になろうということが分かった。
 辻の名と花押、右下には窯印
辻の名と花押、右下には窯印
その後は記帳してきたから夏場に開催の案内状が来るようになったのだが、出物とはめぐり合わないままに数回見ただけ。それが何年か経って後に見た染付の色や絵が固い感じになっているのに気が付いた。恐らく次の世代の作が中心になったのだろうと推測したが、改めて今回調べてみたら最近になって15代目襲名があったようで、先代の作品はかなり前から少なくなっていたのでは。