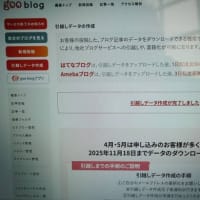以前ここを走ったときには有料だった龍神スカイラインは無料の一般道路になっていたが、尾根伝いに延々と走る道筋はあまり交通量は多くないことだけは変わっていないようだ。あのときは雪が降ったあとだったからほとんど走っていなくて、よくぞこんな山道の有料道路なんぞを造ったもんだと思ったのだが。
スカイラインの最終は下っていって日高川上流沿いの龍神温泉に、ここでも新しいトンネルが出来ていて以前に通り抜けた上御殿、下御殿などが並ぶ温泉街は避けて走るようになっていた。龍神温泉は川中温泉や湯の川温泉とともに日本三美人の湯ということで、以前と通ったときには公衆温泉に入ったことを思い出した、まぁ僕が美人にというわけじゃなかったんだけれど。その先のドライブイン龍の里で一休み、ここにはレストランもあったが皆さんオプション弁当を頼んだようで食べる人はいない、20分の休憩時間じゃ忙しいしね。ここは南高梅で有名なみなべ町から奥に入った場所になるから、お土産売場では安いつぶれ梅を並べていたが、梅干のパックは結構重いし関東のスーパーでも安いからね。ドライブインを出てから昼の弁当を車内で広げる、柿の葉すしは作る店で味がかなり違うとバスガイドが話していたが、一の橋観光センターのものはやや酢が強くて巻いた葉も小さい、昨日買ったほうはもっと慣れた味で包む葉も大きくて香りも強い、僕は昨日のものに軍配を上げる。
このバス車中でもバスガイドが今日駐車場などで出会った同僚バスのガイドから、奈良から高野山にかけてものすごい集中豪雨にあって見物を中止したなどと話していたとかで、我々は飛鳥寺あたりで黒い雲を見ただけで降られなかったのは幸運だったらしい。
このあとは熊野古道の姿が一番残るという中辺路は通り過ぎるだけで、熊野川沿いにある熊野本宮大社には1時前に到着する。ここの本宮は以前は熊野川と音無川の合流する中州にあったのだが、明治22年の大洪水で流されたため今の階段で登る台地上に明治24年に移されたという。その旧殿は未だに残る大鳥居の後のこんもりとした森にあったということはよく分かった。今の本宮社には一から四の社殿があって主神は三殿で家津美御子大神、別名がスサノオノミコトだと、左手一と二殿はイザナミ、イザナギで元々は夫婦だから相殿となっているなのかな、右手四殿に天照大神が祀られ、お参りは正面三殿からするのが仕来りだそうだ。境内には葉書の語源となったその葉に文字を書いて便りとして送ったという御神木タラヨウの木があって、その脇には黒塗りポストが置いてあった。ポストの色は、この地は新宮に上陸した神武天皇が八咫烏に導かれて北上したという伝説から、カラスが熊野神社のシンボルになっているために黒くしているんだね、タラヨウのほうは水害後の明治24年にここに本殿が移されたわけだから、昔は社殿でも何でも無かった場所に生えていた木のはずだよね。


本宮への階段 本宮神門、中は写真撮影禁止


本宮内四社殿の説明 タラヨウの木と黒ポスト
 旧社の鳥居
旧社の鳥居
本宮付近は新たに門前町風に修景していて、近くには本宮温泉卿として湯の峰温泉、渡瀬温泉、川湯温泉など山のいで湯がいくつかあるからまた来たいところではあるなと。余分な話だけれどこの辺りにはやたらとコーナンというDIYの店があって、今は関東でも見かけるがここらが発祥らしいね。
ここからは悠々と流れる熊野川沿い右岸を下流へと走る、世界遺産になってから道路が広げられたそうでスムースなもの、眺め続けた川沿いの感じは流れの様子や色などはこの前見てきた大井川の中流に似ているが、周辺の風景や舟下りがあるところなどは最上川に近いかな。途中にはいくつかの滝があって、バスガイドが指差す右左にと首を忙しく動かすことになる。
 熊野川沿い
熊野川沿い
そして現れたトンネルを抜けたら突然に川から離れて新宮市の街並が出迎えてくる、これで今回の旅行では和歌山三川すべてを巡ったことになったのだが、こちら側に出てきたらすぐ海岸が見えてきたのには山道を走っていると思い込んでいたからビックリした。
 那智勝浦道路からの熊野灘
那智勝浦道路からの熊野灘
市内を少し走ってからは有料道路で那智勝浦へ、そこからまたやや山側に入って那智の滝方面に向う。その手前には熊野古道が残る大門坂(冒頭写真はバスガイド一押しの撮影スポットだという場所で)という場所があって、ご老体二人の辞退者を除いて200mほどの急な石畳の坂道をバスガイドの後に続いてフーフーしながら登る。樹齢千年以上ありそうな物凄い巨木が残っていてやや往時を偲ばせるが、この日は気温が上がっていて大汗をかくことに、蟻の熊野詣でと貴賤を問わず多くの人々が競って古道を歩いたということだが昔の人は健脚だったんだと、法皇上皇もどれだけ歩いたんだろうか。詣でる人々を迎えたという小さな社の最終の九十九王子跡の碑があるところの先まで歩いてバスに迎えられ、那智の滝にまた少し登っていく。
 九十九王子跡
九十九王子跡
国宝となっている根津美術館所蔵の那智滝図でも有名な日本一の名瀑はそのものがご神体にもなっている。奥の院のガイドさんの話では熊野ではここ滝の鳥居だけは伊勢鳥居だそうで、神様の滝だけ祀っているんだね。ここでは蹴上が大きい石段を下って勇壮な滝を見物、有料の滝壺までは行くまでもないかと、手前でも滝の影響かかなり涼しく感じる、でも帰りの登りではまたも汗をかいてしまった。今回のツアーは年配者にはかなりつらそうで、往復するだけでいっぱいいっぱいの人もかなりいたようだね。
 落差133mの那智の滝
落差133mの那智の滝
滝からはすぐ、那智大社と青岸渡寺が並ぶ高台の下の蓬莱閣土産センターの駐車場にバスが回る。ここからの那智大社までの参道の階段は結構登りがキツイです、今日の参拝は歩いたなぁ、それも坂だったり階段だったり、久しぶりにいっぱい運動をしちゃったぞ。こんな参道沿いにも土産屋が並んでいて黒い那智石を使った硯や置物などを売る店が多かった。確か碁石には黒はこの那智黒、白は蛤が最高品であったなと。元々は那智の滝そのものを祀っていたことから今も滝の前面に鳥居があって滝が本殿という姿はあちらに残しているわけで、本宮や速玉神社より新しく那智大社としてこちらに建てられたということだから、そう思って眺めると屋根は銅版葺だし、鮮やかな朱塗りが目立ちケバケバしくて本宮のような厳かさが欠ける感じがしてしまう。こちらの主神は滝ではなくてイザナミ命となっている、そして有名な那智の火祭はここで行われ大変見事なものだとはバスガイドの話であった。


参道の階段 那智大社
ここから右手に歩いてすぐの台地続きに青岸渡寺があって、こちらの本堂はかなり古めかしい造りとなっていて奥ゆかしい。この寺があることで熊野は神仏習合の地であったことがはっきりと分かる、そして西国三十三箇所の第一番となっているのだそうで、観音信仰の寺はこういう急峻な場所に多く建つものだと納得。本堂右手奥に回れば先ほどの那智の滝を上から同寺の三重塔とともに一望できて、この眺めは必見の価値がある。帰りは寺側の階段を降りていくと途中で登りと合流する、ほとんど土産屋には目もくれずバス駐車場まで降りてきて汗を拭きながら風にあたることになった。
 青岸渡寺
青岸渡寺
 那智の滝遠望
那智の滝遠望
本日の観光はこれでほぼ終了、バスは最近コーヴという盗み撮り映画が物議を醸したクジラ漁で有名な太地町を抜けてまた那智勝浦だという海岸線を走って、細長い湾深くにあるマグロ養殖で有名になった近畿大学水産学部を通り過ぎたら本州最南端の町である串本に。
 この眺めは伊根の舟宿みたい
この眺めは伊根の舟宿みたい
今晩のホテルにもすぐ近く、奇岩が並ぶ橋杭岩という場所は予定では明日であったがついでだからと立寄ることになって少しばかりの見物。目の前の大島に弘法大師が橋を架けてやろうとしたのに、手伝わされた天邪鬼が嫌になって鶏の鳴声を真似て鳴いたので、朝になって人々に見付かったら大変と途中で止めたというような伝説が案内板に書いてあった。
 橋杭岩の奇岩群
橋杭岩の奇岩群
ところが真正面には大島とこちらを繋ぐ橋が見えるじゃないですか。民謡に「ここは串本向かいは大島、仲を取り持つ連絡線」というのがあったが、この唄を聞かなくなって久しいのは橋がかかったからなのかしらん。
スカイラインの最終は下っていって日高川上流沿いの龍神温泉に、ここでも新しいトンネルが出来ていて以前に通り抜けた上御殿、下御殿などが並ぶ温泉街は避けて走るようになっていた。龍神温泉は川中温泉や湯の川温泉とともに日本三美人の湯ということで、以前と通ったときには公衆温泉に入ったことを思い出した、まぁ僕が美人にというわけじゃなかったんだけれど。その先のドライブイン龍の里で一休み、ここにはレストランもあったが皆さんオプション弁当を頼んだようで食べる人はいない、20分の休憩時間じゃ忙しいしね。ここは南高梅で有名なみなべ町から奥に入った場所になるから、お土産売場では安いつぶれ梅を並べていたが、梅干のパックは結構重いし関東のスーパーでも安いからね。ドライブインを出てから昼の弁当を車内で広げる、柿の葉すしは作る店で味がかなり違うとバスガイドが話していたが、一の橋観光センターのものはやや酢が強くて巻いた葉も小さい、昨日買ったほうはもっと慣れた味で包む葉も大きくて香りも強い、僕は昨日のものに軍配を上げる。
このバス車中でもバスガイドが今日駐車場などで出会った同僚バスのガイドから、奈良から高野山にかけてものすごい集中豪雨にあって見物を中止したなどと話していたとかで、我々は飛鳥寺あたりで黒い雲を見ただけで降られなかったのは幸運だったらしい。
このあとは熊野古道の姿が一番残るという中辺路は通り過ぎるだけで、熊野川沿いにある熊野本宮大社には1時前に到着する。ここの本宮は以前は熊野川と音無川の合流する中州にあったのだが、明治22年の大洪水で流されたため今の階段で登る台地上に明治24年に移されたという。その旧殿は未だに残る大鳥居の後のこんもりとした森にあったということはよく分かった。今の本宮社には一から四の社殿があって主神は三殿で家津美御子大神、別名がスサノオノミコトだと、左手一と二殿はイザナミ、イザナギで元々は夫婦だから相殿となっているなのかな、右手四殿に天照大神が祀られ、お参りは正面三殿からするのが仕来りだそうだ。境内には葉書の語源となったその葉に文字を書いて便りとして送ったという御神木タラヨウの木があって、その脇には黒塗りポストが置いてあった。ポストの色は、この地は新宮に上陸した神武天皇が八咫烏に導かれて北上したという伝説から、カラスが熊野神社のシンボルになっているために黒くしているんだね、タラヨウのほうは水害後の明治24年にここに本殿が移されたわけだから、昔は社殿でも何でも無かった場所に生えていた木のはずだよね。


本宮への階段 本宮神門、中は写真撮影禁止


本宮内四社殿の説明 タラヨウの木と黒ポスト
 旧社の鳥居
旧社の鳥居本宮付近は新たに門前町風に修景していて、近くには本宮温泉卿として湯の峰温泉、渡瀬温泉、川湯温泉など山のいで湯がいくつかあるからまた来たいところではあるなと。余分な話だけれどこの辺りにはやたらとコーナンというDIYの店があって、今は関東でも見かけるがここらが発祥らしいね。
ここからは悠々と流れる熊野川沿い右岸を下流へと走る、世界遺産になってから道路が広げられたそうでスムースなもの、眺め続けた川沿いの感じは流れの様子や色などはこの前見てきた大井川の中流に似ているが、周辺の風景や舟下りがあるところなどは最上川に近いかな。途中にはいくつかの滝があって、バスガイドが指差す右左にと首を忙しく動かすことになる。
 熊野川沿い
熊野川沿い そして現れたトンネルを抜けたら突然に川から離れて新宮市の街並が出迎えてくる、これで今回の旅行では和歌山三川すべてを巡ったことになったのだが、こちら側に出てきたらすぐ海岸が見えてきたのには山道を走っていると思い込んでいたからビックリした。
 那智勝浦道路からの熊野灘
那智勝浦道路からの熊野灘市内を少し走ってからは有料道路で那智勝浦へ、そこからまたやや山側に入って那智の滝方面に向う。その手前には熊野古道が残る大門坂(冒頭写真はバスガイド一押しの撮影スポットだという場所で)という場所があって、ご老体二人の辞退者を除いて200mほどの急な石畳の坂道をバスガイドの後に続いてフーフーしながら登る。樹齢千年以上ありそうな物凄い巨木が残っていてやや往時を偲ばせるが、この日は気温が上がっていて大汗をかくことに、蟻の熊野詣でと貴賤を問わず多くの人々が競って古道を歩いたということだが昔の人は健脚だったんだと、法皇上皇もどれだけ歩いたんだろうか。詣でる人々を迎えたという小さな社の最終の九十九王子跡の碑があるところの先まで歩いてバスに迎えられ、那智の滝にまた少し登っていく。
 九十九王子跡
九十九王子跡国宝となっている根津美術館所蔵の那智滝図でも有名な日本一の名瀑はそのものがご神体にもなっている。奥の院のガイドさんの話では熊野ではここ滝の鳥居だけは伊勢鳥居だそうで、神様の滝だけ祀っているんだね。ここでは蹴上が大きい石段を下って勇壮な滝を見物、有料の滝壺までは行くまでもないかと、手前でも滝の影響かかなり涼しく感じる、でも帰りの登りではまたも汗をかいてしまった。今回のツアーは年配者にはかなりつらそうで、往復するだけでいっぱいいっぱいの人もかなりいたようだね。
 落差133mの那智の滝
落差133mの那智の滝滝からはすぐ、那智大社と青岸渡寺が並ぶ高台の下の蓬莱閣土産センターの駐車場にバスが回る。ここからの那智大社までの参道の階段は結構登りがキツイです、今日の参拝は歩いたなぁ、それも坂だったり階段だったり、久しぶりにいっぱい運動をしちゃったぞ。こんな参道沿いにも土産屋が並んでいて黒い那智石を使った硯や置物などを売る店が多かった。確か碁石には黒はこの那智黒、白は蛤が最高品であったなと。元々は那智の滝そのものを祀っていたことから今も滝の前面に鳥居があって滝が本殿という姿はあちらに残しているわけで、本宮や速玉神社より新しく那智大社としてこちらに建てられたということだから、そう思って眺めると屋根は銅版葺だし、鮮やかな朱塗りが目立ちケバケバしくて本宮のような厳かさが欠ける感じがしてしまう。こちらの主神は滝ではなくてイザナミ命となっている、そして有名な那智の火祭はここで行われ大変見事なものだとはバスガイドの話であった。


参道の階段 那智大社
ここから右手に歩いてすぐの台地続きに青岸渡寺があって、こちらの本堂はかなり古めかしい造りとなっていて奥ゆかしい。この寺があることで熊野は神仏習合の地であったことがはっきりと分かる、そして西国三十三箇所の第一番となっているのだそうで、観音信仰の寺はこういう急峻な場所に多く建つものだと納得。本堂右手奥に回れば先ほどの那智の滝を上から同寺の三重塔とともに一望できて、この眺めは必見の価値がある。帰りは寺側の階段を降りていくと途中で登りと合流する、ほとんど土産屋には目もくれずバス駐車場まで降りてきて汗を拭きながら風にあたることになった。
 青岸渡寺
青岸渡寺 那智の滝遠望
那智の滝遠望本日の観光はこれでほぼ終了、バスは最近コーヴという盗み撮り映画が物議を醸したクジラ漁で有名な太地町を抜けてまた那智勝浦だという海岸線を走って、細長い湾深くにあるマグロ養殖で有名になった近畿大学水産学部を通り過ぎたら本州最南端の町である串本に。
 この眺めは伊根の舟宿みたい
この眺めは伊根の舟宿みたい今晩のホテルにもすぐ近く、奇岩が並ぶ橋杭岩という場所は予定では明日であったがついでだからと立寄ることになって少しばかりの見物。目の前の大島に弘法大師が橋を架けてやろうとしたのに、手伝わされた天邪鬼が嫌になって鶏の鳴声を真似て鳴いたので、朝になって人々に見付かったら大変と途中で止めたというような伝説が案内板に書いてあった。
 橋杭岩の奇岩群
橋杭岩の奇岩群ところが真正面には大島とこちらを繋ぐ橋が見えるじゃないですか。民謡に「ここは串本向かいは大島、仲を取り持つ連絡線」というのがあったが、この唄を聞かなくなって久しいのは橋がかかったからなのかしらん。