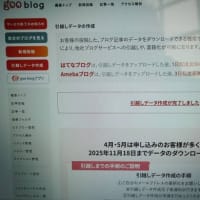午後4時半前に最初の宿である両津港近くの加茂湖温泉吉田屋に到着、そういえば観光バスもYOSHIDAYAの表示でバス観光と宿泊をセットで安い料金で団体客を誘致しているんだろうと想像する。

両津の町、奥がホテルでその先は加茂湖(冒頭写真は手前角から右手の通り)
読売旅行などの佐渡プランは東京からバスでフェリーにもそのバスで乗込むというものばかりだったから、それだと移動だけで丸一日がかりとなってしまうだろう。事実、温泉露天風呂に浸かっていたら後からの別グループが入ってきて、今着いたばかりと話していたから、第一日目の島の観光は出来なかったはず。
宿のホールの展示ケースに土人形や骨董陶磁器などが飾ってあったように、佐渡は北前船で運ばれた古伊万里などの骨董が多く残ると聞いていたので、宿付近の骨董屋を電話帳で調べて明るいうちにと行ってみれば、佐州という店は小さな店舗、もう一つガレージ倉庫のリサイクル店もあったが、両方とも物は少ないのにお値段が高目なのにはガッカリ、団体旅行でもあるしこちらの方は諦めて観光に徹しましょうということに。

宿の展示ショーケースにいろいろと
両津中心部の町の雰囲気は江戸の船乗り達が中継地で遊んだ巷の風情をまだかなり残しており、その真っ只中のレトロ木造店舗が今はケーキ屋になっていたりでかなり面白そうではある。道路も広いところは駐車可のようで、早朝に見てみればおおらかに公道が各家の車の駐車場にもなっているようで、これは島の慣習として認められているんだね。
その街外れ、加茂湖に面する場所にある宿は老舗の旅館風で、何回か増築したらしい鉄筋コンクリート造の建物は一昔前の造りながら、掃除などしっかりしていて、逆に幾分は風格が感じられる。東、西館と南館が並列で建てられているので皆さん方向感覚が分からなくなったようだが、南館の5Fにある我々の部屋は今風のユニットではない在来工法の浴室とトイレ付、入口に畳も敷かれた上がり小部屋と、バルコニー側は縁側付き、本間は8畳間と余裕のある造りで、西南の加茂湖に面するロケーションで文句はない。宿の窓からの景色の印象は、松江で泊まったことがある温泉旅館からの感じとよく似ていて、同じように南側に汽水湖を眺めるからだろうか。

加茂湖の向うに雪を頂いた山が見えて
温泉は1Fの内風呂と5F屋上に露天風呂があり、露天の方はあとから設置したようで洗い場は無いが、気水湖らしく牡蠣棚が浮かぶ加茂湖が目の前に広がって眺めは抜群、なんでも女風呂からは両津湾も見えると女房が言っていた。でも男風呂はペントハウスから屋上に出ると、突然に浴槽の半分ほどがバッチリ見えるので、女性は一瞬ビックリという顔をしていたが、ずうずうしくも亭主を呼びに中に顔を覗かしているお母ちゃんもいたぞ。泉質はナトリウム炭酸水素塩泉(弱アルカリ性低張性温泉)のヌルツルッとした湯質で、臭いは少しだけ鉄っ気が感じられて、チョッピリだけ色が着いているかなという程度の無色透明の湯、若返りの湯と書いてあったがなかなか気持ちの良い温泉である。
夕陽は山に沈むのでかなり明るいうちに隠れて、その後やや暗くなっていって湖の対岸に明かりがポツポツ灯りだす暮れなずむ頃の風景は風情がありますねぇ。名古屋や八王子からという別グループの親爺達と話がはずみ、やや冷たい外気に吹かれて1時間以上を露天に浸かり、上がってくれば部屋で待つ女房に食事時間を30分以上の遅刻と起こられる始末。
6時からというんだから遅れてもと、それにバイキングなんだろうからと適当に広間の食事処に行けばいいと考えていたのだが、なんと今回は銘々にお膳でというスタイルに我々二人だけが大遅刻みたい。これまで沖縄と北海道の2回の団体旅行は全てバイキングだったから、パック旅行はそういうものだと思い込んでいたのでこれはビックリであった。
夕食内容は佐渡では海の幸では小振り紅ズワイ、イカソーメン風、別にお造りと御飯時の大きなお椀でのあら汁は二日目の宿と共通であったが、前菜三点盛、カキ土手鍋風、天ぷら、蟹甲羅茶碗蒸風、アジ塩窯焼、デザートなど吉田屋さんは結構手の込んだものが適度の量で供され、遅かった分パッパと平らげて最後の御飯は女房の方は半分でもう一杯ということとなった。ということで料理の写真を撮る暇がなくなってしまった。夜9時から民謡ショーがあるということだったが、最初だけちょっと覗けばレコードをかけて数人が踊りをするだけ、実際に歌ってくれればよいのにと早々に引揚げ、朝が早かったのでもう一っ風呂だけ浴びて寝てしまう。民謡佐渡おけさについて翌日のガイドさんの話では、おけさとは猫の名前「けさ」からきたという、僕は一番しか歌詞を知らないから分からないけれど、これも一説としてあるのかな、本当ですかねぇ。
翌朝は内風呂だけとなり、早々と入りに行けばこういう団体旅行客が多いと早い出発組もあって、むしろ始めのほうが混みあっている。少しばかりゴロゴロしてからの広間での朝食はイカ刺と海草加工のいごねり、ナガメ入り味噌汁は定番らしく、これらも二日目と同じであった。アジ干物と湯豆腐はコンロで炙り暖めて、あとは厚焼玉子、海苔、漬物と、佐渡では納豆は出なかったがやはり御飯2杯までと、もっと食べたいのを我慢、我慢。食事の終わり具合を見計らって仲居さんの楊枝サービスが各自の前まで回るのは初めての光景、これも二日目の宿でも同様だったので、団体旅行でもバイキングじゃないときはいつもこうなんだろうか、それとも佐渡旅館組合独自のやり方なのかと、女房と顔を見合わせちゃいましたよ。そういえば夜用に氷水ポットが部屋に出されたのも、二つの宿で共通でしたね。