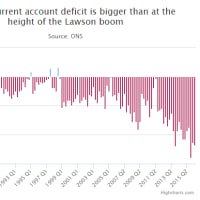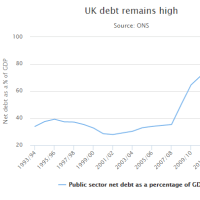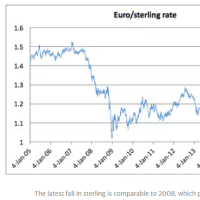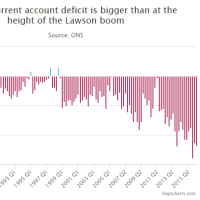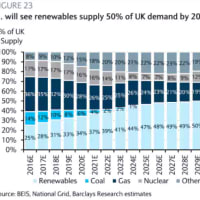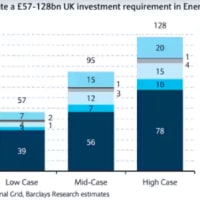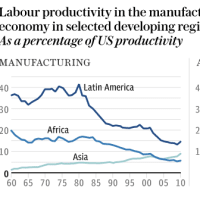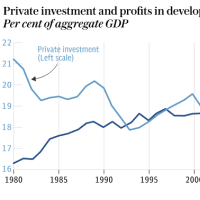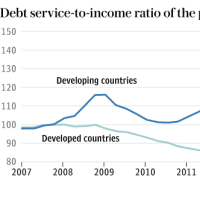Monoliners may make financial crisis a whole lot worse
(モノライン保証会社が、金融危機を更に悪化させるかもしれない)
By Roger Bootle
Telegraph:28/01/2008
(モノライン保証会社が、金融危機を更に悪化させるかもしれない)
By Roger Bootle
Telegraph:28/01/2008
Who said high finance was boring? Last week, as markets gyrated and the US central bank unexpectedly cut interest rates, the new obsession for the markets, the media and ordinary people alike was whether we are heading for recession. Well, are we or aren't we, and if so, what can be done about it?つづく
どこのどいつだ、ハイ・ファイナンスなんてつまんねーなんて言ったのは?
先週は市場がバタバタになってアメリカの中央銀行が電撃利下げする中、メディアも一般人も口を揃えて、ボクらは不況突入ですか?だってさ。
まあね、不況に突入してるかしてないかとか、してたらどーするとか、どーにか出来るもんなのかよ?
Too much attention is paid to the R-word. In this country, by common agreement among economists (a rare thing) a recession means two consecutive quarters of falling output (i.e. negative economic growth). Quite why it is two quarters and not three, or indeed one, I am not sure. On this definition, the UK had a recession in 1990-92 and 1979-81. But since the war, in most developed countries, recessions have been rare.
不況って言葉を気にし過ぎだっつーの。
この国じゃ、不況ってのは2四半期連続アウトプットが落ちること(つまりマイナス成長だな)ってエコノミストの間で決まってんだよ。
何で2期連続で3期じゃねーんだとか、なんで一期じゃダメなんだとか言われても知らねーよ。
この定義でいけば、イギリスは1990-92年、1979-81年に不況だったってことになる。
が、戦争が終わってからこっち、殆どの先進国で不況なんて滅多にないんだよ。
Yet this definition may not be very helpful. An economy might experience exactly two consecutive quarters of slightly falling output and then recover sharply, such that once you look back you wonder what all the fuss was about. By contrast, an economy which normally grows at 2pc-3pc may stagnate for years, although never actually experiencing falling output. In this case the loss of output, and the real human suffering from unemployment and financial anxiety would be much greater, even though it would not technically qualify as a recession.
だけど、この定義もあんまり役に立たないかもな。
きっちり2期連続マイナス成長した後に急反発、とかありかもしれないから、その場合なら後でなんであんなに大騒ぎしたんだよ、ってことになるかもしれない。
逆に、一度もはっきりとしたマイナス成長がなくても、普通なら2-3%で成長してるところが何年も低迷、ってこともあるかもしれない。
この場合なら、技術的には不況じゃねーよといわれたって、生産活動はマイナスだわ、失業やら金銭的な不安からくる現実的な痛みも酷い、ってことになる。
What matters is the extent to which the level of actual output falls below potential and the length of time the economy spends in this state. Looked at in this way, the issue is not binary - it is not a matter of whether or not the economy is in recession, but rather of how much output is lost. This is a continuum.
問題はさ、どれだけ潜在性よりも実際の生産活動が落ち込んでるかってことや、経済がその状態でいる時間の長さだな。
こうやってみれば、この問題はバイナリーじゃないわけ。
つまり、問題は経済が不況にあるかどうかってことじゃなくて、どんだけの生産活動が失われたかってこと。
これは連続してるんだ。
In this regard, the recent experience of Japan is interesting. People talk of a lost decade. In fact, between 1993 and 2002, the Japanese growth rate was not negative. It averaged about 1pc. But this represented an enormous loss of output compared with potential.
この意味じゃ日本の最近の経験は面白いよね。
皆「失われた十年」とやらについて語るんだけどさ、実は、1993-2002年の間も日本の成長率はマイナスじゃないんだね。
平均すると1%。
でもこれは潜在性に比べて実際の生産活動が恐ろしくマイナスだった、ってことなんだな。
So, on this criterion, how do things stack up now? The likelihood is that the problems experienced on the downside will be roughly proportionate to the distortions engendered on the upside. In the US and the UK, in the bull phase, the personal savings ratio reached unplumbed depths while the bubble in residential property prices reached unprecedented levels. On this criterion, you might think that the loss of output on the downside will be enormous.
というわけで、こんな感じて話をすると、今はどのあたりってことなんだけど。
多分ね、下がる時は上がった分だけ落ちるもんなんだよね。
アメリカとイギリスではブルの間、貯金が激減して住宅価格が青天井。
これに基づけば、下降局面のマイナス成長もすっごいことになるかもよ、と思うだろうね。
But there are some countervailing factors. Although UK commercial property prices have been inflated, and banks' exposure to the sector has never been higher, the scale of over-valuation has not been gargantuan. Moreover, equity prices have not been massively inflated.
でも逆のファクターもあるんだよ。
イギリスの商業用不動産の価格は上がったし、銀行のこのセクターに対するリスクは史上最高だけど、過大評価は大したことないんだな。
それに株価だって思いっ切り吊り上げられてたわけじゃない。
Japan in the 1990s provides an interesting yardstick. Like us, they experienced an asset price bubble and when it burst the financial system became extremely shaky. But the Japanese difficulties were on a completely different scale to our current ills. At one point, the real estate value of the gardens of the Imperial Palace in Tokyo exceeded that of the entire state of California. Now they would be lucky to match Sacramento. Meanwhile, at its peak, the price/earnings ratio on Japanese equities reached 102. From this, the stock market fell by 80pc.
1990年代の日本が興味深い定規を提供してくれる。
日本人もボクらみたいに資産バブルを経験した。
それにバブルが弾けた時には、金融システムはおっそろしくガタガタになった。
でも日本人の問題は、現在の我々の問題とは完全に桁違いだったんだよ。
だってさ、東京都の皇居の庭の不動産価格がカリフォルニア州全体よりも高い時があったんだから。
今じゃ幸運にもサクラメント程度だけどね。
かと思えば、ピーク時の日本銘柄のPERなんて102だよ、102。
ここから株式市場は80%も暴落したわけ。
That said, there is a clear danger that our situation could get a lot worse. All along, the complacency of the equity markets about the credit crunch has astonished me. The prevailing assumption seems to have been that the problem was about a little local difficulty in the US sub-prime mortgage market. Regular readers will recall that from the beginning I have been sceptical that matters would end there. From a position a year ago where no sane person had even heard of the sub-prime mortgage market, we have progressed to the position where it is regularly discussed in the Dog and Duck.
つまりね、我々の状況が遥かに酷くなっちゃう危険性は明白だってこと。
最初からさあ、あんまりにも株式市場がクレジット・クランチに無頓着だから、驚いてたんだよね。
皆さ、アメリカのサブプライム・モーゲージ市場の地元でのちょっとしたいざこざ、ぐらいに思ってたでしょ。
常連の読者さんなら覚えてるよね。
最初からボクはそこでおわんねーぞ、って懐疑派だったってこと。
一年前は正気の人間なら「サブプライム・モーゲージ市場」なんて聴いたこともなかったのに、今じゃ床屋談義の十八番ってところまで来ちゃったじゃん。