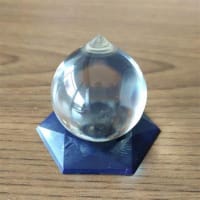1945年8月6日にアメリカにより広島市に原子爆弾投下された日である。
俳句では今日と長崎市にも落とされた8月9日の両日を「原爆忌」として多くの俳句が詠まれてきた。
『季語別鷹俳句集』からぼくの好きな秀句をいくつか拾う。
手がありて鉄棒つかむ原爆忌 奥坂まや
知らぬ子が硝子に映る原爆忌 清水風子
人間の息に囲まれ原爆忌 竹岡一郎
いずれもこの忌日の本質を突いているように思う。ぼくも次のような句を詠んでいる。
原爆忌青い魚を喰うてゐる わたる
文字通り青いなあと思う。忌日俳句とはなんなのか。その日を恭しく畏まることなのか、あるいは慰霊することなのか。俳句で原爆忌を読むことに意味があるのか。
ぼくの場合はそういう日があるなあと思っていると青い魚を喰う自分が浮んだ、それが五七五になった、というだけのこと。
広島市では慰霊祭が行われる。そこで市長が毎年核兵器根絶を世界に向けて訴える。
しかし、政府は2007年4月に国連に提出された核兵器禁止条約に日本は参加していない。アメリカの原爆を食らって敗北しアメリカの仲間となった国。いまその核の傘の下にあって安全保障の大半を依存している身の上では核兵器根絶を叫べないことを納得せざるを得ない。広島市民と日本人全体とでは核をめぐる意識に差がある。
ちょっとものを考える人なら現在の絶望と頽廃とやるせない感じはわかるだろう。「へいわへいわ」と叫ぶたびに何かがこぼれ落ちていく感じ…。
文学も政治も言葉が嘘っぽく感じられる日である。核兵器根絶を言いたい…けれど言えない…言えない危機がそこにある。こういった現実と理想の間で懊悩する作家が白石一文だろう。
彼の『すぐそばの彼方』(2001/角川書店)を読んだ。

【内容情報】(「BOOK」データベースより)
次期首相の本命と目される大物代議士柴田龍三を父にもつ龍彦。
彼は、四年前に起こした不祥事の結果、精神に失調をきたし、父の秘書を務めながらも、日々の生活費にさえ事欠く不遇な状況にあった。父の総裁選出馬を契機に、政界の深部に呑み込まれていく彼は、徐々に自分を取り戻し始めるが、再生の過程で人生最大の選択を迫られる…。
龍彦は父のあとをついで政治家になるのか、不遇のとき知り合った好きな女と自分の娘と共に小さな生活をするか、というわかりやすい選択の物語である。
父龍三も息子龍彦も作家的才能と政治的能力を併せ持つ。それは石原慎太郎を彷彿とさせる。
白石一文の魅力はひとくちで言えば、<青っぽさ>である。政治の言葉、文学の言葉という中で主人公を懊悩させる。
「人間はある特定の個人とのつながりに救いを見い出そうとするかぎりは永遠に苦しみから逃れることはできない。無償の心で多くの人を救おうと発心することによってのみ自らを救うことができるのだ、と彼は考えていた」
この一点において政治という仕事に魅力を抱いてきた龍彦が謀反を起こす…。
メロドラマであり甘いのであるが、政治の世界における金の授受や陰謀、恫喝、詐術などを余すことなく活写する。
嘘っぽさのついてまわる忌日に読んで真摯な青っぽさを見直すにいい本である。