
ネット句会の利点は句評をしかと文字にすることと考える時間がたっぷりあることである。句評の声が消えてゆく対面句会とこれが大きく違う。対面句会でも書きとめている人もいるがなにせ限られた時間内のことゆえおおざっぱな理解で終わることが多いだろう。
ネット句会は論争が微に入り細をうがつことになり、それは利点なのだが、論争をとことんやっても仕方ないということも考えておくべき。
あるいは、ものすごく勉強したい句歴の浅い人がいて彼は句の良し悪しについて徹底的に白黒をつけたい志向が強く、指導者に判定を求める。また、句作のポイントを細かく聴きたがるのだが、合評がそうとうなされているのだからもう少し自分で考えてほしいと思う。
すべてのことを指導者、上級者から一挙手一投足にいたるまで教わろうという姿勢はいかがなものか。
日本の芸道は権威によって支えられているが、とにかく権威にすがって良し悪しを決めてもらおうという姿勢でいいのであろうか。
いま、比較的初心者とネット句会をやっていて、なんでもかでも小生に判定を求めるという依存体質の人がいることに問題を感じている。やれと言われればやるのだが、それが豊かさに通じるような気がしない。めいめいが悩み考える豊かさを奪ってしまうような気がして。
俳句界の今もって大きな権威の高浜虚子は俳句の取捨のみで評価したというのは有名な話である。
いい悪いのわけを言わないという指導である。わけはめいめい考えよ、である。これはもの凄く難解なテキストを何十回も読んで読み解くのに似ている。
ぼくは虚子ほど大物ではないが句の取捨だけで済ませることにときにえらく惹かれる。
惹かれるけれどこれを今やったら誰も小生のところにやって来ないだろう。虚子の権威は凄かったとあらためて思う。
日本の文化、教育がマニュアル化され過ぎていないか。
藤田湘子の『20週俳句入門』をぼくはテキストにしているがこれはマニュアルとしてずば抜けている。今、彼の提唱した「型その4」で作ってもらっていて、問題の人はその型の句でどれが叶っていてどれが外れているのか句会に出た全句について判定をぼくにさせたがる。
けれどその答えは藤田湘子がその本のなかで解説している。しっかり述べている。ぼくがあらためてこれは○これは×などと言うことが本当に豊かなことなのか。
マニュアルはしかとあるのだから、またぼくに詳しい説明を求めていてどうなる。もう自分の頭で考えろよ、と言いたい。
俳句に正解はないし絶対もない。白黒はつけようとしすぎるのは俳句を殺すことになる。わからないことに関し七転八倒して自分で悩むということを放棄してしまったら君はどうなる。
近代化が徹底的に習うことだとしたらそれは間違いではなかろうか。自分で悩んで結論が出ない時間を楽しんでよ、と言いたい。手っ取り早く解決しようと思うなよ、問題を背負って右往左往しろよ。それが豊かさだよ、俳句をやり続ける意義だよ。
撮影地:多摩川


















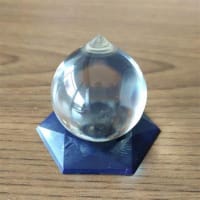







出題は君の奥さんが夕食に何をつくろうかというのに似ている。彼女が献立をそう理論的に考えているのかな。
ポイントというのを湘子があの本で手を替え品を替え展開してる。それをしっかり何度も読むべき。
あの本をしっかり読まないでそれをしっかり読んだ人に要約を教えてほしい、というのが困るわけ。
あの本を5回ほど君は読んだのか。
天地わたる先生はよほど敷居の高い句会で指導されているようですが世の中には色んな方がいらっしゃいます。
ほがらかにおおらかに。