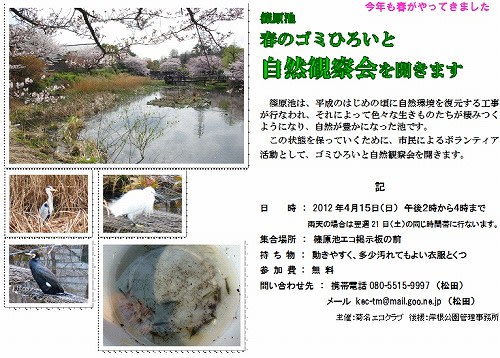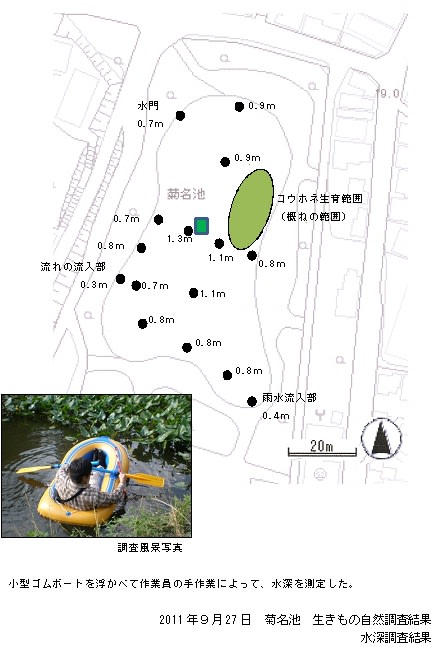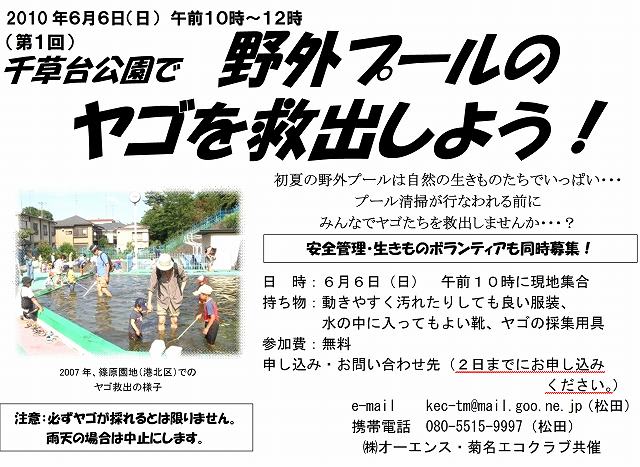「菊名エコクラブ ブログ」は横浜市港北区の町なかにある、いくつかの公園を中心とした
自然や自然の生きものたちについて扱っています。
このように限定された地域での、さらに町なかに島のように点々と残された公園の中の自然
について取り扱っている関係上、そう多くのアクセスがあるわけではありません。
しかし、それでも毎日40~60人、平均で50人の方がこのブログを見てくれています。
そこで、このブログをご覧になっているみなさんに、お願いがあります。
もちろん、強制などできるわけありません。
ただ共感していただけるならば、身近な自然との共存へと第一歩を踏み出していただきたい
のです。
日本は春を迎え、もうすぐ桜が咲こうとしています。
世の中は桜桜と桜ばかりに目を向けますが、春に花を咲かせる植物は桜だけではありません。
しかし、こうした中で桜を見上げてばかりで、足元に咲く小さな春の花を踏みつけにしてし
まうようなことをしてしまいがちです。
私がお願いしたいのは、桜以外の野の花たちにも目を向けて、楽しんでほしいということです。
桜だけじゃなく、春の花全部を見て楽しむつもりで、ぜひ春の花と親しんでほしいのです。
「新年にあたってのメッセージ ~自然を守るわけ~」でもお話したように、自然は私たち
人間にとってあらゆる環境資源となる大切なものです。
そして、その自然というのは桜だけでなく、色々な木や草、そしてそこに住む小鳥や昆虫たち
によってできています。
ですので、これらの春の小さな花たちに目をむけ、その存在を知り、魅力を知ることが、自然
を守る、自然と共存していく第一歩となるのです。
ですので、ぜひ、春の色々な花を楽しんでみてくださいね。
そして参加できる方はぜひ、4月15日の自然観察会にご参加ください。
私が春の野の花たちをご案内いたします。
(菊名池と篠原池とでは少々内容が異なりますが、池の中の生きものを捕獲して観察したり、
池のゴミ拾いも行います。)
自然や自然の生きものたちについて扱っています。
このように限定された地域での、さらに町なかに島のように点々と残された公園の中の自然
について取り扱っている関係上、そう多くのアクセスがあるわけではありません。
しかし、それでも毎日40~60人、平均で50人の方がこのブログを見てくれています。
そこで、このブログをご覧になっているみなさんに、お願いがあります。
もちろん、強制などできるわけありません。
ただ共感していただけるならば、身近な自然との共存へと第一歩を踏み出していただきたい
のです。
日本は春を迎え、もうすぐ桜が咲こうとしています。
世の中は桜桜と桜ばかりに目を向けますが、春に花を咲かせる植物は桜だけではありません。
しかし、こうした中で桜を見上げてばかりで、足元に咲く小さな春の花を踏みつけにしてし
まうようなことをしてしまいがちです。
私がお願いしたいのは、桜以外の野の花たちにも目を向けて、楽しんでほしいということです。
桜だけじゃなく、春の花全部を見て楽しむつもりで、ぜひ春の花と親しんでほしいのです。
「新年にあたってのメッセージ ~自然を守るわけ~」でもお話したように、自然は私たち
人間にとってあらゆる環境資源となる大切なものです。
そして、その自然というのは桜だけでなく、色々な木や草、そしてそこに住む小鳥や昆虫たち
によってできています。
ですので、これらの春の小さな花たちに目をむけ、その存在を知り、魅力を知ることが、自然
を守る、自然と共存していく第一歩となるのです。
ですので、ぜひ、春の色々な花を楽しんでみてくださいね。
そして参加できる方はぜひ、4月15日の自然観察会にご参加ください。
私が春の野の花たちをご案内いたします。
(菊名池と篠原池とでは少々内容が異なりますが、池の中の生きものを捕獲して観察したり、
池のゴミ拾いも行います。)