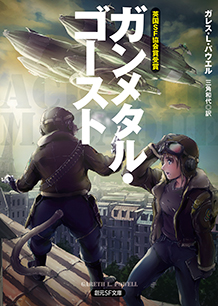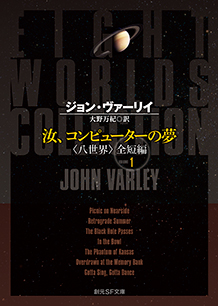『ガンメタル・ゴースト』 ガレス・L・パウエル (創元SF文庫)
みんな猿が大好き!
この猿、イメージ的にはチンパンジーではなく、テナガザルかクモザル。フライトジャケットを着て、片目がアイパッチで葉巻を咥えたハードボイルドな男。その名も、『アクアク・マカーク』が、実は原題そのもの。すべてはこの猿のキャラクターから始まった。
というわけで、邦題の『ガンメタル・ゴースト』って、いったいどこから来たんだろう。
英国SF協会賞を『叛逆航路』と同時受賞だそうだが、ちょっと陰鬱な英国SF独特のテイストは見当たらない。それよりも、日本やアメリカで受けそうなヒーローもの。実際、日本のアニメや、変な日本文化の影響が見られる要素もある。といいつつ、ひねりも効いていてただのヒーローものでは終わらない。
もう一人の主人公はヴィクトリア。元新聞記者ながら、棒術を使いこなし、何度殺されかけてもへこたれずに、マカークとともに殴り込みをかける行動派の女性。
この二人に加え、敵も味方も、いずれもキャラのたった登場人物ばかりで、文体を変えてイラストを付ければラノベとして充分通用するのではないかと思う。
SFとして見れば、歴史改変SFであり、生体改造SFであり、仮想現実SFであり、まぁ本当になんでもあり。
敵となるアンダイイングの主張や陰謀がちょっと陳腐ではあるものの、デジタル的な人格移植が可能になれば、デジタル情報だけを乗せてロケットを飛ばし、現地でアンドロイドにダウンロードなんてことは普通にやれそうだ。
ただ、この小説内のアイディアだと、人格の記録は行動履歴ログの延長上にあり、同じ記憶を持っていれば同じ人格的な取扱いをされているのだが、本当だろうか。人格とは記憶よりももっと身体的な情報なのではないかと思うのだけれど。
まぁ、とにかく痛快な冒険SFなので、ぜひ映像化して欲しいと思う。
なお、シリーズ化されそうな感じもあるが、それはちょっとどうだろう。ネタを大幅に変えないと、この猿、初登場のインパクトは超えられないんじゃないだろうか。