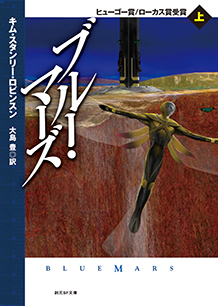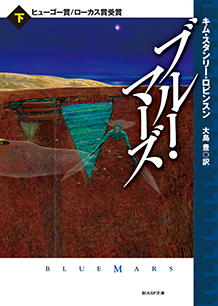なんともお久しぶりの新井素子。
新井素子と言えば、中学校に雑誌付録のピンナップを持ってきた奴がいたが、あれは月刊コバルトだったか、アニメージュだったか。いいか、綿谷りさみたいな、あるいは、川上未映子みたいな美人じゃないぞ。あの、新井素子のピンナップだぞ。思えば、声優だって昔は林原やみやむーが絶世の美女扱いだったのだから、まあそういうこともあるだろう。とにかく、そんな感じで素子姫はアイドルだった時代があるのだよ。……って、いったい何十年前の話だ。
まぁ、そんなことはさておき……。
えっと、この作品は夢を媒介にして過去の自分とつながってしまった主人公が、娘(双子の片割れ)の香苗を事故死から救うために四苦八苦する、というお話です。
まぁ、とにかくこの主人公が、学はそれなりにある(カッサンドラとか知っているし)ものの、かなり知識が偏っていて、しかも本人が思っている以上にすっとぼけているので、かなりイライラする。例えるならば、コニー・ウィリスが繰り返す、すれ違いくらいイライラする。まったく、おばちゃんというものは……!(偏見)
上巻は本当に、なんでこいつらこんなに阿呆なんだろうとイライラしっぱなしで困った。
それが、下巻に入ると、生き残った双子の片割れである菜苗やら、男気のあるママ友やらに助けられ、最後は香苗本人のチカラによってミッションは成功するのだが、そこにはタイムパラドクスが!
しかし、そこはさすがの新井素子。綺麗に感動の枝篇までつなげているところは感心した。なんというか、本人も生粋のSFファンだけあって、SFの勘所を押さえてるよなと思う。このあたりはなんとも説明しづらいのだけれど。
で、やっぱり気になるのが、旦那の不在なのだよ。
香苗の死の直後に、あれだけ妻の支えになり、男性っぽく(そこは新井素子が意識しているのかどうかは不明だけれど)共感よりも問題解決を重視する対策を打ち出し、主人公を救った旦那さんは、いったい何をしていたのか。
これ、もしかしたら、旦那さんは主人公の異常を気づいていて、相談があるまで待っていたのかとも思うんだけど、それにしては解決までが長過ぎ。相談が無いからと言って、半年は待たないよなぁとか。もし、相談があったら何か解決ができたのかとか考えるんだけど……。少なくとも、野球のくだりは簡単になってたよね。あーでも、それだと坂井さんとのきっかけが無くなるか。
まぁそんなわけで、イライラとモヤモヤがつのりながらも、最後はさわやかに感動できた一品でした。