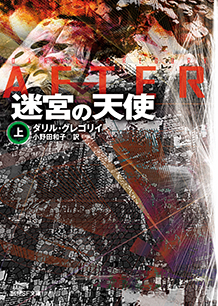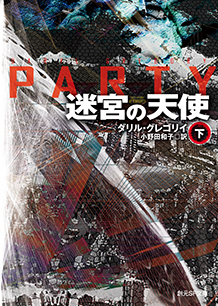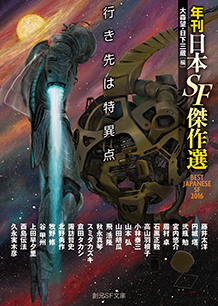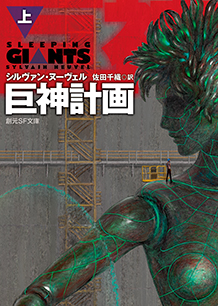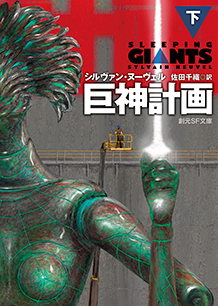『母の記憶に』 ケン・リュウ (新☆ハヤカワ・SF・シリーズ)

ケン・リュウの日本オリジナル第二短編集。
ケン・リュウといえば、前回の『紙の動物園』や、今回の表題作「母の記憶に」などから叙情的なSFの名手と思っていたのだけれど、今回の短編集はもの凄くバラエティに富んでいて、ちょと認識を改めた。
SF的要素のほとんどない中華ファンタジーから、バリバリの本格SFに至るまで、様々な形式の作品が収められている。ひとりの人間がこれらを全部書いたというのが信じられないほどだ。ピース又吉から『紙の動物園』経由でこの本を手に取った人に取っては、逆に違和感があったり、新鮮だったりするんじゃないだろうか。
さらに、このブログでは特に言っておかなければいけないのは、こういう境界領域と見做される作家に多い、SFへの理解の無さを全く感じることがなかったということ。この人、こちら側の人だよ。
「重荷は常に汝とともに」なんて、60年代の日本SFと言われても納得するし、「シミュラクラ」なんて、イーガンが書いてもおかしくない本格SFだし、「レギュラー」にいたってはSFハードボイルドで本当にびっくりだ。
それでいて、「草を結びて……」だったり、「万味調和」だったり、中国生まれのアメリカ人としての立ち位置を体現するような作品も素晴らしいし、一般的にはこちらの顔の方がフィーチャーされるのは良くわかる。
そんなわけで、いずれも甲乙つけがたい珠玉の作品集であるわけだが、今回の作品集の中で敢えて【好み】で選ぶとすれば、やはり「烏蘇里羆」と「母の記憶に」。前者は北海道ゆかりの作品であるというだけで満点。後者はSFファンだからこそ、この濃縮された感動を味わえるのだと思いたい。
一方で、どれが【完成度】が高いかと言われれば、「万味調和」を選ばなければならないだろう。アメリカ西海岸に渡った中国人たちの物語なわけだが、事実だけが書かれているはずのエピローグが、まるでSFのオチであるかのような衝撃だった。
○「烏蘇里羆」
魔術(妖怪)とスチームパンクの共存する世界はワクワクするが、歴史はその共存を許さない。蝦夷の地から満洲へ追いやられた羆族には三毛別事件の影も見られるし、アイヌの姿も重なる。道産子としては必読の一篇。
○「草を結びて環を銜えん」
緑鶸が雀を守ろうとする気持ちと、それに最後まで気づけなかった雀の幼さが泣ける。緑鶸の優しさと勇気が伝えるメッセージが多くの人々に届きますように。
○「重荷は常に汝とともに」
古代文明を読み解くことの難しさを皮肉るような作品。なんというか、とても日本SFっぽい。
○「母の記憶に」
ものすごく短いシーンの羅列にすぎないのだけれど、そこに濃縮された時間の積み重ねを感じる。娘を思う母の気持ちと、母を思う娘の気持ちが何度もすれ違い、それが寄り添った時には残された時間はあまりに少ない。良くある話がさらに圧縮されて、感動が際立つ。
○「存在」
こちらも良くある話が、テレプレゼンスという技術によって距離が圧縮される。このタイトルに「遠隔(テレ)」を付けない「存在(プレゼンス)」としたのもテーマを際立たせている。
○「シミュラクラ」
これも父と娘のすれ違いの可視化。ちょっとSF的な視点では、登場キャラクターのどこまでがシミュレーションなのかが曖昧なところが面白い。
○「レギュラー」
驚くほど形式にのっとったSFハードボイルド。タイトルの言葉が様々な意味で物語に登場するが、“regular”とはどういうことかと、そのたびに考えさせられる。
○「ループのなかで」
“こちら側”のループ。描かれない“向こう側”のループ。悲劇も愚行も繰り返される。
○「状態変化」
魂のありかの問題と、そんなの気のせいということ。
○「パーフェクト・マッチ」
人に奉仕するアルゴリズムがモンスター化する話を、もうひとひねりしている。こっちの方が本質的な問題。
○「カサンドラ」
運命と自由意思の戦い。敵はスーパーマン。
○「残されし者」
著者にとっては重要なテーマの様だが、この手の話はいろいろ破綻しているように見える。世界が破滅したなら、誰がサーバーを管理しているのだ?
○「上級読者のための比較認知科学絵本」
タイトルが指すものが何かが分かったときのちょっとした感動。
○「訴訟師と猿の王」
史実を下敷きにした中華系ファンタジー。しかしまぁ、彼の地での虐殺事件は多いな。そのあたりは南京事件の認識にも影響しているんだろう。ところで、孫悟空って、アメリカ人は知ってるのか。
○「万味調和」
悟空の次は関羽。これも史実を下敷きにした中華系ファンタジーと言えるが、ファンタジー成分はほとんど無し。しかしながら、史実がまるで作り話のように聞こえるところが皮肉にもファンタジー。
○「『輸送年報』より「長距離貨物輸送飛行船」(〈パシフィック・マンスリー〉誌二〇〇九年五月号掲載)」
舞台は現代的なパラレルワールド。作風としては、魔術とスチームパンクの系譜。初読では世界観に惹かれたが、読み直してみると、夫婦のすれ違いと、それでも揺るがない絆の話。こういう、普遍的なテーマをSF的に凝縮するテクニックは巧い。