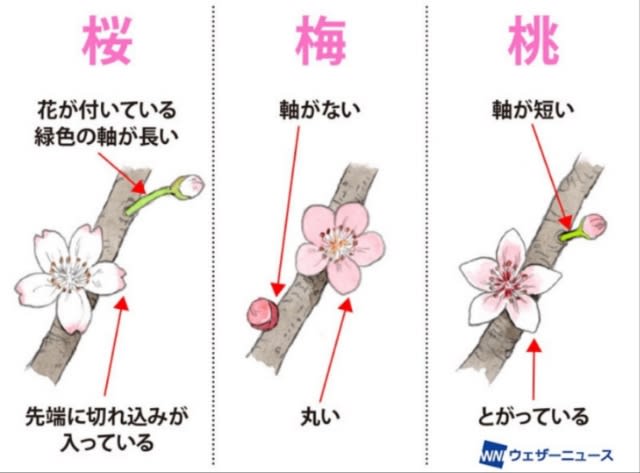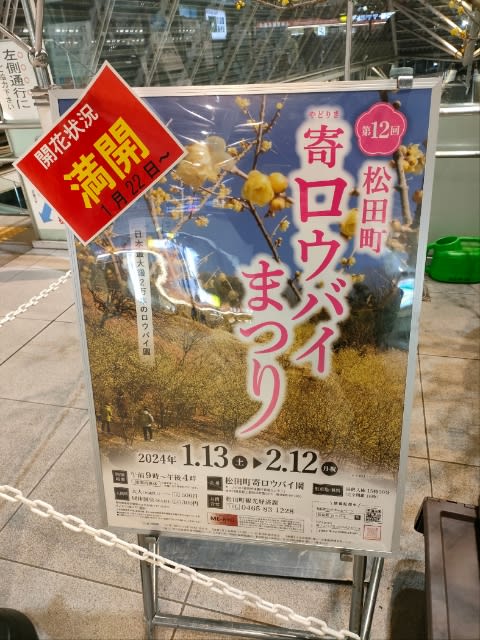今日、小田原の小学校では終業式が行われました。明日からは夏休みですが、私は今日は出勤契約日ではなかったためお休みでした。
さて、どうしようか…と思ったのですが、折角時間があるので今日も蓮見に出かけてみることにしました。しかも、今日は手軽に厚木市内です(笑)。
ということで、今日やって来たのは厚木市棚沢にある常昌院という禅寺です。
雲渓山常昌院は400年の歴史を持つ曹洞宗のお寺ですが、江戸方面から最初の山となる鳶尾山(とびおやま)を背後に擁し、古くから修験道の信仰が深く根づく『里山の寺』でもあります。常昌院付近は沼や池が多く水が豊富な場所で、境内には水の絶えない沢があることから『雨乞いの場』としても信仰されていました。
開創は厚木市の隣の愛川町の八菅山(はすげやま)付近だったそうですが、第5代住職の頃に棚沢の地に移転して来たと伝わります。かつては、
 上の絵図のような茅葺きの本堂と庫裡、坐禅堂などの建物がありましたが、残念ながら昭和33(1958)年に発生した大火で全焼してしまい、三寸の誕生佛のみが残るのみで今は御堂も仏像も当時のものは遺っていません。
上の絵図のような茅葺きの本堂と庫裡、坐禅堂などの建物がありましたが、残念ながら昭和33(1958)年に発生した大火で全焼してしまい、三寸の誕生佛のみが残るのみで今は御堂も仏像も当時のものは遺っていません。
こちらのお寺は花に力を入れていて、境内では四季折々にいろいろな花を楽しむことができるようになっています。現在では『東国花の寺百ケ寺』のひとつに数えられるまでになり、特に春の桜の時期と今の蓮の時期には多くの人たちが訪れるようになっています。
本厚木駅から『あつぎ郷土資料館』行きのバスに乗り、『棚沢』バス停でバスを降りて10分ほど歩くとお寺の入口が見えてきます。

三白眼気味の若干怖いお顔立ち(失礼な…)の仁王像の向こうに

平成時代に新築された鴟尾(しび)を戴く大きな本堂が見えてきます。そこへ上がる石段の手前には

白蓮の鉢が置かれていて

これから訪れる蓮池への期待感を高めてくれます。
本堂の横を回り込むと、裏手にお目当ての蓮池があります。

『不老門』と銘打たれた低い門をくぐると、その先には

一面に大賀ハスが広がっています。
こちらの大賀ハスの花は若干小ぶりながら、なかなか美しい色合いでした。蓮池の上には八ツ橋が架けられていて、咲いている蓮の花の側まで近づくことができるようになっているので、
中には今朝開いたばかりであろう花も見ることができ、


はっとするほどの色の濃さを見せていました。蓮池のほとりには

蓮弁の舟に乗る優美な姿の菩薩像が安置されていて、
境内の木々の枝には
 風鈴が提げられていて、風が吹くと涼しげな音色を響かせています。これは小田原で作られている『鈴虫風鈴』というものですが、こんなところでも小田原市との縁があったことに、個人的にちょっと驚きました。
風鈴が提げられていて、風が吹くと涼しげな音色を響かせています。これは小田原で作られている『鈴虫風鈴』というものですが、こんなところでも小田原市との縁があったことに、個人的にちょっと驚きました。
今日、関西や中部、東海地方での梅雨明けが宣言されましたが、関東地方はまだおあずけのようです。今年は例年になく梅雨明けの判断が難しいと言われていますが、来週くらいには関東でも無事に梅雨明けが宣言されることになるでしょうか。