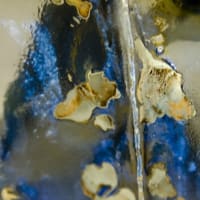2007/07/14 07:00
産経新聞特集記事(山田智章記者筆)
【凛として】ヤミ米“拒否死”の裁判官
山口良忠(1)~(5)2004年5月連載より
「人間として生きている以上、私は自分の望むように生きたい。
私はよい仕事をしたい。
判事として正しい裁判をしたいのだ。
経済犯を裁くのにヤミはできない。
ヤミにかかわっている曇りが少しでも自分にあったならば、自信がもてないだろう。
これから私の食事は必ず配給米だけで賄(まかな)ってくれ。
倒れるかもしれない。 死ぬかもしれない。
しかし、良心をごまかしていくよりはよい」
決死の覚悟だったにもかかわらず、そう語る山口良忠の表情からは気負ったようすはなかった。
妻、矩(のり)子にヤミを食べないことを宣言した昭和二十一(一九四六)年十月初めの夜から一年間、山口は信念のみに生きていくことになる。
ちょうどこのとき、山口は東京刑事地裁から、東京区裁への転勤辞令を受けた。
ヤミによる食管法違反などが頻発していた時期で、経済犯専任の判事に任命されたのだ。これまで以上にヤミと向き合うことが決まり、山口にはこの選択しかなかった。
しかし、山口の覚悟は、ただ判事としての自分にのみ向けたものだった。矩子にはこうも語っている。
「人間は孤独だ。お前がこれについて何を考えようと自由である。私は、お前や子供たちにまで絶対配給生活を強いはしない。それはお前たちの好きなようにしなさい」
二十五歳の司法官試補の山口と、女学校を出て油絵を習っていた二十歳の矩子が出会ったのは昭和十四年の晩秋だった。
山口と同郷の法学博士、織田萬(よろず)の紹介による東京・帝国ホテルでの見合いの場だった。
矩子の父も佐賀県の出身で、元大審院判事の神垣秀六だった。
縁談はトントン拍子で進み、二人は翌十五年十二月二十三日、東京で式を挙げた。
新婚旅行は伊豆湯ケ島だった。
結婚後、山口は横浜地裁予備判事を経て甲府地裁の判事となった。
土地柄とまだ時代がよかったせいか、扱う事件数も多くなく、穏やかなときが過ごせた。
東京に戻ってきたのは昭和十七年六月、東京民事地裁判事としてだった。
この年には二人の間に長男が誕生するなど、まだ飢餓の恐怖はうかがい知れなかった。
しかし、この年の七月、山口を縛ることになる食糧管理法が施行される。
二人が東京で居を構えたのは矩子の牛込区(現・新宿区)の実家だった。
神垣がちょうど青森地裁所長に赴いていたため、留守宅を預かったのだ。
約一年後、世田谷区玉川奥沢町の借家に移った。
戦況は徐々に悪化し、食糧難の波が押し寄せ、施行一年目には順調にみえた食管法が人々を苦しめはじめた。
十九年十一月には、山口は矩子と長男を実家の佐賀県白石町に疎開させた。
矩子は二人目を身ごもっていた。
その後東京は空襲にさらされ、敗戦を迎えた。
山口が妻と長男、そしてまだ見ぬ二男との生活を取り戻したのは二十年十月だった。東京は焼け野原だったが、山口にとっては、元気な二児と若くて気立てのよい妻に囲まれた人生至福のときだった。
しかし、世の中は乱れ、食糧は尽きていた。
ヤミにまつわる事件は日増しに増えていった。
「ヤミは食べない」
と、山口から宣告された矩子は、言いようのない悲しみのなかにいた。
しかし、自分だけは、この孤高の判事である夫についていこうと決心し、二人そろって配給だけの生活を始めた。
矩子は手記にこう書いている。
「主人についていこうと決心しましたのも、私自身、裁判官という特別な家庭に育ったこともありましたでしょうが、主人のすることをすべて信じ切っていたからでしょうね」
この当時、配給だけの食卓はどうだったのか。
矩子はそれを「まことに惨めで、身動きできない有様(ありさま)」と表現している。
主食は缶詰のときはそれだけ、豆のときは豆だけを食べ、子供たちにその多くを与えて夫婦は残りを食べ、水を飲んで過ごしていた。
「人間である以上、生きていたい。おいしいものを食べていたいと思う。しかし、正しいことはしなくてはならない」
と、迷いのない眼で語った山口に矩子は従い、ついていった。
そんな二人をみかねた矩子の父、神垣は「孫の顔を見せてくれ」などと自宅に山口たちを呼んで、あの手この手で食べさせようとした。
しかし、山口は終(つい)ぞ手をつけることもなく、逆に義父らの心遣いを察して、「用事がある」といっては、義父宅に足を向けなくなっていった。
ただ、矩子や子供たちは行かせた。
山口の父、良吾も上京したとき、やつれた息子夫婦を目にしている。
心配する父に山口は、
「単独裁判の裁判長を務めておりますため、疲れ気味なだけです」
と答え、気丈な姿をみせようと、父のために風呂を薪でわかしたという。
しかし、父は食事のときに夫婦が子供にだけ食べさせている姿をみて、矩子を追及し、息子の覚悟を知った。
「命を粗末にするな」
そう戒(いまし)める父に、山口は逆らわず、ただ黙ってうなずいて、ほほえみだけを返した。
山口は周囲の心配通り、倒れた。そして郷里の白石に戻った。
昭和二十二年十月十一日、山口は最期の時を迎えた。
矩子と二人の息子も白石に戻っていた。
その日の午後、矩子は新聞を読みたいと手まねで語る山口のために階下に新聞を取りに降りた。
部屋に戻り、差し出された山口の手に新聞を渡そうとしたその瞬間、手がぱたりと落ちた。あまりにあっけない臨終(りんじゅう)だった
「愚直」。悪法と認めつつも、人を裁く判事ゆえに食糧管理法を守り抜いて“餓死”した山口良忠を、こう表現してきた法曹関係者は多い。
元同級生ですら、しばしばこの言葉を使いたがった。
山口の故郷・佐賀の鍋島藩に伝わる武士道論書『葉隠(はがくれ)』の中の「武士道と云は、死ぬことと見付たり」との一節を引き合いに出し、その死を「自殺」に結びつけようとした批判もあった。
六年の月日を取材に費やし、山口良忠の生涯を追ったドキュメント「われ判事の職にあり」(文芸春秋)を書き上げた弁護士、山形道文(七五)は、こういった山口への論評に、ある解釈を加えた。
「同時代に生きた人々の多くは、山口判事さんを真正面から見ることができないんですよ」
戦後を生き延びた人たちにとって、ヤミを拒んで餓死した山口を肯定することは、自身の存在を否定することになると考えたからかもしれない、という。
戦後の動乱期、生き抜くことは、死ぬことよりも難しかった。
しかし、山形は「山口判事さんを『奇人』『変人』のように扱い、その生き方や人間性まで否定することは非礼以外の何物でもない」と強い調子でいう。
函館弁護士会会長も務めた山形は、法律家の手法で山口の生涯を丹念に調べた。
「事実の認定はすべて証拠による」
あたった資料は数え切れず、得た証言も膨大だ。ときには、反対尋問のごとく厳しく“証人”に詰め寄ったこともあった。
青森県弘前市に生まれ、北海道で育った山形が、山口の死を知ったのは旧制高校三年のときだった。
すでに裁判官を志し、法学部を目指して受験勉強に励んでいたころだ。
「裁判官」という職業について、いろいろ考えさせられたことを今でも覚えている。
山形はその後、東京大法学部に進み、裁判官ではなく、弁護士になった。
裁判官としての山口の死を、どこかに感じながら法曹の世界に入った人間も少なくない。
ダグラス・グラマン事件やリクルート事件などを手がけ、東京地検特捜部長や高松高検検事長、名古屋高検検事長を歴任した宗像(むなかた)紀夫(六二)も、そんな一人だ。
戦後、宗像の父もまた、ヤミを食べることを拒んだという。
「オヤジは食卓をみて、『ヤミなんか並べてないだろうな』
と、いつもお袋にきつく問いただしていた。
オヤジは孤高の人だったから、お袋が『配給だけですよ』といわないとだれも食事に手を出せなかった」
宗像の父は中学校の英語教師と獣医を兼ねていた。
当時、一家は東京から父の郷里の福島県三春町に疎開していたが、母が嫁入り道具の着物を売って米を買い、子供四人に食べさせた。
配給しか口にしようとしない父は、山口と同じように栄養失調から結核を患い、宗像が十五歳のときに亡くなった。
宗像の記憶に残る父の姿は、善悪に対する厳格さで、
「どんなに困っていても、間違ったことをしてはいけない(法を犯してはならない)」
といわれたことだ。
宗像は母の口から、父が、配給のみの生活で餓死した山口の生き方に感服していたことを聞いている。
検察官を目指したとき、自らを厳しく律することが求められる職業だと認識させられたのは、父の存在とともに、山口のことが意識のなかにあったからだ。
現在、司法改革の一環で司法試験は門戸が広げられ、簡単になったといわれる。
中央大法科大学院の教授でもある宗像は「試験突破が簡単になったからといって、持つべき倫理観まで簡単になるわけではない。
倫理観は人間性に基づく。
山口判事が貫いたものは現代でも色あせることはない」と語った。
山口は確かに孤高の人だった。
しかし、家族への思いは深かった。
弟の良和(八五)は、東京の国学院大で学んでいたころ、佐賀へ帰省するときには必ず京都で途中下車し、兄の下宿を訪ねていた。
佐賀高を卒業後、京都大法学部へと進んだ山口は京都市内で一人暮らしをしていたが、当時を知る人のほとんどが、「下宿と大学を往復するだけの生活」だったとその印象を語っていた。
ここでも“ガリ勉”のイメージがつきまとうが、それもまた真実ではなかった。
「一緒に神社やお寺を回りましたよ。金閣寺も一緒に行きました。楽しかった。勉強一辺倒の兄じゃなかったんです」
弟に観光案内ができるほど、山口はちゃんと京都の街を歩いていた。
良和は当時の様子を今でも目を潤ませて語る。
二十代の山口は恋愛も一途(いちず)だった。婚約中だった矩子には精いっぱいの愛情を、自筆のスケッチに込めて贈ったこともあった。
そして、だれよりも矩子が山口の生き方を称(たた)えている。
矩子は夫に一通の手紙をしたため、棺にそっと忍ばせた。
「あなたの一生は本当に清らかでした。私は生涯ひとりで生きます。いずれお会いできる日まで、さようなら」
矩子はのちに、夫の死について、「ただ人間には、笑って死んでいかなければならない時もあることを主人から厳しく教え込まれた気がしているのですよ」と山形に語っている。
亡き夫への誓いどおり、矩子はその後の生涯を独身で通し、六十三歳だった昭和五十七年四月、一人で暮らしていた東京・世田谷のアパートで、ひっそりと山口の元へと旅立った。脳出血だった。
山口は死の直前、一つの歌を詠んだ。
「帰り来て ふるさとの空 かくばかり 青かりしとは しらざりしかな」
これまで背筋をピンと伸ばし、ひたすら真っすぐ前だけをみてきた青年にとっての空は、地平線に向かう一筋の道だった。
病の床で初めて故郷の空を見上げ、その青さと無限の広がりを見た。
※本文は、すべて以下の産経新聞特集記事(山田智章記者筆)からの引用です。
【凛として】
(32)ヤミ米“拒否死”の裁判官 山口良忠<4>決死の覚悟 [2004年05月20日 東京朝刊]
【凛として】
(33)ヤミ米“拒否死”の裁判官 山口良忠<5>貫いたもの [2004年05月21日 東京朝刊]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・