来る7月28日と29日、
一宮神社のお祭り、『天佐志比古命神社大祭』開催です。
神楽、子供歌舞伎、御神輿、他各種芸能、演芸が奉納されます。
江戸時代の1764~1771年ごろ、島に鯨が漂着し、
その後火災や疫病が続いたため、
鯨の祟りではないかと、その霊を慰めるため少年の手踊りを奉納したのが始まりだそうです。
野外観覧席の周り舞台を持つ芝居小屋は
知夫と淡路島文楽の2か所しかないってガイドに書いてあるけど、本当なのかな。
今月はこれから忙しくなるなあ。
今日も週末もお客さん来るし。
オリンピックも始まるしね
朝ドラから「松岡さん」が消えてめちゃくちゃ淋しかったんだけど、
バタバタしてたら気分も切り替わるさ~
一宮神社のお祭り、『天佐志比古命神社大祭』開催です。
神楽、子供歌舞伎、御神輿、他各種芸能、演芸が奉納されます。
江戸時代の1764~1771年ごろ、島に鯨が漂着し、
その後火災や疫病が続いたため、
鯨の祟りではないかと、その霊を慰めるため少年の手踊りを奉納したのが始まりだそうです。
野外観覧席の周り舞台を持つ芝居小屋は
知夫と淡路島文楽の2か所しかないってガイドに書いてあるけど、本当なのかな。
今月はこれから忙しくなるなあ。
今日も週末もお客さん来るし。
オリンピックも始まるしね

朝ドラから「松岡さん」が消えてめちゃくちゃ淋しかったんだけど、
バタバタしてたら気分も切り替わるさ~













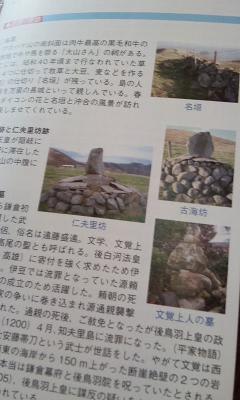





















 、
、







 かっこいい~
かっこいい~ と、
と、

