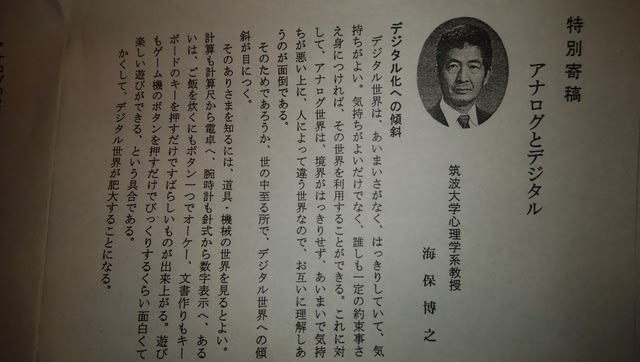心理学研究法の意義をめぐって(放送大学教科書原稿)
《本章の学習目標&ポイント》
心理学研究の多様なアプローチと論理を14回の講義を通じて理解されたことと思う。最終講義では、受講生の方々の疑問にもたれているような事項について、主任講師3人の鼎談の形式で語ることにした。心理学は理系の学問ではないかと言う疑問から始まり、心理学を学ぶとどのような力がつくのか、実際の研究はどのような手順で進めるのか、心理学のプロはなにをめざしているのか、心理学の研究の方向を理解していただき、知的好奇心をかき立てていただきたい
〈キーワード〉実証的研究法、妥当性と信頼性、観察法、面接法、質問紙法
15-1心理学研究法はなぜ大切か
●心理学は文系か理系か
心理学を学ぶ学生から、「自分が思っていた心理学とは違っていた。心理学は心について教えてくれるのではないのか。」という声がよく聞かれる。その理由として、①実験がある、②統計が出てくる、③人の心や心の病気の話があまり出てこない、④ネコやネズミのような動物の行動の話が出てくる、などが挙げられる。
心理学の歴史を見てみると、心についての考え方は哲学から、研究の仕方は生理学から出発し、19世紀後半にそれらの学問から独立した学問領域としての心理学が確立した。前者の流れは、我国の大学においても心理学科が文学部の哲学科から別れて独立した学科となった経緯の中に認められる。後者の流れは、心理学が実証的研究にアイデンティティを求めることにより知ることができる。この実証性のために、心理学では、実験室実験を行い、結果を統計的に処理し、行動を予測するという自然科学的研究法に視点を据えたのである。言い換えると、心理学はその独立のときから、心とは何かについて直接語る方法から分かれて、実証的研究法による心の解明への道を進めてきたのである。
心理学が実証的学問であることは一般に知られていないため、心理学の初学者は、この研究法に触れたとき、心理学に違和感を覚えるのである。心理学は心を扱うが故に文系でもあり、実証的研究法に基づくが故に理系でもあり得る。むしろ心理学は文系でも理系でもなく、両者を融合した独自の心理系であると主張する方がよいのかもしれない。
●心理学ワールドの鳥瞰図
最初、実験室実験として出発した心理学は、人が目や耳などの感覚器官を通して、環境をどのように受け取るのかと言う感覚・知覚の研究、続いて、記憶や忘却についての古典的な記憶の研究を確立した。さらに、イヌやネコやネズミのような動物の行動を研究する動物心理学、経験と行動との仕組みを研究する学習心理学などの分野へと広がっていくことになった。
このような基礎的研究分野に続いて、社会的行動を実験室的手法で扱う実験社会心理学が確立するとともに、隣接科学との学際的研究へと広がることになった。この学際的な動向により、隣接科学領域との豊かな関係を形成し(図1)、心理学が心の解明アプローチとして有力かつ多様な研究法を用いることになるのである。
図1
●心理学を学ぶとどんな力がつくか
人は4歳頃になると、自分についての意識が芽生えるようになる。そして、大人になると、学校で心理学を学ばなくても、自分の心については自分が一番よく分かっているし、心を日常場面でどのように働かせればよいのかについても知っていると思っている。人が自分の心について持っているこのような知識の集積を素朴心理学と呼ぶ。人が、日常生活の中で他者の行為を誤解したり、他者から見るといかにも風変わりな迷信や俗信を信じていることがある。このようなことは、人が物事を自分の狭い経験に基づく素朴心理学によって理解しようとすることから生じるのである。心理学の方法論や研究法を学ぶことによって、素朴心理学の知識は、アカデミックな心理学の科学的な知識体系の中に位置づけられ、合理的で妥当な判断をすることができるようになる。この判断に基づいて実践すると、世の中にはびこる迷信やおかしな風習を力強く排除することができるようになる。
心理学のそれぞれの領域について学ぶことによって、心と行動について豊富な知識を習得し、実践に応用することができる。例えば、発達心理学や社会心理学の知識を得ることにより、人の発達や対人関係についての自己理解や他者理解が深まる。また、認知心理学は人の知的活動の特徴の、生理心理学は心や行動に脳神経や体の働きが深く関わることの理解に繋がっていく。(大野木裕明)
15-2心って何〜研究のアプローチから〜
心理学における科学的の意味は、その研究がいかに科学的な手順に基づいて進められているかにかかっている。それではつぎに、科学的研究の進め方について説明する。
●科学的研究手順の4段階
第1段階は、仮説を立てることである。仮説とは、現実におこる出来事(事象)が人や動物の行動に与える効果を整理し、これらの事象が行動に与える効果についての関係を記述することである。例えば、練習によって成績が良くなるとことを経験的に知っている。この経験から、練習量を増加させると成績が一次関数的に増加するであろうという練習と成績間の関係性についての仮説を導き出すのである。
第2段階は、仮説を実験的に検証することであり、普通に実験をするというのはこの段階である。先の練習の例ならば、異なるグループに異なった練習回数で課題の訓練を行い、その成績を記録する。
第3段階は、実験結果によって仮説を評価することである。つまり、得られた結果が仮説から予測されたものと一致するか否かの判断を行い、仮説を採用するか、採用しないかを決める。この判断のために統計的検定の結果を用いる。
最後が第4段階の研究成果の公開である。その研究の目的、実験の具体的方法、新しく発見された結果、その結果を先行研究などと比較検討したうえで評価し、科学論文として公表する。
●研究の妥当性と信頼性
妥当性とは、調べようとする目的に対して調べる方法が適切であるか、あるいは考え違いをしていないかを問うことである。実験で用いる測度が調べたいことを的確に調べられるのか、これまでに得られた測定の知識とも矛盾していないかが妥当性の基準になる。
信頼性とは、同じ方法で複数回調べた場合に、結果が常に同じ傾向を示すかどうかを問うことである。一定の条件で複数回実験を行い、一貫した結果が得られた場合に、信頼性が高いという。信頼性の高い研究をするには、実験室を常に一定の環境条件に保ち、実験装置や測定器具をよく整備された状態を保つ必要がある。
●研究の具体的なアプローチ
心理学でいう心とは何なのか。心理学ではこの命題について直接答えるのではなく、どんな研究法で心を見ていくのかという研究のアプローチとして取り扱う。そこで、心理学ではどのような方法でデータを集めるのかという、研究のアプローチについて述べる。
①行動を観察して推測するアプローチ
このグループは、大きく2つにまとめることができる。一つは、通常、実験法と呼ばれる実験的観察法であり、人でも動物でも行いうる。実際の実験は、厳密に統制した条件下での行動の変化を観察するために実験室で行うことが多い。そのため、実験参加者にとってはなじみの無い非日常的な場所でテストを受けているという心構えが生じるため、結果が人工的であるという批判を生むことがある。原因と結果の因果的関係を明確に推測することが可能になる。
もう一つは、観察法と呼ばれる自然的観察法であり、日常の自然な生活場面で行う行動を観察し、記録する方法である。そのために、研究者が観察可能な場面に出かけて行く。観察の対象は、人でも動物でもよく、人では乳幼児の研究においてもよく用いられる。
観察法は、研究の初期の時期に用いられることも多く、注意深い観察から、新しい研究の芽が見つかることも多い。しかし、研究者が自分の思い込みや主観によって観察結果を判断してしまう弊害も生じやすい。
②生理的ミクロの反応から推測するアプローチ
脳神経系における中枢性のものと、身体における末梢性の反応がある。いずれの反応も、身体の外から観察しただけでは読み取れないし、本人自身もその反応の変化に気付いていない。このため、このアプローチで用いる手法では専用の測定装置を用いることになる。
中枢性の反応は、脳電図(脳波)やCT、PET、fMRIなどにより測定される。これらの測定は記憶や思考など高次の精神活動と脳の働きとの関係を解明するために欠くことのできない手法になってきている。末梢性では、心拍・心電図や呼吸、GSR(皮膚電気抵抗)、眼球運動などが測定される。
いずれにしても心理学の研究では、これらの測度が単独で用いられると言うよりも、他のアプローチの手法との組み合わせで活用される。
③面接者に対する非面接者の応答から推測するアプローチ
面接法とは、面接者が被面接者に口答で質問し、回答を求める方法である。このため、言語的なコミュニケーションが可能で、質問者の意図が理解できる人が研究対象者となる。臨床心理学における診断・治療や社会心理学における調査など多方面で用いられる。質問の方法には、質問紙を面接によって行う質問紙面接法、質問の意図は明確にするが、個々の質問のやり方は自由で、臨機応変に進めていく自由面接法がある。また、両者の中間にあらかじめ質問を決めてあるが、回答をはっきりさせたいような場合にさらに質問を追加する面接法がある。
④広義の「内観、内省報告」から推測するアプローチ
生活習慣や態度、商品を購入する場合の広告の効果や購買動機など、人間の行動のいろいろの側面について、質問紙(アンケートともいう)を作成し、調査対象者に言葉を用いて記入してもらう方法で、質問紙(調査)法という。自分で言葉による判断が出来ない人には適用できないし、動物も対象外である。1つの質問紙でいろいろな質問項目についての判断や考えを調べることができ、時間的にも経済的にも効率的である。しかし、問題によっては、どのように答えれば自分にとって有利になるかなどの考えによって、回答がゆがめられるというような短所もある。質問項目をよく考えた質問紙から、人間の行動に関わる多様な要因を明らかにすることができる。
⑤言語反応や作業成績から推測するアプローチ
パーソナリティの研究では、言語反応や作業結果の分析からパーソナリティの測定や分析を行う手法が重要な研究アプローチとして用いられてきた。一定の刺激カードに対する言語的な反応やストーリーを分析するロールシャッハテストや絵画統覚テストはその代表である。近年、発話をもとに、行動選択過程を調べるプロトコル分析などが開発されてきた。作業検査法(例えばクレペリン精神作業検査)では、一定時間内に単純な作業を行わせ、作業の進行過程から精神活動の特徴を明らかにしようとするものである。
また、近年高齢者や臨床の事例研究において、日記などの個人の残した言語的な記録の分析が重要な研究手法となっている。
心理学に親しむには、結果ばかりに関心を持つのではなく、いろいろな研究法の違いに注目するとよい。どんな切り口、手口で扱うのかという工夫もまた、心理学の醍醐味なのである。(岡市広成)
15-3 プロの心理学者とは
●心理学者はどこにいる
心理系の公務員としては、福祉、警察、司法関係がある。福祉関係では児童相談書の心理判定員として心理検査や心理カウンセリングを行う。警察関係では科学捜査研究所の研究員として筆跡鑑定を行ったり、生理心理学的手法でポリグラフ(俗に嘘発見器と言われる)による供述の事実確認を行う。また生活安全課の少年補導員や相談専門員としてカウンセリングや補導業務に就く。司法・矯正関係では法務省少年鑑別所の心理技官や家庭裁判所調査官として心理検査や心理カウンセリングを行う。
大学関係では、文学部や心理学部ほかで研究と教育を行う。その他、教員免許の課程認定を受けたいろいろな学部で、教職関係の心理学を講ずる。そこでは子どもの精神発達や学校教員の進路指導や教育相談の技術などを解説する。
●プロの心理学者の仕事
プロは仕事として研究し、その成果を専門の研究雑誌であれ、学会であれ研究者集団に向けて発信し、その研究の評価を同業のプロの研究者たちに委ねる。このためにプロは、きちんとした専門的トレーニングを受けて、信頼される手順を踏んで公表する。プロは、観察された事実をもとに、ある現象とその現象が生じる原因となったと考えられる事象間の関係性について、科学的報告としての共通のルールに従い、適度な厳密性とある程度の普遍性のある説明を行う。プロの関心は、自分の興味と関心が心理学の学問体系のどこに位置づけられ、プロの知的共同体としての学会に認められ、貢献できる研究が行えるかという点にある。
さらにプロの世界は厳しい。画期的な結果がただ1度だけの実験で得られたとしても、その結果が直ちに信用されない。たまたま偶然の結果得られたものであるかもしれず、また、実験者のまったく気がつかなかった他の要因によって生じたのかも知れない。そのため、研究者は、その研究が重大な問題に対する結果を提供している場合ほど、多くの研究者がこの研究方法が妥当であるか、などを検証するために、再現実験(追試)を行うことが不可欠である。この場合に、同じ条件で実験が再現できるように必要な実験方法を記載することが義務づけられているのである。
心理学に造詣を持たないアマの関心は素朴な興味や関心に基づくものが多い。読心術や血液型性格占いも含めて身の回りの不思議な迷信にとらわれることがある。しかし、アマは時として、厳密さと正確さを追求するあまり、おおもとの研究目的から離れたり、袋小路に陥ったプロの眼を醒まさせる役目を果たすこともある。プロは遠回りではあるが、迷信を排除し、生活の質を向上させる示唆を提供できる。
●心理学のプロがノーベル賞をもらえるか
現在のノーベル賞には「心理学賞」はない。その意味で「これが心理学だ」という研究からノーベル賞を得た研究者はいない。しかし、2002年、プリンストン大学とヘブライ大学の教授であったカーネマン(Kahneman,D)がノーベル経済学賞を受賞した。何だ経済学かといったら話にならない。カーネマンは認知、特に意思決定を専門領域とする社会心理学者であったから、関係する心理学の研究者に驚きと感動を与えたのである。「先行順位の普遍性」というミクロ経済学の前提を批判し、
心理学的実証研究によって、経済学にも人の心理的判断が介在することを証明したのである。
カーネマンと同じような経済学と意思決定に関するテーマで、1978年に人工知能の研究で名高く、心理学にも造詣の深いサイモン(Simon,H)が経済学賞を受賞している。
このほか、生理心理学者でも医学・生理学賞候補にあげられるかもしれないという声を聞いたことがある。
このように、研究の進め方によっては関連の研究領域からノーベル賞を手にすることが可能である。(大野木裕明)
15-4 心理学研究法のこれから
●知りたいことが先
心理学研究法の多彩さを実感していただけたことと思う。その一方で、一体どの研究法を使えばよいのかに迷ってしまうではないかとお叱りを受けてしまうかもしれない。
本講義は、研究法だけを独立させて講義を進めてきたので、そのように思われるのは当然である。しかし、実際の研究は、研究法から入るのではなく、研究テーマから入るのである。心の何を知りたいかから始まるのである。それを実証の枠組みにいかに落とし込んでいくかという時に、本講義で紹介したような研究法が役立つのである。この当たり前のことをまずしっかりと理解してほしい。
●なぜ心理学研究法を学ぶ必要があるのか
それなら、本講義の意義はどこにあるのであろうか。
一つは、心理学の勉強と研究をするための準備である。これから心理学を学び、自ら研究するにあたり、教科書や文献、さらに講義を通して様々な研究に出会う。そこには、多彩な研究法が当然のごとく使われている。それらを理解し、さらに自ら進んで研究するためには、本講義で学んだ研究法の基本的な知識と考え方が不可欠なのである。
本講義では、具体的な研究技法についてはあまり紹介しなかった。その点で、やや物足りなさを感じられたと思うが、それぞれの研究技法については、多くの書物が出版されているので、必要に応じてそれらを参照してほしい。
本講義を学ぶ意義のもう一つは、心の問題をとらえる視点の提供である。こちらの方は、本講義の隠れた狙いである。
世間で心に関する関心が強まっているが、それに対してきちんと応えていくために、心理学は実証という枠をはめている。実証に基づかない知識や直感は、単なる憶測にすぎない。その違いを見極めることができる力は、心理学研究法を学ぶことでついてくる。
例えば、ダイエット効果があるとうたう食品の宣伝に、事前事後の写真や体重が載せられているのを見て、衝動的に自分も試してみようと思うかもしれない。こんな時、研究法の知識があれば、宣伝に直ちに飛びつく前に、本当かなと考えてみる。科学的に納得のいく情報が提供されているか、対照群(統制群)が設けられているかや統計的処理がなされているかなど、容易にチェックすることができる。このことを利用すると、安易に説得ずにすむし、うまく利用すると説得のテクニックに強くなる。
●心理学研究法のこれから
認知心理学の半世紀の歴史は、心理学の研究対象と研究方法のレパートリーを格段に豊富にしたことはすでに述べた。そのことには長所もあり、短所もある。
まず、長所の方から述べよう。
心理学の研究法が自然科学的な方法論の桎梏から解き放たれ、7章と8章で紹介したような、社会科学的な方法論に立脚したものが導入されるようになり、心を自由に考え、語れるようになった。このことは、心理学研究者にとっても、また、心理学に期待を持っている一般の人々にとっても、好ましい状況と言える。「こんな心の問題はどうなっているのか」という問いが現実のあちこちから発せられることによって、心理学研究者は、直接、現実の中から研究テーマを見つけることができるようになったし、そうすることを求められるようになった。日常生活の中での素朴な疑問をそれに相応しい研究法を見つけ出して研究する実践的心理学ともいえる領域が拡大している。研究テーマも研究法も、どんどん新しい展開を遂げることが期待される。
こうした状況にも短所がある。2つだけ挙げておく。
一つは、研究が拡散してしまうことで、心理学全体に浅い研究が増えてしまう懸念がある。どのような問題であれ、少しでも心に関係するものをすべて心理学の課題として抱えてしまうと、どれもこれも浅薄な理論や思いつきの研究の段階に止まってしまう恐れがある。
研究テーマの多彩さは、林立する心理学諸学会の数に反映されている。2007年現在、日本には70余の学会がある。学会の多さは悪いことではない。テーマを特定して深く精緻な理論と知見を蓄積することができるからである。ただ、それぞれの学会が「たこ壷化」し、相互の交流がなくなってしまうと、心理学の発展性がなくなる。
もう一つの短所、というより、懸念は、実証がルーズになることである。無論、自然科学的な実証に凝り固まる必要はない。しかし、よほどしっかりと心理学の研究法を身に付けておかないと、何でもありの研究まがいのものがまかり通り、科学的な説得力のない知識が心理学だとして横行する懸念がある。(海保博之)
「課題」
日常生活のいろいろな場面で心理学が用いられている。それでは次の中で心理学の方法を用いているのはどれか。
1.運勢判断
2.カウンセリング
3.カラーコーディネーター
4.動物の訓練
5.振り込め詐欺
解答のヒント
①人の運・不運は心理学的に予測できない。2番、心理臨床的方法論に基づいて行われる。3番、色が与える心理的効果には違いがある。4番、報酬と罰を使うオペラント条件づけに基づいている。⑤人情の機微にたくみにつけこんでいるが、心理学を用いているわけではないはず。
参考文献
東洋・繁多進・田島信元(編)1992 発達心理学ハンドブック 福村書店
東洋・梅本堯夫・芝祐順・梶田叡一(編)1988 現代教育評価事典
波多野完治・依田新・重松鷹泰(監)1968 学習心理学ハンドブック 金子書房
西平直喜・久世敏雄(編)1988 青年心理学ハンドブック 福村書店
海保博之 2003 心理学ってどんなもの(岩波ジュニア新書No.427) 岩波書店
海保博之・楠見孝(監修)2006 心理学総合事典 朝倉書店
佐藤達哉・溝口元(編)1997 通史日本の心理学 北大路書房
詫摩武俊(編)1998 性格心理学ハンドブック 福村書店
《本章の学習目標&ポイント》
心理学研究の多様なアプローチと論理を14回の講義を通じて理解されたことと思う。最終講義では、受講生の方々の疑問にもたれているような事項について、主任講師3人の鼎談の形式で語ることにした。心理学は理系の学問ではないかと言う疑問から始まり、心理学を学ぶとどのような力がつくのか、実際の研究はどのような手順で進めるのか、心理学のプロはなにをめざしているのか、心理学の研究の方向を理解していただき、知的好奇心をかき立てていただきたい
〈キーワード〉実証的研究法、妥当性と信頼性、観察法、面接法、質問紙法
15-1心理学研究法はなぜ大切か
●心理学は文系か理系か
心理学を学ぶ学生から、「自分が思っていた心理学とは違っていた。心理学は心について教えてくれるのではないのか。」という声がよく聞かれる。その理由として、①実験がある、②統計が出てくる、③人の心や心の病気の話があまり出てこない、④ネコやネズミのような動物の行動の話が出てくる、などが挙げられる。
心理学の歴史を見てみると、心についての考え方は哲学から、研究の仕方は生理学から出発し、19世紀後半にそれらの学問から独立した学問領域としての心理学が確立した。前者の流れは、我国の大学においても心理学科が文学部の哲学科から別れて独立した学科となった経緯の中に認められる。後者の流れは、心理学が実証的研究にアイデンティティを求めることにより知ることができる。この実証性のために、心理学では、実験室実験を行い、結果を統計的に処理し、行動を予測するという自然科学的研究法に視点を据えたのである。言い換えると、心理学はその独立のときから、心とは何かについて直接語る方法から分かれて、実証的研究法による心の解明への道を進めてきたのである。
心理学が実証的学問であることは一般に知られていないため、心理学の初学者は、この研究法に触れたとき、心理学に違和感を覚えるのである。心理学は心を扱うが故に文系でもあり、実証的研究法に基づくが故に理系でもあり得る。むしろ心理学は文系でも理系でもなく、両者を融合した独自の心理系であると主張する方がよいのかもしれない。
●心理学ワールドの鳥瞰図
最初、実験室実験として出発した心理学は、人が目や耳などの感覚器官を通して、環境をどのように受け取るのかと言う感覚・知覚の研究、続いて、記憶や忘却についての古典的な記憶の研究を確立した。さらに、イヌやネコやネズミのような動物の行動を研究する動物心理学、経験と行動との仕組みを研究する学習心理学などの分野へと広がっていくことになった。
このような基礎的研究分野に続いて、社会的行動を実験室的手法で扱う実験社会心理学が確立するとともに、隣接科学との学際的研究へと広がることになった。この学際的な動向により、隣接科学領域との豊かな関係を形成し(図1)、心理学が心の解明アプローチとして有力かつ多様な研究法を用いることになるのである。
図1
●心理学を学ぶとどんな力がつくか
人は4歳頃になると、自分についての意識が芽生えるようになる。そして、大人になると、学校で心理学を学ばなくても、自分の心については自分が一番よく分かっているし、心を日常場面でどのように働かせればよいのかについても知っていると思っている。人が自分の心について持っているこのような知識の集積を素朴心理学と呼ぶ。人が、日常生活の中で他者の行為を誤解したり、他者から見るといかにも風変わりな迷信や俗信を信じていることがある。このようなことは、人が物事を自分の狭い経験に基づく素朴心理学によって理解しようとすることから生じるのである。心理学の方法論や研究法を学ぶことによって、素朴心理学の知識は、アカデミックな心理学の科学的な知識体系の中に位置づけられ、合理的で妥当な判断をすることができるようになる。この判断に基づいて実践すると、世の中にはびこる迷信やおかしな風習を力強く排除することができるようになる。
心理学のそれぞれの領域について学ぶことによって、心と行動について豊富な知識を習得し、実践に応用することができる。例えば、発達心理学や社会心理学の知識を得ることにより、人の発達や対人関係についての自己理解や他者理解が深まる。また、認知心理学は人の知的活動の特徴の、生理心理学は心や行動に脳神経や体の働きが深く関わることの理解に繋がっていく。(大野木裕明)
15-2心って何〜研究のアプローチから〜
心理学における科学的の意味は、その研究がいかに科学的な手順に基づいて進められているかにかかっている。それではつぎに、科学的研究の進め方について説明する。
●科学的研究手順の4段階
第1段階は、仮説を立てることである。仮説とは、現実におこる出来事(事象)が人や動物の行動に与える効果を整理し、これらの事象が行動に与える効果についての関係を記述することである。例えば、練習によって成績が良くなるとことを経験的に知っている。この経験から、練習量を増加させると成績が一次関数的に増加するであろうという練習と成績間の関係性についての仮説を導き出すのである。
第2段階は、仮説を実験的に検証することであり、普通に実験をするというのはこの段階である。先の練習の例ならば、異なるグループに異なった練習回数で課題の訓練を行い、その成績を記録する。
第3段階は、実験結果によって仮説を評価することである。つまり、得られた結果が仮説から予測されたものと一致するか否かの判断を行い、仮説を採用するか、採用しないかを決める。この判断のために統計的検定の結果を用いる。
最後が第4段階の研究成果の公開である。その研究の目的、実験の具体的方法、新しく発見された結果、その結果を先行研究などと比較検討したうえで評価し、科学論文として公表する。
●研究の妥当性と信頼性
妥当性とは、調べようとする目的に対して調べる方法が適切であるか、あるいは考え違いをしていないかを問うことである。実験で用いる測度が調べたいことを的確に調べられるのか、これまでに得られた測定の知識とも矛盾していないかが妥当性の基準になる。
信頼性とは、同じ方法で複数回調べた場合に、結果が常に同じ傾向を示すかどうかを問うことである。一定の条件で複数回実験を行い、一貫した結果が得られた場合に、信頼性が高いという。信頼性の高い研究をするには、実験室を常に一定の環境条件に保ち、実験装置や測定器具をよく整備された状態を保つ必要がある。
●研究の具体的なアプローチ
心理学でいう心とは何なのか。心理学ではこの命題について直接答えるのではなく、どんな研究法で心を見ていくのかという研究のアプローチとして取り扱う。そこで、心理学ではどのような方法でデータを集めるのかという、研究のアプローチについて述べる。
①行動を観察して推測するアプローチ
このグループは、大きく2つにまとめることができる。一つは、通常、実験法と呼ばれる実験的観察法であり、人でも動物でも行いうる。実際の実験は、厳密に統制した条件下での行動の変化を観察するために実験室で行うことが多い。そのため、実験参加者にとってはなじみの無い非日常的な場所でテストを受けているという心構えが生じるため、結果が人工的であるという批判を生むことがある。原因と結果の因果的関係を明確に推測することが可能になる。
もう一つは、観察法と呼ばれる自然的観察法であり、日常の自然な生活場面で行う行動を観察し、記録する方法である。そのために、研究者が観察可能な場面に出かけて行く。観察の対象は、人でも動物でもよく、人では乳幼児の研究においてもよく用いられる。
観察法は、研究の初期の時期に用いられることも多く、注意深い観察から、新しい研究の芽が見つかることも多い。しかし、研究者が自分の思い込みや主観によって観察結果を判断してしまう弊害も生じやすい。
②生理的ミクロの反応から推測するアプローチ
脳神経系における中枢性のものと、身体における末梢性の反応がある。いずれの反応も、身体の外から観察しただけでは読み取れないし、本人自身もその反応の変化に気付いていない。このため、このアプローチで用いる手法では専用の測定装置を用いることになる。
中枢性の反応は、脳電図(脳波)やCT、PET、fMRIなどにより測定される。これらの測定は記憶や思考など高次の精神活動と脳の働きとの関係を解明するために欠くことのできない手法になってきている。末梢性では、心拍・心電図や呼吸、GSR(皮膚電気抵抗)、眼球運動などが測定される。
いずれにしても心理学の研究では、これらの測度が単独で用いられると言うよりも、他のアプローチの手法との組み合わせで活用される。
③面接者に対する非面接者の応答から推測するアプローチ
面接法とは、面接者が被面接者に口答で質問し、回答を求める方法である。このため、言語的なコミュニケーションが可能で、質問者の意図が理解できる人が研究対象者となる。臨床心理学における診断・治療や社会心理学における調査など多方面で用いられる。質問の方法には、質問紙を面接によって行う質問紙面接法、質問の意図は明確にするが、個々の質問のやり方は自由で、臨機応変に進めていく自由面接法がある。また、両者の中間にあらかじめ質問を決めてあるが、回答をはっきりさせたいような場合にさらに質問を追加する面接法がある。
④広義の「内観、内省報告」から推測するアプローチ
生活習慣や態度、商品を購入する場合の広告の効果や購買動機など、人間の行動のいろいろの側面について、質問紙(アンケートともいう)を作成し、調査対象者に言葉を用いて記入してもらう方法で、質問紙(調査)法という。自分で言葉による判断が出来ない人には適用できないし、動物も対象外である。1つの質問紙でいろいろな質問項目についての判断や考えを調べることができ、時間的にも経済的にも効率的である。しかし、問題によっては、どのように答えれば自分にとって有利になるかなどの考えによって、回答がゆがめられるというような短所もある。質問項目をよく考えた質問紙から、人間の行動に関わる多様な要因を明らかにすることができる。
⑤言語反応や作業成績から推測するアプローチ
パーソナリティの研究では、言語反応や作業結果の分析からパーソナリティの測定や分析を行う手法が重要な研究アプローチとして用いられてきた。一定の刺激カードに対する言語的な反応やストーリーを分析するロールシャッハテストや絵画統覚テストはその代表である。近年、発話をもとに、行動選択過程を調べるプロトコル分析などが開発されてきた。作業検査法(例えばクレペリン精神作業検査)では、一定時間内に単純な作業を行わせ、作業の進行過程から精神活動の特徴を明らかにしようとするものである。
また、近年高齢者や臨床の事例研究において、日記などの個人の残した言語的な記録の分析が重要な研究手法となっている。
心理学に親しむには、結果ばかりに関心を持つのではなく、いろいろな研究法の違いに注目するとよい。どんな切り口、手口で扱うのかという工夫もまた、心理学の醍醐味なのである。(岡市広成)
15-3 プロの心理学者とは
●心理学者はどこにいる
心理系の公務員としては、福祉、警察、司法関係がある。福祉関係では児童相談書の心理判定員として心理検査や心理カウンセリングを行う。警察関係では科学捜査研究所の研究員として筆跡鑑定を行ったり、生理心理学的手法でポリグラフ(俗に嘘発見器と言われる)による供述の事実確認を行う。また生活安全課の少年補導員や相談専門員としてカウンセリングや補導業務に就く。司法・矯正関係では法務省少年鑑別所の心理技官や家庭裁判所調査官として心理検査や心理カウンセリングを行う。
大学関係では、文学部や心理学部ほかで研究と教育を行う。その他、教員免許の課程認定を受けたいろいろな学部で、教職関係の心理学を講ずる。そこでは子どもの精神発達や学校教員の進路指導や教育相談の技術などを解説する。
●プロの心理学者の仕事
プロは仕事として研究し、その成果を専門の研究雑誌であれ、学会であれ研究者集団に向けて発信し、その研究の評価を同業のプロの研究者たちに委ねる。このためにプロは、きちんとした専門的トレーニングを受けて、信頼される手順を踏んで公表する。プロは、観察された事実をもとに、ある現象とその現象が生じる原因となったと考えられる事象間の関係性について、科学的報告としての共通のルールに従い、適度な厳密性とある程度の普遍性のある説明を行う。プロの関心は、自分の興味と関心が心理学の学問体系のどこに位置づけられ、プロの知的共同体としての学会に認められ、貢献できる研究が行えるかという点にある。
さらにプロの世界は厳しい。画期的な結果がただ1度だけの実験で得られたとしても、その結果が直ちに信用されない。たまたま偶然の結果得られたものであるかもしれず、また、実験者のまったく気がつかなかった他の要因によって生じたのかも知れない。そのため、研究者は、その研究が重大な問題に対する結果を提供している場合ほど、多くの研究者がこの研究方法が妥当であるか、などを検証するために、再現実験(追試)を行うことが不可欠である。この場合に、同じ条件で実験が再現できるように必要な実験方法を記載することが義務づけられているのである。
心理学に造詣を持たないアマの関心は素朴な興味や関心に基づくものが多い。読心術や血液型性格占いも含めて身の回りの不思議な迷信にとらわれることがある。しかし、アマは時として、厳密さと正確さを追求するあまり、おおもとの研究目的から離れたり、袋小路に陥ったプロの眼を醒まさせる役目を果たすこともある。プロは遠回りではあるが、迷信を排除し、生活の質を向上させる示唆を提供できる。
●心理学のプロがノーベル賞をもらえるか
現在のノーベル賞には「心理学賞」はない。その意味で「これが心理学だ」という研究からノーベル賞を得た研究者はいない。しかし、2002年、プリンストン大学とヘブライ大学の教授であったカーネマン(Kahneman,D)がノーベル経済学賞を受賞した。何だ経済学かといったら話にならない。カーネマンは認知、特に意思決定を専門領域とする社会心理学者であったから、関係する心理学の研究者に驚きと感動を与えたのである。「先行順位の普遍性」というミクロ経済学の前提を批判し、
心理学的実証研究によって、経済学にも人の心理的判断が介在することを証明したのである。
カーネマンと同じような経済学と意思決定に関するテーマで、1978年に人工知能の研究で名高く、心理学にも造詣の深いサイモン(Simon,H)が経済学賞を受賞している。
このほか、生理心理学者でも医学・生理学賞候補にあげられるかもしれないという声を聞いたことがある。
このように、研究の進め方によっては関連の研究領域からノーベル賞を手にすることが可能である。(大野木裕明)
15-4 心理学研究法のこれから
●知りたいことが先
心理学研究法の多彩さを実感していただけたことと思う。その一方で、一体どの研究法を使えばよいのかに迷ってしまうではないかとお叱りを受けてしまうかもしれない。
本講義は、研究法だけを独立させて講義を進めてきたので、そのように思われるのは当然である。しかし、実際の研究は、研究法から入るのではなく、研究テーマから入るのである。心の何を知りたいかから始まるのである。それを実証の枠組みにいかに落とし込んでいくかという時に、本講義で紹介したような研究法が役立つのである。この当たり前のことをまずしっかりと理解してほしい。
●なぜ心理学研究法を学ぶ必要があるのか
それなら、本講義の意義はどこにあるのであろうか。
一つは、心理学の勉強と研究をするための準備である。これから心理学を学び、自ら研究するにあたり、教科書や文献、さらに講義を通して様々な研究に出会う。そこには、多彩な研究法が当然のごとく使われている。それらを理解し、さらに自ら進んで研究するためには、本講義で学んだ研究法の基本的な知識と考え方が不可欠なのである。
本講義では、具体的な研究技法についてはあまり紹介しなかった。その点で、やや物足りなさを感じられたと思うが、それぞれの研究技法については、多くの書物が出版されているので、必要に応じてそれらを参照してほしい。
本講義を学ぶ意義のもう一つは、心の問題をとらえる視点の提供である。こちらの方は、本講義の隠れた狙いである。
世間で心に関する関心が強まっているが、それに対してきちんと応えていくために、心理学は実証という枠をはめている。実証に基づかない知識や直感は、単なる憶測にすぎない。その違いを見極めることができる力は、心理学研究法を学ぶことでついてくる。
例えば、ダイエット効果があるとうたう食品の宣伝に、事前事後の写真や体重が載せられているのを見て、衝動的に自分も試してみようと思うかもしれない。こんな時、研究法の知識があれば、宣伝に直ちに飛びつく前に、本当かなと考えてみる。科学的に納得のいく情報が提供されているか、対照群(統制群)が設けられているかや統計的処理がなされているかなど、容易にチェックすることができる。このことを利用すると、安易に説得ずにすむし、うまく利用すると説得のテクニックに強くなる。
●心理学研究法のこれから
認知心理学の半世紀の歴史は、心理学の研究対象と研究方法のレパートリーを格段に豊富にしたことはすでに述べた。そのことには長所もあり、短所もある。
まず、長所の方から述べよう。
心理学の研究法が自然科学的な方法論の桎梏から解き放たれ、7章と8章で紹介したような、社会科学的な方法論に立脚したものが導入されるようになり、心を自由に考え、語れるようになった。このことは、心理学研究者にとっても、また、心理学に期待を持っている一般の人々にとっても、好ましい状況と言える。「こんな心の問題はどうなっているのか」という問いが現実のあちこちから発せられることによって、心理学研究者は、直接、現実の中から研究テーマを見つけることができるようになったし、そうすることを求められるようになった。日常生活の中での素朴な疑問をそれに相応しい研究法を見つけ出して研究する実践的心理学ともいえる領域が拡大している。研究テーマも研究法も、どんどん新しい展開を遂げることが期待される。
こうした状況にも短所がある。2つだけ挙げておく。
一つは、研究が拡散してしまうことで、心理学全体に浅い研究が増えてしまう懸念がある。どのような問題であれ、少しでも心に関係するものをすべて心理学の課題として抱えてしまうと、どれもこれも浅薄な理論や思いつきの研究の段階に止まってしまう恐れがある。
研究テーマの多彩さは、林立する心理学諸学会の数に反映されている。2007年現在、日本には70余の学会がある。学会の多さは悪いことではない。テーマを特定して深く精緻な理論と知見を蓄積することができるからである。ただ、それぞれの学会が「たこ壷化」し、相互の交流がなくなってしまうと、心理学の発展性がなくなる。
もう一つの短所、というより、懸念は、実証がルーズになることである。無論、自然科学的な実証に凝り固まる必要はない。しかし、よほどしっかりと心理学の研究法を身に付けておかないと、何でもありの研究まがいのものがまかり通り、科学的な説得力のない知識が心理学だとして横行する懸念がある。(海保博之)
「課題」
日常生活のいろいろな場面で心理学が用いられている。それでは次の中で心理学の方法を用いているのはどれか。
1.運勢判断
2.カウンセリング
3.カラーコーディネーター
4.動物の訓練
5.振り込め詐欺
解答のヒント
①人の運・不運は心理学的に予測できない。2番、心理臨床的方法論に基づいて行われる。3番、色が与える心理的効果には違いがある。4番、報酬と罰を使うオペラント条件づけに基づいている。⑤人情の機微にたくみにつけこんでいるが、心理学を用いているわけではないはず。
参考文献
東洋・繁多進・田島信元(編)1992 発達心理学ハンドブック 福村書店
東洋・梅本堯夫・芝祐順・梶田叡一(編)1988 現代教育評価事典
波多野完治・依田新・重松鷹泰(監)1968 学習心理学ハンドブック 金子書房
西平直喜・久世敏雄(編)1988 青年心理学ハンドブック 福村書店
海保博之 2003 心理学ってどんなもの(岩波ジュニア新書No.427) 岩波書店
海保博之・楠見孝(監修)2006 心理学総合事典 朝倉書店
佐藤達哉・溝口元(編)1997 通史日本の心理学 北大路書房
詫摩武俊(編)1998 性格心理学ハンドブック 福村書店