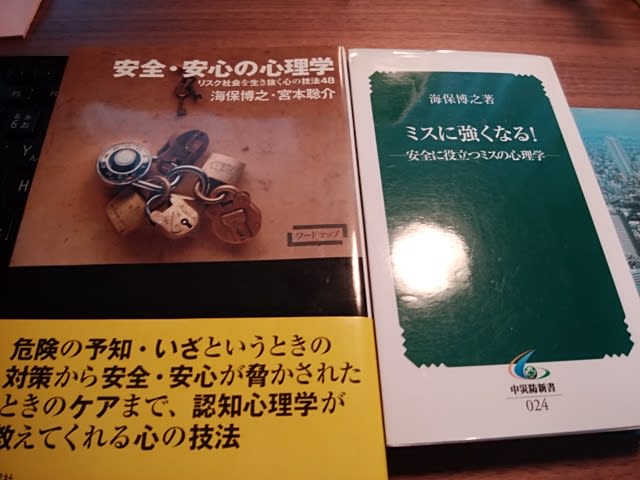
最近は、宅食便関連としびれ薬が多い。
自分のブログでも取り上げているし、
ネット検索もしている。
そのためであろう。
いたるところで、宅食便としびれ薬関連の広告が出現する。
はっきりいってうるさい。
もう購入を決めて満足しているので、
ほしい情報はない。
広告は、かくもうるさいものか。

「参考」ネットより
ターゲティング広告とは
ユーザーやコンテンツの情報を分析して、ユーザーにとって適切と思われる広告を配信するもので自分す。
ターゲティング広告では、PCやスマートフォン・タブレットのブラウザ*ごとのクッキー*上に発行されるIDに紐づいて蓄積される情報(サイト閲覧履歴等)や、スマートフォン・タブレットのOSが発行する広告識別子*に紐づいて蓄積される情報が使われています。
ブラウザやデバイスを1ユーザーと見立てていますが、実際に特定の個人を識別しているわけではありません。
ターゲティング広告では、PCやスマートフォン・タブレットのブラウザ*ごとのクッキー*上に発行されるIDに紐づいて蓄積される情報(サイト閲覧履歴等)や、スマートフォン・タブレットのOSが発行する広告識別子*に紐づいて蓄積される情報が使われています。
ブラウザやデバイスを1ユーザーと見立てていますが、実際に特定の個人を識別しているわけではありません。
集中力の配分ってどんなもの
点検作業のように一点集中もあれば、監視業務などのようにあえて1点集中をせずに満遍なく集中することもあります。
状況に応じて、能動的な集中力はその配分を自在にコントロールできるはずなのですが、ここにもミスへと誘うものが潜んでいます。
それは、能動的な集中の無意識化という問題です。最初は能動的に集中していることは意識できていても、とりわけ1点集中のケースでは、次第に仕事そのものにすべての資源が集中してしまい、集中状態の意識的な自己チェックができなくなってしまうのです。だからこそ仕事の能率も質もあがるのです。
たとえば、発明発見時のエピソードとして知られているようなフロー(熱中)状態、スポーツでは、ゾーン状態のケース、あるいは、何時間、何日、いや何か月にもわたり、非常にレベルの高い集中力を発揮し続けるケースです。
当人は、どんな集中状態なのかについてはまったく意識がない。日常的なケースでもあります。ただし、お笑いともいえるようなケースばかりですが。たとえば、
・電車で小説を読んでいって、乗り過ごしてしまった
・ゲームをしていて、宿題を忘れた
・友達とだべっていて、約束の時間に電話するのを忘れた
・難しい問題を解いていたら、約束を忘れてしまった
いずれもミスのほうを重視すれば、これは好ましいことではありません。しかし、ミスを補ってあまりある至福の状態の体験のほうを考えれば、割にあってはいます。
しかし、ここでは、ミス防止の話であるので、そうとばかりは言っていられません。周りに迷惑をかけることになるし、場合によっては自分の破滅になるかもしれないからです。

最近、アマゾンではじめたサービス?。
でもさっそく、盗難犯罪が発生。
我が屋も、昼の宅食便が置き配になっている。
盗難はこまる。
額はわずかだが、昼に食べるものがなくなってしまう。

◆情報源記憶(source memory)
あることを思い出したときに、それをいつどこで入手したのかを思い出せることもある。これが情報源記憶である。
これには、さらに、いま思い出していることを、自分が頭の中で考えたことか、それとも現実に起こったことかの区別ができることも含む。この区別を特に、現実世界と思惟世界との峻別ということで、現実モニタリング(reality monitoring)という。
鍵を締めたつもり(省略エラー)、あるいは、自分で考えたつもりが人のアイディアだったなどは、現実モニタリングの混乱の例である。

コロナ脳その2
①コロナに関する知識がかなり豊富にある
マスコミのおかげで外在化している知識が垂れ流し状態なので、ほとんど苦労なく、知識をとりこむことができる。
しかも、コロナ恐怖、コロナ不安という感情が伴うので、知識はほとんどチェックさせることなく、とりこまれる。
取り込まれて知識は、「新型」が頭につくように、これまでのウイルスに関する知識とは少しことなっているので、取り込まれた知識は、体系化されずに、ばらばらに格納される。そして、もっぱら不安、恐怖の感情の強度によってランクづけされて格納されている。
②それが日常的にかなり高いレベルで活性化した状態にある
ほぼ毎日、毎時間、コロナ、コロナを目にし、耳にする。さらに悪いことに、「stay home」で自らのみならず周りもコロナに巻き込まれているので、目が覚めている間中、コロナ関連の知識が外からも内からも押し寄せてくる。
ほんのちょっとした刺激で、コロナ関連の知識が頭の中を駆け巡る(活性化)することになる。
デマなどは、ほとんど抵抗なく受け入れられてしまう。
「参考」
池田信夫 twitterより
コロナ対策としては、マスコミが飽きるのが一番。大型の芸能人のスキャンダルかなんかでてきたらーーー
③結果として、見るもの聞くもの、さらに、行動にまで影響する
生活全般が、コロナに支配される。
マスクをしていない人をみただけで、コロナ感染注意となる。
自粛してないお店に腹を立てることになる。自粛警察が一定の社会的許容のもとで出回ることになる。

今日の朝食は、さしみ、卵焼き、味噌汁、なっとう+とろろ、ラッキョウ。
昼食は、わたみのおとどけ食。
4時、とてもおなかがすいて
イチゴ大福
コロッケ
イチゴ
おいしかった。

頭(脳)の中に、
①コロナに関する知識がかなり豊富にあり
②それが日常的にかなり高いレベルで活性化した状態にあり
③結果として、見るもの聞くもの、さらに、行動にまで影響する
「参考」
https://gunosy.com/articles/epQvT 「コロナ脳ってほんとうにあるの?」

ここまでだいたい5か月弱かなー。
長いなー。
日本では、もうちょっとというところまできつつあるかなー
コロナコロナでニュース(ショウ)は持ち切り。
在宅孤独老人は、
それを朝から晩まで視聴させられる。
認知も感情も行動も、コロナ一色になり、
これが、次第に生活を萎縮させたり、ゆがんだ心を生み出したりするようになってしまう。
まさにコロナ脳になってしまう。
そうかといって、手をこまねいているしかないのがまたくやしい。
「参考」アゴラより
コロナ脳とは、私がtwitterで拝見した限りでは「新型コロナウィルスに関する一面的な情報を鵜呑みにしている方々の脳の状態(心理状態)」を指す言葉


心って何なんですか」---心の定義
20世紀前半の心理学は、自然科学の研究パラダイムをそのまま取り込んで研究が行なわれていました。そんな時代には、おかしな話ですが「心なき」心理学がアカデミック心理学として世の中を闊歩していました。
「心って何なんですか」などという疑問を持つ余地などなかったのです。観察できる行動とそれを規定している刺激との関係だけを客観的に記述すべしとする行動主義が、心理学の主流となっていました。心とは何かに思いをめぐらす必要のない?動物を使った研究が、「心」理学として当たり前のごとくに行なわれていました。
もっとも、こうした時代思潮の中でも、J.フロイトの精神分析(Q2・12参照)や、ゲシュタルト心理学などが、「心」理学の研究として細々とではありましたが、行なわれてはいました。
ちょっと脇道にそれますが、ゲシュタルト心理学について一言。その主張は、
「心的経験は、部分の総和以上のものである」に集約されています。 図を見てください。一つ一つの物理的な刺激を単に寄せ集めても存在しないはずの輪郭が主観的にははっきりと見えます。それこそ、部分の総和以上のもの、つまり形態質(Gestalt)の創発です。ここに心の特性をみようとしたのが、ゲシュタルト心理学です。明らかに、これこそ「心」理学と思いませんか。 ***主観的輪郭 別添
さて、こうした隠れ「心」理学の細いが強い流れが、20世紀後半になると、一気に主流を占めるようになってきます。
きっかけは、知的人工物・コンピュータの開発です。コンピュータで人の知的活動を真似してみようという野心的な試み(人工知能)に触発されて、人の頭の働き(認知機能)への関心が、マグマのごとく吹き出しました。それが、行動主義に対抗するものとして、認知主義の流れを一気に作りだし、現在に至っています。
「心とは何か」「意識と何か」「自己とは何か」といったような、心をめぐる根源的な問いが、哲学者や工学者を巻き込んで心理学の中で堂々と議論できるようになりました。なぜなら、人工「知能」というからには、「コンピュータに心は埋め込めるのか」「コンピュータに自己意識を持たせることができるか」などを考えざるをえなくなったからです。
そうした議論の中で出てきた、心とは何かを考える上で基本的な主張を2つほど紹介しておきます。
一つは、A.チューリングが提案した、コンピュータが心を持っていることを証拠立てる手だて(チューリング・テスト)です。 これは、人とコンピュータとを対話させたときに、その人が、相手がコンピュータであることに気がつかないなら、コンピュータは心を持ったとしようというものです。 言葉を操れれば、それは心がある証拠とするわけです。巧妙な、しかしちょっとずるい感じのする提案です。「心の実験室」に一つの関連した試みあげておきましたので、参考にしてください。
もう一つは、ソニーコンピュータサイエンス研究所・茂木健一郎氏が最近、脳機能と心に関する主張「クオリア(qualia;質感)こそ心なり」です(「心を生み出す脳のシステム」NHK Books))。
氏は、クオリアを2つに分けます。 」
1つは、感覚的クオリアです。これは、赤信号を見たときに感ずる、たとえば、「あざやかな赤」「りんごのような赤」というような主観的な感覚の体験(質)のことです。
もう一つ、志向的クオリアもあります。赤信号という言葉を聞いたときに、それが赤信号という物に「向けられている」という感覚のことです。言葉に意味を感じさせるもの、それも志向的クオリアです。
いずれも、質問への直接的な回答にはなっていませんが、「心とは何か」をぴたりと答えられたら、それで心理学の研究は終りです。この疑問を解くための終わりなき探求の営みの中から心理学は心についての豊かな知見を生み出してきたし、これからも生み出していくのです。
********** 心の実験室「コンピュータにも心がある?」********** カウンセリング場面での次の対話の欠けている部分に、あなたがカウンセラー(相談される人)だったらどう答えるかを入れてみてください。
相談者「人は皆同じです」 あなた1「 」
相談者「いつも何かで私たちを悩ませます」 あなた2「 」
相談者「私のボーイフレンドが私をここにつれてきました」 あなた3「 」
相談者「彼が言うには、私はいつも元気がないそうです」 あなた4「 」
相談者「本当に。私は不幸です」 「解説」 この対話の「あなた」のところに、次のようなコンピュータからの応答が入ります。自分の応
答と比較してみてください。
あなた1「どういうふうに?」
あなた2「何か例を思いつきますか?」
あなた3「あなたのボーイフレンドがあなたをここにつれてきたのですね」
あなた4「それはお気の毒です」
この応答は、カウンセリングの基本である傾聴、つまり、相手の言うことに対して「確認」と「同意」をすることに基づいたものです。
もし、次のような応答だとするとあなたには、カウンセらーには不向きかもしれません。解釈や反論や指示は、カウンセリングでは慎重に、が原則だからです。
あなた1「そんなことはありません。人は皆それぞれ個性があります」
あなた2「何かって何ですか」
あなた3「強制的にですか」
あなた4「人の見方はそれぞれですから」
本題は、カウンセリングの話ではなく、人に心があるかどうかの話でした。
これは、J.ワイゼンバウムという人が作った「イライザ(ELIZA)」という人工知能(というには、実はややお粗末なものなのですが)によるカウンセリング場面での応答例です。あまりにもよくできていたため、秘書がすっかりとりこになってしまったそうです。
なお、イライザはそこまではやってはいませんが、コンピュータに言語を理解させる試みは、人工知能研究の最大の課題です。場面を限定するなら、現在でもかなりのところまで成功していますが、人間の言語活動に備わっている臨機応変性、柔軟性を作り込んだ汎用人工知能は、実現できていません。今後も無理との悲観的な見方が一般的ですが、あなたが、この隘路からの脱出の手引きをしてくれることも期待したいところです。
20世紀前半の心理学は、自然科学の研究パラダイムをそのまま取り込んで研究が行なわれていました。そんな時代には、おかしな話ですが「心なき」心理学がアカデミック心理学として世の中を闊歩していました。
「心って何なんですか」などという疑問を持つ余地などなかったのです。観察できる行動とそれを規定している刺激との関係だけを客観的に記述すべしとする行動主義が、心理学の主流となっていました。心とは何かに思いをめぐらす必要のない?動物を使った研究が、「心」理学として当たり前のごとくに行なわれていました。
もっとも、こうした時代思潮の中でも、J.フロイトの精神分析(Q2・12参照)や、ゲシュタルト心理学などが、「心」理学の研究として細々とではありましたが、行なわれてはいました。
ちょっと脇道にそれますが、ゲシュタルト心理学について一言。その主張は、
「心的経験は、部分の総和以上のものである」に集約されています。 図を見てください。一つ一つの物理的な刺激を単に寄せ集めても存在しないはずの輪郭が主観的にははっきりと見えます。それこそ、部分の総和以上のもの、つまり形態質(Gestalt)の創発です。ここに心の特性をみようとしたのが、ゲシュタルト心理学です。明らかに、これこそ「心」理学と思いませんか。 ***主観的輪郭 別添
さて、こうした隠れ「心」理学の細いが強い流れが、20世紀後半になると、一気に主流を占めるようになってきます。
きっかけは、知的人工物・コンピュータの開発です。コンピュータで人の知的活動を真似してみようという野心的な試み(人工知能)に触発されて、人の頭の働き(認知機能)への関心が、マグマのごとく吹き出しました。それが、行動主義に対抗するものとして、認知主義の流れを一気に作りだし、現在に至っています。
「心とは何か」「意識と何か」「自己とは何か」といったような、心をめぐる根源的な問いが、哲学者や工学者を巻き込んで心理学の中で堂々と議論できるようになりました。なぜなら、人工「知能」というからには、「コンピュータに心は埋め込めるのか」「コンピュータに自己意識を持たせることができるか」などを考えざるをえなくなったからです。
そうした議論の中で出てきた、心とは何かを考える上で基本的な主張を2つほど紹介しておきます。
一つは、A.チューリングが提案した、コンピュータが心を持っていることを証拠立てる手だて(チューリング・テスト)です。 これは、人とコンピュータとを対話させたときに、その人が、相手がコンピュータであることに気がつかないなら、コンピュータは心を持ったとしようというものです。 言葉を操れれば、それは心がある証拠とするわけです。巧妙な、しかしちょっとずるい感じのする提案です。「心の実験室」に一つの関連した試みあげておきましたので、参考にしてください。
もう一つは、ソニーコンピュータサイエンス研究所・茂木健一郎氏が最近、脳機能と心に関する主張「クオリア(qualia;質感)こそ心なり」です(「心を生み出す脳のシステム」NHK Books))。
氏は、クオリアを2つに分けます。 」
1つは、感覚的クオリアです。これは、赤信号を見たときに感ずる、たとえば、「あざやかな赤」「りんごのような赤」というような主観的な感覚の体験(質)のことです。
もう一つ、志向的クオリアもあります。赤信号という言葉を聞いたときに、それが赤信号という物に「向けられている」という感覚のことです。言葉に意味を感じさせるもの、それも志向的クオリアです。
いずれも、質問への直接的な回答にはなっていませんが、「心とは何か」をぴたりと答えられたら、それで心理学の研究は終りです。この疑問を解くための終わりなき探求の営みの中から心理学は心についての豊かな知見を生み出してきたし、これからも生み出していくのです。
********** 心の実験室「コンピュータにも心がある?」********** カウンセリング場面での次の対話の欠けている部分に、あなたがカウンセラー(相談される人)だったらどう答えるかを入れてみてください。
相談者「人は皆同じです」 あなた1「 」
相談者「いつも何かで私たちを悩ませます」 あなた2「 」
相談者「私のボーイフレンドが私をここにつれてきました」 あなた3「 」
相談者「彼が言うには、私はいつも元気がないそうです」 あなた4「 」
相談者「本当に。私は不幸です」 「解説」 この対話の「あなた」のところに、次のようなコンピュータからの応答が入ります。自分の応
答と比較してみてください。
あなた1「どういうふうに?」
あなた2「何か例を思いつきますか?」
あなた3「あなたのボーイフレンドがあなたをここにつれてきたのですね」
あなた4「それはお気の毒です」
この応答は、カウンセリングの基本である傾聴、つまり、相手の言うことに対して「確認」と「同意」をすることに基づいたものです。
もし、次のような応答だとするとあなたには、カウンセらーには不向きかもしれません。解釈や反論や指示は、カウンセリングでは慎重に、が原則だからです。
あなた1「そんなことはありません。人は皆それぞれ個性があります」
あなた2「何かって何ですか」
あなた3「強制的にですか」
あなた4「人の見方はそれぞれですから」
本題は、カウンセリングの話ではなく、人に心があるかどうかの話でした。
これは、J.ワイゼンバウムという人が作った「イライザ(ELIZA)」という人工知能(というには、実はややお粗末なものなのですが)によるカウンセリング場面での応答例です。あまりにもよくできていたため、秘書がすっかりとりこになってしまったそうです。
なお、イライザはそこまではやってはいませんが、コンピュータに言語を理解させる試みは、人工知能研究の最大の課題です。場面を限定するなら、現在でもかなりのところまで成功していますが、人間の言語活動に備わっている臨機応変性、柔軟性を作り込んだ汎用人工知能は、実現できていません。今後も無理との悲観的な見方が一般的ですが、あなたが、この隘路からの脱出の手引きをしてくれることも期待したいところです。
病院からの帰路。
抗がん剤投与2時間半、診断待ち時間も含めて10分、会計5分、
薬処方10分。
すいていたので、待ち時間がかなり少なかった。これもいれれば、
トリプルラッキーデイーになるが、本当にラッキーだったのは、これから。
まず、
病院前1時58分発にドンピシャ乗れた。このバス、1時間に1本。
駅についたら、家までの2時15分のバスに、
これまたどんぴしゃりで、乗れた。これも2時台はこれ1本のみ。
これが第一のラッキー。
そして、なんと金曜日は、市内ならバス代金が100円。
これが第2のラッキー。
こんなささいなことに喜びを見つけて生き延びている昨今です。














