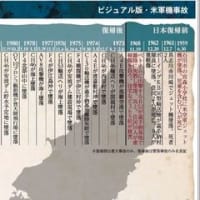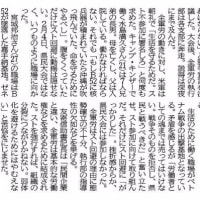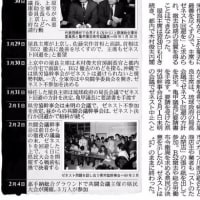2009年5月28日
原爆症認定集団東京訴訟 東京高裁判決についての声明
原爆症認定集団訴訟東京原告団
原爆症認定集団訴訟東京弁護団
原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会
東京都原爆被害者団体協議会(東友会)
日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)
原爆裁判の勝利をめざす東京の会(東京おりづるネット)
原爆症認定集団訴訟を支援する全国ネットワーク
1 本日、東京高等裁判所第4民事部(稲田龍樹裁判長)は、原爆症認定集団訴訟東京第一次訴訟に関し、未認定原告10名及び認定原告1名の未認定疾病について、1名を除いて却下処分を取り消す勝訴判決を言い渡した。
2 本日の東京高等裁判所判決は、これまでの17ヶ所の地裁・高裁判決を集大成したものである。その中で裁判所は、被爆者援護法の前文をふまえて「単なる社会保障的観点に基づくものではなく、戦争遂行主体であった国の国家補償的措置として行われるものである。」と判示した。起因性の判断基準についても、対立する科学的知見がある場合には、厳密な学問的な意味における真偽の見極めではなく、それを前提として全証拠を総合して判断すると判示し、さらに審査の方針には、欠陥があり、判断基準それ自体に合理性を欠くと判示した。
また、肝機能障害及び甲状腺機能低下症の放射線起因性を明快に肯定した。さらに、4㎞、5㎞及び120時間以降の入市のがんについても放射線起因性を認めた。一審原告の一人については、我々の主張が認められなかったことは残念であるが、今後の解決交渉の中で救済を図りたい。
3 河村建夫官房長官は、かねてから「東京高裁判決が一括解決のタイムリミット」と述べ、厚生労働省も、「原爆症認定集団訴訟と認定基準の改訂に関して、5月末までに予定されている大阪高裁判決、東京高裁判決などの司法判断を踏まえて最終的な判断をする」と明言してきた。
さる4月5日、アメリカのオバマ大統領は、核兵器を使用した国としての道義的責任にふれ、核の無い世界に向け行動することを明言した。被爆国日本としては、病気や差別とたたかいながら身をもって原爆被害を告発した集団訴訟の原告・被爆者の声を受け止め、被爆の実態に即した原爆症認定制度を確立し、世界に核兵器の残虐性を示すことが求められている。
集団訴訟の提訴以来すでに67名の原告が亡くなっており、病弱な被爆者にもはや時間はない。
4 本判決は、審査の方針の再改訂と、訴訟の全面解決の指針を示したものであり、いまこそ国は裁判所の判断に従って全面解決に踏み出すべきである。我々は全員救済による訴訟解決を求めてこれから全力で闘う。各位の支援を心からお願いする。
------------------------------
[civilsocietyforum21]から岡林信一さんのコメントなど。
原爆症集団訴訟の基礎知識については、
「原爆症認定訴訟 近畿弁護団通信」が詳しいですが、
http://fujiwaradannchou.blog50.fc2.com/blog-category-2.html
<被爆者手帳を持つ被爆者は現在、25万人余いると言われています。
この中で原爆症の認定を受けているのはわずか1%程度の人なのです。被爆者の方々は高齢になってきておられます。
この訴訟においてもたくさんの原告の方が訴訟中に亡くなられています。>
というように、
原告が求める全面解決(原告全員の救済、認定行政の見直し、国の謝罪など)に向けて、一刻の猶予もない状態ですね。
とくに、焦眉の問題となっている、原爆症認定を求める申請者8000人近くが「順番待ち」という名目で、審査すらされていないのは、国の怠慢・無責任と言わざるをえません。
http://mainichi.jp/select/wadai/heiwa/archive/news/2009/04/02/20090402ddp012040013000c.html
ところで、原爆症集団認定訴訟と、東京と大阪の大空襲裁判との関連について雑感。
大阪空襲訴訟弁護団のHPにあるように、
http://o-bengosi.hp.infoseek.co.jp/osaka-kusyu/
6月3日(水)に大阪地裁202法廷で第1回口頭弁論があるそうです。
大空襲裁判では、矢野宏さんの著作『大阪空襲訴訟を知っていますか』にあるように、「戦争損害受忍論」(あるいは「戦争被害受忍論」)を撤回させることが争点となります。
国は、旧軍人・軍属、その遺族に恩給や年金を支給しているのに対し、、民間の空襲被災者には何の補償していないという、「二重基準」が問題になります。
「受忍論」は 「中国残留孤児訴訟」でも突破できなかったです。そして、原爆被爆者に対しては、被爆者援護法により被爆者手帳の交付による健康管理手当の支給、そして裁判となっている原爆症認定による特別医療手当の支給などの「援護措置」がとられていますが、これはあくまで「国家補償」ではなく、「国の責任」での「援護措置」という、「戦争被害受忍論」に基づくものです。
民間の戦争被害者としては、被爆者が唯一国による手当を支給されており(ただし、在外被爆者が援護法の対象外となっていることでの裁判もおきています)、その対象を広げていくことは、国の戦争責任を問う意味で大きいと言えますが、じつはそれでも「戦争被害受忍論」が大きくたちはだかっていると言えます。
たとえば、広島大名誉教授の舟橋喜恵さんのコメント
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/mediacenter/article.php?story=20080523170638458_ja
<ところが1980年に、厚生大臣(当時)の私的諮問機関「原爆被爆者対策基本問題懇談会」は、戦争による犠牲は受忍すべきだとの意見書をだし、原爆被害を放射線による特殊な被害に限定してしまった。さらに厚労省は放射線被害を初期放射線に限定して、それを認定基準に持ちこんでしまった。これが原爆症認定者が被爆者全体の1%にも満たない状況をつくりだしたのである。 >
そうであれば、大空襲訴訟で「戦争被害受忍論」を乗り越えた司法判断がかちとられれば、「被爆者援護法」とこれに基づく行政の在り方をも変えさせ、25万人の被爆者全員への「国家補償」を実現させる道が開けるかもしれません。
もちろん、「受忍論」を放棄して戦争被害者一般に国家補償することを認めれば、膨大な予算措置をとらなければならないので、今の政府はかたくなに拒否するでしょうが、だからこそどこかで風穴が空けば、画期的な事態になるでしょう。
そして、「戦争被害受忍論」が放棄され、民間人一般の戦争被害に国家補償が認められるようになれば、ひとたび戦争を行えば国は膨大なコストを払うことになるゆえに、「戦争はしない」「軍隊は持たない」と世界に誓った9条と、「平和的生存権」をうたった平和憲法どおりの国づくり、安全保障政策を構築することが、人道的にも財政コスト的にも合理性をもったものとなるのではないでしょうか?
<本日の東京高等裁判所判決は、これまでの17ヶ所の地裁・高裁判決を集大成したものである。その中で裁判所は、被爆者援護法の前文をふまえて「単なる社会保障的観点に基づくものではなく、戦争遂行主体であった国の国家補償的措置として行われるものである。」と判示した。>
とあります。
私は(中略)、被爆者援護法は「戦争被害受忍論」に固執して、「国家補償」ではない「援護措置」であると理解していましたが、
「単なる社会保障的観点に基づくものではなく、戦争遂行主体であった国の国家補償的措置として行われるものである」という司法判断は、ひょっとしたら、「受忍論」を乗り越える内容となっていると解釈したらいいのでしょうか?
日本被団協が公開しているHPでは、
http://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/rn_page/menu_page/side_menu_page/seimei/kougi_seimei_other/00-01/0012sengen.htm
< 1994年に制定された「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」は、「原爆被害への国家補償」を拒否しました。原爆被害が「戦争という国の行為によってもたらされたもの」である以上、「戦争遂行の主体であった国が自らの責任によって救済をはかる」(孫振斗訴訟最高裁判決、1978年3月30日)のは当然のことです。しかし、1980年、厚生大臣の私的諮問機関・原爆被爆者対策基本問題懇談会は、戦争被害は「すべての国民がひとしく受忍しなければならない」とのべ、これが国の被爆者対策の基本にすえられたのでした。>
よろしければ、下のマークをクリックして!

原爆症認定集団東京訴訟 東京高裁判決についての声明
原爆症認定集団訴訟東京原告団
原爆症認定集団訴訟東京弁護団
原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会
東京都原爆被害者団体協議会(東友会)
日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)
原爆裁判の勝利をめざす東京の会(東京おりづるネット)
原爆症認定集団訴訟を支援する全国ネットワーク
1 本日、東京高等裁判所第4民事部(稲田龍樹裁判長)は、原爆症認定集団訴訟東京第一次訴訟に関し、未認定原告10名及び認定原告1名の未認定疾病について、1名を除いて却下処分を取り消す勝訴判決を言い渡した。
2 本日の東京高等裁判所判決は、これまでの17ヶ所の地裁・高裁判決を集大成したものである。その中で裁判所は、被爆者援護法の前文をふまえて「単なる社会保障的観点に基づくものではなく、戦争遂行主体であった国の国家補償的措置として行われるものである。」と判示した。起因性の判断基準についても、対立する科学的知見がある場合には、厳密な学問的な意味における真偽の見極めではなく、それを前提として全証拠を総合して判断すると判示し、さらに審査の方針には、欠陥があり、判断基準それ自体に合理性を欠くと判示した。
また、肝機能障害及び甲状腺機能低下症の放射線起因性を明快に肯定した。さらに、4㎞、5㎞及び120時間以降の入市のがんについても放射線起因性を認めた。一審原告の一人については、我々の主張が認められなかったことは残念であるが、今後の解決交渉の中で救済を図りたい。
3 河村建夫官房長官は、かねてから「東京高裁判決が一括解決のタイムリミット」と述べ、厚生労働省も、「原爆症認定集団訴訟と認定基準の改訂に関して、5月末までに予定されている大阪高裁判決、東京高裁判決などの司法判断を踏まえて最終的な判断をする」と明言してきた。
さる4月5日、アメリカのオバマ大統領は、核兵器を使用した国としての道義的責任にふれ、核の無い世界に向け行動することを明言した。被爆国日本としては、病気や差別とたたかいながら身をもって原爆被害を告発した集団訴訟の原告・被爆者の声を受け止め、被爆の実態に即した原爆症認定制度を確立し、世界に核兵器の残虐性を示すことが求められている。
集団訴訟の提訴以来すでに67名の原告が亡くなっており、病弱な被爆者にもはや時間はない。
4 本判決は、審査の方針の再改訂と、訴訟の全面解決の指針を示したものであり、いまこそ国は裁判所の判断に従って全面解決に踏み出すべきである。我々は全員救済による訴訟解決を求めてこれから全力で闘う。各位の支援を心からお願いする。
------------------------------
[civilsocietyforum21]から岡林信一さんのコメントなど。
原爆症集団訴訟の基礎知識については、
「原爆症認定訴訟 近畿弁護団通信」が詳しいですが、
http://fujiwaradannchou.blog50.fc2.com/blog-category-2.html
<被爆者手帳を持つ被爆者は現在、25万人余いると言われています。
この中で原爆症の認定を受けているのはわずか1%程度の人なのです。被爆者の方々は高齢になってきておられます。
この訴訟においてもたくさんの原告の方が訴訟中に亡くなられています。>
というように、
原告が求める全面解決(原告全員の救済、認定行政の見直し、国の謝罪など)に向けて、一刻の猶予もない状態ですね。
とくに、焦眉の問題となっている、原爆症認定を求める申請者8000人近くが「順番待ち」という名目で、審査すらされていないのは、国の怠慢・無責任と言わざるをえません。
http://mainichi.jp/select/wadai/heiwa/archive/news/2009/04/02/20090402ddp012040013000c.html
ところで、原爆症集団認定訴訟と、東京と大阪の大空襲裁判との関連について雑感。
大阪空襲訴訟弁護団のHPにあるように、
http://o-bengosi.hp.infoseek.co.jp/osaka-kusyu/
6月3日(水)に大阪地裁202法廷で第1回口頭弁論があるそうです。
大空襲裁判では、矢野宏さんの著作『大阪空襲訴訟を知っていますか』にあるように、「戦争損害受忍論」(あるいは「戦争被害受忍論」)を撤回させることが争点となります。
国は、旧軍人・軍属、その遺族に恩給や年金を支給しているのに対し、、民間の空襲被災者には何の補償していないという、「二重基準」が問題になります。
「受忍論」は 「中国残留孤児訴訟」でも突破できなかったです。そして、原爆被爆者に対しては、被爆者援護法により被爆者手帳の交付による健康管理手当の支給、そして裁判となっている原爆症認定による特別医療手当の支給などの「援護措置」がとられていますが、これはあくまで「国家補償」ではなく、「国の責任」での「援護措置」という、「戦争被害受忍論」に基づくものです。
民間の戦争被害者としては、被爆者が唯一国による手当を支給されており(ただし、在外被爆者が援護法の対象外となっていることでの裁判もおきています)、その対象を広げていくことは、国の戦争責任を問う意味で大きいと言えますが、じつはそれでも「戦争被害受忍論」が大きくたちはだかっていると言えます。
たとえば、広島大名誉教授の舟橋喜恵さんのコメント
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/mediacenter/article.php?story=20080523170638458_ja
<ところが1980年に、厚生大臣(当時)の私的諮問機関「原爆被爆者対策基本問題懇談会」は、戦争による犠牲は受忍すべきだとの意見書をだし、原爆被害を放射線による特殊な被害に限定してしまった。さらに厚労省は放射線被害を初期放射線に限定して、それを認定基準に持ちこんでしまった。これが原爆症認定者が被爆者全体の1%にも満たない状況をつくりだしたのである。 >
そうであれば、大空襲訴訟で「戦争被害受忍論」を乗り越えた司法判断がかちとられれば、「被爆者援護法」とこれに基づく行政の在り方をも変えさせ、25万人の被爆者全員への「国家補償」を実現させる道が開けるかもしれません。
もちろん、「受忍論」を放棄して戦争被害者一般に国家補償することを認めれば、膨大な予算措置をとらなければならないので、今の政府はかたくなに拒否するでしょうが、だからこそどこかで風穴が空けば、画期的な事態になるでしょう。
そして、「戦争被害受忍論」が放棄され、民間人一般の戦争被害に国家補償が認められるようになれば、ひとたび戦争を行えば国は膨大なコストを払うことになるゆえに、「戦争はしない」「軍隊は持たない」と世界に誓った9条と、「平和的生存権」をうたった平和憲法どおりの国づくり、安全保障政策を構築することが、人道的にも財政コスト的にも合理性をもったものとなるのではないでしょうか?
<本日の東京高等裁判所判決は、これまでの17ヶ所の地裁・高裁判決を集大成したものである。その中で裁判所は、被爆者援護法の前文をふまえて「単なる社会保障的観点に基づくものではなく、戦争遂行主体であった国の国家補償的措置として行われるものである。」と判示した。>
とあります。
私は(中略)、被爆者援護法は「戦争被害受忍論」に固執して、「国家補償」ではない「援護措置」であると理解していましたが、
「単なる社会保障的観点に基づくものではなく、戦争遂行主体であった国の国家補償的措置として行われるものである」という司法判断は、ひょっとしたら、「受忍論」を乗り越える内容となっていると解釈したらいいのでしょうか?
日本被団協が公開しているHPでは、
http://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/rn_page/menu_page/side_menu_page/seimei/kougi_seimei_other/00-01/0012sengen.htm
< 1994年に制定された「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」は、「原爆被害への国家補償」を拒否しました。原爆被害が「戦争という国の行為によってもたらされたもの」である以上、「戦争遂行の主体であった国が自らの責任によって救済をはかる」(孫振斗訴訟最高裁判決、1978年3月30日)のは当然のことです。しかし、1980年、厚生大臣の私的諮問機関・原爆被爆者対策基本問題懇談会は、戦争被害は「すべての国民がひとしく受忍しなければならない」とのべ、これが国の被爆者対策の基本にすえられたのでした。>
よろしければ、下のマークをクリックして!