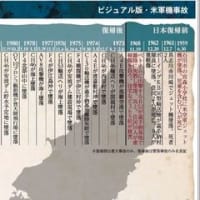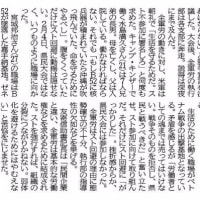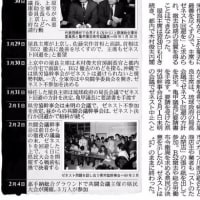岡真理です。
パレスチナ難民2世の作家、イブラーヒーム・ナスラッラー(ヨルダン在住)の小説に『アーミナの婚礼』という作品があります(拙著『アラブ、祈りとしての文学』(みすず書房、2008年)でこの作品に言及した際には『アーミナの縁結び』としましたが、原題を忠実に訳すならば『アーミナの(複数の)婚礼』です)。第二次インティファーダのさなかのガザを舞台にした小説で、イスラエル占領軍によって日々、愛する誰か――夫、息子、姉、友人…――が殺されていく中で、主人公のアーミナが、愛する者たちの縁結びを願うという物語です。
この春、ガザに滞在し、そこで、婚礼(披露宴)と、婚約式の二つに出席する機会がありました。封鎖下のガザでも、人々は、披露宴には大勢の人(数百人)が集まって、壇上で新婦とともに踊ります。新しい人生の門出を祝って、生きることを言祝いで。結婚式はいずれの社会、いずれの文化においても人生のメインイヴェントですが、しかし、追放と離散の生を70年近くも強いられ、占領下で人間としての生を奪われている彼、彼女たちにとって婚礼とは、一個人、一家族の出来事を越えて、共同体全体にとっての大きな意味のある、未来への投企にほかならないのだ、ということを――なぜ、アーミナが、愛する者たちのためにほかならぬ婚礼を夢見たのか――ガザの婚礼と婚約式に出席して理解しました。
そう言えば、パレスチナ人監督ミシェル・クレイフィの名作『ガリレアの婚礼』(1987年)も、婚礼を通して、イスラエル軍の支配のもとで生きるパレスチナ人の抵抗の姿を描いた作品でした(日本語版VHSあり)。
8月13日、ガザ北部の、避難所となっている国連の学校で、避難民同士の結婚式が催されたことは日本でも報道されています。ただ、日本語の報道を見てみると、「はやく一緒になりたかった、みんなに喜んでもらいたかったと」いうような新郎の話が紹介され、戦争の中でも結婚式を挙げるカップルがいた、戦争で疲れている人たちがそれを喜んだ、というような、戦争という大きな物語の中の挿話的な話に矮小化されており、なぜ、UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)が乏しい予算のなか、ほかを差し置いて全額負担してまでもこの結婚式を開催したのか、その意味が、まったく伝わらないように思いました。
以下は、アラビア語のニュースです(英語字幕つき)。3分間の映像がありますので、よろしければご覧ください。新郎のインタビュー、結婚式の模様(ダンス風景)、UNRWA職員のインタビューという構成になっています。
http://www.middleeasteye.net/news/video-gaza-wedding-defies-israeli-war-carnage-1800007475
新郎はインタビューの中ではっきり、結婚式をしたのは、世界に向けて、私たち(ガザのパレスチナ人)が「サーミディーン」だということを示したかった、と語っています。
英語字幕では、we are steadfast と訳されています。「サーミディーン」とは「ソムードする者たち」のことで、「ソムード」とは、そこに踏みとどまってがんばる不屈の抵抗を表す言葉です。
そして、その言葉を体現するかのように、若者たちがクーフィーエ(白黒格子のパレスチナの伝統スカーフ)を首にまいて、パレスチナの伝統舞踊、ダブケを力強く踊る姿が紹介されます。最後に国連職員が、私たちは自由と独立のために闘っているのだ、ということを語ります。
この結婚式は、単に、戦争で打ちひしがれている同胞を束の間、人生の慶事で喜ばせるためだけでなく、これだけの破壊と殺戮に見舞われても、その破壊の中でもこうして「生きる」ということを手放さず、生を言祝ぐことができる、その不屈の意志を、自分たちをこの世から抹殺し、隷従させようとする者たちに見せつけると同時に、自由と尊厳を求めて闘う自分たちを応援してくれている世界の人々にその姿を見せる、そのようなものであると私は感じました。
これは、パレスチナ映画『壊された5つのカメラ』でも描かれていたことです。どのような抑圧下にあろうと、敵がどんどんその人間性を失っていく中で、決して敵の似姿になることなく、占領と闘いながら、同時に、あくまでも人間の側に、生の側に踏みとどまって、生の一瞬一瞬を精一杯楽しむ村人たちの姿が感動的に描かれていました。
そして、イスラエルをパレスチナ人に対する殺戮に駆り立てるのは、これだけの破壊と殺戮に見舞われてもなお、力強く大地を踏みしめダブケを踊る若者たちのように、パレスチナ人が決して折れない、挫けない姿を彼らに見せつけるからにほかならないと思います。
いま、ガザで起きていることは、イスラエル対ハマースではなく、7年以上にわたる封鎖のあとでさえ、そして1ヶ月にわたるジェノサイドのあとでさえ、占領者に服従することを拒否して、占領からの解放を求めるパレスチナ人と、彼らのその意志を打ち砕こうとする者たち(=イスラエルおよびその同盟国)の闘いなのだと、この結婚式を見て、あらためて思いました。
【2014.7-8 ガザ】岡真理さんの発信 まとめ
http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/4ae6d774bb67f253bb05e3ec5ac285e9
よろしければ、下のマークをクリックして!

よろしければ、もう一回!

パレスチナ難民2世の作家、イブラーヒーム・ナスラッラー(ヨルダン在住)の小説に『アーミナの婚礼』という作品があります(拙著『アラブ、祈りとしての文学』(みすず書房、2008年)でこの作品に言及した際には『アーミナの縁結び』としましたが、原題を忠実に訳すならば『アーミナの(複数の)婚礼』です)。第二次インティファーダのさなかのガザを舞台にした小説で、イスラエル占領軍によって日々、愛する誰か――夫、息子、姉、友人…――が殺されていく中で、主人公のアーミナが、愛する者たちの縁結びを願うという物語です。
この春、ガザに滞在し、そこで、婚礼(披露宴)と、婚約式の二つに出席する機会がありました。封鎖下のガザでも、人々は、披露宴には大勢の人(数百人)が集まって、壇上で新婦とともに踊ります。新しい人生の門出を祝って、生きることを言祝いで。結婚式はいずれの社会、いずれの文化においても人生のメインイヴェントですが、しかし、追放と離散の生を70年近くも強いられ、占領下で人間としての生を奪われている彼、彼女たちにとって婚礼とは、一個人、一家族の出来事を越えて、共同体全体にとっての大きな意味のある、未来への投企にほかならないのだ、ということを――なぜ、アーミナが、愛する者たちのためにほかならぬ婚礼を夢見たのか――ガザの婚礼と婚約式に出席して理解しました。
そう言えば、パレスチナ人監督ミシェル・クレイフィの名作『ガリレアの婚礼』(1987年)も、婚礼を通して、イスラエル軍の支配のもとで生きるパレスチナ人の抵抗の姿を描いた作品でした(日本語版VHSあり)。
8月13日、ガザ北部の、避難所となっている国連の学校で、避難民同士の結婚式が催されたことは日本でも報道されています。ただ、日本語の報道を見てみると、「はやく一緒になりたかった、みんなに喜んでもらいたかったと」いうような新郎の話が紹介され、戦争の中でも結婚式を挙げるカップルがいた、戦争で疲れている人たちがそれを喜んだ、というような、戦争という大きな物語の中の挿話的な話に矮小化されており、なぜ、UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)が乏しい予算のなか、ほかを差し置いて全額負担してまでもこの結婚式を開催したのか、その意味が、まったく伝わらないように思いました。
以下は、アラビア語のニュースです(英語字幕つき)。3分間の映像がありますので、よろしければご覧ください。新郎のインタビュー、結婚式の模様(ダンス風景)、UNRWA職員のインタビューという構成になっています。
http://www.middleeasteye.net/news/video-gaza-wedding-defies-israeli-war-carnage-1800007475
新郎はインタビューの中ではっきり、結婚式をしたのは、世界に向けて、私たち(ガザのパレスチナ人)が「サーミディーン」だということを示したかった、と語っています。
英語字幕では、we are steadfast と訳されています。「サーミディーン」とは「ソムードする者たち」のことで、「ソムード」とは、そこに踏みとどまってがんばる不屈の抵抗を表す言葉です。
そして、その言葉を体現するかのように、若者たちがクーフィーエ(白黒格子のパレスチナの伝統スカーフ)を首にまいて、パレスチナの伝統舞踊、ダブケを力強く踊る姿が紹介されます。最後に国連職員が、私たちは自由と独立のために闘っているのだ、ということを語ります。
この結婚式は、単に、戦争で打ちひしがれている同胞を束の間、人生の慶事で喜ばせるためだけでなく、これだけの破壊と殺戮に見舞われても、その破壊の中でもこうして「生きる」ということを手放さず、生を言祝ぐことができる、その不屈の意志を、自分たちをこの世から抹殺し、隷従させようとする者たちに見せつけると同時に、自由と尊厳を求めて闘う自分たちを応援してくれている世界の人々にその姿を見せる、そのようなものであると私は感じました。
これは、パレスチナ映画『壊された5つのカメラ』でも描かれていたことです。どのような抑圧下にあろうと、敵がどんどんその人間性を失っていく中で、決して敵の似姿になることなく、占領と闘いながら、同時に、あくまでも人間の側に、生の側に踏みとどまって、生の一瞬一瞬を精一杯楽しむ村人たちの姿が感動的に描かれていました。
そして、イスラエルをパレスチナ人に対する殺戮に駆り立てるのは、これだけの破壊と殺戮に見舞われてもなお、力強く大地を踏みしめダブケを踊る若者たちのように、パレスチナ人が決して折れない、挫けない姿を彼らに見せつけるからにほかならないと思います。
いま、ガザで起きていることは、イスラエル対ハマースではなく、7年以上にわたる封鎖のあとでさえ、そして1ヶ月にわたるジェノサイドのあとでさえ、占領者に服従することを拒否して、占領からの解放を求めるパレスチナ人と、彼らのその意志を打ち砕こうとする者たち(=イスラエルおよびその同盟国)の闘いなのだと、この結婚式を見て、あらためて思いました。
【2014.7-8 ガザ】岡真理さんの発信 まとめ
http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/4ae6d774bb67f253bb05e3ec5ac285e9
よろしければ、下のマークをクリックして!
よろしければ、もう一回!