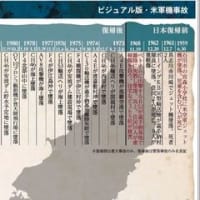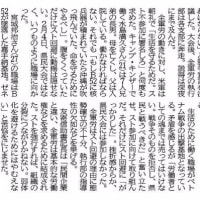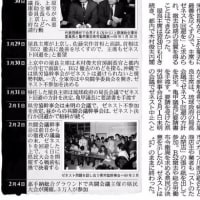そう言えば、フィンランドに来る前、1月にフランスの家の暖房にも異変があった。格別寒い夜中に暖房用のボイラーが停まる。故障かと思って据え付けた業者に電話で相談すると、たぶん安全装置が作動して停止したのだから、まず赤いランプがついていることを確認して、それからその横にあるスイッチを押せばリセットできるという。「なんだかあっちこっちの家で同じようなことになっているんですが、どうしたんでしょうね」と彼は言った。
異国の客 048
厳寒体験、エネルギー問題、全世界が流謫の地 その2
そう言えば、フィンランドに来る前、1月にフランスの家の暖房にも異変
があった。
格別寒い夜中に暖房用のボイラーが停まる。
故障かと思って据え付けた業者に電話で相談すると、たぶん安全装置が作
動して停止したのだから、まず赤いランプがついていることを確認して、そ
れからその横にあるスイッチを押せばリセットできるという。
「なんだかあっちこっちの家で同じようなことになっているんですが、どう
したんでしょうね」と彼は言った。
以下はまさかとは思うが、あり得なくはない推理。
寒い夜中だからどの家のボイラーも稼働している。
そこでガス圧が充分でないとボイラーは停止する。
もし起こったのがそういう現象だったとして、それはロシアとウクライナ
の間のあの騒ぎの影響ということは考えられないだろうか。
ウクライナ向けのガスの販売価格を国際市場の水準に合わせるための交渉
が難航して期限切れになったというのが公式の説明だった。
そして実際には、ロシアを離れて欧米に近づこうとするウクライナへの懲
罰だったという説の方が説得力がある。
そのすぐ後でまた、モスクワで零下30度まで下がった寒気のためにヨー
ロッパ向けの分を国内に回したので、ヨーロッパはまたも影響を受けた。
零下30度がどのくらいの寒さかはフィンランドを体験した今ならばわか
る。暖房が充分でないと恐怖感を覚える。
いずれにしてもロシアからヨーロッパへ送られるガスが減り、我が家のボ
イラーが停止し、寒い思いをすることになった。
結局のところ、本当にそれがフランスの我が家まで波及したのか否かは調
べられなかった。
ぼくの仮説は間違いである可能性の方が高いと思うが、ともかく何かしら
の影響はあって、それをぼくは象徴的に自分の家の寒さとして受け止めた。
ヨーロッパ全体がこれを機にロシアの天然ガスに過度に依存することは危
険だと考えはじめた。
何かで対立した時にガスを停めると脅されたのではかなわない。
同じ理由から佐藤優は東シベリアと日本をパイプラインで結ぶ計画は危険
だと指摘する(『国家の自縛』産経新聞社)。
資源外交というけれど、資源はそのまま武器になる。
では代わりに何があるか? 原子力はどうだろう?
ぼくは原発は廃止すべき技術だと考えてきた(例えば『楽しい終末』の
「核と暮らす日々」の章)。
今の軽水冷却炉による原子力発電所は構造が複雑すぎる上に、事故が起こ
った場合にその規模が大きすぎる。
構造が複雑になるのは基本原理に無理があるのを多くの付帯的な装置で補
っているからだ。
シンプルでないし、技術としていかにも醜い。
人間にはこれを絶対安全に運転する能力がないのはチェルノブイリの一例
を見てもわかる。
事故というものについては自分だけは大丈夫とは思わない方がいい。
先日、チェルノブイリの事故の際にキエフの住民を避難させるかどうかが
検討され、非常に困難なその避難が実行されなかったのはたまたま風がそち
らに向かって吹いていなかったからだったという報道があった。
ジャック・レモン主演で映画にもなった小説『チャイナ・シンドローム』
の最後は「そこで風向きが変わって、放射能を含んだ雲はロサンジェルスに
向かったのです」という恐ろしい証言で終わっていた。
しかしフィンランドは今年のエネルギー危機を機にここ5年間ずっと凍結
してきた原発計画の再開を検討することにしたという。
チェルノブイリの事故の時にフィンランドはずいぶん大きな影響を受けた。
特に北方のいわゆるラップランドでは(今回ぼくが行っていたあたりだ)
トナカイの餌になる蘚苔類に放射能が蓄積して大きな問題になった。
だから原発に対しては慎重な姿勢で来たのだが、そうも言っていられなく
なったらしい。
フランスはどうか。
人も知るごとくこの国は原発大国であって、電力の実に75パーセントを
原子力に頼っている。
そして、その実情に反対する声はあまり聞かない。
フランスはなぜこんなに原発への依存度が高いのだろう。
世界でフランス以上に発電を原子力に頼っているのはリトアニアだけだ
(79・9パーセント)。
全体に旧ソ連の衛星国は比率が4、50パーセント代と高いが、他は日本
の35パーセントがそれでも高い方。
ある時、このフランスの姿勢についての説明に接して、そうだったのかと
思った。
要は外交のために石油依存から脱却したかったというのだ。
国際社会の主役でいたいというフランスの意欲は昔から強い。
冷戦下でアメリカがすべてを仕切るようになったのが悔しいという思いも
ある。
それで中東政策で産油国に振り回されないように石油エネルギーの比率を
下げたというのはわからなくもないが、そのために事故のリスクを無視する
のはやはり問題があると思う。
エネルギー政策はむずかしい。
一方では今の生活水準を下げたくないとみなが考えている。
核や化石燃料は資源が枯渇することを心配しなければいけないし、核につ
いては特に事故の危険と、廃棄物の始末、燃料の再処理、廃炉のむずかしさ
などを考慮しなくてはいけない。
ではいわゆる自然エネルギーはというと、ぼくはある意味でその信奉者で
あるのだが、実際にはすべてをそちらに移行するのは難しいだろう。
われわれはどこかで未来像を持っていたくて、その象徴として風力や太陽
光を信奉しているのではないか。
それで、数年前から気になっているのが絶対安全原子力発電の話。
具体的には『「原発」革命』(古川和男著 文春新書)という本が綿密に
書いている。
そんなものがあるかと最初は思ったけれど、理系中退で科学啓蒙書の書評
くらいはできるぼくが読んで納得できるような話なのだ。
要点は核燃料を溶融塩を用いた液体にすること。
今の軽水冷却炉は燃料が固体ウランであるために種々の難問を抱えている。
技術的に複雑すぎるものになる理由の多くはここにある。
ここで燃料をウランからトリウムに替え、これをフッ化トリウムの形でフ
ッ化リチウムならびにフッ化ベリリウムと合わせて高温で溶融塩にする。
すると固体燃料よりも扱いがずっと容易になる。
これでどれほどの利点があるかは実際にこの本を読んでいただきたい。
炉心溶解のような大事故の可能性はなくなる。
資源は世界に広く分布しているので外交のための武器にはなりにくい。
テロリストが脅迫の道具に仕立てることも、また軍事面で利用するのも非
常に困難。
今たくさん貯まってしまって処理が困難なプルトニウムも安全に燃やすこ
とができる。
危険がなく小型化が容易なので小規模な発電所を消費地の近くに造ること
ができるから、送電効率が上がって無駄がない。
軽水冷却炉は常に全出力で運転しなければならないが、こちらは出力を絞
っても問題ない。
トリウムは爆弾にできないので、ウランとプルトニウムの精製や流通を禁
止すれば核拡散を効果的に防ぐことができる。
炉の構造が単純で運転効率がよく、豊富にある資源なので、経済性は非常
に高い。
以上が利点で、欠点はまだ実証性がないこと。
これから具体的に実験炉、実証炉とデータ収集を続ければやがては実用炉
が普及すると古川は言う。
しかし、この本が出てから5年になるが、その後この話題に接したことは
ない。
インターネットで見ても未だ啓蒙の段階で具体的な動きはないようだ。
もしもこの本に書いてない決定的な欠陥があって専門家が将来性を否定し
ているのなら、その理由を知りたいと思うのだが。
<つづく>
(池澤夏樹 執筆:2006‐03‐25)
*「異国の客」は『すばる』(集英社)に連載しています。
http://subaru.shueisha.co.jp/
──────────────────────────────────
【池澤夏樹の最近の著書】
□『憲法なんて知らないよ』池澤夏樹著 集英社文庫
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4087478149/impala-22
□『世界文学を読みほどく』池澤夏樹著 新潮社刊
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4106035448/impala-22
□『パレオマニア』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4797670959/impala-22
□長編小説『静かな大地』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4022578734/impala-22
■『DO YOU BOMB THEM?』
戦争前のイラクの姿を映し出すビデオ作品です。
本橋成一・監督/撮影、池澤夏樹・文/語り、坂田明・音楽
価格:2000円
詳しくは、ポレポレタイムス社 TEL:03-3227-1870
http://www.ne.jp/asahi/polepole/times/polepole/index.html
異国の客 048
厳寒体験、エネルギー問題、全世界が流謫の地 その2
そう言えば、フィンランドに来る前、1月にフランスの家の暖房にも異変
があった。
格別寒い夜中に暖房用のボイラーが停まる。
故障かと思って据え付けた業者に電話で相談すると、たぶん安全装置が作
動して停止したのだから、まず赤いランプがついていることを確認して、そ
れからその横にあるスイッチを押せばリセットできるという。
「なんだかあっちこっちの家で同じようなことになっているんですが、どう
したんでしょうね」と彼は言った。
以下はまさかとは思うが、あり得なくはない推理。
寒い夜中だからどの家のボイラーも稼働している。
そこでガス圧が充分でないとボイラーは停止する。
もし起こったのがそういう現象だったとして、それはロシアとウクライナ
の間のあの騒ぎの影響ということは考えられないだろうか。
ウクライナ向けのガスの販売価格を国際市場の水準に合わせるための交渉
が難航して期限切れになったというのが公式の説明だった。
そして実際には、ロシアを離れて欧米に近づこうとするウクライナへの懲
罰だったという説の方が説得力がある。
そのすぐ後でまた、モスクワで零下30度まで下がった寒気のためにヨー
ロッパ向けの分を国内に回したので、ヨーロッパはまたも影響を受けた。
零下30度がどのくらいの寒さかはフィンランドを体験した今ならばわか
る。暖房が充分でないと恐怖感を覚える。
いずれにしてもロシアからヨーロッパへ送られるガスが減り、我が家のボ
イラーが停止し、寒い思いをすることになった。
結局のところ、本当にそれがフランスの我が家まで波及したのか否かは調
べられなかった。
ぼくの仮説は間違いである可能性の方が高いと思うが、ともかく何かしら
の影響はあって、それをぼくは象徴的に自分の家の寒さとして受け止めた。
ヨーロッパ全体がこれを機にロシアの天然ガスに過度に依存することは危
険だと考えはじめた。
何かで対立した時にガスを停めると脅されたのではかなわない。
同じ理由から佐藤優は東シベリアと日本をパイプラインで結ぶ計画は危険
だと指摘する(『国家の自縛』産経新聞社)。
資源外交というけれど、資源はそのまま武器になる。
では代わりに何があるか? 原子力はどうだろう?
ぼくは原発は廃止すべき技術だと考えてきた(例えば『楽しい終末』の
「核と暮らす日々」の章)。
今の軽水冷却炉による原子力発電所は構造が複雑すぎる上に、事故が起こ
った場合にその規模が大きすぎる。
構造が複雑になるのは基本原理に無理があるのを多くの付帯的な装置で補
っているからだ。
シンプルでないし、技術としていかにも醜い。
人間にはこれを絶対安全に運転する能力がないのはチェルノブイリの一例
を見てもわかる。
事故というものについては自分だけは大丈夫とは思わない方がいい。
先日、チェルノブイリの事故の際にキエフの住民を避難させるかどうかが
検討され、非常に困難なその避難が実行されなかったのはたまたま風がそち
らに向かって吹いていなかったからだったという報道があった。
ジャック・レモン主演で映画にもなった小説『チャイナ・シンドローム』
の最後は「そこで風向きが変わって、放射能を含んだ雲はロサンジェルスに
向かったのです」という恐ろしい証言で終わっていた。
しかしフィンランドは今年のエネルギー危機を機にここ5年間ずっと凍結
してきた原発計画の再開を検討することにしたという。
チェルノブイリの事故の時にフィンランドはずいぶん大きな影響を受けた。
特に北方のいわゆるラップランドでは(今回ぼくが行っていたあたりだ)
トナカイの餌になる蘚苔類に放射能が蓄積して大きな問題になった。
だから原発に対しては慎重な姿勢で来たのだが、そうも言っていられなく
なったらしい。
フランスはどうか。
人も知るごとくこの国は原発大国であって、電力の実に75パーセントを
原子力に頼っている。
そして、その実情に反対する声はあまり聞かない。
フランスはなぜこんなに原発への依存度が高いのだろう。
世界でフランス以上に発電を原子力に頼っているのはリトアニアだけだ
(79・9パーセント)。
全体に旧ソ連の衛星国は比率が4、50パーセント代と高いが、他は日本
の35パーセントがそれでも高い方。
ある時、このフランスの姿勢についての説明に接して、そうだったのかと
思った。
要は外交のために石油依存から脱却したかったというのだ。
国際社会の主役でいたいというフランスの意欲は昔から強い。
冷戦下でアメリカがすべてを仕切るようになったのが悔しいという思いも
ある。
それで中東政策で産油国に振り回されないように石油エネルギーの比率を
下げたというのはわからなくもないが、そのために事故のリスクを無視する
のはやはり問題があると思う。
エネルギー政策はむずかしい。
一方では今の生活水準を下げたくないとみなが考えている。
核や化石燃料は資源が枯渇することを心配しなければいけないし、核につ
いては特に事故の危険と、廃棄物の始末、燃料の再処理、廃炉のむずかしさ
などを考慮しなくてはいけない。
ではいわゆる自然エネルギーはというと、ぼくはある意味でその信奉者で
あるのだが、実際にはすべてをそちらに移行するのは難しいだろう。
われわれはどこかで未来像を持っていたくて、その象徴として風力や太陽
光を信奉しているのではないか。
それで、数年前から気になっているのが絶対安全原子力発電の話。
具体的には『「原発」革命』(古川和男著 文春新書)という本が綿密に
書いている。
そんなものがあるかと最初は思ったけれど、理系中退で科学啓蒙書の書評
くらいはできるぼくが読んで納得できるような話なのだ。
要点は核燃料を溶融塩を用いた液体にすること。
今の軽水冷却炉は燃料が固体ウランであるために種々の難問を抱えている。
技術的に複雑すぎるものになる理由の多くはここにある。
ここで燃料をウランからトリウムに替え、これをフッ化トリウムの形でフ
ッ化リチウムならびにフッ化ベリリウムと合わせて高温で溶融塩にする。
すると固体燃料よりも扱いがずっと容易になる。
これでどれほどの利点があるかは実際にこの本を読んでいただきたい。
炉心溶解のような大事故の可能性はなくなる。
資源は世界に広く分布しているので外交のための武器にはなりにくい。
テロリストが脅迫の道具に仕立てることも、また軍事面で利用するのも非
常に困難。
今たくさん貯まってしまって処理が困難なプルトニウムも安全に燃やすこ
とができる。
危険がなく小型化が容易なので小規模な発電所を消費地の近くに造ること
ができるから、送電効率が上がって無駄がない。
軽水冷却炉は常に全出力で運転しなければならないが、こちらは出力を絞
っても問題ない。
トリウムは爆弾にできないので、ウランとプルトニウムの精製や流通を禁
止すれば核拡散を効果的に防ぐことができる。
炉の構造が単純で運転効率がよく、豊富にある資源なので、経済性は非常
に高い。
以上が利点で、欠点はまだ実証性がないこと。
これから具体的に実験炉、実証炉とデータ収集を続ければやがては実用炉
が普及すると古川は言う。
しかし、この本が出てから5年になるが、その後この話題に接したことは
ない。
インターネットで見ても未だ啓蒙の段階で具体的な動きはないようだ。
もしもこの本に書いてない決定的な欠陥があって専門家が将来性を否定し
ているのなら、その理由を知りたいと思うのだが。
<つづく>
(池澤夏樹 執筆:2006‐03‐25)
*「異国の客」は『すばる』(集英社)に連載しています。
http://subaru.shueisha.co.jp/
──────────────────────────────────
【池澤夏樹の最近の著書】
□『憲法なんて知らないよ』池澤夏樹著 集英社文庫
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4087478149/impala-22
□『世界文学を読みほどく』池澤夏樹著 新潮社刊
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4106035448/impala-22
□『パレオマニア』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4797670959/impala-22
□長編小説『静かな大地』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4022578734/impala-22
■『DO YOU BOMB THEM?』
戦争前のイラクの姿を映し出すビデオ作品です。
本橋成一・監督/撮影、池澤夏樹・文/語り、坂田明・音楽
価格:2000円
詳しくは、ポレポレタイムス社 TEL:03-3227-1870
http://www.ne.jp/asahi/polepole/times/polepole/index.html