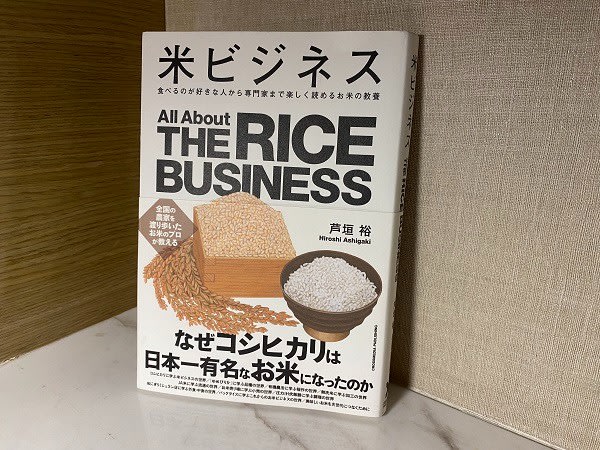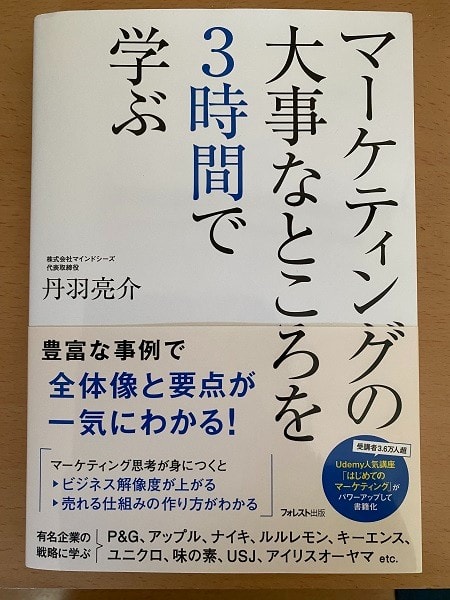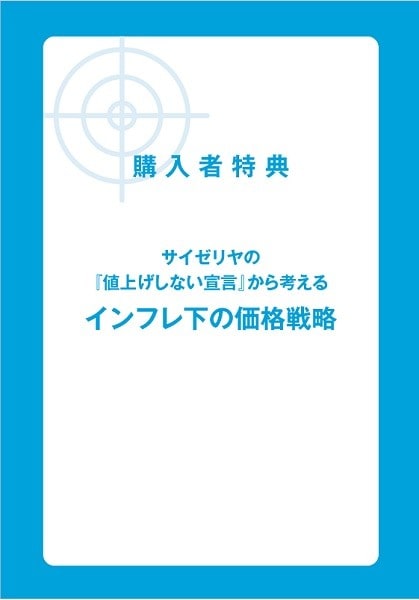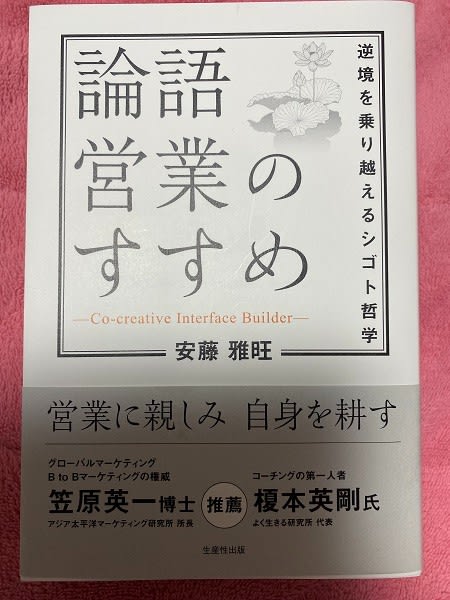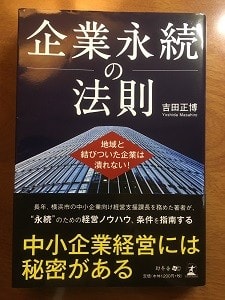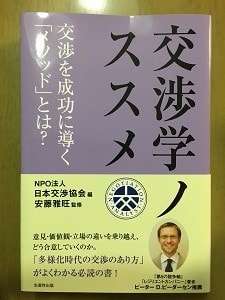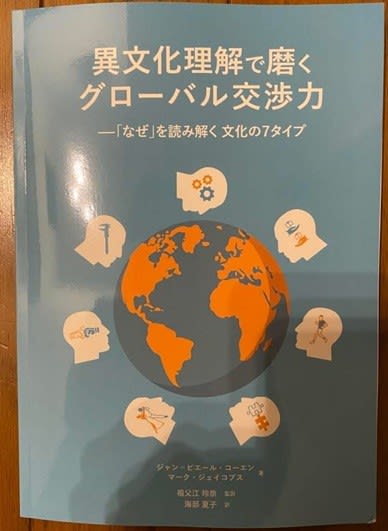
ちょうど、日本人の交渉スタイルについての文献を読んでいるとき、タイムリーに発売されたので早速購入し読んでみました。本書は複数の指標で異なる文化を測定した異文化理解の先駆的研究であるヘールト・ホフステードの6次元モデル(当初は5次元でしたが、後に1次元追加されました)をベースに、異なる文化に属する交渉者のマインドセットを「勝負師」、「プロセス信奉者」、「つながり重視」、「外交官」、「身内びいき」、「スタミナ自慢」、「職人」の7つの型に分類しています。約60ヶ国の交渉者のマインドセットがこのいずれかに分類可能だそうです。
前者の次元による分析には、ジェズワルド・W・サラキューズの研究(1998)や、より最近ではエリン・メイヤーの研究(『異文化理解力―相手と自分の真意がわかる ビジネスパーソン必須の教養』、英治出版、2015)があります。後者の交渉者のマインドセットについては、ずいぶん前に読んだので正確には覚えていませんが、エリカ・フォックスの研究(『ハーバード実践講座 内面から勝つ交渉術』、講談社、2014)などがあったかと思います。
さらに本書は、典型的な交渉プロセスである「営業」を例に、「アポイント」、「信頼関係構築」、「ニーズの見極め」、「提案」、「価格交渉」、「クロージング」のスッテプごとに各型の交渉者にどのようにアプローチするのが良いのかを説明しています。折に触れて挿入される実際の経験に基づく事例が豊富なのも本書の特徴です。このように、理論と経験が補完し合った、読みやすく実用的な本となっています(なので、早くもコメントが書けるのです)。本書のブラーブにもあるように、「小説のように読みやすく…理論を簡潔にまとめ…内容は極めて実践的」です。
もちろん、本書も前提として断っているように、文化を説明する次元の値は相対的なものですし、その国における平均値であって、ある文化のすべての人に特定の型が当てはまるものでないことは理解しておく必要があります。サラキューズ(1998)が明らかにしているように国よりも職業による文化差の方が大きく出ることもあります。しかしながら、それを踏まえた上で、初対面の異文化の交渉者と交渉する際、相手を理解する手がかりとしてこれらが有用であるという点は変わらないでしょう。
例えば、前述の営業プロセスにある「信頼関係構築」。お互いがWin-Winの結果となる合意を目指す「統合型交渉」においても信頼関係の構築は成功の鍵となる要素ですが、ある文化においては率直な物言いが信頼関係を構築する要素として認識されているのに、それが他の文化では無礼であると受け取られる場合があるなどです。マインドセットの型を知っていれば、少なくともそのような誤解が生じる前に探りを入れることができたでしょう。すなわち、統合型交渉の基本ステップを我々の中に無意識に刷り込まれている自国文化の基準に従ってなぞっても、上手くいかないことがあるということです。これは本書を読んでいて感じた、非常に興味深い点でした。
同じように考えると、俗に「ハーバード流」と呼ばれるアメリカ発の交渉理論が、日本人には使えないといった意見を時々耳にします。しかしこれも、文化的相違を考慮することにより、理解の隔たりを埋めることができるのではないでしょうか?すなわち、交渉を「Win-Lose」ではなく「Win-Win」の結果を目指すものと捉え、それを良しとする「統合型交渉」の概念と理論は、本書の言葉を借りれば主にアングロサクソンの「勝負師」型文化で生まれ、発展してきました。本書でも示唆されている通り、何をもって「Win-Win」とするかにも文化差があるかもしれないと理解すれば、ハーバード流は「使えない」のではなく、「ちょっとしたカスタマイズが必要」というレベルにとどまるのではないかと思います。
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした