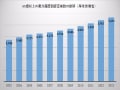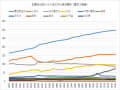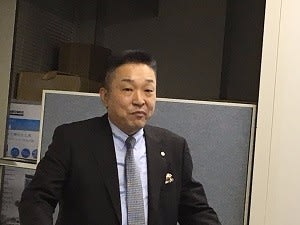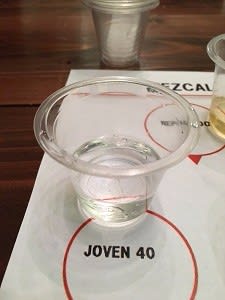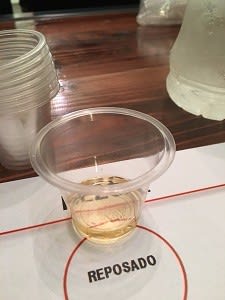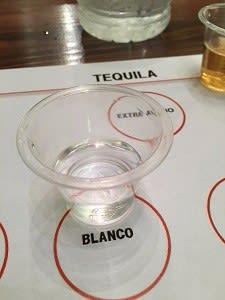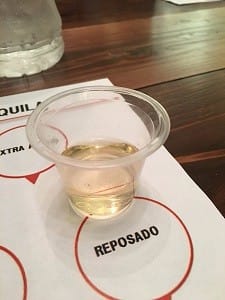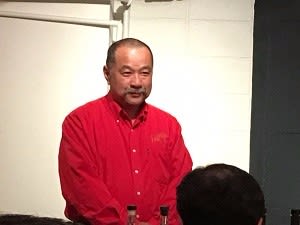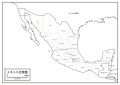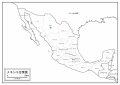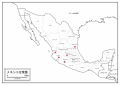3月18日、WBN(早稲田ビジネスネット横浜稲門会)の分科会に参加してきました。

今回は、芳香療法士、調香師の中田真世様より、自然の力で心と体を癒すアロマセラピーについてのお話を伺いました。

アロマセラピー、つまり香りを用いた療法では、エッセンシャルオイルと呼ばれる植物の香り成分を抽出した油を用います。素人の僕は、油に植物の香りをつけたものだと思っていたのですが、違うんですね。水蒸気蒸留法や圧搾法によって抽出された貴重なオイルは、わずか1滴に450グラムものハーブが必要なのだそうです。
香りと人類との歴史は古く、およそ3000年前、古代エジプトに遡るそうです。彼らは政治交渉、医療、美容、権威づけなどの場で香りを活用していました。例えば、身分の高い女性や神官が、ミルラやフランキンセンス(乳香)と牛脂を混ぜ、ワインで煮て固めた香油コーンを頭にのせている絵が古代の墓の壁画に描かれています。牛脂が溶けることで体臭をおさえる、あるいは儀式のために用いられていたと考えられています。また、ミルラには乾燥させる効果があり、彼らはミイラを作るためにそれを用いていました。
ちょっと脱線してしまいますが、香油コーンのお話を伺ったとき、白隠禅師(1686–1769)の「軟蘇の法」を思い出しました。「軟蘇の法」とは、呼吸により気を丹田集めることで心身の調和、健康回復を目的とした瞑想のことですが、その際、頭の上にのせた「蘇」がゆっくりと溶け、それが全身に染みわたるようにイメージせよと述べているのです。「蘇」とは、通常チーズあるいはヨーグルトのような乳製品とされますが、禅師の『夜船閑話』では、「蘇」について次のように表現しています。
「蘇とは、乳のごとく白く柔らかにして、香気馥郁(ふくいく)として、鼻を撲(う)つがごとし」
それが呼吸とともに溶けていくというのです。勝手な想像ですが、ここで蘇と言われているものは古代エジプトの香油コーンに源流があるのかもしれません。
そもそも、嗅覚は視覚や聴覚などと比べて最も古くからある感覚です。視覚や聴覚が、多細胞生物が進化した後に発達したと言われているのに対し、嗅覚は単細胞生物の時代からあったと考えられています。嗅覚とは生存のために化学物質を感知する能力のことであり、人間の場合、鼻の奥にある嗅毛が受容体の役割を果たし、わずか0.2秒で脳の大脳辺縁系に届くのだそうです。このことは、生まれたての赤ちゃんで目が見えず、耳が聞こえない段階でも、嗅覚はあるということからも分かります。この大脳辺縁系は感情、情動、本能に関わる、進化の過程から見て比較的古くからある部分です。つまり、香りは脳にほぼダイレクトに届き、感情や情動、自律神経などに働きかけます。香りが心身の調和に資するメカニズムはここにありそうです。本能的な快/不快のレベルなので、自分が好きな匂いだと感じれば、それが脳内ホルモンの分泌を促し、心身を活性化させたり、落ち着かせたりします。逆に不快だと感じれば、それは生存のために脳が危険だと判断していることでもありますので、かえって心身の負担となってしまうことがあります。アロマセラピーでは、自分が好きと思える香りを見つけることが大切です。
さて、今回5種類のエッセンシャルを体感しました。
1.オレンジ(実)

オレンジの皮から抽出したオイルです。今回の中では、個人的に一番好きな香り。不眠、不安、ストセスなどに良いとされ、ストレス性消化器疾患、便秘や下痢などに効能があるようです。個人的には柑橘系の香りが好きなのだなと思いました。
2.ユーカリ(葉)
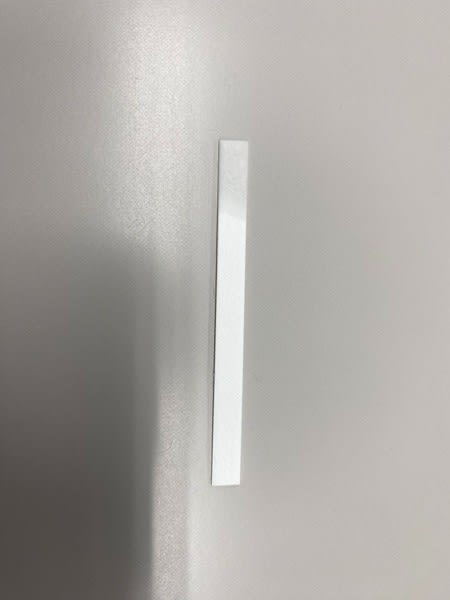
コアラが大好きなユーカリですが、実は毒性の強い植物なのだそうです。そんなユーカリを食べざるを得なかったコアラ。クマ科なのに竹を食べざるを得なかったパンダとともに、生存競争の悲哀を感じます。ユーカリはウイルス性の風邪や花粉症などに良いとされ、呼吸器系に働きかけます。また、集中力を増すのにも良いそうです。
3.ジャスミン(花)
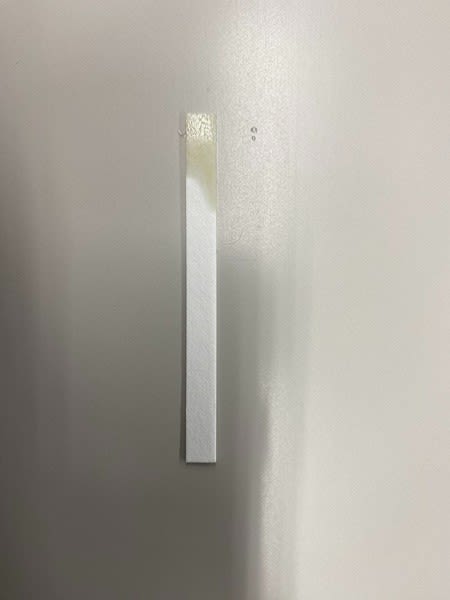
ジャスミン茶のイメージからは想像もできない、僕には形容しがたい香りでした。クレオパトラはこのジャスミンのオイルを好んだそうで、政治交渉の場で相手を威圧するためにも用いていたそうです。ホルモンバランスを保つ、自信をつけるのに良いとされています。香りは嗅いだ時に肺からも吸収され、血液によって全身をめぐります。それを通じても臓器などに働きかけるようです。
因みに、様々な香りを連続で嗅ぐのに、前の香りをリセットするには、水を飲む、コーヒー豆の香り、あるいはアンモニア臭を嗅ぐといった方法があるそうです。
4.フランキンセンス(樹脂)

いわゆる乳香のことです。子供のころ読んだ物語の影響で、乳香や白檀は、中世アラブの交易商人によって高値で取引される香木というイメージがあります。

こちらがフランキンセンスの樹脂。先ほどのユーカリを強くしたような香りに感じました。好き嫌いは別にして、落ち着きます。実際、外に向いた意識を内に向ける効果があり、瞑想の時などに用いられるそうです。
因みに、複数の香りを組み合わせると、それぞれを強め合うことがあります。例えば、リラックスには、ラベンダー とスイートオレンジとサンダルウッド、爽やかさや活気にはペパーミントとレモンとユーカリといったようにです。
5.シダーウッド(木)

比較的強い香り。どこか覚えがあると思っていたのですが、自分が28年使っている香水「アクア・ディ・ジオ」が、時間がたって古くなった時の香りに似ています。檜風呂からもイメージできるように、木系の香りは呼吸を落ち着かせる働きがあります。気を落ち着かせ、また霊性を高めるとも言われています。
個人には木系の香りは好きだと思っていて、今でも車でサンダルウッドのアロマオイルを使っているのですが、今回エッセンシャルオイルを直接嗅いだ限りでは、ちょっと強すぎるように感じました。泌尿器系に良いそうです。
これを機会により意識的に香りを生活に取り入れてみようと思います。子供にも勧めてみます。
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした