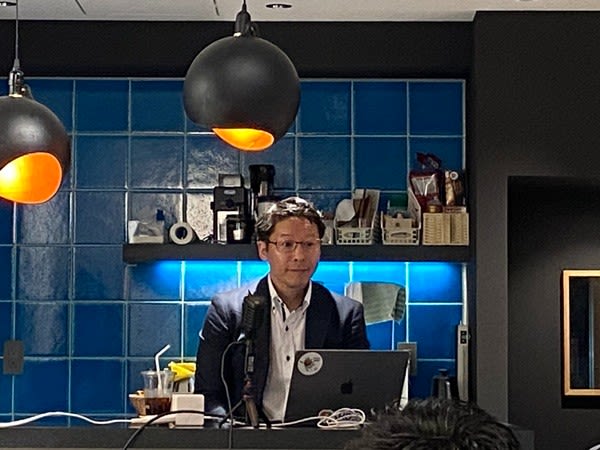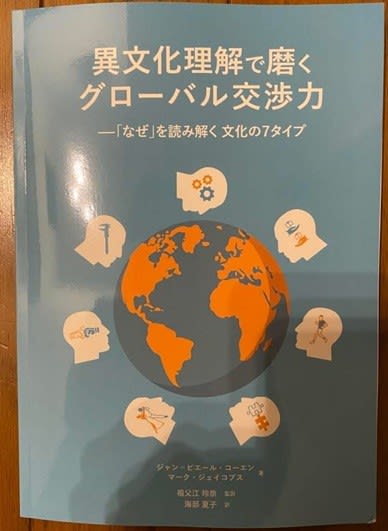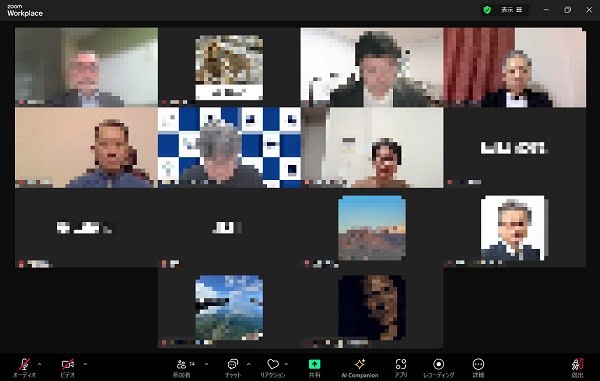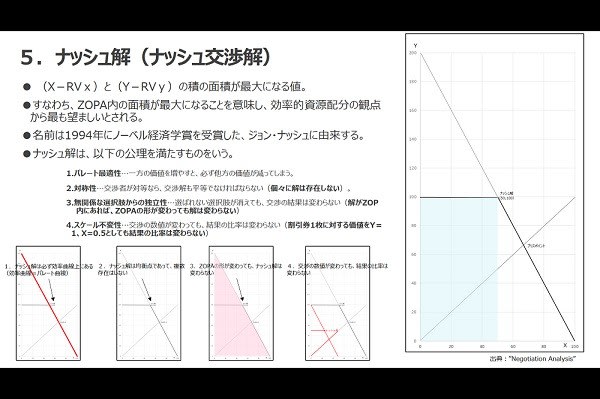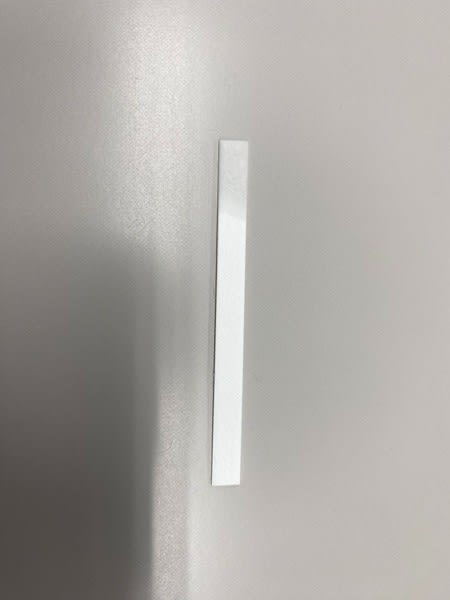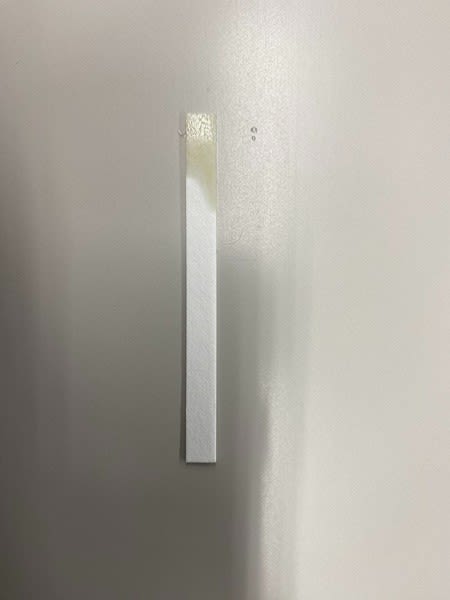久しぶりに筆跡診断について投稿します。第二次トランプ政権がスタートし、彼がさまざまな大統領令に署名するシーンが度々ニュースなどで流れました。まるで剣山のような密集した刺々しい特徴的なサインは印象的で、ご記憶の方も多いのではないかと思います。ご覧になられてない方も、ネットで例えば” Donald Trump signature”というようなキーワードで検索すればたくさん出てきますので、ぜひご覧ください。
上の動画での分析とは関係ないのですが、10年近く前に読み、このブログでもご紹介したアンドレア・マクニコルの” Handwriting Analysis Putting It to Work for You”によれば、普通に書いている文章の筆跡がその人の「本当の、私的な自己像」を反映しているのに対して、サインは「公的な自己イメージ」を表しているのだそうです。つまり、公の場で自分をどう見せたいか、他人にどう思われたいかといった「社会的ペルソナ(仮面)」を象徴しています。それには、実際に他人が自分のことをどう見ていると「自分が考えているか」も含まれます。
したがって、ある人のサインの筆跡を分析する時、本当はその人が書いたサイン以外の文章の筆跡とも比較したいところです。何故ならそれによって、私的な自己像と公的な自己像とのギャップが見えてくるからです。
さて、そのトランプのサインの筆跡をざっと見てみますと、何と言っても特徴的なのは、字間と語間が極端に狭く、まるで棘のように過度に角ばっている点です。これは、神経質、狭量、非開示的、厳格、柔軟性がない、かつ他人のパーソナルスペースやプライバシーを侵害する傾向であることを表しています。そして全体的に垂直ですが、やや右に傾いています。これもオープンマインドで将来指向な傾向はみられるものの、感情抑圧的で現在指向の傾向の方が強く表れています。
筆圧は何とも言えませんが、強そうに見えます。一般に筆圧が強い人は意思が強く、自己主張が強く、積極的、活動的、極端だと好戦的と言われますが、僕などはペンがしばしば折れてしまうほど握りが強く、筆圧も強いので、自己抑圧的という解釈もあるのではないかと個人的に思っています。上の動画で、ミシェル・ドレスボルドが「筆圧が強い人は、非常に緊張感が高く、強迫的な傾向があります」と述べていますが、それですね。字の大きさは大きそうに見えますが、ジョセフ・バイデン前大統領が同じく大統領令に書いたサインと比較しても、必ずしも特別大きいということはなさそうです。因みに、大きな文字は、社会的に卓越したい、大きな名声を得たい、公の場で目立ちたいといった傾向を表しています。そして、筆記体を三本の罫線で分類した場合の、上・中・下の空間を表すゾーンについて見ると、一見Donald TrumpのD、d、T、pが上に突き出ているので、単語の一部だけが上に優勢とも思えますが、サインの場合は姓名の最初が突き出るのは普通にあることです。しかし、ベースラインから見て11文字の内4文字がいずれも上に優勢というのは興味深い点で、現実を犠牲にして空想の世界に生きている人、アイデアはあるが根拠がない人といった性質があるかもしれません。
因みに上の動画で、ドレスボルドは、「(やはり刺々しい文字に対して)リラックスできない性質を持っている。つまり、緊張感が強く、競争心が強く、行動的で、攻撃的で、怒りを抱えている人物だと読み取れる」、「(サインの真ん中部分の文字が衝突している点に関して)これは『私に逆らうな、さもなければ、戦う準備がある』ということを示しています」と分析しており、興味深い点として「実は彼の内面は、自分が大物だとは感じていません。むしろ強い不安感を抱えていて、それを過度に補う形で外向的、自信満々に振る舞っているのです」と述べています。これは先ほども述べたように、サインは公の場で自分をどう見せたいか、他人にどう思われたいか、あるいは他人が自分のことをどう見ていると「自分が考えているか」といった「公の自己像」が現われるということを踏まえれば、十分考えられることです。「公の自己像」だからこそ、恣意的にサインをデザインしているかもしれません。
なお、トランプのサインですが、” Handwriting Analysis Putting It to Work for You”に掲載されている、80年代から90年代初頭頃のものと思われるサインとは似ても似つかぬほど違います。同書の中で当時の彼のサインは、気取ったり自分がいかに大物か他人に分からせようとしたりする必要がない「人生で本当に成功した人」に多く見られる、非常に平均的なサインの代表例として説明されているのです。ところが、そのサインが90年代後半になると現在のような刺々しいサインへと変化が見られます。それでもまだ現在のものほど字間は詰まっていません。2015年の第1次政権発足前時点でも同様です。ところが第1次政権発足時になるとほぼ現在と同じサインになっています。これが彼の内面の変化によるものなのか、意図的にそうしているのかは分かりません。同じ人でも筆跡は変化します。例えば、ナポレオン1世のサインも若い時と晩年とでは全く違います。僕も30年前、20代前半だった頃の筆跡を見ると、あまりの違いに自分でも驚くほどです。
最後に、以前も述べたように、筆跡特徴とパーソナリティの相関関係を調べた研究はネガティブなものの方が多いです。しかし、コンコーディア大学のアフナン・ガルートの論文“Handwriting Analysis and Personality: A Computerized Study on the Validity of Graphology”(2021)によれば、性格を測る心理テスト「ビッグファイブ性格特性マーカーテスト」による結果と自動筆跡分析システムによる結果の相関関係をスピアマン相関分析によって検証した結果、外向性については、弱いながらも正の相関があり、誠実性と開放性については中程度の相関があり、協調性については強い正の相関があり、情緒安定性につてはごく弱い相関にとどまったことが明らかになりました。なお、この自動筆跡分析システムは、英語、フランス語、中国語、アラビア語、スペイン語で書かれた計1,066人分の筆跡サンプルを学習させたAIによる筆跡分析システムで、予測精度93%、AUC(予測の信頼度を示す指標)0.94、Fスコア(バランス評価指標)90%という結果が得られたものだそうです。
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした