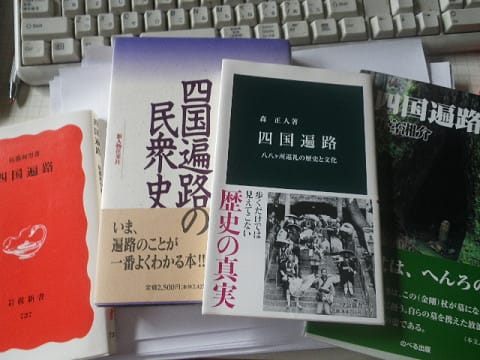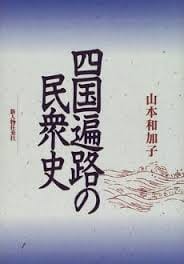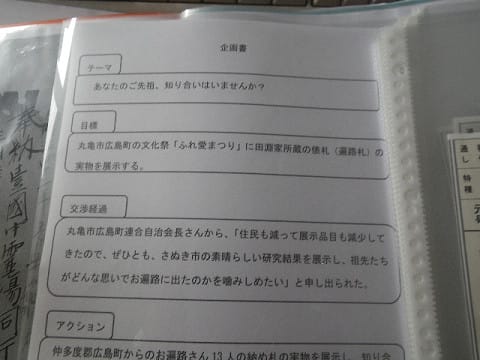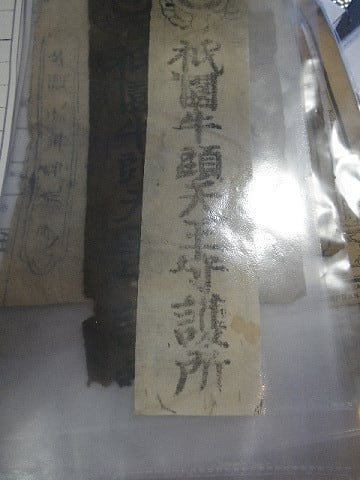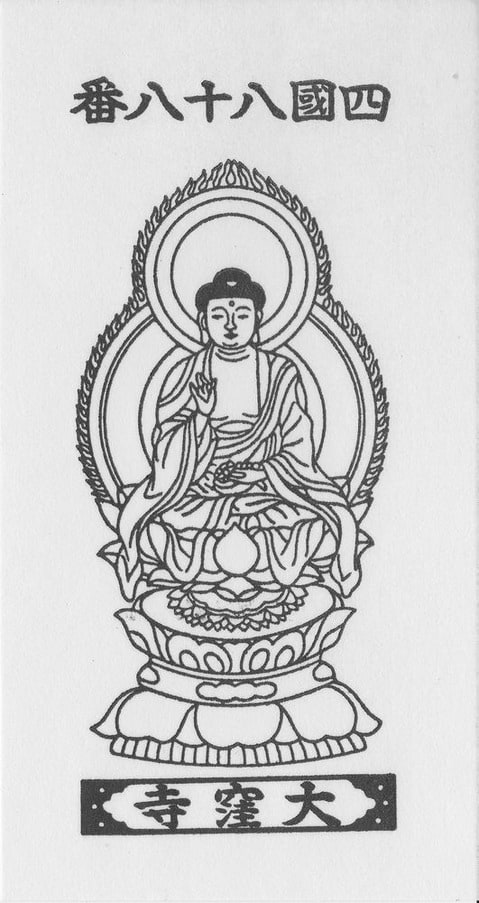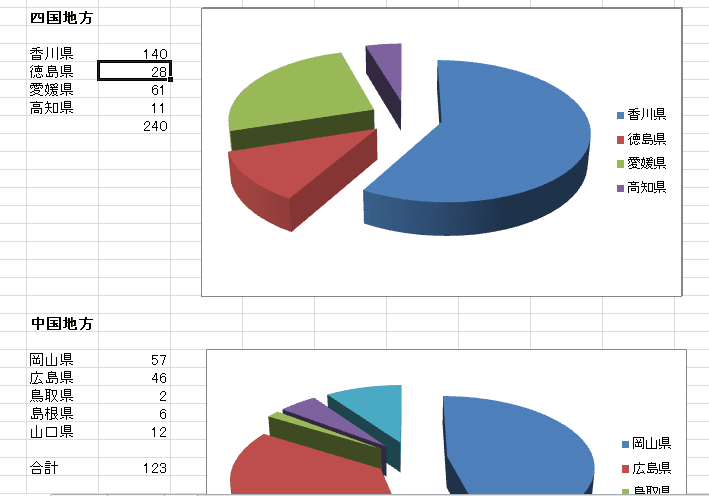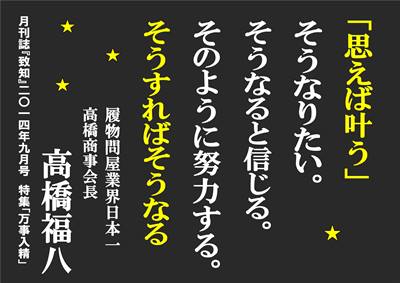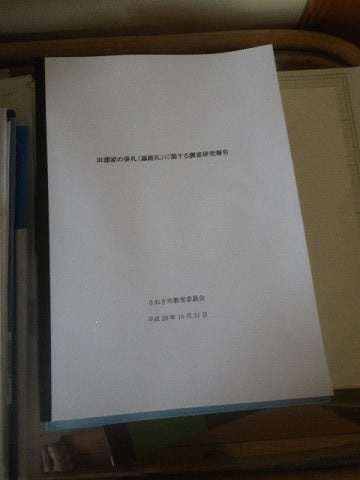さぬき市地方は気圧の谷の影響で曇っていた。気温は16.2度から20.6度どまり。湿度は85%から57%、風は3mから1mの北北東の風が少しばかり。明日の14日は、気圧の谷の影響で曇りますが、高気圧に覆われてくるため、昼前からは次第に晴れる見込みらしい。

まずは、咸臨丸子孫の会、元事務局長・小杉伸一さんの逝去の報に接し、合掌・お念仏。 生前にはいろいろとお世話になりました。心より哀悼の誠を捧げます。

朝方は寒い・・と感じるようになった。そこで、気になっていた家の横の水路脇の草刈りをすることにした。暑いから・・雨だから・・・と、ついつい先延ばしになっていたから草がぼうぼう・・。

ここはわが家のものではないが、わが家のすぐ前だから気持ちが悪い。そこで、いつも私が刈り払ってきた。

秋になると、草や細い木は丈夫に育ってきて堅くなって刈りにくい。だから、力任せに刈り払ってしまう。

水路の右側はお隣さんちの畑だが、おじさんが亡くなって80過ぎのおばあさんが一人。だから草刈りもままならない。水路とわが家のブロック塀との間は、水利組合の「泥揚げ場」である。

その反対側の草丈は長くはないが、ついでに刈り払っておく。

これで草が枯れてくるとさっぱりとする。

その後、遍路札の整理をしてみたが、額が足りない。わが家にあるものは、どれも帯に短し、タスキに長し・・・。

で、100円ショップで額を探してみたが、これまた、帯に短し・タスキに長し・・・ばかり。

仕方がないから、ホームセンターをのぞいてみたが、最近は額の需要がないものか、高級なものしか置いてない。

結局の薬局で、100円ショップの200円コーナーのものを買ってきたが、うまく並ぶじゃろうか。

これはこれでいいとしよう。
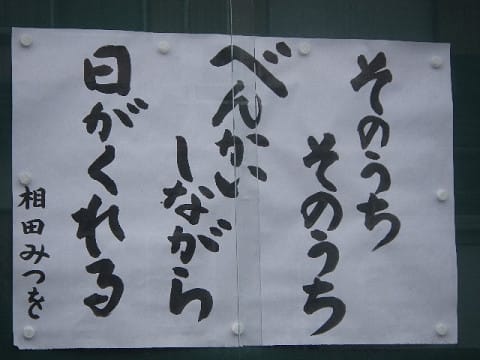
今日の掲示板はこれ。「そのうち そのうち べんかいしながら 日がくれる」という相田みつをさんの言葉から。いつもお世話になっている赤松先生のお寺の掲示板にあったもの。
「 そのうち 」
そのうち お金がたまったら
そのうち 家でも建てたら
そのうち 子供から手が放れたら
そのうち 仕事が落ちついたら
そのうち 時間のゆとりができたら
そのうち……
そのうち……
そのうち…… と、
できない理由を
くりかえしているうちに
結局は何もやらなかった
空しい人生の幕がおりて
頭の上に 淋しい墓標が立つ
そのうちそのうち
日が暮れる
今来たこの道
かえれない

じゃぁ、また、明日、会えたらいいね。













 。
。