終末期医療の意思決定、話し合いで納得の最期を
https://news.goo.ne.jp/article/sankei/life/sankei-lif1810190008.html
自分の人生の最終段階について自身で考え、準備を行う「終活」。その最も大切な事柄のひとつに「終末期医療」がある。死期が近づいたとき、死を受け入れて緩和ケアに移行するのか、それとも延命治療を徹底的に続けるのか。厚生労働省が今年3月に新たなガイドラインを示すなど、終末期医療の意思決定のあり方がさらに進んでいる。(「ソナエ」編集部 古田雄介)
◆「リビングウィル」
終末期医療については、「尊厳死」という言葉とともに、約半世紀にわたって議論が行われてきた。不治の病で死期が近づいていても、現代医療の技術があれば相当な延命が可能だ。半面、健康を回復する見込みがないのに何本ものチューブにつながれ、“生かされ続ける”ことを望まない人は少なくない。
医師は人命を助けることが使命であることから、延命治療を必然と考える場合がある。また家族は少しでも長く生きていてほしいという思いと、苦しめてしまうのではないかという思いから、終末期医療をどうするかを委ねられると、非常に苦しい判断を迫られることになる。
そこで重視されてきたのが「リビングウィル」(生前意思)だ。延命治療を希望する、しないにかかわらず、意識がしっかりしているうちに、自分の終末期医療について事前に明確に指示しておくことが重要と考えられている。
◆一歩進めてACP
厚労省が3月に示した「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(改訂版)は、リビングウィルの考え方からさらに一歩進んで、家族や友人、医療関係者らと繰り返し話し合い、その都度、文章にしておくことが望ましい、とするもの。この繰り返し行われる話し合いは「アドバンス・ケア・プランニング」(ACP)と呼ばれ、欧米ではすでに普及している考え方だ。
リビングウィルは、病気の進行や本人の心身の状態の変化などにともなって、その意思が変化していく可能性がある。ガイドラインが「繰り返し話し合う」ことを強調するのは、この意思の変化に対応するためだ。
また改訂ガイドラインでは、終末期の医療・ケアについて本人や家族らと話し合うメンバーとして、医師や看護師ら医療関係者だけでなく、介護従事者が含まれることを明確化している。これは今後広がるとされる在宅医療、在宅介護を意識したもので、看取(みと)りの場は病院から自宅へという流れが背景にある。
◆1人暮らしを意識
改訂のポイントはもうひとつある。改訂前のガイドラインでは、本人に立ち会って「家族」が話し合いに加わるとされていたが、改訂後は「家族ら」と範囲が広げられているところ。
話し合いに家族が参加することは、本人の意識が混濁して自らの意思を伝えられなくなったときに、本人に代わってその思いを伝えるという意味で非常に重要だ。ガイドラインでも信頼のおける家族らをあらかじめ定めておくことが大切だと述べている。
そこで「家族」を「家族ら」としたのは、1人暮らしの高齢者が増えることを踏まえ、家族だけでなく親しい友人なども本人の意思を代弁することができるということを示したものだ。
仮に家族がいなくても、強い信頼関係でつながった親友であれば、家族と同じような気持ちで支えてもらうことができる。「おひとりさま」であれば、そんな信頼のおける友人に看取ってもらいたいのではないだろうか。
人生の最終段階で、どのような医療・ケアを受けたいかについて考えるのはつらいことだが、きちんと意思表示をしないと、望まない治療に苦しむかもしれない。
納得のいく最期を迎えるためにも、元気なうちから終末期医療をどうするかについて考えるとともに、1人暮らしになったとき、ACPの話し合いに立ち会い、看取ってくれる友人を育てることが大切だろう。










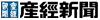

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます