
(標題クリックで投稿欄)
久し振りに28号線で榛名に向かう。今日は「右京のむだ掘り」の標識
附けである。事の発端は去年榛名湖畔で「壱つ岩」の取り扱いを見て
からである。この吾妻と高崎藩の水騒動に関する表示にバランスを欠く
と感じた。高崎藩で旱魃を防ぐために取水方法に腐心した松平右京の事、
多数の犠牲者を出した工事参加の農民の事が高崎側ではすっかり忘れ去ら
れている。この件の顛末についてはH-17-11-23の記事に書いたが、出所は
伊香保・水月亭HPで野口正雄氏の詳細な研究発表。
http://homepage2.nifty.com/harunako/harunamukasi.htm
黒岩登山口下の「鷹ノ巣林道」入り口脇に駐車して、黒岩岩壁に取り付く
クライマーの姿を見上げながら林道を下る。(10.33)

暫くで旧黒岩キャンプ場入り口の古い鉄製ゲートを左折して林道をダラダラ
登り、マークに依って榛名白川源流左岸の作業道に移る。(10.50)
ここから四つ目の堰堤で「ヨハネス・デ・レーケの石積堰堤」の看板を目当て
に対岸の広い尾根に登る。

ここは背の低い熊笹の原で踏み跡はやや薄いが目印テープが豊富で安心。
やがて左からの作業道を合わせると、古い木製の表示の処で右の土手の
切れ目から右折して尾根の右側を進む。(11.28)

次ぎの分岐は左折して再び川筋に近づくと三本線の派手な目印で大きな
空沢を渡って(11.36)正面に見え始めたスルス岩に向っていく。

暫くで前方に「保安林」と書かれた錆びだらけの鉄板看板が見えるところに
去年つけた「むだ掘り跡」への左折指示テープ。

(11.44)持参の案内板を付け足し、

雑木の中をテープを補足しながら左へ百㍍余りで「むだ掘り跡」に到着。
(11.58)

早速持参のゴム長靴(中は水浸しのため)とビームライトを取り出して
洞窟内に入る。

上からは絶え間無く水が染み出して入り口の泥の堆積で水深10㌢の
溜まり水。入り口は横160㌢、縦120㌢の荒掘りであるが7㍍ほど
から先は縦横1㍍強のきっちりした穴で、狭くなりで四つん這いになら
ないと進めず奥の探検は断念。但しライトで見る限りは全長二十㍍ほど
にしか見えない。

入り口に標識を付けたり、

写真を撮ったりした後、もう一度経路にテープを付け足してからゆっくり
昼食と休息。
帰りは分岐から違う道をとつて上流の堰堤群を見物しなが駐車場所に
帰着は(14.10)
ここは旧箕郷町で今は高崎であるから、高崎市教育委員会あたりが、
十五年も高崎城主であった松平輝貞の苦労を世に知らしめてもらいたい
ものである。

位置・N-36-28-15-2 E-138-53-25-4 1.068m
愛知県に在るデ・レーケの銅像

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

久し振りに28号線で榛名に向かう。今日は「右京のむだ掘り」の標識
附けである。事の発端は去年榛名湖畔で「壱つ岩」の取り扱いを見て
からである。この吾妻と高崎藩の水騒動に関する表示にバランスを欠く
と感じた。高崎藩で旱魃を防ぐために取水方法に腐心した松平右京の事、
多数の犠牲者を出した工事参加の農民の事が高崎側ではすっかり忘れ去ら
れている。この件の顛末についてはH-17-11-23の記事に書いたが、出所は
伊香保・水月亭HPで野口正雄氏の詳細な研究発表。
http://homepage2.nifty.com/harunako/harunamukasi.htm
黒岩登山口下の「鷹ノ巣林道」入り口脇に駐車して、黒岩岩壁に取り付く
クライマーの姿を見上げながら林道を下る。(10.33)

暫くで旧黒岩キャンプ場入り口の古い鉄製ゲートを左折して林道をダラダラ
登り、マークに依って榛名白川源流左岸の作業道に移る。(10.50)
ここから四つ目の堰堤で「ヨハネス・デ・レーケの石積堰堤」の看板を目当て
に対岸の広い尾根に登る。

ここは背の低い熊笹の原で踏み跡はやや薄いが目印テープが豊富で安心。
やがて左からの作業道を合わせると、古い木製の表示の処で右の土手の
切れ目から右折して尾根の右側を進む。(11.28)

次ぎの分岐は左折して再び川筋に近づくと三本線の派手な目印で大きな
空沢を渡って(11.36)正面に見え始めたスルス岩に向っていく。

暫くで前方に「保安林」と書かれた錆びだらけの鉄板看板が見えるところに
去年つけた「むだ掘り跡」への左折指示テープ。

(11.44)持参の案内板を付け足し、

雑木の中をテープを補足しながら左へ百㍍余りで「むだ掘り跡」に到着。
(11.58)

早速持参のゴム長靴(中は水浸しのため)とビームライトを取り出して
洞窟内に入る。

上からは絶え間無く水が染み出して入り口の泥の堆積で水深10㌢の
溜まり水。入り口は横160㌢、縦120㌢の荒掘りであるが7㍍ほど
から先は縦横1㍍強のきっちりした穴で、狭くなりで四つん這いになら
ないと進めず奥の探検は断念。但しライトで見る限りは全長二十㍍ほど
にしか見えない。

入り口に標識を付けたり、

写真を撮ったりした後、もう一度経路にテープを付け足してからゆっくり
昼食と休息。
帰りは分岐から違う道をとつて上流の堰堤群を見物しなが駐車場所に
帰着は(14.10)
ここは旧箕郷町で今は高崎であるから、高崎市教育委員会あたりが、
十五年も高崎城主であった松平輝貞の苦労を世に知らしめてもらいたい
ものである。

位置・N-36-28-15-2 E-138-53-25-4 1.068m
愛知県に在るデ・レーケの銅像

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。


















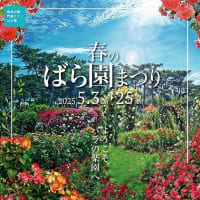








爺イは冬装備は全く持っていないし、雪道を歩く体力もありませんので、今冬はもっぱら甘楽・吉井の低山ハイキングで過ごしました。榛名を休んでいるうちに構想ばかり膨れ上がって黒岩の上に立ちたいとか、音羽から三つ峰に縦走してみたいとか一寸分不相応な事も考えています。もっとも、竜ヶ岳にも未だなのでそっちも行きたいし、何とか片付けます。
先人の業績に頭が下がる思いでした。
ついでにキツネとタヌ公?野ウサギ?もいました。
クマもいるのかな。
コースとして名が売れて欲しいものです。松平輝貞は余りにも
綱吉に重用され、柳沢吉保とも姻戚関係を結んだので次代将軍に吹っ飛ばされたのでしょう。しかし、七年の出羽左遷の後
吉宗に呼び返されていますから有能であった事には間違いなし。まあ、戦国の城主と違って領主ですから何となく現代の
高崎での知名度はイマイチ。市の教育委員会関係者にも
もっと顕彰したらと言いましたが、予算云々で良い返事は
今のところありません。デ・ケーレの事も忘れられている
のかな?