
数回の偵察の結果、徳明園の紅葉は見頃になった筈なので見学者が
押し寄せることを予想して開園直後に徳明園に向かった。
ここの紅葉は高低差と植樹の種類のため池の傍から紅葉が始まり
次第に台地の上に移って行くから期間が長いとはいえ全面が
燃上るようにはならないが池中心で見るなら今が最適の判断。
それに紅葉だけではなく創設者のユーモアと物語性が随所に
隠されているのでそれらを感じ取るのも楽しみの一つ。
入口から直ぐに池の傍に降りずに遊歩道の最上段へ直進、ここの具合で
大体、下の紅葉具合は判断できる。ほぼ紅葉全開で安心。
4668

少し下りながら様子を観察。
4687 4692 4794 4802 4803





途中にしめ縄の様なものが巻かれた「徳明園奉納赤石」。約一億年前に
変成された紅簾石とのこと。
4681

池の周りを反時計回りに歩くと「弁財天」。
0

小さな流れを渡るがこれが「三途の川」の見立て、石門を潜ると
エンマ大王と鬼が待ち構えるが一杯やっているのか?笑い顔。
4711

その先に高崎の誇る村上鬼城(1865-1938)の句碑。鬼城の旧宅が鞘町にあったころ
ここの創建者・山田徳蔵氏(1885-1964)と親交があったご縁とか。
もう一基の句碑も並列してあるがこちらは一般市民の寄贈だから割愛。
「傘(からかさ)に いつか月夜や 時鳥」で1916年に『ホトトギス』に発表。
4721

この池が「浦島の池」と云われる由来の浦島太郎の石造物が池の中。
4755

関連らしい蛙が三匹とおまけの様なツル。だが、ツルは
出来栄えからこの園の石造を一手に引き受けた高橋楽山のものではないと
思われるので画像は割愛。
4757

突然、東から霧状のものが風に乗って流れてきた。どうやら「苔の庭」から
らしいのでそちらに回る。観察すると苔庭の周囲にはびっしりと噴霧器が
取りつけられて盛んに霧を吹きだしている。辺りは霧が立ち込めて
幽玄の世界を見せているが実はこれは只の苔への加湿に過ぎない。
乾燥地帯の群馬の平地では苔は育たないとされるので年間を通じで
絶えず加湿しているのだ。
4731 4744 4748 4849 4750 4752






その奥に今年、整備が完了した「石庭」。
本来石庭とは京都の龍安寺庭園のみの別称なのだが、近年では石組を
主体とした枯山水庭園を広くさすようになっているからこう呼称しても
良いらしい。
4741

さて、記念館の前を通ると「亀の石」。じっと見ないと亀の姿は
見えてこない。
4738

この亀の石から背面に上る石段散策路一帯が「枯山水」と称する場所
だが、本日爺イが最も感覚の違いで苦戦したところ。
解説を見ると枯山水とは水のない庭のことらしく、池や遣水などの
水を用いずに石や砂などにより山水の風景を表現する庭園様式だそうだ。
そうなるとさっきの亀の石の周りなどは既に水面に見立てているんだろう。
それで斜面全体と云われても撮れた画像はこんなものだからピンとこない。
4787

その上の最上段がエスプリ利きすぎ位の面白さ。まず真ん中に山田徳蔵像。
その脇の石碑に「「人間萬事 屁の如し ぶーっと云う字は 佛なりけり」
とふざけて居る。
4783

そしてその左右に翁の未来の姿と称した二体の石像。右のこれは
雰囲気からしてどうしても良寛さんなんだがな。
4782

左は徳蔵氏未来の姿というが、もうこれは一休さんの「目出度い髑髏」
の逸話を現したものだ。
その逸話とは正月元日の朝、京都の家々の門口に髑髏をさし入れては、
「目が出てしまって穴だけ残っているのを『目出たい』とほざき
更には「にくげなき このしゃれこうべあなかしこ 目出たく
かしくこれよりはなし」と言ったという話。
4784

これで一巡。
池の周辺紅葉。
其の他の紅葉
ご来訪の序に下のバナーをポチッと。
 登山・キャンプランキング
登山・キャンプランキング
押し寄せることを予想して開園直後に徳明園に向かった。
ここの紅葉は高低差と植樹の種類のため池の傍から紅葉が始まり
次第に台地の上に移って行くから期間が長いとはいえ全面が
燃上るようにはならないが池中心で見るなら今が最適の判断。
それに紅葉だけではなく創設者のユーモアと物語性が随所に
隠されているのでそれらを感じ取るのも楽しみの一つ。
入口から直ぐに池の傍に降りずに遊歩道の最上段へ直進、ここの具合で
大体、下の紅葉具合は判断できる。ほぼ紅葉全開で安心。
4668

少し下りながら様子を観察。
4687 4692 4794 4802 4803





途中にしめ縄の様なものが巻かれた「徳明園奉納赤石」。約一億年前に
変成された紅簾石とのこと。
4681

池の周りを反時計回りに歩くと「弁財天」。
0

小さな流れを渡るがこれが「三途の川」の見立て、石門を潜ると
エンマ大王と鬼が待ち構えるが一杯やっているのか?笑い顔。
4711

その先に高崎の誇る村上鬼城(1865-1938)の句碑。鬼城の旧宅が鞘町にあったころ
ここの創建者・山田徳蔵氏(1885-1964)と親交があったご縁とか。
もう一基の句碑も並列してあるがこちらは一般市民の寄贈だから割愛。
「傘(からかさ)に いつか月夜や 時鳥」で1916年に『ホトトギス』に発表。
4721

この池が「浦島の池」と云われる由来の浦島太郎の石造物が池の中。
4755

関連らしい蛙が三匹とおまけの様なツル。だが、ツルは
出来栄えからこの園の石造を一手に引き受けた高橋楽山のものではないと
思われるので画像は割愛。
4757

突然、東から霧状のものが風に乗って流れてきた。どうやら「苔の庭」から
らしいのでそちらに回る。観察すると苔庭の周囲にはびっしりと噴霧器が
取りつけられて盛んに霧を吹きだしている。辺りは霧が立ち込めて
幽玄の世界を見せているが実はこれは只の苔への加湿に過ぎない。
乾燥地帯の群馬の平地では苔は育たないとされるので年間を通じで
絶えず加湿しているのだ。
4731 4744 4748 4849 4750 4752






その奥に今年、整備が完了した「石庭」。
本来石庭とは京都の龍安寺庭園のみの別称なのだが、近年では石組を
主体とした枯山水庭園を広くさすようになっているからこう呼称しても
良いらしい。
4741

さて、記念館の前を通ると「亀の石」。じっと見ないと亀の姿は
見えてこない。
4738

この亀の石から背面に上る石段散策路一帯が「枯山水」と称する場所
だが、本日爺イが最も感覚の違いで苦戦したところ。
解説を見ると枯山水とは水のない庭のことらしく、池や遣水などの
水を用いずに石や砂などにより山水の風景を表現する庭園様式だそうだ。
そうなるとさっきの亀の石の周りなどは既に水面に見立てているんだろう。
それで斜面全体と云われても撮れた画像はこんなものだからピンとこない。
4787

その上の最上段がエスプリ利きすぎ位の面白さ。まず真ん中に山田徳蔵像。
その脇の石碑に「「人間萬事 屁の如し ぶーっと云う字は 佛なりけり」
とふざけて居る。
4783

そしてその左右に翁の未来の姿と称した二体の石像。右のこれは
雰囲気からしてどうしても良寛さんなんだがな。
4782

左は徳蔵氏未来の姿というが、もうこれは一休さんの「目出度い髑髏」
の逸話を現したものだ。
その逸話とは正月元日の朝、京都の家々の門口に髑髏をさし入れては、
「目が出てしまって穴だけ残っているのを『目出たい』とほざき
更には「にくげなき このしゃれこうべあなかしこ 目出たく
かしくこれよりはなし」と言ったという話。
4784

これで一巡。
池の周辺紅葉。
其の他の紅葉
ご来訪の序に下のバナーをポチッと。
















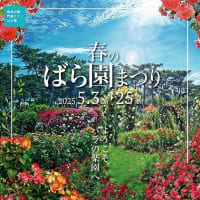



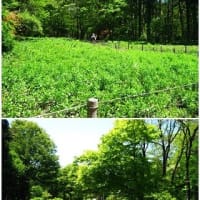





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます