彦根藩の当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨か
ら救ったと伝えられる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言え
る赤備え(戦国時代の井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を
朱りにした部隊編成のこと兜(かぶと)を合体させて生まれ
たキャラクタ-
【季語と短歌:7月3日 】
お黙りに返す言葉は金魚草 ![]()
高山 宇(綺鬼)
🪄My wife tells me to shut up,
so I reply that it's like a goldfish plant.
🟡 日本発Z革命 ⓰
気候変動禍ゼロ・再エネ・人工燃料・超資源回収
1️⃣フッ素ナノチューブで海水の淡水化できるか?
✳️純水製造・脱塩濃縮システム事例考案❶
これまで、「特許第7678511号 蟻酸生成装置」を参考に脱水
(純水製造)と同時に脱塩・脱懸濁物質処理及び濃縮を行い、
連続循環する。循環投入時はナノバブル投入することで、海
水濾過膜表面を清浄に維持できるようにする。ろ過処理液は
傾斜支持された分離膜裏面より回収貯槽に戻し、①純水・超
純水製造処理水向けに送水し、②水素電解水素製造、③アン
モンニア製造、④ギ酸・過酸化水素製造、⓹炭化水素化合物
製造等の製造、そして、⑥その他群コンビーナート用水向け
に使用する。率は特に海水溶出物質の濃縮率を1,000以
上に処理し、次工程の選択濃縮に送り、高品位回収処理する。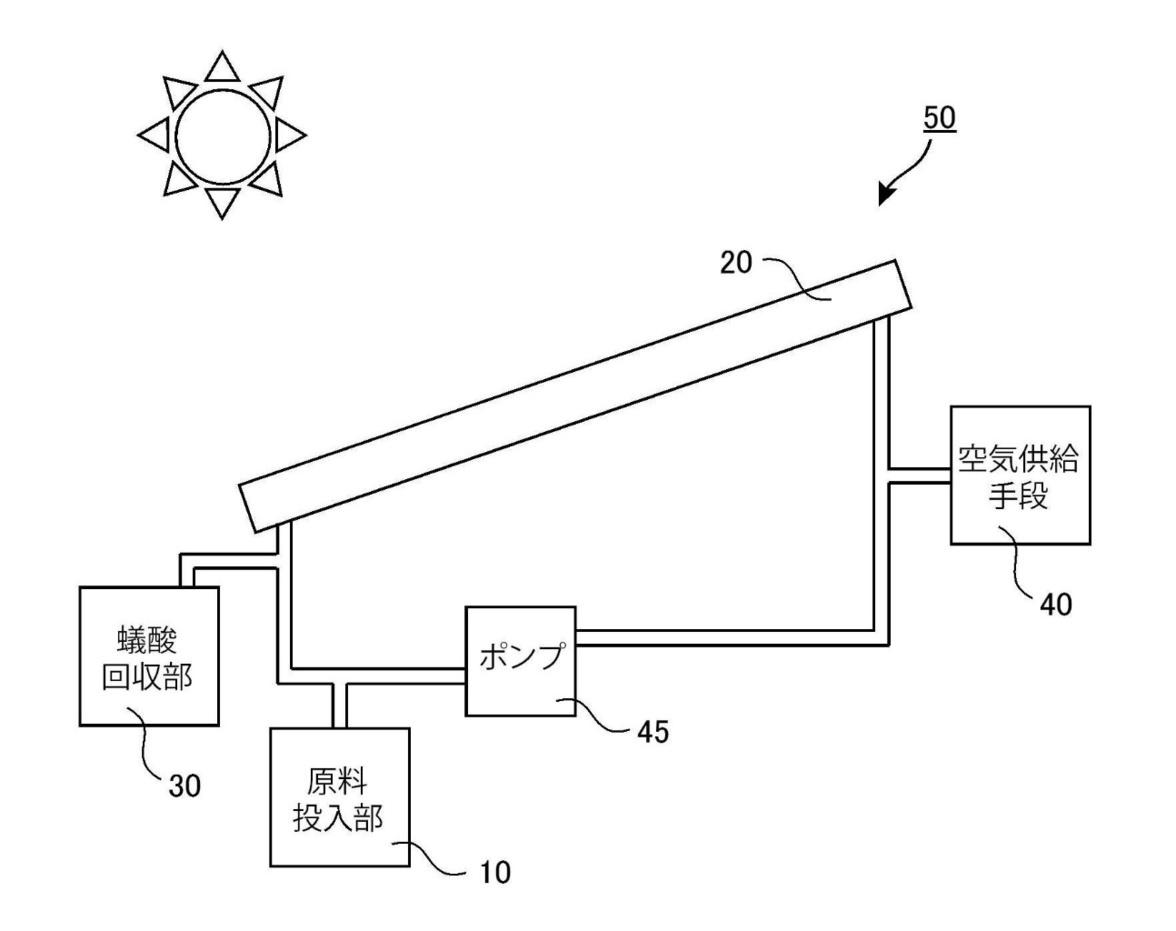
特許第7678511号 蟻酸生成装置概節図(参考)
2️⃣ 水浸透膜の機構設計の決定
当初、既存の東レ・旭化成等の膜メーカらの水平多層透水膜
方式を考えていたが、ナノフィルター(NF)系統で簡素で
低圧の膜設計をと考え、厚み1,000mm、内径Ø.3~数
1.2nmのフィルムをレーザなどで穿孔し、フッ素蒸着し支
えのセラミック製井桁に貼り付け常圧マイナス数ミリバール
で減圧分離方式を構想しているが、その対策として、
------------------------------------------------------------------
①セラミックタイル(形は、正方形・六角形)穿孔部円筒貫
通しは予め開け、焼き固めておく。
⓶そのに、フッ素コート処理しておいた、透水NFチューブを
挿入し、タイルとNFチューブのギャップに樹脂で固定する。
③タイルへのNFチューブ数を設計配置するかは材料を含めた
最適化実験を行い決定。
④タイルを配置固定し実証実験して処理能力を求め最大処理
量と耐久性を確認する。
🪄この程度で書き留めておくことにする。
-------------------------------------------------------------------
ここで、「エネルギーと環境 281」で記載したように逆浸透法
は淡水化技術のスタンダード。水の透過能と塩の除去能には
超えられない壁がある。水を速く通そうとして膜の網目を粗
くすると塩が通り抜けてしまい、塩が通らないように網目を
細かくすると水が通りにくくなってしまうためだ。そのジレ
ンマがトレードオフラインとして立ちはだかり、水処理膜の
性能は20年以上も向上していない。そこで、次世代の水処理
膜モデルの「アクアポリン」(アクアポリンは2003年にノーベ
ル化学賞を受賞したタンパク質の一種)で、細胞膜を介して
水分子だけを超高速で通す性質を持つ。これを敷き詰めて処
理膜を作成すれば超高効率脱塩が可能と考えたが、タンパク
質の性質上正しく働かせるには生体内に近い環境が必要条件
が限定される。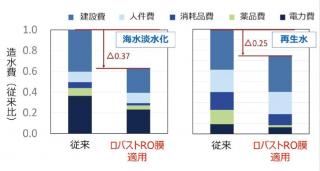
1991年に飯島澄男氏が発見したカーボンナノチューブ。水処
理膜に応用した場合はトレードオフラインを超えるとの試算
がありそれを信州大学の研究グルーが実証に成功しているの
で考察する。 信州大学アクア・イノベーション拠点(COIプ
ログラム)は、福岡県北九州市にある「ウォータープラザ北
九州」に海水淡水化パイロット試験設備を設置。2019年10月
から本格的に、拠点で開発したナノカーボン膜の海水淡水化
実証試験を開始。ステム全体で一日11トンほどの真水を海水
から作り、およそ1年をかけて、脱塩性や透水性、耐汚濁性
などの膜の性能や運用コストを検証。
🔸ナノカーボン膜適用のコスト削減試算
ロバスト(頑強)性などのナノカーボン膜の特性を生かし、
真水の高回収化、前処理簡易化、省エネルギー化の3つによ
る低コスト造水システムを構築。試算では、ナノカーボン膜
を適用することで、従来の造水システムより3割程度のコスト
削減が期待できた。
🔸汚れが付きにくい膜とスペーサの開発に成功! 画像は信
大開発のロバストカーボン複合膜、実験室で調製したPA膜、
市販膜それぞれで耐汚濁性試験を行い、汚染物質(緑色部分
)の付着を評価したもの。
信大開発膜への汚れの付着は他の2つに比べて著しく少なく、
優れた耐汚濁性を示しています。さらに、海水の原水中に含
有する天然有機物に対し、優れた耐汚濁性を有する革新的な
スペーサ(膜と膜の間に挟み海水を通しやすくする部材)と
して、一般的な材料のポリプロピレン(PP)とCNTを複合し
たCNT/PP複合原水スペーサの開発に成功。
膜とスペーサとの相乗効果で、処理装置の中でスムーズな
水の流れを維持することができる。
信州大学の研究チームが、太陽光を用いて水から直接的に水
素を得る水分解プロセスとして、新しい光触媒によりシンプ
ルな構造で大規模化が容易な低コストの手法を開発した。
ペロブスカイト系光触媒Y2Ti2O5S2表面における水の分解に
おいて、水素と酸素を2段階で発生させたものであり、面積
100m2のシート形状の実証装置を数カ月間作動させることに
よって、太陽光から水素への変換効率STH(Solar-To-Hydrogen
energy conversion efficiency)が向上することを確認した。
✳️ 酸ハロゲン化物光触媒の酸素生成効率を劇的に向上
京都大学の研究グループは、岡山大学 山方啓 教授KEK 物質
構造科学研究所 野澤 俊介 准教授と共同で、第一原理計算注
1を基に理想的な光触媒-助触媒界面を設計することで、酸
ハロゲン化物光触媒注2の酸素生成効率を大幅に向上。
半導体光触媒を用いた水分解は、太陽光を活用したクリーン
な水素製造法として注目されており、その高効率化に向けた多
様なアプローチが検討されている。なかでも、表面反応を担う
助触媒(金属種微粒子)の設計は極めて重要ですが、光触媒-
助触媒界面の構造や機能の理解は不十分であり、従来は経験
に基づいた試行錯誤による最適化が主流。本研究では、層状
構造を有する酸ハロゲン化物をモデル光触媒とし、第一原理
計算から予想された電荷分離状態に基づいて、正孔の集積し
やすい層を選択的に露出させ、そこに高活性な助触媒(酸化
イリジウム)を担持する界面設計を行いました。その結果、正
孔の移動が促進され、未処理試料に比べて酸素生成速度が飛躍
的に向上し、可視光照射下で16%という高い反応量子収率注
3を達成した。
本研究で得られた知見は、酸ハロゲン化物に限らず、広範な光
触媒における界面構造の合理設計の可能性を示すものであり、
今後の人工光合成技術や太陽光水素製の高効率化に大きな貢
献が期待される。
本研究成果は、2025年6月19日に、国際学術誌「Journal of
the American ChemicalSociety」にオンライン掲載された。
<掲載誌>
タイトル:Interface Engineering between Photocatalyst and
Cocatalyst: A Strategy for Enhancing Interfacial Charge Transfe
r and Water Oxidation
of Layered Oxyhalides (光触媒-助触媒間の界面エンジニアリ
ング:層状酸ハロゲン化物光触媒の界面電荷移動・酸素生成能
の向上)
✳️年間150トンのCOを生成可能なCO2電解装置「C2One™」
の実証運転
東芝エネルギーシステム年(東芝ESS)と東芝は2025年
6月24日、工場などから排出される二酸化炭素(CO2)を
電気分解して一酸化炭素(CO)に変換できるCO2電解装
置「C2One」の試作機を開発したと発表した。
2025年06月30日 11時00分 公開
P2Cプロセス(炭素循環社会モデルのイメージ)

そこで東芝は、電流密度を大幅に向上させるために、反
応時にCO2を水溶液に溶かし込むことなく気体の状態の
まま直接利用できる触媒電極の開発を進めてきた。
今回、固体(触媒)、気体 (CO2)、液体(水)の三相を同
時に反応させる三相界面反応が可能な触媒電極を独自開
発し、開発した触媒電極に、気体のままのCO2と水を同
時に反応させることで、CO2の直接利用に成功し、変換
反応の停滞や電流密度の低下を解消することができた。
さらに、この触媒層の構造として、ナノサイズの細孔に加
え、CO2ガスの流路となるマクロ孔を導入した独自構造を
採用することで、ガスの拡散抵抗が小さくなり、より多く
のCO2ガスを触媒に供給することが可能です。これらの結
果、通常(常温常圧)の環境下において電流密度700mA
/cm2という高速の変換速度でファラデー効率)92%と、
これまでの当社技術と比べ約450倍にあたる世界最高レベ
ルの変換速度で一酸化炭素の生成に成功しました。
本成果により、変換システムの設置面積の省スペース化が
可能となり、合わせて低コスト化を実現します。将来的
には火力発電所や産業施設などのCO2を多く排出する施
設に近接してシステムを設置し、系統接続された太陽光
や風力などの再生可能エネルギー発電施設からの電力を
活用してCO2の削減を行うことが可能となする。
✳️マイクロLEDを迎え撃つ有機EL、輝度向上。
AR(拡張現実)グラスやVR(仮想現実)ゴーグル向けの
超小型ディスプレーは、大きく3種類の技術の競合になっ
ている。(1)シリコン(Si)基板上に形成した液晶ディス
プレーであるLCoS(Liquid Crystal on Si)(2)画素1つ
ひとつをLED素子にして発光を制御するマイクロLEDディ
スプレーまたはLEDoS(LED on Si)(3)有機ELディスプ
レーまたはOLEDoS(Organic LED on Si)――の3技術。
赤色発光、青色発光、緑色発光、そしてより深い青色発光
のスタックを重ねている(出所:LG Displayの出展パネル
を日経クロステックが撮影)
🔸6万cd/m2超のOLEDoSをデモ
ARやVR向けOLEDoSでこのタンデム化技術を実装してみ
せたのは、冒頭で触れたFraunhofer IPMSである。SIDの
展示会では、発光ユニットを3層重ねて作製したフルカラ
ー0.62型OLEDoSで、輝度を最大6万cd/m2以上にまで高
めたデモを披露した。これまで、OLEDoSの限界とされた
1万cd/m2を大きく上回る輝度である。「基本的なアイデア
は城戸先生と同じ」(Fraunhofer IPMS)だと言う。特定
の参照基板上に形成したモノクロ版OLEDoSでは20万cd/m2
も実現しているという。
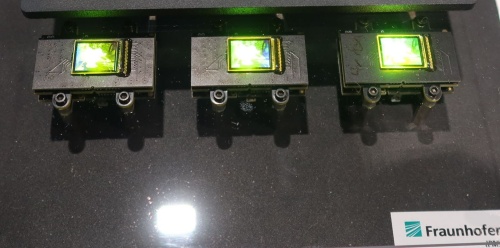
5万cd/m2以上、6万cd/m2以上(写真:日経クロステック)
もっとも、Fraunhofer IPMSの今回のポイントは、OLEDoS
の各素子の発光を制御するバックプレーン回路側の工夫に
あるとする。タンデム化した有機EL素子では、各発光層
に流れる電流密度は変わらない一方で、素子全体に印加
する電圧は発光層が1層の場合の数倍になってしまう。
Fraunhofer IPMSはこの高電圧を扱えるように、OLEDoS
のバックプレーン回路を設計し直した。 『 End Of The World』
https://youtu.be/PeyyIzk0yg0?t=41
この世の果てまで」(The End of the World) は、米国の女性
歌手、スキータ・デイヴィスのヒット曲。1962年12月に
発売され、世界流行した。作曲はアーサー・ケント、作
詞はシルビア・ディー。
春だというのに自然は沈黙している。
レイチェル・カーソン 『沈黙の春』
![]()















