総評:★★☆☆☆ 長かった。。
面白い度:★★☆☆☆ あまり印象に残らなかった。
読みやすい度:★☆☆☆☆ 長いし読みにくい。。。
ためになる度:★★☆☆☆ 普通。
また読みたい度:★☆☆☆☆ 2回目はいいかな。
面白い度:★★☆☆☆ あまり印象に残らなかった。
読みやすい度:★☆☆☆☆ 長いし読みにくい。。。
ためになる度:★★☆☆☆ 普通。
また読みたい度:★☆☆☆☆ 2回目はいいかな。
久しぶりの投稿になります。
前回の「ワーク・シフト」から続いて同じ作者の同じようなタイトルの本。
何やら有名だったので読んでみた。
感想としては、「長かった。。」という一言に尽きる。
前回は「働くこと」がメインのテーマになっていたが、今回は「生きること」とりわけ100年生きる時代に向けてどういった生き方や考え方がいいのか?という内容になる。
でも本当に。。洋書の翻訳の本は本当に読みづらくて困る。なんかだらだら書いてあるし、、本当に長い。
読んでて時間がかかって後悔したが、頑張って読み終わった。。でもあまり得たものはなかったかなと思う。現代の言葉で言うと「コスパが悪い」だった。
この本で言おうとしていることを自分なりに要約してみると、
さまざまな無形の資産を活用し、100年生きる時代に向けて人生を豊かにしていきましょうという話。
無形の資産は以下の3つのカテゴリーに分類される
①生産性資産:人が仕事で生産性を高めて成功し、所得を増やすのに役立つ要素。いわば仕事のスキルのようなものだと思う。
②活力資産:肉体的・精神的な健康と幸福のこと。健康、友人関係、パートナーやその他の家族との良好な関係などが該当する。良い人生の重要な要素の一つ。
③変身資産:100年ライフを生きる人たちは、その過程で大きな変化を経験するが、その変化をするために必要な資産を変身資産とこの本では定義している。自分について良く知っていること、多様性に富んだ人的ネットワークを持っていること、新しい経験に対して開かれた姿勢を持っていることなどである。
今後、今まで定着した考え方の3つのステージ(人生前半の教育のステージ、仕事のステージ、引退のステージ)から、今後訪れる100年ライフでは、3ステージの人生に代わり、マルチステージの人生になるとのこと。例としては、生涯に二つ、もしくは三つのキャリアを持つようになる。金銭面を最も重視して長時間労働をしたり、家庭とのバランスを優先させたり、社会への貢献を軸に生活を組み立てたりと、その時の状況に応じて、優先とするものを変えることが何回か訪れるのをマルチステージと言っている(っぽい)。
その変化をするための資産を変身資産とこの本では言っているのだ。
そんな変身資産を増やし、活用していきましょうという話。だと理解した。
そんなんで、長かった割にちょっとあまり伝えたいことのポイントがあまり分かったという感想でした。
読んだのが結構前だったので、あまり覚えていないということもあるのだが、ちょっと最後に興味深いと思った内容について抜粋する。
・経済学の分野で注目されている考え方に、「イースタリンのパラドックス」がある。これは、豊かな人ほど幸福な傾向はあるものの、国の平均所得と国民の平均的な幸福度の間に直接の関係は見られない、という現象のことだ。国が経済的に豊かになっても、それに比例して幸福度が高まるわけではないのだ。ということは、所得以外の要因が人々の幸福度を左右していることになる。
お金が重要でないわけではない。無形の資産をお金で直接買うことはできないにしても、無形の資産に投資するためには、お金があり、経済的安定を実感している必要がある。健康維持のためにスポーツジムに入会したり、家族で休暇を楽しんだり、愛する人たちと余暇を過ごすゆとりを感じたりするには、お金をもっているほうがいい。また、お金が無形の資産を支えるだけでなく、無形の資産が金銭的資産づくりを支える面もある。この相互関係は非常に重要だ。100年ライフに備えるためには、二種類の資産のバランスを取ることが欠かせない。
・変わるのは、どんなスキルや知識を学ぶかだけではない。学び方も大きく変わる。とくに、「経験学習」の比重が大きくなるだろう。教科書と教室での学習にとどまらず、実際の活動を通じて行う学習のことだ。
経験学習の価値が高まるのは、一つには、インターネットとオンライン学習が発展して、単純な知識なら誰でも簡単に獲得できるようになるからだ。知識の量ではライバルと差がつかず、その知識を使ってどういう体験をしたかで差がつく時代になるのだ。その背景には、前章で論じたポランニーのパラドックスとモラヴェックのパラドックス、そしてマニュアル化できない暗黙知の重要性の高まりがある。暗黙知は、身につけるのは簡単ではないが、きわめて大きな経済的価値をもつ。それは知恵を洞察と直感の土台であり、実践と繰り返しと観察を通じてはじめて獲得できるものだからだ。
・グロイスバーグの研究から見えてきたことがもう一つある。それは、投資銀行のアナリストの成績が同僚ネットワークに大きく後押しされているということだ。その効果は、チームのメンバーが信頼し合い、互いの評判を大切にしているとき、ことのほか大きい。それを裏づけるように、アナリストが移籍しても成績が落ちなかったり、むしろ上昇したりしたケースはほぼ例外なく、チームのメンバーと一緒に移籍していた。しかし、会社を移った花形アナリストの多くは、チームのメンバーと切り離された結果、「スター」どころか「流れ星」のようになり、新しい職場でたちまち輝きを失う。
このような人脈や人間関係は、生産性資産の重要な要素だ。これを「職業上の社会関係資本」と呼びたい。強力な人間関係を築いている人は、ほかの人の知識を容易に取り込み、自身の生産性を向上させ、イノベーションを促進できる。高い信頼性と評判をもつ人たちと緊密な協力関係を築くことにより、自分が個人で蓄えているよりずっと広い知識と見方を得られるのだ。そのような人間関係は、他人と協働して働くための豊かな土壌を生み、さまざまな見方を組み合わせる機会をつくり出す。イノベーションを成し遂げるうえでは、多様な視点を組み合わせることがとりわけ重要だと言われている。
なかでも重要なのは、小規模な仕事仲間のネットワーク、それも相互の信頼で結ばれた強力なネットワークらしい。そのようなネットワークのメンバーは、互いに似たようなスキルと専門知識をもっていることが多く、職業上の成長を支え合うことができる。著者(グラットン)は以前の著書で、こうしたネットワークを「ポッセ」と呼んだ。同じ志をもつ仲間のことである。この強力な職業上のネットワークのメンバーは、信頼し合い、互いのコーチや支援者になり、人脈を紹介し合い、貴重な助言を送り合う。
では、ポッセはどうやって築けばいいのか? 社会関係資本の多くがそうであるように、それは一朝一夕では築けない。自分と同様のスキルと知識をもつ人たちとの関係を深めるために多くの時間を費やし、その人たちと直接対面して会話する時間も割かなくてはならない。高度な専門知識がはぐくまれ、共有されるためには、そのような時間が必要なのだ。
このような人脈や人間関係は、生産性資産の重要な要素だ。これを「職業上の社会関係資本」と呼びたい。強力な人間関係を築いている人は、ほかの人の知識を容易に取り込み、自身の生産性を向上させ、イノベーションを促進できる。高い信頼性と評判をもつ人たちと緊密な協力関係を築くことにより、自分が個人で蓄えているよりずっと広い知識と見方を得られるのだ。そのような人間関係は、他人と協働して働くための豊かな土壌を生み、さまざまな見方を組み合わせる機会をつくり出す。イノベーションを成し遂げるうえでは、多様な視点を組み合わせることがとりわけ重要だと言われている。
なかでも重要なのは、小規模な仕事仲間のネットワーク、それも相互の信頼で結ばれた強力なネットワークらしい。そのようなネットワークのメンバーは、互いに似たようなスキルと専門知識をもっていることが多く、職業上の成長を支え合うことができる。著者(グラットン)は以前の著書で、こうしたネットワークを「ポッセ」と呼んだ。同じ志をもつ仲間のことである。この強力な職業上のネットワークのメンバーは、信頼し合い、互いのコーチや支援者になり、人脈を紹介し合い、貴重な助言を送り合う。
では、ポッセはどうやって築けばいいのか? 社会関係資本の多くがそうであるように、それは一朝一夕では築けない。自分と同様のスキルと知識をもつ人たちとの関係を深めるために多くの時間を費やし、その人たちと直接対面して会話する時間も割かなくてはならない。高度な専門知識がはぐくまれ、共有されるためには、そのような時間が必要なのだ。
・エクスプローラーとして生きるのに年齢は関係ないが、多くの人にとって、このステージを生きるのにとりわけ適した時期が三つある。それは、10~30歳ぐらいの時期、40代半ばの時期、そして10~30歳ぐらいの時期である。これらの時期は人生の転期になりやすく、エクスプローラーのステージを経験することが明確な効果を生みやすい。現状を再確認し、自分のもっている選択肢について理解を深め、みずからの信念と価値観について深く考える時間にできるのだ。
エクスプローラーの日々は、見違えるほど若さを取り戻せる機会になりうる。70代の人はややもすると、長寿のリスクに脅えて生きることが当たり前になりがちだ。しかし、日々の生活を脇に置いて冒険に乗り出せば、現在のライフスタイルを問い直し、新しい選択肢を見いだすことを通じて、活力の回復が大きく後押しされるかもしれない。70代のジェーンは、まさにそのような経験をする。
・ほとんどの人は善良でありたいと思うが、なぜかいつも善良な行動を先延ばししてしまう。減量のために運動すべきだとわかっていて、それを実行に移すつもりはあるのに、実際にはそのとおりに行動しない。誰もがセルフ・コントロール(自己抑制)に苦労している。長寿化がさらに進めば、セルフ・コントロールの失敗が生むコストはいっそう膨らむ。長寿化時代には、現在の行動と未来のニーズのバランスを取ることが不可欠だ。現在の行動が未来の自分に影響を及ぼすことを理解し、必要なセルフ・コントロールをすべきなのは、金融の分野に限った話ではない。生産的で充実した人生を100年以上生きるうえで核になるのは、セルフ・コントロールの能力なのである。
セルフ・コントロールの失敗は、いま社会科学で脚光を浴びているテーマの一つだ。神経学、心理学、経済学の知見を組み合わせる形で研究が進められている。セルフ・コントロールがうまくいかない理由は、脳の異なる領域同士の戦いという図式で見るとわかりやすい。脳の前頭葉は進化のプロセスで比較的最近に(約15万年前)発達した領域であり、これが人間とほかの動物の違いを生む。認知的・合理的思考と長期計画をつかさどるのが前頭葉なのだ。しかし、脳にはもっと古くから存在する辺縁系という領域もある。これは、人の情緒的・本能的反応をつかさどる領域だ。
単純化して言うと、前頭葉は、長い目で見て自分の利益になる行動を取るよう私たちに命令し、辺縁系は、目先のことを優先させた判断を、言い換えればいますぐ満足を味わえるような行動を促す。この両者の緊張関係をゾウ(=辺縁系)とゾウ使い(=前頭葉)の関係になぞらえる論者もいる。巨大なゾウの背中に小柄なゾウ使いが乗っていて、ゾウの行動をコントロールしようとしているイメージだ。ゾウとゾウ使いが同じ方向に進みたいと思っている場合はいいが、両者の願望が食い違えば、結局はゾウの主張が通る。
人類の歴史のほとんどの期間は、辺縁系の命令に従い、目先の満足を追求することが理にかなっていた。過酷な環境に生きていて、人生が短かった時代は、それでよかったのだ。しかし、平均寿命が延びたいま、合理的な前頭葉にもっと大きな力をもたせ、優れた長期計画を立てるほうが賢明なのではないか?
一旦こんな感じでしょうか?
セルフ・コントロールの失敗は、いま社会科学で脚光を浴びているテーマの一つだ。神経学、心理学、経済学の知見を組み合わせる形で研究が進められている。セルフ・コントロールがうまくいかない理由は、脳の異なる領域同士の戦いという図式で見るとわかりやすい。脳の前頭葉は進化のプロセスで比較的最近に(約15万年前)発達した領域であり、これが人間とほかの動物の違いを生む。認知的・合理的思考と長期計画をつかさどるのが前頭葉なのだ。しかし、脳にはもっと古くから存在する辺縁系という領域もある。これは、人の情緒的・本能的反応をつかさどる領域だ。
単純化して言うと、前頭葉は、長い目で見て自分の利益になる行動を取るよう私たちに命令し、辺縁系は、目先のことを優先させた判断を、言い換えればいますぐ満足を味わえるような行動を促す。この両者の緊張関係をゾウ(=辺縁系)とゾウ使い(=前頭葉)の関係になぞらえる論者もいる。巨大なゾウの背中に小柄なゾウ使いが乗っていて、ゾウの行動をコントロールしようとしているイメージだ。ゾウとゾウ使いが同じ方向に進みたいと思っている場合はいいが、両者の願望が食い違えば、結局はゾウの主張が通る。
人類の歴史のほとんどの期間は、辺縁系の命令に従い、目先の満足を追求することが理にかなっていた。過酷な環境に生きていて、人生が短かった時代は、それでよかったのだ。しかし、平均寿命が延びたいま、合理的な前頭葉にもっと大きな力をもたせ、優れた長期計画を立てるほうが賢明なのではないか?
一旦こんな感じでしょうか?
ちょっと最近本を読むのがお預けになってしまったが、またちょっとずつ読んだ本の投稿をしていきたいと思う。
そんなんで以上☆











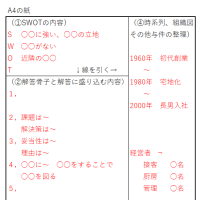
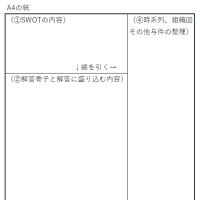

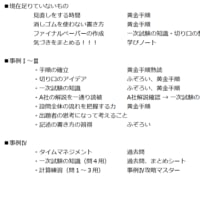
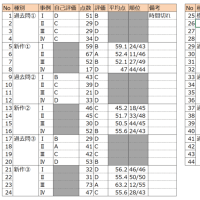









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます