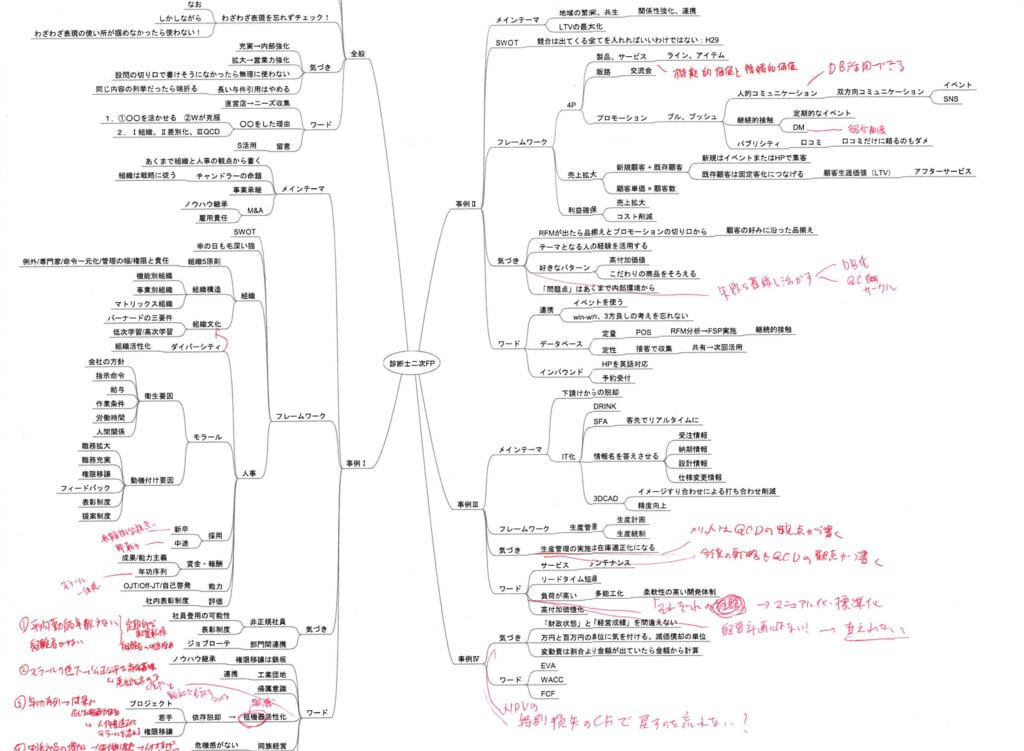総評:★★★★☆ いい感じ。
面白い度:★★★★★ さらっと読み終わってしまった。
読みやすい度:★★★★★ とても読みやすい。
ためになる度:★★★★☆ ためになる内容多数。
また読みたい度:★★★☆☆ 機会があれば。
久ぶりに読んだ本の投稿をする。
今まで中小企業診断士のカテゴリーの投稿を続けていたが、色々一段落したので、また読んだ本の投稿を続けていきたいと思う。
読んでそのままになっている本が色々溜まっているので。。。(笑)
そんなんで再開後の1冊目は前回投稿した野村克也さん関連の本である。
前回の「
負けに不思議の負けなし」はノムさんが新聞紙上に連載していた記事のまとめだったので、当時のプロ野球界の内容がメインで、どちらかというと外れ本だった。。。(笑)
でも今回の「野村ノート」はレビューの評価も高く、こちらの方が楽しみにしていた本だった。
そんなんで読んでもやはりなかなか面白い内容だった。
野村さんは監督時代、毎日ミーティングを実施し、野村さんの考えや野球のルール、戦術など自らの考えを選手たちに教える時間を作っていたらしい。
それをありがたいと思った選手もそうでない選手もいたと思うが、自分から見ると、そんな野村さんの考えを毎日聞ける時間があるなんてなんて贅沢なんだ!と思う。
もちろん名捕手の古田さんとかは野村イズムの体現者で、めちゃくちゃ教えを受けたということだが、長嶋一茂さんはそんなミーティングの時間、ノートを取らず寝ていたらしい(笑)
それはそれでただ者じゃないと思う。
そんな野村さんは、「
野村再生工場」で有名で、当時他球団で成績の振るわなかった選手を引っ張ってきては見事に立て直し、プロ野球の第一線で大きな活躍をする選手に育て上げたらしい。
自分もそんな人間になりたい。
野村さんはどこでそんな達観した考えを得ることができたのだろう?
とりあえず、この本は目次からもう凄い「ぶっ刺さる」内容になっている。
目次は次の通りである。
第1章 意識改革で組織は変わる
第2章 管理、指導は経験がベースとなる
第3章 指揮官の最初の仕事は戦力分析にある
第4章 才能は学から生まれる
第5章 中心なき組織は機能しない
第6章 組織はリーダーの力量以上には伸びない
第7章 指揮官の重要な仕事は人づくりである
第8章 人間学のない者に指導者の資格なし
もう凄い。何かのビジネス書?と思う内容である。
もう「その通りです」としか言えない。
野村さんの深淵な考え、知見、とても興味深く、プロ野球という業界で活躍された方だが、ビジネス界におられた場合でも本当に輝かしい功績を残せた方なんだろうなあと思う。
「監督業」はとても興味深い。
野村さん、侍ジャパンを率いた栗山監督。
サッカーで言うと去年J2を率いて1年でJ1に昇格し、さらに現在J1の首位にいる町田ゼルビアを率いる黒田監督、今年の箱根駅伝優勝した青山学院率いる原晋監督。
海外で言うとリバプールを率いるクロップ監督、マンチェスターシティのグアルディオラ監督、現在アーセナルを率いているアルテタ監督、また去年からトットナムを率いているポステコグルー監督、アトレティコマドリードのシメオネ監督、最近で言うとレバークーゼンを率いるシャビ・アロンソ監督等々。
どのような理念を持ってどのような考え方、戦術を選手たちに植え付けているのか、選手たちをどのように管理しているのか、とても興味深い。
皆さんとても人間味があり、チームの選手たちの心を鷲掴みにしているんだろう。
そんな組織を成長させ、成果を出し、そして人を成長させられる、人間味のあふれる人に自分もなりたいと思う。
というのが今回の感想を書きながら思ったことでした。
そんなんで興味深かった内容を抜粋する。
・私は監督をやっていくうえで、次の5原則に従って職務を遂行してきた。
①「人生」と「仕事」は常に連動しているということを自覚せよ。(仕事を通じて人間形成、人格形成をしていくということ)
②人生論が確立されていないかぎりいい仕事はできないということを肝に銘じておくこと。人間はなぜ生まれてくるのか。それは「生きるため」と「存在するため」である。すなわち価値観と存在感である。その人の価値や存在感は他人が決めるものだ。従って、他人の評価こそが正しいということになる。”評価に始まって評価に終わる”と言われる所以である。
③野球をやるうえで重要なのは、「目」(目のつけどころが大事だ)、「頭」(考えろ、工夫しろ)、「感性」(感じる力を養え。それには負けじ魂や貪欲な向上心やハングリー精神がポイントとなる)の3つである。
④技術的能力の発揮には次の3点、「コツ」(投げる、打つ、守る、走るときのコツ(感覚)を覚える)、「ツボ」(相手チームの得意な形、相手バッテリーの配球の傾向、マークする選手、打席でのマークする球種、相手打者の攻略法、クセ探しなどのツボを押さえておくこと)、「注意点」(相手のなかでマークする選手、投手は相手のコースや球種は絶対になげない、理想のフォームを崩さないための”意識付け”をしておくこと。性格面もそうであるように無意識だとどうしても欠点がでてしまう)が重要である。
⑤無形の力をつけよ。技量だけでは勝てない。形に出ない力を身につけることは極めて重要である。情報収集と活用、観察力、分析力、判断力、決断力、先見力、ひらめき、鋭い勘等々である。
・「うちは他のチームより進んだ野球をやっている」という思いを生じさせ、さらにデータをもとに具体的な攻略法を授けると、「それならおれにもできそうだ」という気にさせることができる。選手の監督に対する尊敬と信頼が芽生え、他チームに対しては優越感や優位感のようなものが生じる。これがチームにとって大きな効果を生み、戦力となる。
弱いチームには特にそういう優位感をもたせることが必要だ。なにせ選手も自分たちは弱いと思っており、たとえば巨人のような豊富な資金で有望選手を次々と獲得しているチームと対戦すると、劣等感で勝負をする前にびびってしまう。
ところが優位感をもたせると、選手が変わってくる。まずヤジが違ってきて、相手がちょっと奇策めいたことをしても、「そんなの古い、古い」という声がどこからか出てくる。これは相手を見下ろしている証拠で、こうして選手の意識はおのずといいムードに変わっていく。
逆に相手は「ヤクルトは何をやってくるかわからない」 とおどおどし始めて、こちらが何もしなくても、過剰な警戒心から集中力を失い、ミスを犯す。スクイズやエンドラン、あるいは盗塁を警戒したあげく結局四球を出すなどが、その代表例だ。他にも足の速い走者が塁に出て、走るぞ走るぞと見せかけることで、走られたくないバッテリー心理から甘い直球を投じさせるなどの現象が生じる。
・チームは2年、3年のビジョンで考えれば、少しずつでも変わることはできる。
そこで大事になるのは、人間はみな人生を生き抜くという使命をもって存在しているということを選手に説き、その使命感を選手ひとりひとりに認識させることである。だからこそいやが応にも、人生を教えなくてはならないのだ。
人生という2文字から私は次の4つの言葉を連想する。
「人として生まれる」(運命)
「人として生きる」(責任と使命)
「人を生かす」(仕事、チーム力)
「人を生む」(繁栄、育成、継続)
監督においては3番目の「人を生かす」が求められる。「人を生かす」プレーが選手を伸ばし、そしてチームの力となる。選手それぞれを動かすことで、他の選手が活きる。強いチームになるにはこうした相乗効果が不可欠である。
さらにチームをつくりあげるうえでは2つ目の「人として生きる」を選手に徹底して教え込まなくてはいけない。
人間とは人の間と書くが、そもそも人と人との間にいるのが人間であり、そのためにはいかに人間関係を円滑に生きていくかということが、人生では大きな比重を占める。
ところが職人気質が多いプロ野球選手は、この点がたいへん無頓着である。自分ひとりでうまくなった。自分で勝てたとすぐ錯覚するが、人は全然そう思ってくれていないということが往々にしてある。謙虚さ、素直さが要求されるのはそのためだ。
自分が思うほど人は思っていないということをどうやって選手にわからせるか。評価は人が下した評価こそが正しいのだ。
・ヤンキースや巨人のように、毎年膨大な資金で補強しても優勝できるとはかぎらない。強い者が必ず勝つとはかぎらないのが野球である。
ならば4対6、あるいは3対7ほどの戦力差がある弱者が強者に勝つにはどうしたらいいか。それは野球というスポーツの性質をよく理解し、その特性にのっとって相手の心理を探り、対策、戦略を練る―ひと言でいえば、考えて戦うことだ。
・長く監督をやってわかったことは、選手時代に悩んだり苦労していない、創意工夫していない、頭を使わずにプレーしてきた。そういった選手はコーチをやってもろくな指導ができないということである。
相手ピッチャーを打てない。選手がそういう局面に接したとき、「ちょっと頭をひねって工夫してみろ」といった程度のアドバイスも送れない。
どのコーチも打者への技術指導の内容はさほど変わらない。
「ヘッドが下がっている」
「バットが下から出ている」
「肩が開いている」
「軸足に体重が乗っていない」
「トップの形ができていない」
コーチのアドバイスとはその程度のもの。それでも打てないから打者は困っているのだ。
指導者に求められるのは、選手にどうすれば実践力をつけることができるかということである。
「おれの現役のときは、こういうタイプのピッチャーにはこう対処した。おまえも一度やってみんか」といったアドバイスができるようになるには、やはり選手時代からしっかり考え、悩み、苦しんでおかなければならない。そのなかから方法を見つける。そういうことが将来、指導者になったときに必ず活きる。野球にかぎらず、どんな職業においても、いいものをつくる、いい結果をだすには自分が得た経験がベースとなる。これらは管理職共通のテーマである。
・理をもって戦うということが私の戦い方の根底にあるが、ふだんから観察や洞察、あるいは考えるという行為をなおざりにしていると、いざという場面で何をもとにした配球を探るべきか、その根拠となる理を探すことができない。
世の中に存在するものはすべて理があるというが、なるほどそう思う。野球などはまさに理でもって成り立っている。その理を活かすのが、勝利への近道と言える。
・決断と判断。監督になったばかりのころ、私はこのふたつの言葉を混同していた。ところがあるとき、まったく意味が異なると気づいた。
「決断」とは賭けである。何に賭けるか根拠が求められる。また決断する以上、責任は自分で取るという度量の広さをもたなくてはならない。「功は人に譲る」という精神をもって決断しなくてはならない。覚悟に勝る決断なし、つまり迷ったら覚悟を決めること。決断力と包容力は表裏一体である。
一方、「判断」とは頭でやるもの。知識量や修羅場の経験がものをいう。判断に求められるのは判断するにあたっての基準、根拠があるかどうかである。
監督の采配のなかで、決断(=賭け)ではなく、判断(=基準がある)が求められるものがある。選手起用や代打、そして投手交代など選手の抜擢であり、なかでも投手交代、継投というものは完全に判断能力が問われる。
・私は指揮官、つまりリーダーについて、常に以下のことを念頭に置いている。
①リーダーいかんによって組織全体はどうにでも変わる。
②リーダーはその職場の気流にならなくてはならない。
③リーダーの職務とは「壊す・創る・守る」
①については、「水は方円の器に随う」という言葉があるが、器(指揮官)が四角ければ水(組織)は四角く、円ければ円く、指揮官しだいでどうにでも変わってしまうものなのである。
②はまさに自分が率いる人間を巻き込むことができるかどうか。ひとりひとりに仕事の意義を感じさせ、興奮させる。感奮興起という言葉があるが、感じて奮い立たせる、意気が奮い起こるそれこそが指揮官の使命である。
③は信長(旧価値社会の破壊)、秀吉(新価値社会の建設)、家康(既存の事業のローリングによる維持管理)、この3つの作業を組み合わせることができるかどうか。
リーダーはチームが機能する軸を「まとまり」におかなくてはならない。まとまりを無視し、ただ能力の高い選手を集めて、個々の選手の能力の合計=チーム力と考えてしまうと、「これだけの選手がいるのに、なぜうちは結果が出ないんだろう」というジレンマに襲われる。
「まとまり」とはわかりやすくいえば、目的意識、達成意欲をみんなが持ち続けることである。全員が”勝とうぜ”という気になってくれることなのだ。
そんな感じでしょうか?
前回までの野村監督の本に比べてとても興味深く、得るものが多い本でした。
そんなんで今回は以上☆