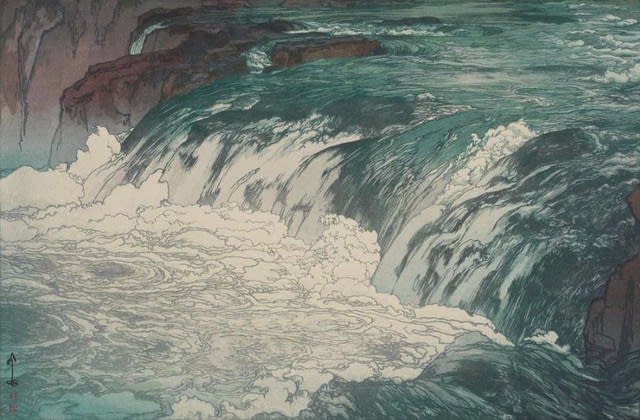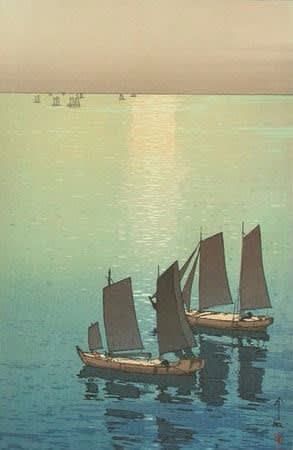昨年から取り組んでいたY'sDAY(家具ショップ)が今日リニューアルオープンしました。途中で熊本地震が発生し紆余曲折がありましたが、施工者も人手不足の中頑張ってくれ、予定の4月29日にどうにか間に合いました。
昨日の夕方まで既設店舗のクロス張替が続いていたので、お店のデイスプレイは今朝の3時までか掛かったそうです。

当初写真の駐車場側奥に店舗を建てる計画で設計し、確認申請も下り着工寸前まで行っていたのですが、今新店舗が建っている所の古い民家が被災し解体後の敷地の購入をY'sDAYに頼まれました。間口約5.5M奥行33Mの細長い敷地は駐車場にも使えず、悩んだ挙句購入敷地側に店舗を新築し、古い店舗と繋ぐ計画に変更することになりました。
ところが既設店舗(2階アパート)は確認申請の完了検査を受けておらず、詳しく調べると確認申請時から変更部分があり、壁量計算上の壁が大きく不足していました。急遽適法化案を作り熊本市建築指導課に相談に行きました。不足耐力壁の増設、非常用照明の設置など是正報告書を作成し、如何にか確認申請許可を取得しました。
昨年12月に着工しましたが、暮れに店舗長さを約29.0Mから33.0Mに増設依頼があり、一時工事ストップ、計画変更申請手続きを行い。1月末に工事再開。



この建物はL型のコンクリート(ベタ基礎とRC壁)を長手方向に作り、反対側の壁と屋根は木造の混構造です。長い敷地の短編方向の耐力壁を無くす為、コンクリート壁に地震力を持たせ、木造部分は屋根と外壁を面材耐力壁で固める事でシンプルな構造としました。コンクリートの上は土台、大梁、母屋組みの間に出来るスリットをガラス張りにすることで軽やかさを演出しています。
天井高さが4.0Mあることとコンクリート壁は熱容量が大きいので、外断熱化し、屋根は外張り断熱にしました。気持ちの良い空間も温熱環境が悪いとガッカリなので、これまで培ってきたパッシブソーラーの考え方をここでも活かしています。



今日は最も気候の良い時期でもあるのですが、店舗の中を流れる空気が気持ちよく、今朝ギリギリまで掛かってディスプレイされた家具たちもコンクリート打ち放しと杉梁と光の中で一際存在感が増していました。
私も店舗設計は久しぶりだったので、苦労も多かったですがイメージした空間が気持ちよく使われていて嬉しくなりました。
空間の力強さと空気の流れは風(プネウマ)を呼んでくれます。