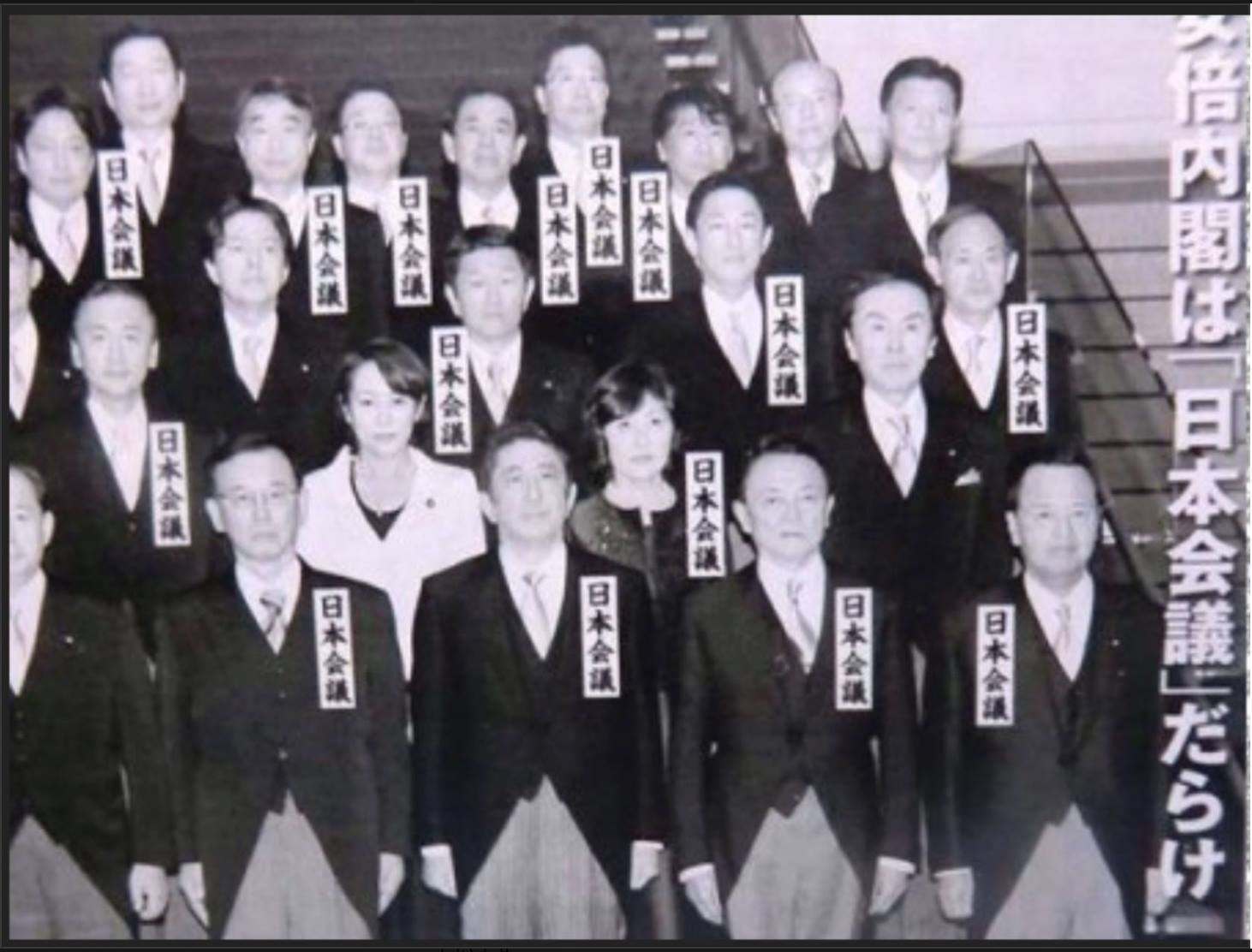利権に群がり、売国を旨とするアベシ政権・・・・武器三原則を解除し特定秘密保護法案を決め、日本版NSCを作り、安保法制で海外で自衛隊を軍隊として活用できるようにしようとしている。口先は日本人の安全を守るためと言いながら、いつでも狙われる状況に追い込んでいる・・・・・一方アフガニスタンで住民のために支援活動をしている人がいる。彼に言わせると、日本の憲法9条が自分たちの活動を守ってくれていると話しています。
マガジン9の「この人に聞きたい」より転載します。
9条をバックボーンに活動を続けてきた
もちろん、みなさんご存知のように、中村さんは「ペシャワール会」の代表として、
パキスタン、アフガニスタンで、さまざまな活動に携わっておられます。
その中村さんに、現地での活動状況と、特に憲法9条との関連について、お伺いしました。

なかむら・てつ
1946年福岡市生まれ。九州大学医学部卒。NGO「ペシャワール会」現地代表、PMS(ペシャワール会医療サービス)総院長。専門は神経内科(現地では内科・外科もこなす)。国内の診療所勤務を経て、1984年パキスタン北西辺境州の州都のペシャワールに赴任。ハンセン病を中心としたアフガン難民の診療に携わったのをきっかけに、井戸・水路工事による水源確保事業など現地での支援活動を続ける。著書に『医者、用水路を拓く−−アフガンの大地から世界の虚構に挑む』(石風社)『アフガニスタンで考える−−国際貢献と憲法九条』(岩波ブックレット)など。
アフガニスタンの人々の「生活」を取り戻すために
編集部
中村さんがお書きになった本や、インタビューなどを読ませていただきました。その中でも、最近出版された『医者、用水路を拓く』(石風社刊)は、ほんとうに面白い本でした。
中村
そうですか。ありがとうございます。そう言っていただけると、とても嬉しいです。あの本は、土木工事のかなり専門的なことを重点に書いたもので、一般の方が読んで面白いのかな、と、少し心配していたんです。
編集部
いえいえ、いい喩えにはならないかもしれませんが、まるでハードボイルド小説を読んでいるみたいにスリリングで。
中村
それはとても嬉しいです。“面白い”と言われるのが、何よりの励みになりますね。
編集部
船戸与一さんの小説みたいでしたよ。まあ、船戸ハードボイルドには、癖のある悪人ばかりが登場しますが、この『医者、用水路を拓く』には、悪人がほとんど出てこない。とても読後感の爽やかなハードボイルド…(笑)。いや、中身はほんとうにハードですけれど。
中村
そうですか。そういう読まれ方もあるんですね。なにはともあれ、面白く読んでいただけたのは、とても嬉しいことです。
編集部
この本では、「ペシャワール会」(編集部注・中村医師のパキスタンやアフガニスタンでの活動を支えるために、1983年に作られた組織。パキスタンのペシャワールにちなんで名付けられた)が行っている、用水路建設について詳しく触れておられますね。現在ではむしろ、医療よりも水源確保により多くの力を注いでいる、という印象を受けますが。
中村
そうですね。現在は、アフガニスタンでの灌漑事業に主力を注いでいますので、毎日が土木作業です。ほとんど用水路建設にかかりきりで、野外での作業ばかりなんですよ。それで、ごらんのように真っ黒です。ナニ人か分からない、なんてしょっちゅう言われますね。この用水路建設事業は、僕が言い出しっぺなので、仕方なしに土木技師をやっているわけです。
編集部
医療よりも用水路建設が優先、ということですか。アフガニスタンは、現在、それほど水源が枯渇している状況にあるのですか。
中村
そうです。2000年から始まったアフガニスタンの大干ばつは、凄まじいものでした。アフガンの人々の生活を、根底から突き崩してしまったといってもいいと思います。我々ペシャワール会は、彼らの元の生活を、まず取り戻すことが、なによりも先決ではないかと考えたわけです。
まず「生き延びる」ための支援を
編集部
日本政府はよく国際貢献と言いますが、どうもそれがズレている感じがします。中村さんたちがなさっているような事業に、もっとお金を出すべきじゃないか、なんて単純に思ってしまいますけど。
中村
端的に言えば、人々が生存するための、生きていくための事業に対する支援。これがなんと言っても第一だと思いますけどね。我々は、日本政府からは一円の援助も受けていませんが、どうも、日本政府の援助の仕方は、あまりそういう生存への援助にはなっていないんじゃないか、と思いますね。いや、日本政府に限ったことじゃなく、アメリカやほかの国際組織のやり方にも、僕は違和感を覚えることが多いんです。
編集部
生存への援助になっていない?
中村
そう。例えば欧米の団体などでは、男女平等を訴えるグループもあれば、情報網の完備だとか言って、通信網やネットの整備に力を注ぐ人たちもいます。いまや、首都カーブルの一角には、インターネットカフェなんかまでできています。
もちろん、それが悪いとは言いませんが、そんなことよりももっと以前に、まずみんなが生きていかなくちゃ、ということが不思議なくらい話題にならない。どうしても、政治的な動きだけが伝えられて、それにしたがって、僕に言わせれば無駄なところへ援助資金が投下されている、そんなふうに見えるんです。完全に、情報操作としか言いようがないですよ。まず、生き延びることが、いちばん大切なはずでしょ?
編集部
援助すべきところが違うんじゃないか、と。
中村
例えば、アフガンの大干ばつにしても、それを防ぐために何をすべきか、というところをよく考えて援助の方向を決める。それは、みんなが納得することなんですね。アフガンでは、ほんとうに生きていけない人たちが増大している。なにしろ、2500万人の人口のうち、1200万人がこの干ばつで被害を受け、500万人が飢餓線上、100万人が餓死寸前という状況にあるのがアフガニスタンですよ。そこへ、男女平等だとか情報網の整備だとか言っても、それがどうだと言うんですか。
編集部
まず、命を、ですね。
中村
アフガンに限って言いますと、生き延びることに対する支援でしょうね。単に学校教育――自分の国の教育もきちんとできていないのに、よその国の教育がどうのこうの言ったって仕方ない。まず、生きられるようにしてあげる協力ですよ。これには、誰もが納得するんじゃないでしょうかね。
編集部
それが、中村さんたちペシャワール会が目指したことなんですね。
中村
そうです。大干ばつの後、我々の診療所にやってくる患者は、子どもたちがほんとうに多かった。その背景には、栄養失調と水不足があるんです。それが、子どもたちを直撃したんですよ。水不足で農業ができなくなり、村そのものが消えてしまったところも珍しくない。それが、アフガン全土で起こった現実です。うちのダラエルヌールの診療所の近所でも、一時、2軒を残して完全に無人化したこともあったほどです。全部、難民化したんですよ。
編集部
それで、水資源確保のために、井戸掘りを始められたわけですね。
中村
そうですね。井戸掘りを始めたのが、2000年の7月でした。それは、すでに1670本になりました。そのおかげで、40万人以上が村を離れずにすんだんです。
編集部
それがさらに、用水路の建設へと発展していった…。
中村
もちろん、診療をやめたわけではありませんが、ある意味、医療だけでは限界があると感じたんです。水がなければ農業が続けられない。日々の糧を得ることができないんですから、生きて行きようがない。それに、きれいな水がなければ、伝染病などが蔓延するのを防ぐことだってできない。だから、我々の現在の仕事は、用水路の建設と医療の2本立てなんです。
数字だけを見ることには、何の意味もない
編集部
用水路建設の進み具合はいかがですか。そうとうの難工事の連続だったようですが
中村
2003年3月から始めて、現在まで16.5キロを完成させています。これで、合計5000ヘクタール弱の農地を潤せる計算になります。漠然としたことしかいえませんが、この用水路1本で、数十万人が食えることになるのは確実です。
編集部
ここまで来るには大変だったでしょうね。
中村
ほんとうに、最初は手探り状態。その中で、日本各地の取水方式が、とても参考になりました。日本方式と言っても、江戸時代や戦国時代の技術を、アフガンで再生しているんです。ほとんど機械が使えないような状況の中では、こんな日本古来の人力に頼った技術が、思わぬ効果を発揮するんですね。
編集部
そういう活動を、ほかの団体がなぜもっと行わないんでしょうか。
中村
たとえば国連の機関なんかも、すべてを数字で置き換えてしまうんですね。ソ連軍の侵攻と撤退とそれに伴う内戦や大混乱、さらにはその後の大干ばつなどで、故郷を捨てざるを得なかった難民が大発生しました。それに対し、国連などが“帰還事業”を行い、「200万人のうち、130万人を1年間で帰した」なんて発表するんですよ。そうすると、ほんとうは難民は70万人しか残っていないはずじゃないですか。ところが実際は、300万人の難民が現実に存在している。
僕らは言うんです。「むしろ、難民は増えている」と。「復興帰還プロジェクトなんて、帰ってそこで人々が生活できる基盤を作らないと成立しないんだ」と、僕らが盛んに言うもんだから、それで反感を買ってしまう、という面もあるんでしょうね。国際機関は、とにかく数字を示して自分たちの活動の成果を誇示しようとします。そうすることが、次期の予算やなんかにも影響してきますからね。
編集部
スタンスが違うわけですね。お聞きしていると、まずどんな事業に資金や援助をつぎ込むかを、もっと見極めなくては、という気がしますね。優先順位を、きちんとつけて重要なところから始めていく。
中村
そうです。まず生きることです。あとは、はっきり言って、タリバンが天下を取ろうが反タリバン政権になろうが、それはアフガンの内政問題なんですね。そのスタンスさえ崩さなければ、我々を攻撃する連中なんかいませんよ。それどころか、政府、反政府どちらの勢力も、我々を守ってくれるわけです。
「平和国家」日本に期待されていること
編集部
現地では、NGOとか国際機関なんかが襲撃されるということは、かなりあるんですか?
中村
何回も、見聞きしたことはありますよ。でも、我々ペシャワール会が襲われたことは一度もありません
編集部
それだけ、ペシャワール会の活動が現地の方々に浸透しているということでしょうか。
中村
そうですね。アフガンの人たちは、親日感情がとても強いですしね。それに、我々は宗教というものを、大切にしてきましたから。
編集部
宗教とは、やはりイスラム教…。
中村
おおむね、狙われたのはイスラム教というものに無理解な活動、例えば、女性の権利を主張するための女性平等プログラムだとか。現地でそんなことをすると、まず女性が嫌がるんです。キリスト教の宣教でやっているんじゃないか、と思われたりして。
編集部
宗教的対立感情みたいなものですか?
中村
いや、対立感情は、むしろ援助する側が持っているような気がしますね。優越感を持っているわけですよ。ああいうおくれた宗教、おくれた習慣を是正してやろうという、僕から言わせれば思い上がり、もっときつくいえば、“帝国主義的”ですけどね。そういうところの団体が、かなり襲撃されています。民主主義を波及させるというお題目は正しいんでしょうけれど、やっていることは、ソ連がアフガン侵攻時に唱えていたことと五十歩百歩ですよ。
編集部
ペシャワール会は、そういうことからは無縁であったということですね。
中村
そうです。それに僕はやっぱり、日本の憲法、ことに憲法9条というものの存在も大きいと思っています。
編集部
憲法9条、ですか。
中村
ええ、9条です。昨年、アフガニスタンの外務大臣が日本を訪問しましたね。そのとき、彼が平和憲法に触れた発言をしていました。アフガンの人たちみんなが、平和憲法やとりわけ9条について知っているわけではありません。でも、外相は「日本にはそういう憲法がある。だから、アフガニスタンとしては、日本に軍事活動を期待しているわけではない。日本は民生分野で平和的な活動を通じて、我々のために素晴らしい活動をしてくれると信じている」というようなことを語っていたんですね。
編集部
平和国家日本、ですね。
中村
ある意味「美しき誤解」かもしれませんが、そういうふうに、日本の平和的なイメージが非常な好印象を、アフガンの人たちに与えていることは事実です。日本人だけは、別格なんですよ。
編集部
日本人と他国の人たちを区別している?
中村
極端なことを言えば、欧米人に対してはまったく躊躇がない。白人をみれば「やっちゃえ」という感覚はありますよ。でもね、そういう日本人への見方というのも、最近はずいぶん変わってきたんです。
編集部
それは、なぜ、いつごろから、どのように変わってきたんですか?
中村
いちばんのキッカケは湾岸戦争。そして、もっとも身近なのは、もちろんアフガン空爆です。アメリカが要請してもいない段階で、日本は真っ先に空爆を支持し、その行動にすすんで貢献しようとした。その態度を見て、ガッカリしたアフガン人はほんとうに多かったんじゃないでしょうかね。
編集部
せっかくの親日感情が、そのために薄らいでしまったんですね。
中村
それでも、いまでもほかの国に比べたら、日本への感情はとても親しいものです。この感情を大事にしなければならないと思うんです。湾岸戦争のときに、「日本は血も汗も流さずお金だけばら撒いて、しかも国際社会から何の感謝もされなかった。それが、トラウマになっている」なんて、自民党の議員さんたちはよく言うようですけど、なんでそんなことがトラウマになるんですか。「お金の使い方が間違っていた」と言うのならいいのですが、「もっと血と汗を流せ」という方向へ行って、とうとうイラクへは自衛隊まで派遣してしまった。僕は、これはとても大きな転回点だったと思っています。
これまでは、海外に軍事力を派遣しない、ということが日本の最大の国際貢献だったはずなのに、とうとうそれを破ってしまったんです。これは、戦争協力ですよね。そんなお金があるんだったら、福祉だの農業復興だの何だの、ほかに使い道はいくらでもあるというのに。
編集部
ほんとうにそうですね。お金をどのように使うか、国際貢献とか国際援助とかいうのなら、最初に中村さんがおっしゃったように、まず「生存」のために使うべきですよね。
中村
日本は、軍事力を用いない分野での貢献や援助を果たすべきなんです。現地で活動していると、力の虚しさ、というのがほんとうに身に沁みます。銃で押さえ込めば、銃で反撃されます。当たり前のことです。でも、ようやく流れ始めた用水路を、誰が破壊しますか。緑色に復活した農地に、誰が爆弾を撃ち込みたいと思いますか。それを造ったのが日本人だと分かれば、少し失われた親日感情はすぐに戻ってきます。それが、ほんとうの外交じゃないかと、僕は確信しているんですが。
9条は、僕らの活動を支えてくれるリアルで大きな力
編集部
そう言えば、雑誌『SIGHT』(07年1月)のインタビューで、「9条がリアルで大きな力だったという現実。これはもっと知られるべきなんじゃないか」とおっしゃっていましたね。
中村
そうなんですよ。ほんとうにそうなんです。僕は憲法9条なんて、特に意識したことはなかった。でもね、向こうに行って、9条がバックボーンとして僕らの活動を支えていてくれる、これが我々を守ってきてくれたんだな、という実感がありますよ。体で感じた想いですよ。
武器など絶対に使用しないで、平和を具現化する。それが具体的な形として存在しているのが日本という国の平和憲法、9条ですよ。それを、現地の人たちも分かってくれているんです。だから、政府側も反政府側も、タリバンだって我々には手を出さない。むしろ、守ってくれているんです。9条があるから、海外ではこれまで絶対に銃を撃たなかった日本。それが、ほんとうの日本の強味なんですよ。
編集部
その体で実感した9条を手放すことには、どうしても納得できない。
中村
具体的に、リアルに、何よりも物理的に、僕らを守ってくれているものを、なんで手放す必要があるんでしょうか。危険だと言われる地域で活動していると、その9条のありがたさをつくづく感じるんです。日本は、その9条にのっとった行動をしてきた。だから、アフガンでも中東でも、いまでも親近感を持たれている。これを外交の基礎にするべきだと、僕は強く思います。
編集部
お話を伺って、中村さんたちの活動は、それこそ「ノーベル平和賞」に十分に値するものじゃないかと、とても強く感じました。これからも、ほんとうにお体や健康にお気をつけて、素晴らしい活動をお続けください。
本日は、長時間、ほんとうにありがとうございました。
中村
はい、こちらこそありがとうございました。第2期用水路建設に向けて、もっと日焼けしてきます(笑)。
※中村さん(ペシャワール会)の活動の場所をGoogleMapでご覧ください。
(ブラウザのバージョンによっては、閲覧できません。)
●ペシャワール会
http://www1a.biglobe.ne.jp/peshawar/
○活動エリアについては、以下にもあります。
http://www1a.biglobe.ne.jp/peshawar/ayumi.html
「9条がある」ことこそが、日本という国の本当の強みだ、と指摘する中村さん。
さまざまな困難に身をさらしながらの活動の中から生まれたその「実感」に、
私たちはもっと真摯に耳を傾けるべきなのではないでしょうか?
中村さん、ありがとうございました!