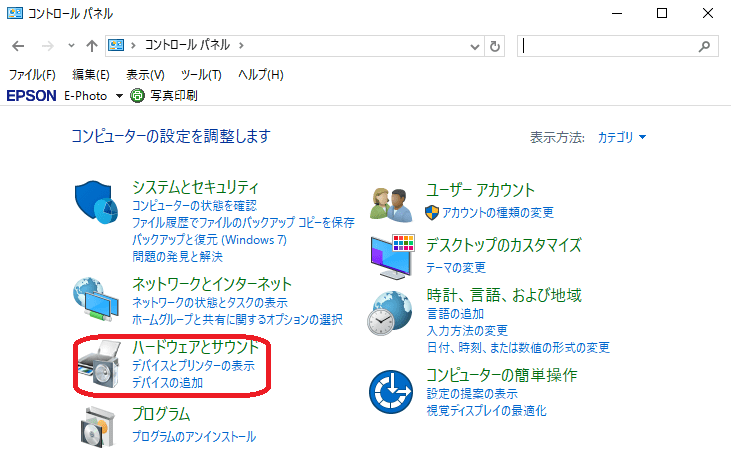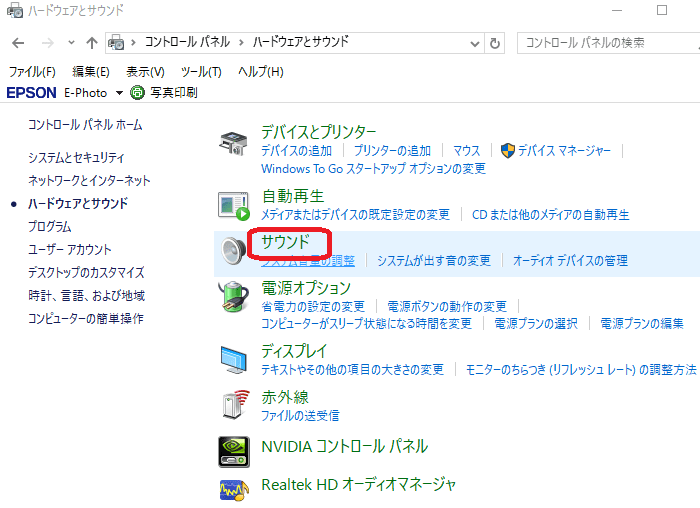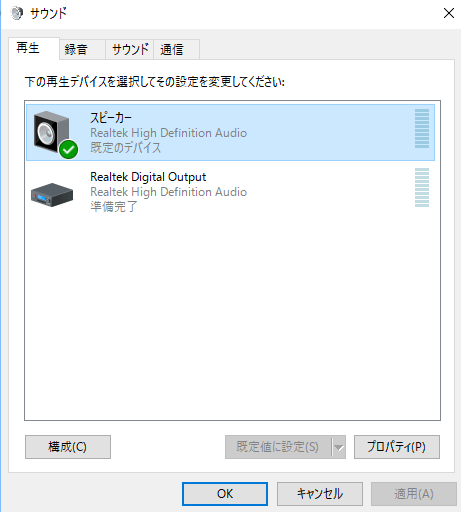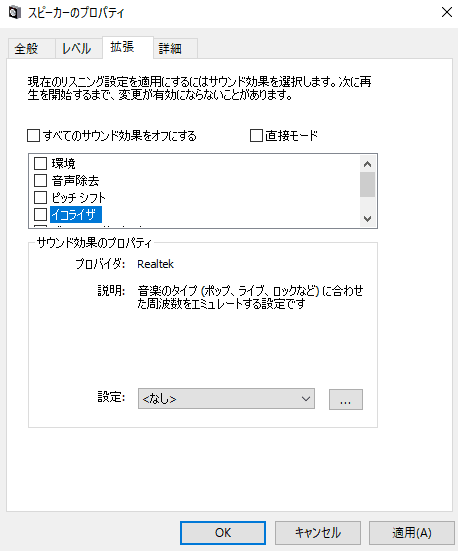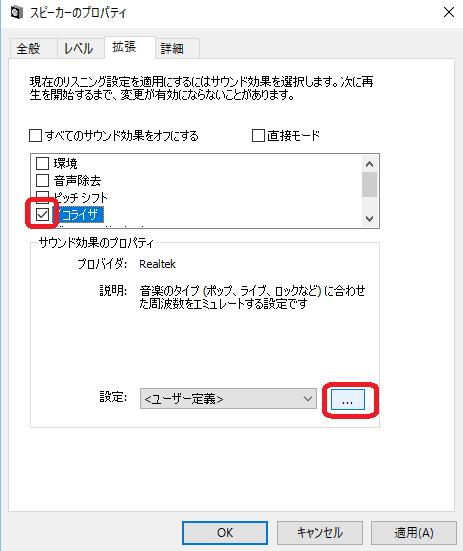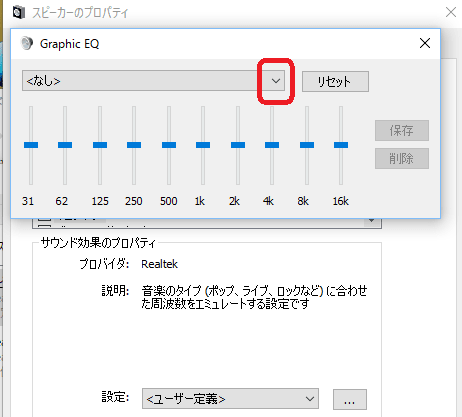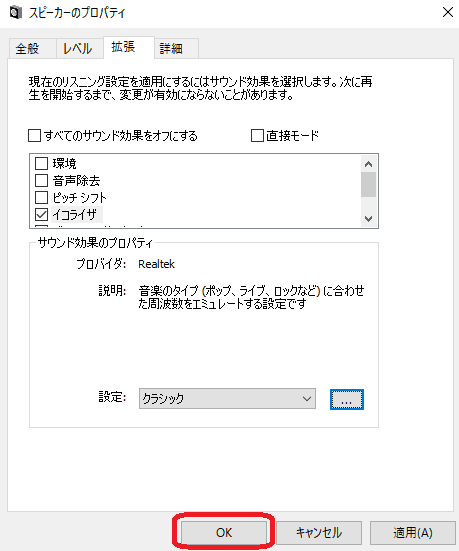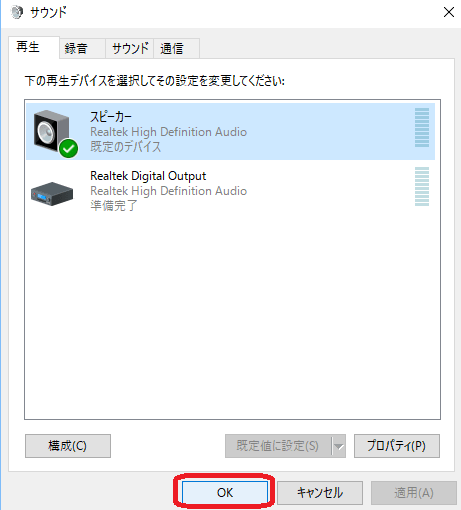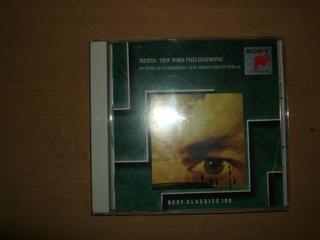ケーブルの話の続きになるが、前回はスピーカーケーブルについて話したが、今回はピンケーブルの話だ。接続のしかたや、グレードによる線の違いなどついて紹介する。
まずコンポを購入すると、アンプとCDプレーヤーを接続しなければならないので、ピンケーブルが必要になる。多くは1mのケーブルで接続しているのではないかと思う。
まずCDプレーヤーの方から説明すると、基本は左右のチャンネルで端子が出ている。左チャンネルが白。右チャンネルが赤なので、ピンケーブルの白をCDプレーヤーの端子の白いジャックに接続する。同様にピンケーブルの赤いケーブルと、プレーヤーの赤いジャックに接続する。
次はアンプのリアパネルには、PHONO、CD、TUNER、AUXなどずらっと端子(ジャック)が並んでいるが、その中に「CD」を見つけて白い端子と、CDプレーヤーから来た白のピンケーブルを接続する。同様に右チャンネル用に「CD」の赤端子と、赤いケーブルを差し込むと、アンプとCDプレーヤーが接続された。
ちなみに「PHONO」はアナログレコード専用端子で、規格が違うので他の機器とは接続できない。「TUNER」はラジオ用であり、これはCDプレーヤーと規格が同じなので、仮にCDプレーヤーに接続しても問題なく再生できる。「AUX」は予備端子であり機器を増設した場合に接続する。
ピンケーブル、ラインケーブル、RCAケーブル
さて、今までピンケーブルとして話してきたが、オーディオではラインケーブルと呼ばれる事が良くある。実は呼び名が違うだけで中身は同じものであり、CDプレーヤーなどに「LINE OUT」と記載されている物が多いが、ピンケーブルの事であり、「LINE IN」や「LINE OUT」と書かれている機器がある時は「ピンケーブルとつなぐ」と思えばよい。余談だがたまに「RCAケーブル」と呼ぶ場合があるが、これもピンケーブルの呼び名が違うだけだ。昔、家電メーカーのRCAが規格を作ったので、世界的に普及したのだ。言葉の片隅に覚えておこう。
不要に長いケーブルは問題がある
先ほども書いたが1メートルのケーブルで接続する場合が多いが、本当はケーブルが短い方がノイズが抑えられるので有利なのだ。安いピンケーブルは単純に銅線を巻いただけなので、電磁波から受けるノイズは無防備なのでノイズを受けてしまう。
グレードが高くなると銅線の外側にシールドを巻く事で電磁波の影響を減らしている。これはテレビのアンテナ線でよく見る同軸ケーブルと同じ構造であり、内側の芯線と外側には網線が囲まれていて、芯線が大切な信号を送り、側の網線でノイズを遮断する仕組みとなっている。良質なケーブルなのか、安いケーブルなのかの違いは、アンテナ線のように太いケーブルなのか、100円ショップとかで売られている細いケーブルなのかでおおよそ見分ける事が出来る。
ピンケーブルは1メートルの長さが一般的だが、グレードの高い(高価)ケーブルは50cm用、1m用、1.5m用と売られているが、少しでも音の劣化を減らすために必要な長さのケーブルを選べるようになっている。「大は小を兼ねる」から長いケーブルを束にしている人がたまに見かけるが、これはオーディオとしては問題のある方法だ。だから不用意に長いケーブルは使わない方が良い。
同軸ケーブルはピンケーブルに使えるのか?
アンテナに良く使われる5C-2Vケーブルはホームセンターでも安く売られるが、プラグがあれば、はんだごてを使ってケーブルを自作する事が出来る。5C-2Vの芯線はとても太いので、電気抵抗が少なくて済むし、網線により外部からの電磁波を防ぐことができる。この場合はプラス極の芯線と、マイナス極の網線とつなぐわけだ。手始めとしてはとても安いし効果も期待できるので、工作が得意な人は、はんだごてとテスターで導通確認が可能なら自作してみると良いだろう。ただ、同軸ケーブルは、プラス側に芯線、マイナス側は網線になるので、行きと帰りの線が異なってしまうので、明らかにケーブルの特性がついてしまう。だからオーディオ用には芯線を2本にしたケーブルを使うのが理想だ。「RCAケーブル 自作」で検索するとキットが市販されているので、手ごろな価格でかなりグレードの高いケーブルを手に入れる事ができる。
電磁波対策でアルミ箔は使えないか?
細いピンケーブルしか無い場合で、電磁波の影響を防ぐためにアルミホイルを巻き付けては?と考える人は多いと思う。昔、私も実際にやった事があるが、結論から言うとほとんど効果が無く、トライガードテープのほうがはるかに効果があった。アンプなどを全体にアルミホイルでくるむと効果があるのかもしれないが、放熱の邪魔になるし、危険なのでやめておいた方が良いだろう。
高いケーブルは本当に良いのか?
ケーブルが違えばそんなに音が変わるのか?と疑問に思う人も多いだろう。「100円ショップのケーブルでもいいんじゃない?」と言われると一概にダメとも言えない。それで満足ならそれで十分だし、不満に感じたらグレードを上げていけば良い。見栄を張ってすごいグレードのケーブルを使っている人でも、歌謡曲しか聞いていないなら宝の持ち腐れなのだ。スピーカーケーブルの時に書いたように、私も一番最初は普通のケーブルから初めて、徐々にケーブルが不満になりグレードを上げていった。

初めは長さ1mの普通のピンケーブルだった。
その後、本格的にクラシック音楽を聴くようになり、ケーブルがとても頼りなくなく思えたので、ソニーの上位クラスのケーブルに乗せ換えた。

写真は50cmのケーブル。現在は今のところ何も使っていない状態だ。グレードが上がったのではっきりと音質の改善を認識できた。他に1mケーブルもあり実際にサウンドフィールドプロセッサ用に使っている。やはり1mケーブルは使い勝手が良いのだ。
その後オーディオ雑誌でオーディオテクニカのArt linkケーブルを知り、PC-OCCケーブルをずっと使用している。初めは50cmで8,000円くらいだったと思う。そして一番最後はスーパーPC-OCCのハイブリッドで1mで20,000円を超えていたと記憶している。音の立ち上がりが抜群に速くて透明なのだ。あのスピード感は他には代えがたいのでずっと愛用している。
このように実際にケーブルの音を聞いてみて、必要性を感じれば高い買い物ではないと思う。
さて、本日の視聴はモーツァルトのセレナード13番。アイネ・クライネ・ナハト・ムジークだ。

イムジチ合奏団の演奏。

このCDには13番以外にも、セレナード6番と、ディヴェルティメントが3曲収録されている有名な曲ばかりだ。
Youtubeで「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」を検索してみると、カラヤン/ベルリンフィルの演奏が出てきた。こちらの演奏も素晴らしい。