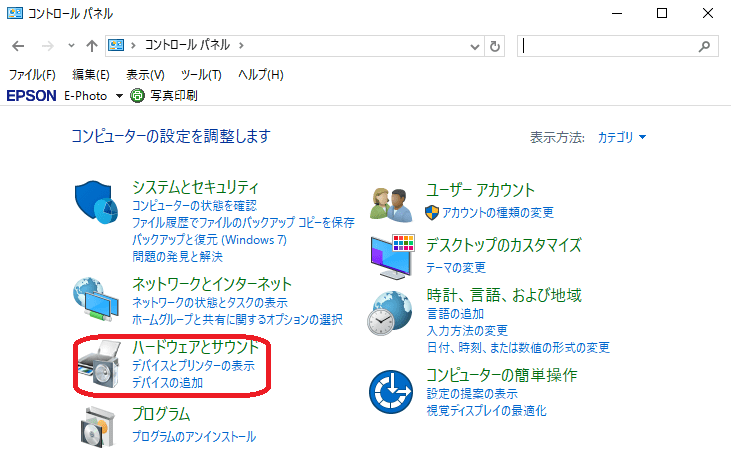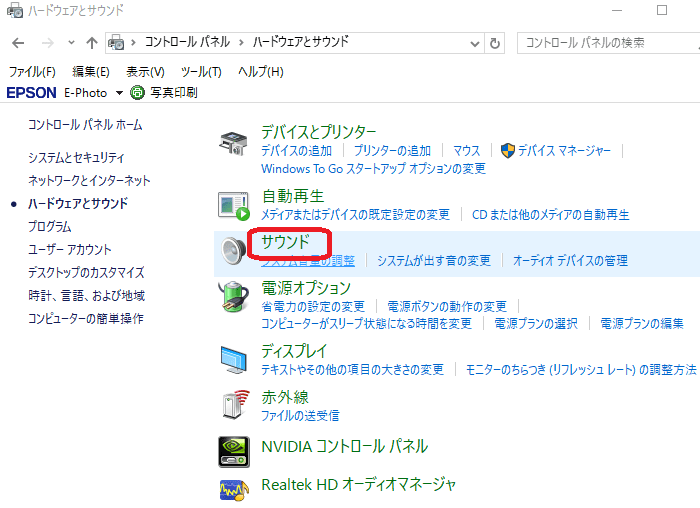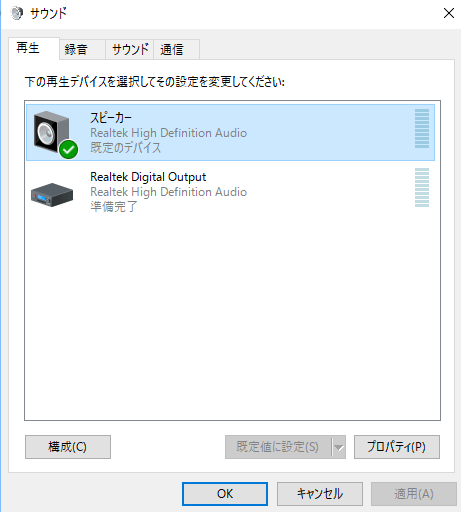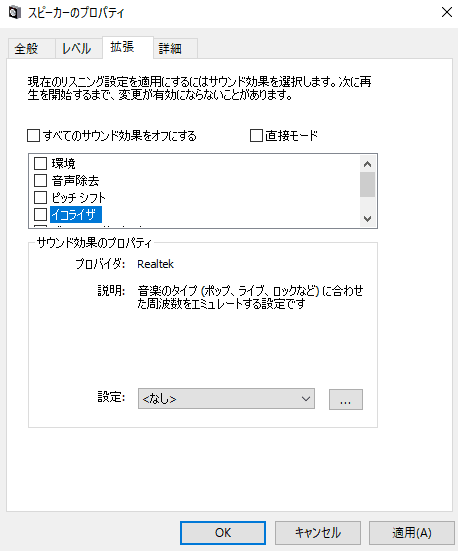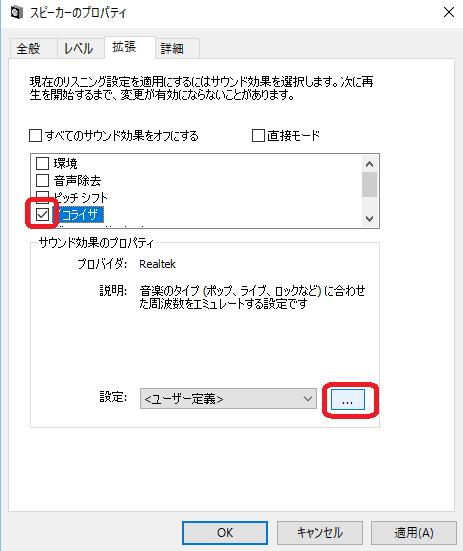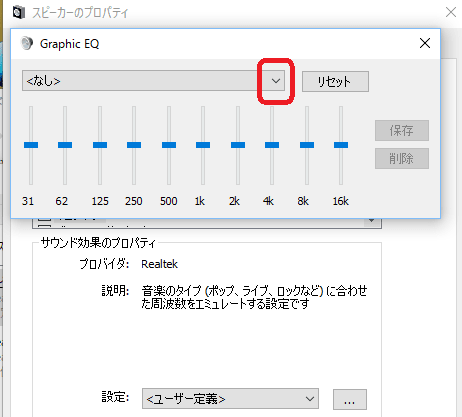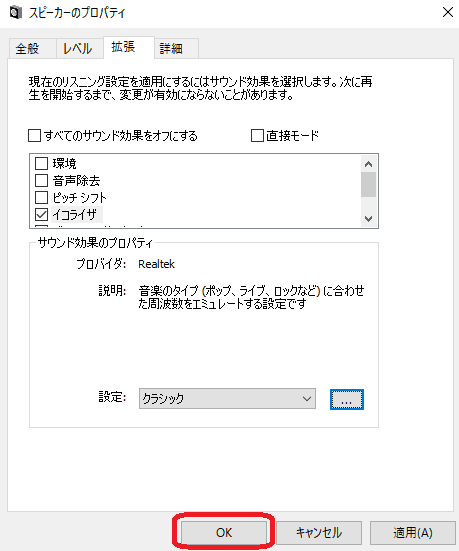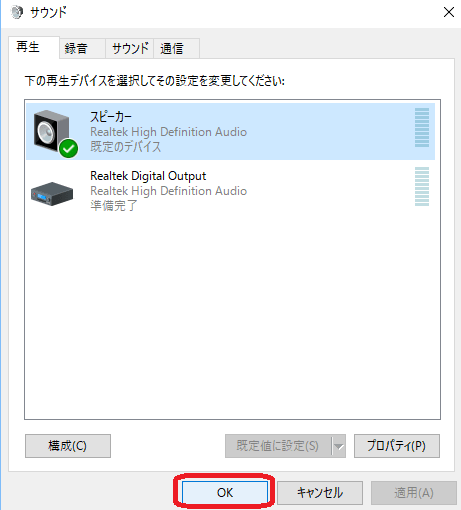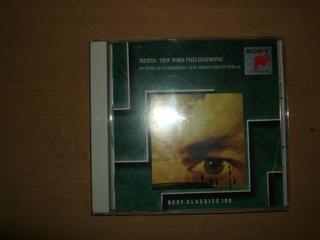今回はアンプの基本的な事について書こうと思う。よって音質が良くなるとか改善の話ではなく、普通に操作の事なんかを書いていく。
まずはボリュームから説明しよう。

写真は私のアンプなのだが、右寄りの一番大きいのがボリュームで音量を調節する。一番大きなつまみがボリュームであることを示しており、大音量を聴いた後は音量を下げておいたほうが良い。これは単純に後日聴いたときにビックリしない為の配慮だ。
バランス
バランス(Balance)は左右のチャンネルで出力を調整するための物で、アンプのすぐ隣に配置されている機種が多い。モノラルレコードを聴くの最もわかりやすいのだが、歌謡曲もセンターが中心に聞こえるはずなので、中心よりもどちらかに外れて聞こえる場合は、バランスを動かして中心に聞こえるようにする。CDなど最近のデバイスを再生する場合は、センターにそろっていると思うが、スピーカーからの出力差など、いろいろな要因があるので、一度きちんとセンターが合っているかバランスを確認してみよう。
インプットセレクター
CDプレーヤーやチューナー、レコードプレーヤーなど、入力されたデバイスを切り替えるのがインプットセレクターだ。CDプレーヤーの再生以外にも、FM放送を聴いたり、昔ながらのレコードをかけるなど、セレクターを切り替えて交通整理を行っている。また再生以外にも平行して録音できるように「RECセレクター」が搭載されている機種が多く、通常はOFFにしておくが、録音時は任意のデバイスを選択することができる。RECセレクターを選択する事により、CDを再生しながら、FMチューナーで録音することも可能なのだ。RECセレクターを搭載しているアンプは試してみると良いだろう。ちなみに私のアンプはRECセレクターが無いため、インプットセレクターの選択がそのまま録音先となる仕様だ。
treble と bass
たいていのアンプには、トレブルとバスの2つのつまみがある。trebleはトレブルと読み高音を強調する。bassはバスと読み低音を強調する。トレブルのつまみを右に回すと高音が増していく。バイオリンやピッコロなどのかん高い音が増幅されるようになる。他方はバスのつまみを右に回すと低音が増すので、ベースがよりずしんと鳴り響くようになる。これら2つのつまみはトーンコントロール(Tone control)と呼ばれるもので好みに合わせて活用しよう。
ラウドネスボタン
多くのアンプにはラウドネス(Loudness)が付いており、これは音量が小さい場合には低音が増すようになっている。これはラウドネス曲線という計算式があり、それに基づいてアンプが補正してくれるものだ。スイッチをオンにすると低音が増すようになっている。これは「小さい音量」というのがポイントで、音量を上げていくと、低音不足が解消されていくので、大音量の場合は自動的に解消されるようになっている。余談だがラウドネス曲線は低音のほかに、高音についても補正すべきなのだが、実際には補正される事はなく、より影響が大きい低音についてのみ補正されるようになっている。
夜間など大音量で音楽を聴けない場合は、積極的にラウドネスボタンを押すようにしよう。音質が悪くなるからという理由でラウドネスを押さない人を見かけるが、耳が半分塞がれた状態で高音質を求めようとする方が間違っていると思う。
ダイレクトボタン
ダイレクト(Direct)ボタンは、パイオニアのアンプでは一般的に搭載されているもので、トーンコントロールとラウドネスボタンを無効にしてしまう機能だ。このボタンを押すと音がとてもクリアになる。トーンコントロール回路の影響はかなり大きく、例えるなら景色を透明なビニールで覆うようなもので全体的にぼやけてしまうのだ。それとラウドネスボタンも無効となるため、おのずと大きな音量で流せる時にしかできないが、ダイレクトボタンをオンにすると、インプットセレクターからの信号を増幅するだけになるので、余計な色が付かないとてもクリアな音になる。ただ先に書いたように、ラウドネス機能は小音量で聴く際には必須だし、小音量だからこそトーンコントロールで全体的な音を調整する必要がある。大きな音で聴ける条件がそろった時だけ全開で聴けると考えば良いだろう。
今回はアンプの基本的な使い方について話したが、一口にアンプと言ってしまったが、今回説明したのはプリメインアンプだ。インテグレーテッドアンプとも呼ばれる、ごく一般的なものだ。もう一つ、高級オーディオの部類になるが、プリアンプとメインアンプに別々の機械に分かれている物もある。インプットセレクターとトーンコントール回路などの微小信号を扱う「プリアンプ」と、大きな電力を担う「メインアンプ」の2つで、プリアンプとメインアンプが一緒になって働くようになっている。また、プリアンプはコントロールアンプ、メインアンプはパワーアンプとも呼ばれおり、呼び名が違うだけで、機能的には同じだ。
そしてこれら2つの機能を一つにしたのがプリメインアンプとなり、機能を統合という意味でインテグレーテッドアンプとも呼ばれる。つまりプリメインアンプと呼び名が違うだけだ。
本日の視聴
さて本日はリヒャルト・シュトラウス 「交響詩」ツァラトゥストラはかく語りき」
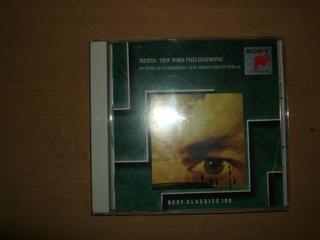

ズービン・メーター指揮。ユーヨークフィルハーモニック演奏の演奏だ。このCDにはムソルグスキーの展覧会の絵も収録されている。
ツァラトゥストラ~といえば、映画「2001年宇宙の旅」だろう。実は、今回のトーンコントールの話で、重低音が聴きたくなり、真っ先に思ったのがこの曲だ。冒頭のコントラファゴットによるバタバタバタというか、ゴゴゴゴゴゴと地響きのように震える音。口径の大きなウーファーでないと地響きは聞こえてこないのだ。30cmを超える大型スピーカーを持っている人はぜひ聞いて欲しい。
youtubeでツァラトゥストラはかく語りきで検索すると、カラヤンさんの演奏があった。ちなみにこのこの曲はCDを2枚持っているが、正直言ってよくわからないのが本音。そしてつい、「美しく青きドナウ」が聴きたくなってしまう。ちなみに映画「2001年宇宙の旅」はレーザーディスクを持っているが、エンドクレジットにはカラヤン/ベルリンフィルと書かれていた。ウィーンフィルの演奏はとても優雅に流れるが、ベルリンフィルはとても統制のとれたドイツらしい演奏となっている。
Youtube