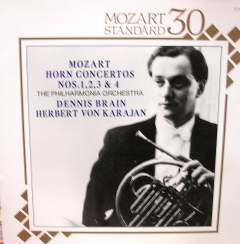ブラームス:バイオリンとチェロのための協奏曲
バイオリン:ジノ・フランチェスカッティ
チェロ:ピエール・フルニエ
シューマン:ピアノ協奏曲
ピアノ:ユージン・イストミン
指揮:ブルーノ・ワルター
管弦楽:コロンビア交響楽団
CD:CBS/Sony 35DC 126
このCDは、ブルーノー・ワルターが既に第一線を退いた後に、ワルターのために特別に編成されたオーケストラであるコロンビア交響楽団により、当時最新のステレオによって録音された一連のシリーズの中の1枚である。当初はレコードとして発売されていたが、このCDはマスターテープから直接制作されただけあってか、音を今でも鮮明に聴くことができ、ワルターの雄大な音楽性を余すところなく伝えている。このCDでのワルターの指揮ぶりはいつもながら包容力があり、特にブラームスではスケールが大きく、しかも劇的な表現にも優れ、マエストロという表現がぴったりの指揮内容となっている。
ブラームスのバイオリンとチェロのための協奏曲は、バイオリン協奏曲やピアノ協奏曲に比べて地味な存在ながら、一度その良さが分かると生涯付き合うほどの中身のある協奏曲だといえる。他にあまりバイオリンとチェロの協奏曲というのは聴いたことがないだけに、初めは少々戸惑うところもあるが、何回も聴くうちに、これもありかという気分になり、それを通りすぎると、なかなかいいじゃないかといった気分になってくる。今回のCDの演奏が最高レベルを行っているのでなおさらだが、ブラームスにありがちな晦渋さがあまり感じられず、逆に内に込めた親密さのような温もりに浸ることができる。
バイオリンのフランチェスカッティは情熱のこもった熱っぽい演奏を聴かせる一方、チェロのフルニエはというと理性の利いた淡々とした演奏を披露している。普通このような組み合わせは、往々にして不統一な演奏になりがちだが、ワルターの存在もあるのか、バイオリンがチェロにうまく絡み合い、絶妙のコンビネーションの演奏を聴かせる。
カップリングされたシューマンのピアノ協奏曲を演奏するユージン・イストミン(1925年ー2003年)はアメリカのピアニストとしてわが国でもお馴染みであった。全体にすっきりとした演奏をするピアニストで、あまり癖がないためか、室内楽でも名を馳せていた。このCDでも、素直なしかも透明感のあるピアニズムを聴かせてくれる。ワルターもブラームスとは異なりイストミンに合わせるように、スケールが大きいというよりも、内面的で緻密な指揮振りを見せる。数あるシューマンのピアノ協奏曲のCDの中でも、緻密な演奏として秀逸な1枚であることだけは確かだ。なお、このCDの録音はブラームスが1959年11月20日、シューマンが1960年1月20、25日となっている。
(蔵 志津久)